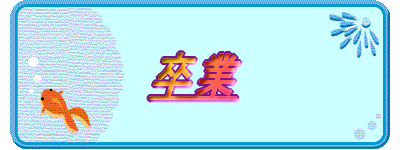
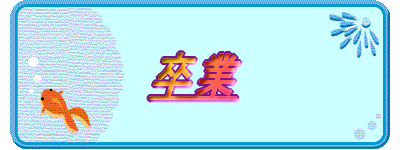
| 一 | 七 | 十三 | 十九 | 二十五 | 三十一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 八 | 十四 | 二十 | 二十六 | 三十二 | ||||||
| 三 | 九 | 十五 | 二十一 | 二十七 | 三十三 | ||||||
| 四 | 十 | 十六 | 二十二 | 二十八 | 三十四 | ||||||
| 五 | 十一 | 十七 | 二十三 | 二十九 | 三十五 | ||||||
| 六 | 十二 | 十八 | 二十四 | 三十 | 三十六 |
| 三十七 | 四十三 | 四十九 | 五十五 | 六十一 | 六十七 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三十八 | 四十四 | 五十 | 五十六 | 六十二 | 六十八 | ||||||
| 三十九 | 四十五 | 五十一 | 五十七 | 六十三 | 六十九 | ||||||
| 四十 | 四十六 | 五十二 | 五十八 | 六十四 | 七十 | ||||||
| 四十一 | 四十七 | 五十三 | 五十九 | 六十五 | 七十一 | ||||||
| 四十二 | 四十八 | 五十四 | 六十 |
六十六 | 七十二 |
まだまだ続きます・・・
新・暴風雨ガール
| 一 |
|---|
|
土砂降りの雨の中、大阪駅からタクシーに乗って引越し先のマンションの前に着いた時刻はもう午後七時を過ぎていた。妻から追い出され、必要最低限の荷物を夜間指定の宅配便で送っていたので、大阪駅に着いたときに突然激しい雨が降り出したこともあってタクシーで急いだのだ。 大阪の通称はキタと呼ばれる界隈からちょっと外れた、歓楽街と言っても北ノ新地とは趣が異なる、やや庶民的な飲食店街である曽根崎通りを抜けたところに位置する兎我野町の外れが私の引っ越し先である。 妻から追い出された理由については、先々その気があれば述べることとするが、ともかく季節外れのフライング台風が、まだ梅雨も明けていないのに日本列島を縦断しているのだ。狂っている。 五階建てのかなり老朽化したマンションの五階の一室が私の新たな住処である。タクシーを降りてマンションの入口まで走り、エレベーター前で待った。ほんのわずか雨に体を晒しただけでタオルが必要なくらいの叩きつけるような土砂降りになっていた。 ノロノロと降りてくるエレベーターを待っていると、ひとりの女の子が全身ほぼびしょ濡れになってマンションに走り込んできた。長い髪はまるで怪談に登場する幽霊みたいに顔半分を隠して、毛先から雨粒を滴らせていた。私はギョッとしながらも開いたエレベーターに先に乗るように手で示して、彼女が少し頭を下げて乗り込んでからゆっくりと乗った。だが、エレベーターはふたりが乗るとほぼギュウギュウの狭苦しい代物であった。エレベータもかなり狂っていた。 「何階ですか?」 私は女の子に訊いた。 「あっ、五階です。すみません」 五階のボタンを押して、極めてゆっくりと上がりだしたエレベータの階数表示ランプを見上げた。階がひとつ上に表示されるのに五秒以上もかかり、五階に到達するまでに女の子の髪から滴り落ちた雨粒で床に小さな水溜りができたくらいだ。 エレベータのドアが開き、先に彼女を降ろした。続いて私が出ると彼女の姿はなく、不動産屋から受け取っていた部屋のキーをポケットから取り出し、501号室のドアに差し込んで振り返ると、エレベータのすぐ隣の部屋の前に立ってこちらを見ている彼女の姿があった。エレベータと部屋の入り口とがコンクリート壁で隔てられていたので、さっきは見えなかったのだ。 私は無意識に軽く手を振った。すると彼女は少し頭を下げたようでもあり、そうでないようでもあったが、相変わらず顔の半分が髪で隠れたままの状態でドアの向こうに消えた。 それが暴風雨の夜に沢井真鈴を見た最初であった。 |
| 二 |
|---|
翌日から部屋のレイアウトをはじめた。二部屋とリビングという間取りを、事務所と寝室に使うために必要なものを買い揃え、整理をし、そして電話回線とインターネット回線の敷設を申し込んだ。スマホの時代と言っても、事務所にはパソコンが必要である。このマンションにはインターネット回線は導入されておらず、各入居者が自分で通信会社に申し込まなければならないのだ。時代から取り残されたマンションだ。 夜になって食事に出た、七年ほど前までの数年間は、このあたりでは肩で風を切る感覚で歩いていたものである。そのころと変わらず営業している店は数軒見かけたが、おそらく半分以上は店が替わってしまっているような気がする。七年も経てば様々なものは移りゆくのだろう。 曽根崎通りに出る新御堂筋の手前に「安曇野」という小さな小料理屋がある。前の商売のころは度々立ち寄っていた店だ。懐かしさのあまり暖簾をくぐってみた。カウンター席のみ十席あまりの店の様子は全く変わっておらず、奥の方で菜箸を使って天ぷらを揚げていた女将さんがこっちを向いた。 「いらっしゃい、あら?岡田さんじゃないの、どうしてらっしゃったの、ホントに」 「すみません、ちょっと下手を打って豚箱に入っていたものですから」 以前は週に二度も三度も立ち寄っていたのに、本当に下手を打ってからはピタッと無沙汰になってしまったので、豚箱に入っていたという冗談は、まるっきりそうとも言えないなと自嘲した。 ビールを注文すると、何も言わずとも女将さんが今夜のおすすめを適当に出してくれる。以前と変わっていないことに嬉しさを隠せなくなる。 「でもホントに、どうしてたの?幸子も心配していたのよ。短い間だったけど、すごくお世話になったのにって。幸子はね、あれから次の年に薬学部に合格してね、今は薬剤師で寝屋川の市民病院に勤めてるのよ。岡田さんがピタッと見えなくなったら事務所をたたんでしまったらしいって聞いてね、ずっと心配していたのよ」 無沙汰していた私を責めるかのように言葉を連射してくる女将さんの顔は、もちろん責めているわけではなく、ほころんだ口元から察するに、私の久しぶりの登場に安堵と嬉しさを感じているように思えた。 幸子さんとは女将さんのひとり娘で、私が前の仕事で事務所を構えていたときに、某大学の薬学部を現役で不合格となったので、浪人中に一年足らず手伝ってもらっていたのだ。 「女将さん、近くでまた商売をはじめますから、これからまたしょっちゅう寄せてもらいますよ。ずっと顔を見せずにすみませんでした」 昔の常連がひとりも店にいなかったことにホッとして、小一時間ほどでお勘定を頼み店を出た。いくら常連客といっても、酒の数杯以上の付き合いは真っ平ごめんだ。 兎我野町の夜は昔に比べて飲食店よりも風俗営業店やラブホテルが増えたように思え、徘徊する男は怪しげな店の呼び込みに吸い寄せられ、ラブホテルから出てくる不似合いなカップルが視界に飛び込んで来て、少しの酔いも醒めてしまいそうになる。 そのとき、目の前のホテル・キャンディポケットから見覚えのある女性が飛び出て来た。いくつもの垣根のような観葉植物で隠れた出入り口から、スーツ姿の中年サラリーマン風の男に続いて、やや下を向いて出てきたのは、昨夜土砂降りの雨の中、エレベータ前に駆け込んできたあの女の子であった。 |
| 三 |
|---|
女の子の方も私の姿に気がつき、一瞬だけ「アッ」というふうに口を小さく開いたのを私は見逃さなかったが、気付かなかったふりをして帰りを急いだ。彼女はどう見てもおとなの女性ではない、中学生にさえ見えるくらい、まだ全身に未完成の少女の部分が窺えた。しかし間違いなくあの女の子だ、いったいどうなっている。世の中、まったく狂っている。 某テレビ局の跡地の裏手に位置するマンションは、国道と賑やかな通りに挟まれた狭い路地のような通りで、派手な店は無く、もう何十年も昔から贔屓客だけを相手にしている料理屋や、セルフコーヒーショップ全盛のカフェ事情など関係ないと言わんばかりの小さな純喫茶店などが、静かに佇むように営業している。取り残された路地裏のようだが、私は気に入っている。 オートロックも何もないマンションの敷地に入り、エレベータのボタンを押して待つ。指令を受けても、しばらくしないと動き出さないエレベータである。こんなマンションの一室で商売を始めて大丈夫かなと不安が掠める。 ようやくエレベータが到着し、乗り込もうと思ったそのとき、うしろに人の気配を感じて振り向くと、あの女の子が立っていた。この前と同じように、ギョッとしながらも先に乗るように勧めた。 「こんばんは、暑くなってきたね」 並んで立つと身体が触れるほどの狭いエレベータなので、少しだけうしろに身体を引いて、沈黙に我慢しきれずに私は言った。 「悪いことはしてません、私」 「えっ?」 時候の挨拶とは無関係のいきなりの言葉に、私はすぐに言葉が出なかった。 「悪いことって?」 「だから、さっき私を見たでしょ。でも違うの」 「違うって・・・何だろう?」 本当に彼女が何を言っているのか分からなくなってきた。 「だから、男の人とあんなところから出てきたら、悪いことをしてるって思うでしょ?」 「でも、してないんだろ?」 「うん」 五階に着いてエレベータが開いた。エレベータから出ても、彼女はすぐ横の自宅へは入ろうとせず、私の方を見て何か言いたそうな素振りを見せた。 「大丈夫だよ、誰にも言わないし、心配ない」 「だから変なことしてないから」 「分かってるよ、悪いことも変なこともしていない。そうだね?」 しばらく私の言葉の意味を考えていたようだが、何も言わず私に背を向け、ドアの向こうに消えた。私は急に身体が重くなったような気がして、少しふらつきながら自分の部屋の前までたどり着き、鍵を差し込んでドアを開けた。 |
| 四 |
|---|
|
事務所としての機能が整うまで約一週間を要した。電話とインターネット回線の敷設が終わり、パソコンなどを設定し、いつでも動ける体制になったが、営業をかけるとすぐにオファーが来ると踏んでいたので、慌てなかった。 「両親がね、離れて暮らしてるんだったら、もう離婚したらどうかって言うのよ」 考えてみれば、ふたりの間に子供がないことが、お互いの自由な動きを可能にしていた。子供もいないのに、離れて暮らしながら婚姻関係を保つ意味がないというのも理解できた。私は少し考えてみると言って電話を切った。 翌日、七時半に部屋を出て京都へ向かった。開業したらすぐに仕事を回してもらうために、業界では比較的古い業容を持つ企業への挨拶である。 阪急梅田駅の改札を入って京都線のホームへ歩いていると、売店で見たことのある顔が視界に飛び込んできた。あの少女であった。男性とラブホテルから出てきたところに遭遇したあの夜以来、ずっと見かけなかったのだが、今朝は女子高生の姿、白いシャツと紺のベストとスカート、手には大きなカバンを持っていた。 私は気付かなかったふりをして、大きな駅構内の最も隅に位置する京都線のホームへ歩こうとした。だが、彼女が売店での用をすませて振り向いたとき、顔が合ってしまった。 「おはよう、こんなところで遭うなんてね、まったく」 「学校です」 彼女は一瞬驚いた顔を見せたが、すぐに表情を戻して冷静に言った。 「知ってるよ、その制服」 「行ってきます」 そう言い残して、宝塚線のホームへ速足で去った。彼女の制服は、十三駅近くにある有名校のものだった。やっぱりまだ高校生だったのだ。 |
| 五 |
|---|
|
京都市内の西寄りにある西院という駅を出て、道路を渡ったところにある五階建ビルの三階にA社がある。私は金融業を失敗したあと大手の探偵調査会社に勤務して六年余りの経験を積み、もともとが独立したがりの性分が、凝りもせずに再びこころの奥底から湧き出て来てはやし立てはじめたので、世話になった調査会社を退職して自分の事務所を出すことにしたのだ。 これから訪ねる調査会社はビルの一室と言っても、私の居宅兼事務所の広さとは比べ物にならず、相談室や応接室、事務室を含めて四つの部屋に区切られていた。社長は五十代の女性で、業界の会合などで何度か面識はあったが、直接訪ねていくのは初めてである。事務室には三人の若い女性とひとりの中年男性が、パソコンと向き合って忙しそうに業務をしていた。 「岡田です。よろしくお願いします。さすがに御社ほどになれば朝から皆さんお忙しくされていますね」 「忙しいのは事務関係だけね。私のところは調査員を抱えていないから、外注ばかりでちっとも儲からないのよ」 名刺交換のあと、社長は苦笑いをしながら言った。調査の仕事はすべて下請け、つまり外注に出すのがこの調査会社のやり方で、暇なときのリスクは軽減できるが、ひとつの案件の純利益は少なくなる。自社の調査員を抱えて利益を優先するか、外注本意で売り上げを優先しリスクを減らすか、どちらが良いかは分からない。 「岡田さん、早速だけど急ぎの尾行調査が入ってるのよ。外注さんが皆目いっぱいでの状態で頼めないの。すぐにやっていただけないかしら」 いきなりの依頼はありがたいが、まだ各種調査案件別の下請け金額や取り決めなど、何も話し合っていない。 「車の尾行ですか、歩きですか?」 「歩きなのよ。男子高校生の尾行で依頼人はご両親。朝自宅を出てから帰って来るまでを十日間、とりあえず追って欲しいという内容ね」 私は断る理由もなく引き受け、依頼内容を確認し、簡単な契約書を交わして、早速明日から調査開始となった。 「ご存知かもしれませんが、私の得意分野は結婚調査と所在調査、それと企業です。まあ何でもやらせていただきますけどね」 「知ってるわよ、どんどんお願いするからよろしくね」 朝からの営業訪問は、思いがけず翌日からの尾行調査が舞い込んできた。 梅田に着いて自宅兼事務所に帰り、明日からの尾行調査の準備をした。準備といっても歩きの男子高校生の尾行なので特にはない、カメラ位のものである。 調査の指示書を読むと、ときどき家を出てから学校に行っていない日があるので、いったい何をしているのか、という依頼内容である。おそらくゲームセンターなどで遊んでいるのだろう。あまり気がすすまなかったが、金で割り切ろうと考えた。 この尾行調査が沢井真鈴との長い長い不思議な関係の序章になるとは、このときまったく想像もつかなかった。 |
| 六 |
|---|
|
依頼人宅は兵庫県宝塚市の高級住宅街、息子が家を出てから帰宅するまでの行動を十日間追ってくれというものだった。彼はお坊ちゃん高校といわれているN学園の三年生になったばかり、来年は大学受験を控えていた。もともと真面目でおとなしい性格で、二年生の二学期の前半までは何の問題もなかったが、昨年の十一月ごろから親には内緒でときどき学校をサボるようになった。学校から通知が来て三者面談となったが、学校をサボった理由は「公園で本を読んでいた」と言うだけだった。彼は親から毎月それなりの小遣いをもらっていたが、本を購入するからと言ってさらに何度かまとまった金を求めた。だが購入した様子はなく、母親がこっそり部屋を調べてみたところ、お年玉やこれまで郵便局で何度かバイトをして貯めた預金が定期的に引き出されていた。金の使途は?そして学校をサボってどこで何をしているのか?という調査依頼だった。 高校三年生といえばもうおとなだ。金はおそらくゲームセンターや遊びに使っているのだろう。放っておけばいずれ本人が馬鹿馬鹿しく思ってやめるだろうにと、私は調査指示書に目を通して呆れてしまった。 依頼人の息子の尾行は数日何も動きはなかった。宝塚市の自宅を出て、阪急宝塚線の山本駅から電車に乗り、宝塚駅で今津線に乗り換え甲東園駅で下車し、真っ直ぐN学院に登校した。百七十センチほどの背格好に少し長めの髪、彫りの深い精悍な顔つきは、依頼人から預かった写真と同じだった。 動きがあったのは四日目の木曜日だった。朝いつもの時刻に家を出て山本駅に入ったのだが、電車を待つホームが違った。宝塚方面ではなく大阪梅田方面のホームで電車を待ったのだ。 数分後、急行電車が滑り込んで来た。本人が乗り込んだ同じ車両のひとつ隣のドアから乗り込む。まだ六時台だから混み具合はそれほどでもなかった。本人は車両の連結部分近くに立って本を読んでいた。私はつり革を持って外の景色を眺めながら、彼を右目の端に捉えた。電車が駅に着くときだけ彼から目が離れないように注意した。急行電車はいくつかの駅に停車し、そのたびに社会に関係している人々を積み込み、車内は次第に混み合ってきた。社会や組織に関係しない私は本人の位置に少し近づき、見失わないように注視した。 三十分ほどで電車は阪急梅田駅に到着した。本人は気だるい歩き方で電車から降り、エスカレータで階下のフロアに降りた。すぐに改札口を出ずに同フロアのトイレに入った。しばらく遠目で待っていた。ところが、五分経っても十分経っても出てこない。でも見落とすはずがない。念のためトイレに入って確認をした。だが彼の姿はない。少し焦るが絶対にトイレから出ていないと確信して外で待った。 二十分近くも経ってからようやく本人がトイレから出てきた。N学院の制服から紺のジーンズに海老茶のパーカーに服装は変わっていて、バッグは消えていた。代わりに手提げの大きな紙袋を持って出てきた彼は、改札口を出て同じ階の東隅にあるコインロッカーへそれを放り込んだ。すっかり服装が変わり、イメージまでも全く違って見えた。まるで彼が探偵みたいだなと私は思った。エスカレータを降りて、梅田地下センターへ出て東梅田方向へ歩いた。途中、喫茶店に入りトーストと卵のモーニングサービスを食べはじめた。私も離れた席に座り、同様のものを注文しだ。彼はどこへいくのか、仕事を忘れてこの日の行動に興味深くなってきた。 本人は午前八時半を過ぎるまでコーヒーショップで粘り、その間ずっと本を読んでいた。店内は四人がけのテーブル席がおそらく三十はある大きな規模で、サラリーマンやOLが出勤前のコーヒーを飲み、ほとんどが十五分か二十分程度で店を出た。彼らや彼女たちは会社組織に関与しているレギュラーな人たちだ。私と本人だけがこの一時間半ほど、社会の動きとは無関係な存在のような気がした、つまりイレギュラーだ。 九時少し前にようやく本人は腰を上げ、梅田地下センターを東方向へ歩き出した。手にはずっと読み続けている文庫本が一冊、直線の見通しの良い地下通りなので、私は二十メートルほどの距離を開けて尾行を続けた。この時間、地下街の人通りは少ない、彼は「泉の広場」で立ち止まり、中央にある円形の大きな噴水スペースの縁に腰をかけて再び本を読み始めた。誰かを待っている様子に思えた。 九時四十分になった。本人は同じ姿勢で本を読み続けていた。するとそこに一人の女性が歩いてきた。ぼんやりと張り込んでいたが、緊張感が戻ってきた。うつむき加減に近づいてきた女性は、私には「少女」に見えた。髪の毛は首までの短め、背は彼の肩位なのでやや小柄な感じ。薄いピンクのスニーカーを履き、本人と同じようにジーンズ姿でスニーカーと同色のシャツをラフに着こなしていた。 少女がこちら側を向いたとき、私の目が点になった。同じマンションの五階に住む、あの女子高生だったのだ。こんな時間に学校にも行かずに、いったい何をしてるんだ? |