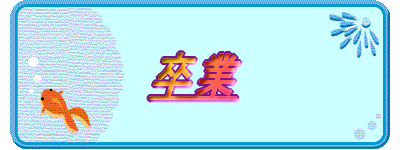
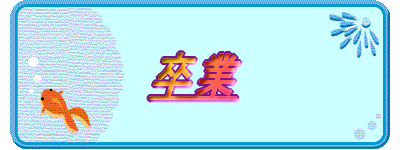
| 四十三 |
|---|
|
七月に月が変わって暑さが本格的になってきた。有希子は右の乳房を全摘出し、リンパも切った大手術だったが、手術後の経過は意外にも順調で、働ける状態にまで回復してきたようだった。だが、高齢の両親を置いて仕事には出られない、一時期は父の散歩にも付き合える状態ではなかったが、最近はもとの日課が戻っていた。 二週間に一度程度はこの部屋にやって来て、夕方まで何をするでもなくぼんやりとしたあと、「帰らなきゃ」と言って生駒の実家に帰って行く有希子を、私は何とも言えない気持ちで毎回ドアの外まで見送った。 「最近はまた、君の両親、早く離婚しろって言わないんだな」 「もうあの人たち元気がないのよ。私、お金なんていらないから、もう少しよくなったら家を飛び出すから」 有希子はときどき涙ぐみながらそういうふうに言う。でも、現実的には高齢の両親を置き去りにして家を出るわけにはいかない。私が彼女の実家に引っ越して、一緒に暮らせば有希子の悩みは解決する。だが、この提案も現実的には彼女の親に受け入れられるはずはなかった。 有希子が帰ったあと、山下達郎さんの「街物語」という曲を聴いた。この前、真鈴に梅田丸ビルのタワーレコードに付き合ってもらって買ったCDだ。 山下さんはこの楽曲で、「サヨナラは終わりじゃない。思い出は消せないから、この道でふたりして小さな空を見上げていた。きらめきが色褪せても、温もりは残っている〜」と歌っている。 有希子とは大学生のころからの長い付き合いだ。このまま、万が一サヨナラになってしまったとしても、大学のキャンパスや学食、そしてふたりで贔屓の球団の応援にたびたび野球場へ一緒に行ったことや、あてもなく夜行列車に飛び乗ってふたりして旅に出たことなど、たくさんの思い出は消えないし色褪せない。有希子との先のことは、もう流れに任せようと思っていた。 さて、七月最初の仕事は京都府宮津市に住む親子の調査だった。私は調査資料をもらうためT社を訪れた。ファックスを送ってもらってもよかったのだが、依頼人の目的を直接部長から訊いておきたかったからだ。そんなものにいちいち立ち入らなくともよいのだが、なぜかこの案件が気になったのだ。理由は特になく、私の持つ「勘」だった。 私の「勘」は自分自身が意識しないところで働くことが多い。昨夏も真鈴の父を捜しはじめた際、彼が経営していた会社に役員として勤めていた佐久間氏と会ったのだが、手がかりとなる話は全く得られなかった。だが、別れ際にその会社に当時勤めていた女子社員のことを訊いた。無意識に訊いただけなのだが、それが私の持つ「勘」だった。結果的に、後日彼から送られてきた女子社員リストにあった三枝さんと会うことになり、彼女から沢井氏が会社経営当時に取引先のない徳島へ、なぜかたびたび立ち寄っていたことが分かり、真鈴の父の実家のある香川県丸亀市を訪れて、そこからの調査の流れで徳島の「穴吹療育園」にたどり着いたのだった。 そういえば、穴吹療育園の関さんはあれからどうしているのだろう。私が療育園を訪ねたとき、受付にまるで「空を翔る少女」のように駆けつけてきて、そして空を翔ぶように巨大な療育園の内部を案内してくれた関さん。彼女は調査が暗礁に乗り上げた感があったときに素晴らしい情報を与えてくれたのだが、基幹の部分は私の「勘」から真鈴の父を捜し出せたのだった。 今回の依頼人A氏と村井沙織が知り合ったのは、A氏が三十代後半の頃、大手建設会社勤務の同氏は管理職に就き、仕事がますます面白くなってきた年齢だった。神戸市内に妻子との平穏な家庭を築いていたが、京都府舞鶴市の大規模なプラント建設現場へ二年間の予定で出向の命が下った。当時、A氏のふたりの子供はいずれも小学生、出向先が特に遠方でもなかったため、彼は単身赴任を選択した。舞鶴から神戸まで、舞鶴自動車道から中国自動車道を経て、少し車を飛ばせば三時間程度で戻ることができる。赴任後も、当初は毎週末には妻子の元へ帰っていたという。舞鶴市内に会社が用意してくれた二DK程度のアパートに引越し、朝から夜遅くまで現場監督としてA氏は働いた。真面目で仕事一途の性格で、家庭も大切にするマイホーム人間であったが、仕事の疲れで週末に神戸へ帰る頻度が次第に減ってきた。そして単身生活にも慣れたころ、宮津市内の料理店で取引先から接待を受け、沙織とはその店で知り合った。 宮津市は当時人口二万人あまりの小都市で、地場産業といえるものは特になく、天橋立や丹後由良海水浴場などの観光産業に市の収入を依存していた。そのころ沙織は二十五歳を過ぎたばかり、市内の高校を卒業後、地元の観光物産会社に就職、みやげ物店に勤務した。両親と弟がいたが、弟はやがて大阪へ就職のため家を出た。沙織は両親との三人暮らしを送り、A氏と知り合う少し前に観光物産会社を辞めて、父の知人が営む料理店を手伝った。A氏がその料理店を初めて接待で訪れて沙織と知り合って以来、土日に彼のアパートを訪れて食事や洗濯などの世話をするようになったという。A氏は仕事の疲れもあって、神戸の家族の元へ帰るのが二週間に一度となり、やがて月に一度となっていった。そして一年余りが経過し、沙織が妊娠した。A氏には家庭があり、当然結婚はできない。彼は苦悩した挙句、中絶を求めたらしいが、沙織は産みたいと首を横に振った。二年の出向赴任期間が終わり、現場を引き払うころには沙織はすでに妊娠八ヶ月を過ぎていた。A氏は話し合いの末、沙織に三百万円を手渡し、神戸へ帰った。そしてそれ以後、たった一度たりとも沙織からA氏に連絡がない。A氏が部長に語った内容は以上だった。 「まあ昔の愛人が今どうしているのか?ってな内容の調査やな、岡田君。気楽に行って来てくれたらええで。宮津は魚介類が美味いよってな。カニはこの時期は食えんがな」 部長は相変わらず気楽な調子で言った。調査の背景を部長から訊いて、「よくある別れた愛人の現況調査ってやつか」と私はため息をついた。A氏は部長に「子供が健康に育っているか、どんな子供なのか、写真を撮っていただけるものなら一枚でもいいから欲しい」と言い残して帰ったとのことだった。 別れたあと、沙織からA氏にただの一度たりとも連絡がないということだが、逆を言えばA氏にしたって一度も沙織に連絡を取らなかったということではないか。何かほかに事情があるのかも知れないが、調査指示書を読んだ限りでは依頼人の身勝手な行動と、今更ながらの調査依頼としか思えず、あまり気乗りしなかった。 いずれにしても、調査は沙織の現況についてだけではなく、A氏との間にできた子供の写真撮影も必要となった。調査発覚のおそれがあれば無理な写真撮影はやらないと依頼人に伝えているとのことだが、それをやり遂げるのがプロの調査員だから僕にとっては必須事項なのだ。 二日後、宮津へ向かった。三日間程の出張となる。向かう列車の中で、わずか数日間にしても部屋を空けることを連絡する相手が存在しないことに気づいた。大阪からJR山陰本線経由の北近畿タンゴ鉄道に乗った。列車は、京都から綾部まではほぼ一直線に北西方向へ延びる線路をひたすら走り、その後北上して午後二時ごろには宮津に着いた。法務局で沙織の実家の不動産登記事項を参考程度に閲覧したあと、彼女が勤めていたとされる料理店の所在を確認した。そのあと、少し早いがいったんビジネスホテルにチェックインし、真鈴に電話をかけた。彼女は珍しく一発で電話に出た。 「どうしたの?岡田さんから電話をくれるなんて珍しいね」 「今日から数日、京都の宮津で仕事なんだ」 「フーン、京都に宮津ってところがあったのね。どのあたりなの?」 「ほら、天橋立で有名な日本海側の町だよ」 「天橋立なら聞いたことがあるよ。観光地でしょ?それでいつ戻ってくるの?」 「もう戻らない」 「えっ?」 「僕の人生は宮津で終わりだ。真鈴、家族と仲良くして、来年は頑張って必ず大学に合格するんだぞ」 「何を言ってるの?どうしたの?」 「ごめんな、もういろいろ辛くて、生きていくことに疲れてしまったよ。残念だけどサヨナラだ。日本海は綺麗な海だから、優しく包み込んでくれそうだよ」 「嘘でしょ?冗談だよね」 「真鈴、君はこんな僕のこと、よく慕ってくれたね。すごく感謝しているんだ」 「嫌だって、そんなの。馬鹿なこと言わないで。明日そっちへ行くから、今いる場所を教えて」 ジョークで言っているのに真鈴は乗ってこなかった。普段からめったに冗談やふざけたことなど口にしない私だから、彼女は本気で心配してくれた。真鈴が焦っている様子がスマホから伝わる吐息にも感じられた。 「どうして黙ってるの。岡田さん、どうしたの?」 「ごめん、冗談なんだ。悪かった」 「えっ?」 「ごめん。少しだけ話を聞いてくれるかな?」 「冗談なの?」 「うん、ごめん」 しばらくの沈黙があった。 「本当に死んじゃうって思ったじゃない。絶対に許さないからね」 真鈴の半泣きの反応や言葉が、本当に死んでもよいくらい嬉しかった。 「悪かったよ。まさか本気にとるなんて思わなかったから」 「だめ。帰ってきたら覚悟して」 「謝るから、そんなに怒らないで。でもな、本当にちょっと落ち込んでいたんだよ。この宮津の仕事はおそらく三日か四日で終わると思うんだけど、その間、当然だけど部屋を留守にするだろ。今の僕には自分の予定なんかを伝える相手がいないって、今更だけど思ったんだ。そしたら急に寂しくなってね。君なら僕のことどう思ってくれるかなって試してみたんだ。ごめんな、悪かったと思ってるよ」 真鈴はまた黙った。電話がつながっているのか切れてしまったのかが不安に思ったころに、ようやく彼女が返事した。 「そういうときがあったら私に連絡してくれればいいじゃない。私がいるんだから、寂しく思わないで」 「この仕事から帰ったらいつものプランタンでエビフライを食べて、それからホテルでテレビゲームをして遊んでくれるかな?」 「いいよ」 「今日はありがとう、安心したよ」 「早く帰って来て、待ってるから」 真鈴は囁くように言って電話を切った。私はホテルの窓から見える鮮やかな橙色の夕焼を眺めながら、「真鈴を本気で愛してしまったなら、これは一大事だな」と思った。 この日は暑さと移動の疲れがあったので、ホテルのレストランで簡単に食事をして、午後九時にはベッドに入った。明日の作戦を考えているとなかなか寝付けなかったが、真鈴の言葉を思い起こしているうちに気持ちが落ち着き、いつの間にか眠りに落ちた。 |
| 四十四 |
|---|
|
翌日、部長から受け取った事前調査資料に基づいて村井沙織の現住所を訪ねてみると、宮津駅から徒歩五分程度、国道百七十八号線の大膳橋を渡って斜めに少し入ったところで、外観がお洒落な二階建アパートの二階の一室に居住していた。 アパートの前の国道の向こうには宮津港が見えた。国道といってもそれほど交通量は多くなく、アパート周辺は住宅と宮津港から水揚げされる魚介類の加工会社や倉庫などが混在しているが、比較的静かな環境だった。 今夜、沙織が勤めている店を直接訪れるのだから、アパートの近隣や大家への聞き込みは行わないことにした。ただ、彼女と息子との写真をどうやって撮ろうかとあれこれ考えてみたが、よい方法は浮かばなかった。 夜まで時間が余っていたので天橋立を少し観光した。天橋立ビューランドという展望台から、昨日電話したばかりの真鈴に再び電話をかけてみた。 「はい、真鈴」 「あっ、今話せないか?」 「予備校よ。あとでかける」 電話が切れた。予備校の講義中になぜ彼女がスマホに出られるのかが不思議だった。展望台から海を眺めていたら、海と空の分岐点が分からなくなってきた。それくらい海も空も鮮やかに青かった。 空の青に唯一浮かんでいる太陽が私の頭上に強烈な熱射を注いできた。それはまるで射るような熱の線だった。茹だるような暑さの中、今夜の聞き込みの作戦を考えた。この調査は沙織に会う以外に状況はつかめないし、子供の写真撮影も不可能だろう。沙織と接触する方法を様々考え続けたが、ともかく以前働いていた店を訪ねてみないことには何も始まらないと思った。あまりの暑さで思考が揺れ始めたとき、ようやく真鈴から電話がかかってきた。 「どうしたの?」 「特に用事はないんだ。ごめんな、昨日電話したところなのに、また電話してしまって」 「そんな気遣いなんていらないよ」 「ありがとう。真鈴もこの暑いのに夏期講習なんて大変だな」 「夏が勝負って先生が言うのよ。勝ち負けじゃないのに、馬鹿みたいでしょ」 彼女は小さくため息をついて言った。 「暑いなぁ、こっちは茹だる暑さで参ってるよ」 「え〜、そうなの。大阪は暴風雨だよ、傘なんか役に立たないわ」 そういえば、昨日から天候が悪くなっていて、太平洋側を台風が通過する予報が出ていた。 「台風、直撃じゃないから、明日はカラッと晴れるよ」 「雨、大嫌い」 「僕は好きだな」 「なんで?」 「真鈴と最初にあった日のこと、憶えてないかな?」 「わかんない、そんな前のこと」 「土砂降りの暴風雨の夜、マンションのエレベータの前に幽霊みたいな髪で走り込んできただろ。あれが最初だよ」 「そうだったかな?でも幽霊って、それひどすぎる」 ともかく午後の講義も頑張れと励まして電話を切った。真鈴は来春、K大学を受験すると言っていた。 「K大学か・・・。難易度、超ハイレベルじゃないかよ」と、私は声に出して呟いた。そして今夜はキンキンに冷えたビールを飲ながら、真鈴のことをもう一度出会ったあたりから思い起こしてみたいと思った。 いったん宿に戻ってシャワーを浴びて、夕方五時半を過ぎてから沙織が働いていたとされる料理店へ向かった。A氏から聞いていたその店「魚膳」は旅館や飲食店などが並んでいる一角にあった。A氏が赴任していたころから十三年もの長い年月が経過していたにもかかわらず、今も変わりなく営業を続けていた。店の入り口は格子戸になっていて、ガラっと開けると店内は意外に広く、ゆったりした雰囲気の店だった。 「いらっしゃいませ」 愛想のよい和服姿の女性に迎えられ、私は意識的に目の前に調理場が見えるカウンター席の最も奥の位置に座った。屋根が高く、テーブルやカウンターをはじめ、店内のものすべてに高価そうな木材を使ったなかなか立派な店の造りだ。 厨房内に板前さんなどが三人と店内係の女性がふたりいて、ひとりは明らかに五十歳をとうに過ぎていそうな女性で、もうひとりの女性は二十代の前半とみられ、沙織らしき四十歳前後の女性はいなかった。まだ時間も早く、客は少なかったので、ビールと料理を適当に注文してから、混み合わないうちに年配の方の店内係に尋ねてみた。 「久しぶりに大阪から出張に来たのですが、もうずいぶん以前、ここに沙織さんという方がいらっしゃいましたよね。今日はお休みなのですか?」 「ああ沙織ちゃんならもうとっくに辞めていますよ。お客さんは久しぶりに来られたのですかね。今は駅の向こうの大膳橋の近くで、自分でお店をやっていますよ」 大膳橋といえば、沙織が住んでいるアパートがあるあたりではないのか。 「お店って、飲み屋さんですか?」 「まあそうですね。ひとりで小さくやっていますよ。行かれますか?」 せっかくだしこのあと少し寄って帰りたいからと、店の名前と場所を訊いてメモをした。店はおそらく十時半くらいまでは営業しているはずだが、お客さんの具合によっては遅くまで開けている様子とのことだった。 店内係の女性に沙織の店を教えてもらったあとも、しばらく「魚膳」で飲み続けた。沙織の店をできるだけ遅い時間に訪れて、閉店間際まで飲むためだった。遅くまで粘って酔いつぶれたふりをして、相手を安心させていろいろと訊きだす作戦なのだ。ところが魚膳で夜九時前まで飲んでいたら、本当にすっかり酔ってしまった。 魚膳を出たあと、夜の宮津の街をふらつきながら歩いた。大阪などと違って街灯の数は圧倒的に少なく、少し離れた国道を車が走行するときのヘッドライトの明かりが、ときおりサーチライトのように舗道を照らしていた。 少しふらつきながらも、どうにかこうにか沙織の店にたどり着いた。店はカウンター席のみ十席程度と小ぢんまりしていた。ウイークデーの夜ということで男性客がふたりいただけで、その客たちも、私が店に入ってから十五分程で帰ってしまった。沙織から直接話を訊くには絶好の条件となった。でも私はかなり酩酊していた。昼間、天橋立の展望台で真鈴と熱い会話を交わしたこころと身体を冷やすため、「魚膳」で生ビールをたて続けに何杯も飲んでしまったのがいけなかった。 「沙織さん、A氏からの依頼であなたの近況を訊きに来ました」 危うくそう宣言して、手帳を左手に、ペンを右手に持って取材を始めてしまいそうなくらい、私は酔っていた。 和服に割烹着を羽織った沙織はかなりの美人で、四十歳の年齢よりは若くは見えなかったが、洋酒メーカーのコマーシャルで囁く女優みたいだった。私はA氏が彼女に惚れてしまった理由を、ひと目見ただけで理解できたような気がした。 「いらっしゃい、どうぞ」 沙織はおしぼりを手渡しながら、「何を飲まれます?」と訊いてきた。私は彼女の色気に圧倒されて、頬をピシャリと叩かれた感じになってしまい、「ビールを」と返事した声が少し嗄れていたのが自分でも分かった。一気に酔いが醒めそうだった。 「お客さんはどちらから宮津にお越しですの?」 沙織は低いカウンター越しに差し出した手の着物の袂をつかみながら、お通しと箸やすめを前に置き、首を傾げて訊いてきた。 「地元の人間じゃないって、すぐに分かるのですか?」 「そりゃあ、もちろん分かるわよ。水商売に長くいる女の勘ね」 沙織は「フフフ」と笑った。自分で言うのもなんだが、僕だって調査の「勘」は天性のものを持っていると自負しています。沙織さん、貴方には負けません。 「大阪から出張なんです。観光物産会社のサラリーマン。お菓子や饅頭などの食べ物ではなくて、つまりその・・・ほら、手ぬぐいとか、暖簾とか巾着とか・・・それから観光地の名称を書いた提灯なんかもあるでしょ。そんなものを作っているんです」 「出張で営業ですか?」 「そう、売り込み」 「じゃあ、あっちこっちに出張に行かれるのね」 「北は北海道から、南は沖縄まで。これまで行ったことのない都道府県は秋田県だけ」 「秋田って有名な温泉地が多くなかったかしら」 「そうなんだけど、秋田だけは別の担当がいるから、これまでチャンスがなかったんです。秋田美人のお酌で地酒を楽しむことだけが実現していません」 私は思いつくままに喋った。 「そんなにあちこち仕事で行かれたら奥様も大変ね。月に何日くらい出張に出られるの?」 「奥さんは、その・・・ちょっと訳あって別居」 「別居?アハハハ、お客さん面白いわね、訳あってね、そうよね、訳がなければ一緒に暮らしてるものね。アハハハ」 沙織は腹立たしいくらい笑ったが、迂闊に身の上を言ってしまった私はかなり酔っていたのは間違いなかった。 「女将さんは?」 「私は独り身よ」 沙織は「独身」とは言わずに「独り身」と言った。その言葉の響きがとても素敵だと思った。何か飲むように勧ると、「ビールよりも日本酒をいただこうかしら」と沙織は言った。 「ジャンジャン飲んでください。僕も今夜は綺麗なママさんに酔うから」 「おかしな人」 私と沙織はカウンターを挟んで飲んだ。確か沙織の店は午後十時半ごろまでだと、「魚膳」の店内係の女性が言っていたはずだ。 「もうそろそろ閉店の時間じゃないのかな?」 沙織は小さなグラスで冷酒を飲んでいた。 「いいのいいの、私んちはすぐそこだから」 そう言ってカウンターの中から出てきて、外に出していた暖簾を店内に入れた。小さな雨音が聞こえてきた。宮津の夜はいつの間にか雨になっていた。 「ご自宅はこの近くなの?」 「そう、道路を渡ってすぐ前、徒歩三十秒ね。だからいいのよ、遅くなっても」 沙織は気さくに笑いながら答えた。 「静かだね、まだこの時間なのに」 「今日はすごく暑かったけど、まだ夏の観光シーズンが本格的じゃないからね。もう少しすると海水浴客も増えてくるし、夏祭りもあるから少しは賑わうけど、宮津は年々人が減っているのよ」 沙織としんみりと人生の悲哀を語り明かしたい気持ちになるほど静かな夜だった。 「さっき独り身って言っていたけど・・・」 「そう、ひとりよ。寂しいわよね、相方がいないと」 ため息をついたような表情で沙織は言った。 「ママさんのような綺麗な人が、なぜひとり?僕ならママさんのような奥さんがいたら、それこそ二十四時間寝ないで働くよ」 「本当に寝ないで働いてくれるの?」 沙織は冷酒の入ったグラスを持って中から出てきて、私が座っている席からひとつだけ間を置いて座った。着物の襟首のあたりにドキッとするほどの色気が漂っていた。私には真鈴という少女の「恋人?」がいるが、沙織と並んで飲んでいると、真鈴の可憐さが生意気にさえ思えてくるのだった。それはもちろんアルコールの酔いと、沙織のおとなの魅力に惑わされそうになっているからではあったが、それほど彼女は魅力的だった。彼女がウイスキーではなく冷酒を飲んでいるのが不思議だった。ウイスキーグラスを持って「少し愛して、長く愛して」と沙織に言って欲しいと思った。私は完全に酩酊してしまっていた。 「息子がね、ひとりいるのよ」 少しの沈黙のあと、沙織がため息混じりに言った。 「えっ、息子さんが?でもそれじゃご主人とは・・・」 「ご主人様は最初からいないのよ」 沙織は「フフッ」と鼻で自嘲気味に笑いながら、少し投げやりな口調で言って冷酒のグラスを口に運んだ。私は次の言葉の選択に戸惑い、ビールのグラスを何度も口に運んだ。 「昔ね、あなたのように仕事で宮津に来た人がいてね。あなたは出張だけど、その人は何年かの期間を出向でこちらに来たの。神戸にちゃんとした家庭がある人だったのだけど、私がその男の人に惚れてしまったのよ。仕方がないわね」 沙織はいったんカウンターの中に入り、もう一本小さな冷酒の瓶を持って出てきた。今度もウイスキーではなかった。私は彼女に「ウイスキーは飲まないのですか?」と訊いてみた。「なぜ?」と沙織は首を傾げた。 「少し愛して、長〜く愛してって言って欲しいと思ったんですよ」 「アハハハ。面白い人ね、お客さんって」 沙織は不思議そうな顔で私をジッと見たあと、数秒間考えてから声をあげて笑った。そんなに面白いことを言ったつもりはなかったのだが、意外に大笑いだった。 |
| 四十五 |
|---|
|
「初めてのお客さんなのに、込み入った話をしてしまってごめんなさいね。でもお客さん話がしやすいのよね。その飄々とした感じが・・・きっとお客さん女性にモテるでしょ?」 沙織は酔っているふうには見えなかったが、突然わけの分からないことを言いはじめた。私が女性にモテるはずがないではないか。四十歳にもなって何ひとつ構築していないのに、誰がどのような角度から見てもだめな男だ。何かを成し遂げたという自負はこれまでだだの一度もない。たった一ミリさえ社会に貢献したこともなく、誰かを幸せにしたこともない。大学時代から人の世話になり続け、社会に出てからも多くの人に助けられてこれまで生きてきた、どう仕様もない男なのだ。人に迷惑をかけて、人を悲しませ傷つけ続けているのがこれまでの生き様だ。いや待てよ、ひとつだけ感謝してもらえたことがある。それはほかでもない。昨年の熱風のような夏、暴風雨の夜に目の前に現れた真鈴の父を捜すために駆けずり回り、それを成し遂げたことだろうか。 時刻はもう十一時近くになっていた。耳を澄まさないと分からないほどの静かな雨音と、エアコンが唸る音だけが聞こえていた。ふたりとも黙ったまま、私はビールを、彼女は冷酒を飲んでいた。この店だけがどこか遠くの小さな島に存在しているような感覚になった。そんな沈黙の中、ふたりがカウンターにグラスを置くときの「コトリ」という音だけが、ときどき現実に引き戻した。 沙織は話の成り行きでA氏のことを思い出しているのだろうか、しばらく黙ったままだった。私は彼女の誤ったお世辞が発端で、これまでの人生の不甲斐なさに苦虫を噛み潰していた。おそらくふたりの沈黙が十数分続いた。今夜はこのくらいにして明日もう一度来よう。そしてもう少し突っ込んだことを訊いてみよう。そう思ったとき店の電話が鳴った。沙織は立ち上がって電話に出た。 「ちょっと久しぶりに来られたお客さんがね・・・ハイハイ、大丈夫だって。先に寝てなさい。戸締りちゃんとしてね・・・お弁当は朝作るからね・・・ハイハイ」 電話は沙織の息子からのようだった。 「息子からなのよ。ごめんなさいね、気になさらないで。時間の方は大丈夫だから」 電話を切って再び冷酒グラスを手にして沙織は言った。 「さっき言っていた息子さんのお父さんのことだけど、神戸に家庭があるって・・・」 「そうよ、神戸にキチンとした家庭があって、私とはどうにもならないの」 「認知や養育費はもらっているの?」 さりげなく訊いてみた。 「子供がお父さんに会いたいと言ってきたら、そのときは彼を捜して認知してもらうかもね。でもそんなことは戸籍上のことだし、息子が将来結婚を考える人が現れたときに、その相手のご両親が興信所かどこかを使って調べない限り分からないわよね。だから認知なんてどうでもいいのよ。養育費も一切もらっていないけど、最初にそれなりのことをしていただいたから、感謝こそすれ恨んではいないの」 まさか疑ってはいないだろうが、沙織から「興信所」という言葉が出たときに、思わずウッとビールを喉に詰まらせて少し咳き込んでしまった。沙織は子供から電話がかかってきたあともすぐに店じまいに取り掛かろうとはせずに、味わうように冷酒を飲み続けていた。小さなグラスを口元に運ぶたびに、A氏との思い出のシーンを蘇らせているようだった。古井戸の底に沈んでいた記憶を私が無理やり汲み上げてしまったのかも知れない。 「良い人だったのよね、その・・息子の父親ね。浮気心で私と関係したのじゃなくて、本当に私のことを思ってくれたの。ちょっと照れてしまうけど、真面目に愛してくれたのよね。でも奥さんも子供さんもいたらどうにもならないじゃない?仕方がなかったのよ」 私はビールを口に運びながらどう言葉を挟んでよいものか分からず、黙って話を聞いていた。沙織はもっと話を続けたそうだったし、私も店を引き揚げ難い気持ちになっていた。 「生きていくって大変だよなあ。でも立派にお店をやっているのだから、息子さんのお父さんになる男性もきっと安心しているんじゃないかな。たまには連絡があるの?」 「それが、別れてからお互いに一切連絡を取っていないのよ。でもきっと私のことをずっと心配しているに違いないの。連絡を取りたくても我慢しているはずと私は思っているの。だって、私の方も彼に連絡したい、少しだけでも会いたいと思ってもずっと我慢して耐えてきたんだものね。お互いが別れたあとも耐え切ることが、ふたりが決めた約束事なのよ」 沙織は遠くを見るような目で語った。 「いずれ別れることは最初から分かっていたから、彼が出向期間を終えて家族のもとに帰ることになったとき、私は妊娠していたけど彼に何も求めなかったの。最初は中絶して欲しいと言っていたけど、私が絶対に産みたいって譲らなかったの。逆に彼は奥さんと離婚してこちらに来るとまで言ってくれたのだけど、それはルール違反だものね。ただそこまで言ってくれたことで、この恋愛は間違ってはいなかったと思ったの。それでお互い一切連絡を取らないことに耐えていくことが、私たちの関係が間違っていない証なのって話し合って決めたのよ。それから十三年かな、その約束は守られているのよ」 言葉の最後のあたりで沙織は少し「フフッ」と笑いながら言った。そこにはいわゆる「私生児」を育てている母親の陰や後ろめたさは微塵もなく、愛する人の子供と暮らしている「女」の自信のようなものが感じ取られた。時刻は午後十一時をかなり過ぎた。 「すっかりお客さんにプライベートな話をしてしまったわね、ごめんなさい」 沙織は少しだけ赤くなった顔で謝るのだった。 「いえ、ご自身のことを僕のようなこんな一見客に話をしてくれて、ほんとに嬉しいですよ。僕の滅茶苦茶な人生も披露したくなってきたけど、もう遅いからね」 「いいわよ、時間なんて。まだ十一時半じゃないの。ときどき日付が変わっても、お客さんによっては店を開けている日もあるから」 沙織も私も友達と話すような感覚になっていた。そういう気さくな雰囲気を彼女は持っていた。おそらくこの店は繁盛しているに違いない。ツンと気取ったところがなく、話し上手だし訊き上手でもある。料理も悪くないし、料金も良心的、これで繁盛しないわけがない。 「明日の夜また来るかもしれないから、そのときは嫌でなければママさんとその男性との話の続きを訊きたいものだね」 「続きはないわよ。その人とはそれっきりだから」 沙織はカウンター内に戻り、片付けをはじめながら悪戯っぽい顔で言った。 「実家はこの近く?」 「そう、この先の商店街の向こうなの」 「なぜ実家に住まないの?」 「大阪に就職していた弟が結婚して実家に帰ってきて、両親と住んでいるのよ。家は広いけど、そこに私たち親子が同居するのは、気持ちが窮屈だし気を遣うのよ」 沙織はあっさりとした口調で説明した。沙織の現在の暮らしぶりや実家の状況、昔とおそらく変わらないだろうさっぱりした気性など、もうすでにA氏が満足するだけのレポートを書くのに十分だった。 沙織の口から、A氏への恨みに該当する言葉はひとつも出なかった。恋愛に真面目や不真面目があるとすれば、ふたりの恋愛は極めて真面目なものだったのだろう。沙織は相手の家庭を壊してまで愛に生きたくはなかった。自分の幸せは、A氏の妻だけではなく、家族をも不幸にしてしまうことが分かっていたのだ。A氏と別れる際に、お互い連絡を取り合わないことがふたりの関係が純粋だったことを証明することになると考え、ふたりはそれを約束し実行している。恋愛が本物であるほど、その取り決めを守る苦しみはついて回る。今日までふたりはその苦しさを乗り越え、耐えてきた。 沙織は私のような全く利害関係のない客がある日突然やってきて、プライベートな部分を語りだしたことで、自分の身の上話を披露した。でもきっと、普段はこの宮津の常連客や一見客が来たとしても、決してA氏との関係や約束事などは語らないに違いない。大阪から出張で店に来た一見客だから警戒心なく打ち明けたのだろう。沙織は暗さの欠片も感じない堂々とした生き様だと思った。小さな町だから、私生児を産んで育てていることが噂にもなったことだろう。肩身の狭い思いに陥り、辛くてたまらないこともあったかもしれない。いやおそらく、様々な苦しみや嫌な思いの繰り返しだったことだろう。でもそれらを乗り越えたように見えるのは、A氏との愛を信じ続けている沙織の強いこころの証明なのだ。 さて、そろそろ店を退いて宿に帰ろうと思っていたところ、入り口がガラッと開いた。そこにはジャージ姿の丸刈り少年が立っていた。 「どうしたの、あんた。先に寝ていたらいいじゃないの。すみませんお客さん、息子なんですよ」 「こんばんは」 息子は軽く頭を下げて挨拶をした。浅黒い賢そうな顔をした少年は、中学一年生にしては立派な体格だった。 「ちょっと遅いからあと片付けを手伝おうと思って・・・」 「そんなのいいって言ってるでしょ、明日も朝レンでしょうが。帰って早く寝なさい」 息子は野球部に入っているようだった。私はカバンからコンパクトカメラを取り出した。 「ママさん、今夜は良い酒だった。ちょっと悪いが記念に写真を撮ってくれませんか?」 「ああ、いいですよ。こんな店でも楽しんでくれたら私は嬉しいですから」 沙織は洗い物の手を休め、エプロンで手を拭きながら出てきてカメラを受け取った。私はビールグラスを手に持ち、顔の辺りに掲げた。そのポーズを沙織は慎重に撮った。 「今度は僕が撮らせて。ママさん、息子さんとそこに並んで」 息子をママさんの隣に立つように誘導して、一気にシャッターを押した。念のため二枚撮った。息子はキョトンとしながらもピースサインまでしてくれた。A氏が望んだ沙織とふたりの間の息子の写真撮影は、わずか三十秒ほどで成功した。 「ありがとう。また来ます。お元気で」 お勘定を済ませて店を出た。傘を持っていなかった私に、息子は自分が持ってきていた傘を手渡すのだった。このように礼儀正しく素直に育てあげた沙織は立派だ。赤ん坊のころから今日まで、きっと辛く苦しいこともたくさんあっただろう。A氏に連絡を取りたい、力を借りたい、そばにいて欲しいと何度も思ったはずである。失って初めて相手の存在の大きさが分かったとしても、守らなければならない約束に苦しんだに違いない。だが、沙織はA氏との約束を守り通した。関係が本物だと、交わされた約束は必ず果たされ、そしていつまでも忘れない。A氏も同様だった。仮にA氏が沙織のことや息子のことを思わない、こころない人間だとしたら、今回のような調査を依頼してこなかっただろう。 私は静かに降り続ける小雨の中、宿に向かってゆっくり歩いた。街はすべての家々や商店の明かりが消えてしまっていた。ところどころに立つ街灯だけが心寂しく舗道を微かに照らしていた。夜になると本当に寂しい街だ。このような街でA氏と別れたあと、一人で子供を育てて商売を続けながら生きてきた沙織は凄いなと、素直に思った。 ところがそのとき、なぜかうしろから沙織が駆けて来た。「お客さん、ちょっと待って」と言いながら小走りに近づいてきた。忘れ物などないはずなのだがどうしたのだろう。 「これ、宮津名産の黒ちくわとかまぼこ。少しだけど持って帰って」 沙織は持っていたひとつの袋を僕に差し出した。 「どうしてこんなものまで・・・」 「いいのよ、いろいろと話を聞いてくれてありがとう。それから、あの人によろしく言っておいてね。私はなんとか元気にやっているからって。じゃあね、ありがとう」 沙織はそう言って立ち去った。礼を言う間もなく、身を翻して行ってしまった。私は呆然と佇んだ。沙織は気づいていた。なぜなんだ?私のような優秀な探偵がどういうわけか感付かれてしまったようだ。道理でいろいろと喋ってくれたわけだ。普通、初対面の客に、あんなには次々とプライベートな事柄を話さない。どうしてそんなことに気がつかなかったのだろう。きっと沙織は途中から、私がA氏から頼まれて様子を見に来たと気づいたのだろう。しかし沙織さん、なぜなんです? 真鈴も沙織もいったいどうしたっていうんだ?なぜ君たちは調査に気づき、目的を見破ることができたんだ?私は沙織のうしろ姿が見えなくなるまで見届けた。そしてそれから宿の方向へ、まるで戦い疲れた兵士のようにふらつきながら歩いた。途中で雨は降り止んだ。 「僕も独特の勘を持っているが、沙織さん、あなたの素晴らしい勘には参りました」 私は濃紺の夜空に向かって声に出して呟いた。二時間半ほどの接触で、ふたりの関係が細部まで理解できたような気がした。この先、ふたりはおそらく連絡を取り合わず、相手の思いを抱き続けながら生きていくことだろう。連絡を取りたい、今すぐにでも会いたい、でも必死で耐える。そういう切なさが人生にはついて回るものなのかも知れない。 翌日、宿をチェックアウトしたあと、昨夜借りた沙織の息子の傘を店の入り口にそっと立てかけ、少し名残り惜しい気持ちで宮津をあとにした。 |
| 四十六 |
|---|
|
予定より早く出張を終えて兎我野町の部屋に戻った。どういうわけか、久しぶりに帰ってきたような感覚になり、まるでここで生まれ育ったような錯覚にも陥った。事務所の真ん中に置いているテーブルと向かい合った二つの椅子が私の帰りを待っていた。それ以外に私を待ってくれている人や物は存在しなかった。 宮津の調査の余韻がこころの中にどっかりと腰を下ろしていた。満足のいく仕事だったが、結果的には沙織に気づかれてしまった。でも彼女は昨夜のことを決して口外するようなことはないだろうと、根拠もなく思った。沙織はひたむきに生きている素晴らしい女性だった。真鈴も、そして関さんも有希子も、私の周りの女性たちは皆一生懸命生きている。自分だけが出鱈目に生きているような気がして、帰って来て早々に自己嫌悪に陥ってしまった。ふと見ると、ベッド脇の電話の留守番メッセージランプが点滅していた。 「真鈴だよ、おかえりなさい。岡田さん、寂しいのは分かるけど、私がいるんだから、元気出してね」 もう一件も女性からのものだった。 「お久しぶり、関です。憶えてくれていますか?七月の二十日から二十三日まで関西方面を旅行します。京都と神戸と大阪に一泊ずつする予定。お忙しくなければお会いしたいです。また旅行の少し前に電話してみますね」 穴吹療育園の関さんからのメッセージだった。私はこの二件のメッセージは、よく考えてみるとつながりがあると思った。関さんは真鈴の父の居場所が判明したキーパーソンに間違いなかった。沢井家の菩提寺を訪ねたことから始まった調査は、穴吹療育園に父の姉が入院していることが判明するまで進展したのだが、訪ねてみるとそこには父・圭一の姿はなく、手がかりを得られないままうなだれて大阪に帰った。だが数日後、療育園で私を案内し、圭一の姉・悦子と面会させてくれた関さんから電話が入ったのだった。まるで天使の翼を背中につけて、電話口まで翔けてきたかのように息を切らせながら真鈴の父の情報を教えてくれた関さん。真鈴と関さんは、求める側と与える側とでひとつの線上にあった。 関さんが七月二十日に関西に来る。私はしばらく考えてから、着信記録の残っていた番号にかけてみた。電話番号は穴吹療育園の受け付け番号だった。応対には関さんが出た。 「電話をくれてありがとう。しばらく京都の日本海側に出張していたものですから」 「いえ」 「今、話せないですよね。仕事中だから」 「そうですね。では夜八時以降に自宅へお願いします。電話番号は・・・」 彼女が教えてくれた電話番号を控えて、じゃあと言って電話を切った。受話器からカフェオレの香りが漂ってきそうな気がした。私はミルクをたっぷり入れたインスタントコーヒーを飲みながら、兎我野町の街並みを眺めた。多くの働く人々を抱え込んだビル群、様々な人生をも抱え込んだビル群を眺めながら、私は真鈴にLineを飛ばした。時刻は午後二時前。いつもならすぐに反応があるのだが、十数分経ってもLineも電話もなかった。少しためらいながらも電話をかけてみた。 「はい」 「岡田だけど、メッセージありがとう」 「ごめんなさい、今ちょっとダメなの。あとでかける」 真鈴はそう言って電話を切った。少し慌てた様子だった。ベッドでしばらく横になって疲れを取ってから午後六時過ぎに「安曇野」を覗いた。真鈴は「あとでかけるから」と言ったきり電話をかけてこなかった。もちろん心配だが、あまり彼女のことを考えると胸が苦しくなるので、意識的に振り払った。 「岡田さんって、もう何年もこの店に来てくれているのだけど、いつも久しぶりのような気がするのよね。どうしていらっしゃったの?」 何かを思い出したような表情で女将さんが訊いてきた。確かにそうなのだ。私は二週間に一度程度しか顔を出さないが、街金融業時代から数えると、もうかれこれ十年近くもこの店に通っているのだ。女将さんの美貌が通い続けている理由のひとつではあるが、美貌や料理の美味しさだけでなく、彼女のちょっとすっ呆けた意外性というか、天然のような性格が好きなのだ。 「実は日本海側の宮津という町で、沙織という女性と飲んでたんです」 「アハハハ、岡田さんっていつも変なことを真顔で言うから可笑しわね」 女将さんは意外に大きな声を出して笑った。そんなに大笑いしなくてもと思ったが、説明するのが面倒なので黙った。そのとき真鈴からLineが飛んできた。 「ごめんなさい、ちょっといろいろあって電話できなかったの」 メッセージと一緒にウサギがしょげているスタンプが送られてきた。心配なので電話をかけた。 「どうしたんだ?」 「ごめんなさい、すぐに連絡できなくて」 「まさかまた変なことしていないだろうな?」 「何よ、変なことって」 「変なことって、あれだよ。その・・・」 「光一、しつこいよ、本当に。お父さんも帰ってきてるんだから、変なことするわけないじゃない。寂しいって言うから心配していたのに、まだそんなこと言うんだね。ガックリだよ。相談したいことがあったのに、私のこと、信じないならもういい!」 スマホがプツンと音を立てて切れた。私の言い方が悪かったのかも知れないが、彼女はいつも短気過ぎる。それに二十歳以上も年上の私に「光一!」だって?いったいどうしたっていうんだ? 店に戻ると女将さんが「あら、どうされたの。難しい顔をして」と言った。「少女と喧嘩してしまいました」と私は返事した。今度は女将さんだけでなく、常連の中年の男性客ふたりも「アハハハ」と大笑いした。笑いごとではなかった。 穴吹療育園の関さんは、午後八時以降に電話して欲しいと言っていた。私は七時半を過ぎて「とうりゃんせ」を出た。短時間に生ビールを三杯と焼酎の水割りを四杯ほどを勢いよく飲んだので、すっかり酔っ払ってしまった。女将さんが「あら、もうお帰り?」とお勘定の際に言った。 「今から生意気な少女と大人のレディと、ダブルヘッダーで囁かないといけないんです」 店は爆笑に包まれていた。その爆笑を背に店を出、夏の夜の大阪市北区兎我野町をふらつきながら歩いた。真っ黒な大きな雲が新御堂筋の高架を鷲づかみにしていた。雲のうしろには鮮やかな月が遠慮がちに浮かんでいた。雲なんかよりも月のほうがもっと堂々とするべきだ。暗闇なんかに負けてはいけないのだ。 |
| 四十七 |
|---|
|
部屋に戻ると案の定、留守番電話のランプが点滅していた。 「何よ、さっきの言い方。私だっていろいろあるんだからね。知らないから!」 真鈴は意味不明なことをメッセージに残していた。「私だっていろいろあるんだからね」ってどういう意味なんだ。すぐに話をしたかったが、関さんとの約束を優先した。部屋の中がグルグル回っているような感覚に襲われながら電話をかけた。ベッドに腰をかけて身体を安定させようとするのだが、まるで小舟に乗って宮津湾を漂っているように揺れた。関さんは待っていたかのようにすぐに電話に出た。 「昼間せっかく電話をもらったのにごめんなさい。近くに人が大勢いたものだから」 「いえ、気にしないで下さい。それよりまたこちらに来られるんですね」 「そう。今回はかなり開いてしまったの。前回の旅行が去年の九月だったから、もう十ヶ月も山の中から出ていないのよ。春先に体調を崩して寝込んでしまったこともあって、なかなか旅行に出られなくて」 「それは可哀相に。でもようやく山から下りるんですね」 「そう、山から下りるの」 「空を翔けてこちらに来て下さい。僕はいつも窓の外を眺めて待ってますから」 「ウフフフ」と関さんは笑った。彼女の声を聞いていると、こころが身体の中から浮遊して、空を翔けていってしまうような不思議な感覚になった。揺れ続ける部屋全体がメリーゴーランドみたいだった。ベッドが回転木馬のようだなと思った。 「関さん、あなたは今、カフェオレを飲んでいるんじゃないですか?」 「えっ、どうして?」 「いや、何でもないんです」 受話器からカフェオレの甘く香ばしい匂いが漂ってきた。でもそれは心地良い酔いからの錯覚だった。 「二十日は午後一時に新神戸駅に着いて、それから元町にあるホテルにチェックインするの。もし岡田さんが都合よければ大阪まで出るわ」 「いえ、神戸まで僕が出向きます。どこのホテルなんですか?」 「ポートサイドホテルなの。波止場の近くにあるらしいのだけど、神戸は初めてだから少し不安だわ。岡田さんに来ていただければ嬉しいけど、お忙しくないかしら?」 「大丈夫。すべてを投げ打って駅まで迎えに行きます」 関さんは再び「ウフフ」と電話の向こうで笑った。 「ごめんなさい。またお付き合いさせてしまうことになりそうで」 関さんは申し訳なさそうに言った。 「関さんが翔けて来てくれることを、ずっと待ちわびていました」 「相変わらず面白いことを言うのね、岡田さんって」 関さんは昨年の九月に私のマンションを突然訪ねてきた。真鈴の父の所在を追って穴吹療育園を訪ねた際に会ったことがあるだけなのに、連絡もなく訪ねて来たことが不思議だった。でも現実に関さんは、昨年の九月下旬の雨降る土曜の昼下がり、背中に天使の翼をつけて、マンションのエレベータ前にしゃがみこんでいた。天使の翼は明らかに錯覚だったとしても、真鈴の父の所在判明に最も重要な役割だった関さんがやって来たのは事実だった。まるで空を翔けてきたかのように突然目の前に現れた関さん。彼女と私と真鈴はひとつの線上でつながっていた。その線上に妻の有希子は存在しない。 関さんと二十日の約束を交わして電話を切ったあと、少しためらいながら真鈴に電話をかけてみた。でも彼女は出なかった。「私だっていろいろあるんだからね」の意味を知りたかった。一度そう思うと、一刻も早く言葉の意味を確かめたかった。確か「相談したいことがあったのに」とも言っていた。何を相談したいと言うのだ。私は何度も電話をかけLineメッセージも送った。「どうしたんだ?Lineメッセージの返信も出来ないのか?」と執拗に送った。名探偵コナンが慌てている表情のスタンプまで送った。でも真鈴から応答はなかった。あきらめてベッドに仰向けに寝て目を閉じると、アルコールが体内の隅々まで染みわたり、天井が高速でグルグルと回りはじめた。ベッドに乗ったままどこかへ飛んでいきそうな感覚になった。不意に誰かが頬を撫ぜた。目を開けてみると有希子の顔があった。なぜ有希子がベッドの横に立っているのか分からなかった。 「有希子、どうした?」 有希子は問いには答えずジッと私を見下ろしていた。長い長い沈黙が続いた。そして一分ほどが経って、私の頬に涙の雫が落ちた。一滴・・・二滴・・・そして三滴。 「光一、私はもうあなたの手の届かないところへ行くわ。本当にサヨナラね」 有希子は呟いた。 「なぜサヨナラなんだ?」 でも有希子は何も言わず、冷たい手で私の頬を撫ぜ続けるだけだった。 「どうしてサヨナラって言うんだ、有希子!」 涙が溢れ出た。涙は頬に落ちてくる有希子の涙の雫と一緒に耳元に流れ落ちた。 「私はあなたともう一度暮らしたかった。光一の意気地なし。両親の反対なんて蹴散らしてくれる勇気を持ちなさい。でないと、また女の人を泣かせるわよ。しっかりしなさい」 有希子は泣きながら言った。私の顔はふたりの涙でびしょ濡れになった。こころの中も悲しみでびしょ濡れになってしまった。 「サヨナラ、大好きな光一」 有希子はそう言って、私の唇に濡れた冷たい唇を合わせた。懐かしいジャスミンの香りが漂った。そして背を向けた。 「有希子、ちょっと待ってくれ」 手を伸ばし、叫ぼうとした。でも声が出なかった。有希子は瞬時にいなくなってしまった。そのときスマホがブーブーと音をたてて震えた。 「真鈴か、よかった」 「どうしたの?声が震えているよ」 「夢を見ていたんだ」 「お風呂に入っていたの。どうしたの、この着信とLine」 「真鈴が言ったことが気になって、すごく焦ったんだ」 「変な人」 「変じゃない。私だっていろいろあるって、知らないからって、どういうことなんだ?」 「今度会ったときに相談する。今は言えないから」 「そんな言い方したら、相談されるまでこっちとしてはずっと気になるじゃないか」 「ごめんなさい。でも電話で話すことじゃないと思ったから」 「知らないからって言ってただろ。あの言葉の意味は?」 「だって、変なことしていないだろうなって、まだ私を信じていないようなことを言うから、それがショックであんな言い方してしまったの。ごめんなさい」 「そうか・・・それは僕が悪かった。真鈴が電話で戸惑ったような話し方をすると、どうも前のことがトラウマみたいに心配になるんだ」 「大丈夫だから、光一。私はもう環境が整っているんだから」 「何だって?」 「ううん、いいの」 「相談したいことは特に急がないんだな?」 「うん、だから今度ゆっくり話をしたいの。ごめんね、気にしてくれてありがとう」 「いいよ、お互い様だからな。でも、光一って僕のことを呼んでくれるんだな」 「だめ?」 「いや、そのほうが嬉しいよ」 七月いっぱいは予備校の夏期講習が忙しくてゆっくり会えないと真鈴は言った。八月になれば会おうと約束して電話を切った。電話を切るときに「私、こころはもうおとなだよ」とポツンと言った。「分かってるよ」と私は返事した。でも、そのあと本当はまだ分かっていないような気がした。 |
| 四十八 |
|---|
|
関さんが神戸にやって来た。約束の午後一時より少し早めに新神戸駅に到着し、改札口近くで待った。でも彼女はどうして再び私と会おうと思ったのだろう。 昨年の九月、彼女は山を下り谷を越え、瀬戸内海を渡り山陽道を東へ突き進み、関西へやって来た。真鈴の父捜しの過程で立ち寄った穴吹療育園で手渡した一枚の名刺を持って、関さんは京都を観光で訪ねた帰りに私のもとに予告もなく現れた。 私は関さんの突然の来襲に驚きながらも、最も大阪らしい場所と思っている大阪の街を案内した。通天閣からジャンジャン横丁などを回り、動物園を横に見て天王寺公園を突き抜けて戻ってきた。それから彼女が予約していたホテルまで送って行ったあと近くで飲んだ。ふたりとも酔っ払っていて、そのまま一気に深い関係に突入するかと思ったのだが、彼女はあっけなく私の前から消えた。私はその夜、人生の辛苦を舐めながら、うなだれて部屋まで帰ったことを思い出す。 その日からしばらく、本当のことを言うと関さんのことを忘れていた。彼女が消えてしまったあと、妻の有希子の癌が悪化したり落ち着いたり、そして相変わらず別居生活を余儀なくされ、冬の寒さが身体の隅々からこころの中まで染み込んできた。痛みのような辛さを紛らわせるために、依頼された案件はすべて請けて仕事に没頭し、東奔西走する探偵になった。だから年が明けてからもずっと、関さんのことを忘れていたのだ。 その関さんがやって来た。彼女は改札口を出て恥ずかしそうな顔で近づいてきた。 「こんにちは。迎えに来てくれてありがとう」 関さんは水色のTシャツに濃紺のジーンズを身に着け、なぜか迷彩色のキャップをかぶっていた。彼女のとてもラフな服装が意外だった。 「ともかくホテルにチェックインしておきましょう」 神戸駅からタクシーでポートサイドホテルへ向かった。渋滞もなく十数分で到着し、少し早いがチェックインを済ませた。関さんはキャリーの付いた小さなバッグを部屋に置き、しばらくして薄茶色の小さなショルダーバッグを引っ掛けてフロントに出てきた。 私は目の前のメリケン波止場や神戸ポートタワーなどを訪ねてみようと彼女を誘導した。この辺りはよく知っている。昔勤めていた金融会社の神戸営業所は元町の大丸百貨店の西側、南京町の入り口のビルに事務所があったからだ。 関さんは手をつなぐようなことはなかったが、寄り添って肩を並べて歩いた。関さんはときどき汗を拭きながら、鮮やかな風景画のような港の景色や海の青さに驚いていた。彼女は昨年よりずいぶんと痩せたように見えた。腕や身体全体が一回り細くなったように私には思えた。 「関さん、去年の九月のときよりずいぶん痩せたんじゃないですか?」 昨年七月に穴吹療育園を訪ねたときも、九月に彼女が大阪に来てくれたときも、こんなにも痩せてはいなかった。贅肉のないタイトな身体つきだったが、今日みたいに折れそうなほど腕が細くなかったし、顔も心持ち小さくなったように見えた。 「少しね。そうね、三キロちょっと位かな、体重が減ったの。電話で言ったように春に少し体調が悪い時期が続いて、あまり食べられなかったからかも知れない」 迷彩色の帽子がちょっと悪戯っ子みたいな今日の関さんだったが、身体が細くなったからか、あまり元気がないように見えた。 私たちはメリケン波止場を離れて、神戸港を見ながらハーバーランドのほうへ歩いた。猛烈な暑さで汗が首筋を流れ落ちた。暑さには辟易したが、彼女と並んで歩く神戸ハーバーランドを楽しんだ。大阪を案内したときにも感じたが、彼女と過ごす時間が心地良いのだ。言葉をあまり交わさなくても、気遣う気持が生まれない、時間が経っても疲れない感覚とでも言おうか、まるで幼少時のころから知っていて、一緒にいるとホッと安心するような感覚だった。 真鈴と一緒にいるときは、彼女の仕草や言葉に自然と敏感になり気遣う。最初のころのように腫れ物に触るような気遣いはしなくなったが、今でも彼女の言動にいつも敏感になる。でも関さんとの時間は、彼女のすべてを包み込みたくなるような気持ちになるのだった。その快適さを私は楽しんだ。 神戸ハーバーランドは平成七年の阪神淡路大震災で営業休止を余儀なくされたが、その年のうちに阪急やダイエーをはじめ、ほとんどの商業施設が営業を再開した。さらに暮れには「モザイク」という名称の大規模商業パークもオープンするなど震災後の復興は急速度で行われた。 「すごい、映画館もある。私、こんな大きなショッピングセンターは見たことがないわ」 私たちはハーバーランド内の「モザイク」に入った。徳島にはない大きな施設に、関さんは大きな瞳をクルクル回して驚いていた。彼女は驚くときも少し恥ずかしそうな表情を見せた。彼女のすべての表情には、恥ずかしさや気弱さが含まれていた。 午後三時を過ぎて、昼食をとっていなかったので早めの夕食にした。すでに夏休みに入っている学校も多いのか、グルメフロアはこの時間でもかなりの客で混み合っていた。私たちは数ある店の中で「中納言」を選んだ。 「僕が住んでいる近くの商店街に、オーナーは変な人だけどエビフライがとても美味いプランタンという店があるんです」 メリケン波止場からハーバーランドへ歩く途中の会話の中で、関さんは私の言葉に反応して、伊勢海老を食べてみたいとリクエストしたからだった。中納言は有名な店で、神戸勤務のときに元町のプラザホテル店を訪れたことがあるが、プランタンのエビフライ定食と、中納言の伊勢海老の中程度のコースの値段とは、文字通り桁が違っていた。 「伊勢海老なんて私、初めて」 関さんは目を輝かせて喜んだ。私はメニューの値段に目が点になりそうになった。 「やっぱり山の幸より海の幸のほうが、美味しいものがずっと多いような気がするね」 「でも山にだって美味しいものがたくさんあるのよ。例えばきのこだけど、岡田さんが知らない種類もいっぱいあると思うの。穴吹には地元でしか食べないきのこがあるのよ」 関さんは口をモグモグさせていたものを飲み込んでから意見した。穴吹川は四国で最も水質が良い、いわゆる清流だということや、地元で栽培されるシイタケは大きくて肉厚だということなどを、彼女は少しムキになって説明した。私はその主張に素直に頷いた。 すっかり満足して中納言を出てから、私たちは岸壁の階段に腰を下ろした。情熱の太陽はまだ十五度位の位置にしぶとく粘っていた。目の前の海の向こうに赤いポートタワーがそそり立っていた。関さんは海を眺め続けていた。穴吹町には海がないから、旅行中はしっかりと目に焼き付けておこうとしているのだろうと思った。しばらく神戸の海を眺めながらゆっくりと歩いた。 「地上に降りてきたらホッとしますか?」 冗談のつもりで訊いてみた。情熱を放出し疲れて、本日の予定をほぼ終了した太陽が遠く地平線に沈みはじめていた。綺麗な光景だった。関さんはおそらく誰が見ても素敵な女性だ。その彼女と肩を並べて夏の夕陽を黙って眺めている私は、もしかすれば人が羨む幸せな男なのかも知れないなと思った。 「そうね・・・ホッとするけど、旅行中も職場のことが頭から離れないのよね。自分が嫌になるの。あっさり旅行を楽しめばいいのだけど、それができないのよ。私は事務職だから、介護をする職員さんたちに比べるとそんなに大変じゃないんだけど、ときにはお風呂に入れる介護をサポートしたり、緊急患者を運ぶのを手伝ったりね、いろいろするのよ。そういう大変な職場を数日離れただけで、仕事のことが気になって旅行を楽しめないの。私がいなくったって療育園では何の影響もないんだけど、性分っていうのかしら」 「分かります、その気持ち」と私は頷いた。関さんは「フフッ」と微笑んだ。 「私はいろいろ余計なことを考えすぎなのかも知れない」 関さんは自分に言い聞かせるように呟き、目の前の青い海を、目を細めて眺めていた。 「穴吹療育園を訪れたとき、あのような山奥にすごく大きな施設があることに驚きましたね。本当にビックリだった。でも、あなたが広い事務室の奥から翔けるように受付にきてくれたことがもっと驚きました」 「どうして?」 「まるで山の妖精が翔けつけてくれたような気がしました」 「岡田さんって、相変わらずおかしいのね」 「でもそれは本当だよ。あなたはキーパーソンなんだから、真鈴や僕にとっては」 「えっ?」 「いえ、何でもないんです」 関さんはもう一度「ウフフ」と笑った。少し恥ずかしそうに笑う関さんは、きっと穴吹町で一番笑顔が素敵な女性に違いない。夕陽が沈み、太陽は明日への休息に入った。関さんと私はポートサイドホテルへ向かった。 |