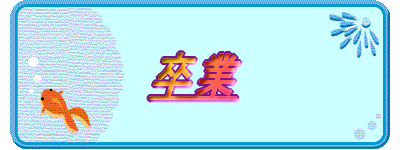
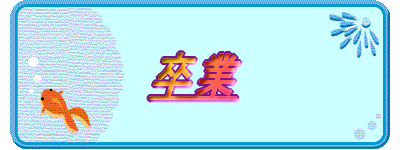
| 二十五 |
|---|
|
穴吹療育園を訪れた三日後、私は真鈴と扇町公園にいた。この日、昼過ぎに「今から会いたい」とLineが飛んできた。「学校はどうしたんだ?」と訊くと、「今日は一学期の終業式だよ。今、学校を出たところ」と、ウサギのピースマークと一緒に返信が届いた。 新たな調査案件の予定を組んでいただけだったので、「いいよ」と了解した。七月もそろそろ終わりだ。彼女に捕まってから三ヶ月があっという間に過ぎ去ろうとしていた。 「お父さん、どこにいるんだろう」 真鈴は公園の石コロを蹴ってポツンと呟いた。白のミニスカートと淡いピンクのポロシャツがよく似合っていた。私たちはアイスを買って、木陰の芝生に座った。 「どこかで真鈴のことを毎日思っているよ」 「そうかなあ」 容赦なく照りつける太陽を眩しそうに見ながら「体育座り」に足を揃えた。ミニスカートがさらに上にずれて眩しい太ももが露わになった。 「それより真鈴、今度から僕と会うときは、そんな短いスカートはやめなさい」 私は前を向いたまま言った。 「えっ?」 私の言葉がすぐに分からない様子だったが、「なんだ、変な人」と言いながら両手でスカートの裾を下に引っ張った。 「こんなのちっとも短くないよ。今の女子高生って、もっとこんなところまでの短いスカートを履いてるんだよ」 真鈴はスカートの裾を足の付け根に近い位置まで上げた。この光景を公園内の人が見たなら、きっと警察に通報するだろうなと思った。 「おとなをからかうんじゃないよ、まったく。それより今年の九月のお彼岸に丸亀のお寺でお父さんを待つかな、それとも住職さんにお願いしておくかな。お父さんが現れたらその場からすぐに電話をくれるようにって」 真鈴は黙っていた。 「でもそんな簡単なことじゃないからなあ」 そんなことでは片付かない。大切なことは、真鈴の父が自分の意思で家に戻ってくることだ。戻る前に父のほうから彼女に連絡することが大切なのだ。 「ごめんなさい、いろいろと」 「少し時間をくれるかな、方法を考えてみるから」 「ううん、岡田さんには本当に感謝しているの。心の支えにもなってくれているから。でもどうして私にこんなに親切にしてくれるの?何のメリットもないのに」 真鈴は首を数回左右に振りながら言った。 「メリット?メリットはあるよ。素敵な女子高生とデートできるんだから」 「デート?」 「デートだろ、こうして公園で一緒にアイスを食べてる」 「変な人」 真鈴は小さくため息をついた。 「いつも食事はどうしてるんだ?」 「チーンだよ」 「は?」 「だから、コンビニ弁当とかを買って、電子レンジでチーンするの」 「若い女の子が、そんなんじゃだめだな。ちゃんと料理しないと」 「フン、偉そうに言って、岡田さんだって外食ばっかじゃない?」 公園を出て、マンションへの途中にあるスーパーで真鈴に食材をいろいろ買ってやった。「料理を作れって言うのね」と、最初は不服そうな顔をしていたが、作った料理で自信作を持ってきてくれるらしく、「作れって言うのなら、ちゃんと味見してよね」と、結局、彼女の料理教室に関わることになった。 真鈴と別れて部屋に戻ると、電話の留守番メッセージランプが点滅していた。普段、自宅の電話に留守電を残すのはT社の部長かA社の社長だ。また急ぎの案件かと思って、私は荒っぽく再生ボタンを押した。 「関です、先日は遠いところを沢井様のお見舞いにお越しくださってありがとうございました。お伝えしたいことがあって電話しました。また夕方か夜にかけなおします」 メッセージをくれていた関という女性が、先日の穴吹療育園の人だと分かるのに十数秒かかった。西川医師に差し出した私の名刺を、関さんに手渡していた光景を思い出した。 夕方までの時間が待ち遠しかった。夕方とは何時あたりを指すのだろうと、国語辞典で調べたりもした。辞書には日没時刻の前後一時間と定義されていた。私は三重県の調査案件について、現場の地図やルートを確認しながらも全く頭に入らず、関さんからの電話を待ち続けた。でも陽はとっくに沈んでいるのに、電話は午後七時を過ぎてもかかってこなかった。私はインスタントコーヒーを何杯も飲みながら待った。そしてようやく午後八時前になって電話が鳴った。 「関です。憶えていらっしゃいますか?」 「電話を待っていました。もちろん憶えています」 「今、少し話をしても大丈夫でしょうか?」 関さんの声は、遠くから急いで駆けて来たみたいに少し息が乱れているようだった。多分電話の向こうで右手を胸に当てて呼吸を整えているに違いないと思った。 「僕は何時間でも大丈夫ですよ。電話代がかかるからこちらからかけます」 「いいの。今夜は当直なんです。今は休憩時間だし、会社の電話だから大丈夫。昼間自宅から電話してみたのだけど、お留守だったから」 「すみません、公園でアイスを食べていたものですから」 「えっ?」 「いえ、何でもありません。ところでこの前は突然訪ねたのに、いろいろとありがとう」 ようやく落ち着いた様子の関さんに私は礼を言った。関さんは「いいえ」と短く答えた。 「岡田さん、西川先生には内緒にして下さい。岡田さんは多分、沢井さんの奥様から依頼されてお越しになったのですよね?ずっと長くご家族に行方を教えずにいるのですもの」 関さんは切り出した。私はとりあえず「はい」と返答した。 「実はここで前に働いていた女性と沢井さんが親しくなって、それはもうずいぶん昔の話で、私がこの施設に就職する前からのことらしいのです。私が勤め始めたときにはすでに沢井さんがお姉さんを、つまり悦子さんの様子を見に来られるたびに、その女性の家に泊まって帰るようなお付き合いでしたから。記憶にあるのは療育園の裏山にその年の桜が咲きはじめたころでした。沢井さんがここにいつもより長くいらっしゃって、多分十日以上・・・それからその女性職員が急に退職して、ふたりでここを出ていかれました。突然いなくなったわけではないんですよ。キチンと退職手続きをして引っ越していかれましたから」 関さんは、記憶を思い起こすように、言葉を選びながら話をして、そして少し黙った。 「それで、あなたはおふたりの現在の居場所をご存知なのですか?」 「はい」と関さんは答えた。受話器を持ちながら頷いている様子が分かる「はい」だった。 「その女性が辞められてからも、暑中見舞いや年賀状が療育園に届いていました。でも、昨年も今年も届いた様子はなかったから、今もまだそこにいらっしゃるかどうかは分かりません。ただ昨年の秋にも悦子さんをお見舞いに来られています」 「関さん、私におふたりの居場所を、今はもういらっしゃらないかも知れませんが、その場所を教えていただけませんか?」 「霧島温泉です」 「えっ?」 「鹿児島県の霧島温泉というところです。そこから年賀状や暑中見舞いが届いていました」 私は気持が昂った。真鈴の悲しげな表情が頭をよぎった。 「霧島温泉に住んでいらっしゃるのでしょうか?」 「そう、霧島温泉にある湯治温泉で、旅館の名前は田丸本館。確かそういう名前でした」 私は慌ててメモをとった。関さんはここで大きなため息を一度ついた。受話器から彼女の吐息がカフェオレの香りとともに流れてきそうな深い吐息だった。 |
| 二十六 |
|---|
|
「このこと、本当に内緒にしてくださいね。西川先生も知らないことなの。私も森さんみたいに、誰かにここから連れ出して欲しいわ。この施設でずっと働いていると、正直言って気が滅入るの。仕事は嫌いじゃないのよ、望んでここに就職したのだから。ただ、こういう山の中でしょ、気持ちが塞いでしまうときがあるのよ」 「森さんというのはその・・・沢井氏と一緒に療育園を出て行った女性職員の名前ですか?」 「そう、森京子さん。今はもう四十歳くらいになっているはず」 関さんはそう言ってもう一度、今度は軽くため息をついた。 「私、もう仕事に戻らなくちゃ。沢井さんとお会いできればいいですね」 彼女は電話を切ろうとした。 「なぜ、鹿児島、つまり霧島温泉に行かれたのでしょうか?」 私は最後に訊いた。 「森さんの実家が鹿児島だからです」 関さんは答えた。そして「岡田さん、また電話してもいいですか?」と言った。 「いつでも電話して下さい。スマホにいただけたらすぐに分かります。電話番号は・・・」 スマホの電話番号を伝えた。 関さんは電話を切った。関さんの声は「空を翔る少女」のように透明で繊細だった。そして素晴らしい情報を提供してくれた。私は一度大きく深呼吸をした。 その週の土曜日、有希子が連絡もなく突然やって来た。私は地図や時刻表や手帳をテーブルに広げて、鹿児島へ行く準備をしていた。三重の仕事が終われば鹿児島に行く予定だった。 「また出張?」 有希子はハンカチで汗を拭いて私の前に座った。白地に水玉模様のブラウスがよく似合っていて、正面から見ると、知り合ったころに比べてずいぶん綺麗になった気がした。 「どうしたの?私の顔をジッと見て」 有希子はコーラを二つのグラスに注いで、一つをこちらに差し出しながら言った。 「いや、知り合ったころに比べてすごく綺麗になったと思ってね」 私は正直に答えた。「フン」といった表情をして彼女はコーラを飲んだ。 「女盛りなんやから、少しは女っぽくなるわ」 「いつもいきなり来るんだな」 「急に来たら都合悪いことでもあるの?」 「いや、別に何もないけど、いつもビックリするからね。お父さんが様子を見て来いって言うんだろ?」 「そんなんじゃなくて、あなたに会いたいと思うときもあるのよ」 私は椅子から立ち上がり、有希子をきつく抱きしめた。 「光一、それが終わったらプールへ行こうよ。スパワールドっていうのが天王寺にあって、プールも温泉も遊園地もあるらしいから」 スパワールドは地下深くから天然の温泉が沸き出ていて、「世界の大浴場」をキャッチフレーズにして人気があるのは知っていた。 「分かった。そうしよう」 この日、私は久しぶりに遊んだ。有希子は鮮やかなグリーンの水着を持ってきていて、それがよく似合っていた。私たちはプールやジャグジーでふざけ合い、人が見ていないところでキスをしたり、まるで青臭い若者のようにじゃれ合った。 プールから出て別々になって、ゆっくりと温泉に浸かった。鹿児島の霧島温泉と関さんが言っていたが、真鈴の父はそんなところでいったいどんな暮らしをしているのだろうと想像してみた。でも行ってみないことには分からないので考えるのをやめた。真鈴には今夜知らせてやろうと思った。 スパワールドから帰って来たのが午後七時を過ぎていた。プールではしゃぎすぎて少し疲れていたが、有希子は「久しぶりだからエッチしよう」と言った。意外な言葉に私は驚いたが、「人は変化し、そして進化する」という誰かの言葉が頭に浮かんだ。別居して四か月ほどになるが、これまでとは違った有希子の反応に戸惑ってしまうほどだった。 有希子は疲れも見せずに帰った。彼女が帰ったあと、私は真鈴に「遅いけど電話してもいいかな?」とLineを飛ばした。もう時刻は午後九時を過ぎていた。十数秒後、スマホに電話がかかってきた。 「まだ九時過ぎだよ、子供じゃないんだからいつでも電話して」 「今、何してるんだ?」 「さっきまで勉強していたの。でも終わった」 「こっちに来ないか?」 「だからぁ、嫌だって。女の子だよ」 「頑固だな、まったく。ともかく今週中に鹿児島へ行くことになったよ。おそらく明後日の夜に大阪南港からカーフェリーで向かうことになると思う」 「仕事?」 「お父さんが鹿児島にいるかも知れないんだ。だからちょっと行って来る。帰って来たらすぐにまた連絡するからね」 「分かった。車の運転に気をつけてね」 「うん、ありがとう」 「岡田さん」 「うん?」 「岡田さんのこと・・・私、好きよ」 真鈴はそう言ってからすぐに電話を切った。私はスマホを握りしめたまま一分間ほど呆然とした。君は何を言ってるんだ?いつも「変な人」って言うくせに、君のほうこそ猛烈に変な女子高生だ。 |
| 二十七 |
|---|
|
「岡田さん、またまたお久しぶりね。どうしていらしたの?」 「すみません、ちょっとややこしい男女関係に巻き込まれていたものですから」 私は思わず意味不明なことを言ってしまった。 「岡田さんって、どこまでが本気でどこまでが冗談か分からないわね。アハハハ」と、女将さんが意外に大笑いした。「私・・・岡田さんのこと好きよ」だって?アハハハ、大笑いだよ真鈴、本当におかしい。 翌日の夜、私は大阪南港フェリー乗り場にいた。午後八時の出航で翌日の午前十一時前には宮崎港に到着する。車を乗り入れて、二等寝台の客室でくつろいだ。部屋には二段ベッドが八床、窓際にはテレビが置かれた四畳半ほどの和室が設けられていて、長距離トラックの運転手たちが早めに身体を休めていた。 フェリーは深夜、高知沖を走っている時はバシャーン、ザブーン、バシャーンと波をかき分け、上下の揺れが大きかったが、日向灘に入ってからは静かになり、翌日の午前十時四十分ごろには無事に宮崎港へ到着した。 宮崎市内を南進すると、道路はそのまま宮崎自動車道とつながる。高速道路をドンドン西へ走行し、えびのジャンクションで九州自動車道にチェンジする。二十分も南へ走れば横川出口だ。天降川(あまもりがわ)沿いの国道五十号線をさらに南下すると霧島市牧園町に到着した。妙見温泉は天降川沿いにあり、もともとは湯治温泉だった。今でも一般の温泉旅館以外に自炊施設のある湯治温泉宿も数軒営業を行っている。 到着したのは午後二時前、天降川に架かった赤茶けた橋の手前に周辺図が立てられていて、田丸本館はこの橋を渡って左折したところにあった。沢井氏が今もいるのかどうか、女性と一緒なのか、ともかく訪れてみないと分からない。駐車場は建物の一階にあって、裏側が天降川だった。このあたりに数軒ある湯治宿の中では最も大きかった。いわゆる湯の町の温泉街とは趣が異なるが、山に囲まれた自然豊かな風景が素晴らしい。車から降りてフロントを訪れた。 田丸本館は新館と旧館とに分かれていて、食事は朝食付きと朝夕二食付を選択できて、もちろん自炊もできた。小さなフロントで女性から簡単に説明を受けて、「商用で来られたのでしたら二食付きで六千円のお部屋がございます」と勧められた。私はさりげなく「沢井様はまだこちらにおられますか?」と訊いてみた。 「沢井ですか?沢井は今ちょっと所用で鹿児島空港まで出ております」 「そうですか。お帰りになられたら挨拶だけでもさせていただきたいのですが」 「夜までには戻りますからお部屋に伺わせましょうか?」 「差し支えなければ、お願いします」 声が上ずりそうになるのを辛うじて堪えた。真鈴の父、沢井圭一はここでまだ働いていた。真鈴が扇町公園で「お父さん、どこにいるんだろう」と、石ころを転がしながら父を案じていた姿が思い出された。 案内された部屋は極めて質素で、テレビと小さな卓袱台があるだけで、トイレと洗面所は共用だった。ただ、食事付きの客は料理を部屋まで持ってきてくれて、寝床も時間になれば作ってくれるらしい。私はせっかくなので部屋に用意された手ぬぐいを持って温泉に入った。浴槽は十五人も入れば窮屈になるくらいで、板塀に囲まれた装飾も何もない温泉場だったが、湯治温泉なので昼間でも数人の入湯客がいた。 さて、沢井氏が部屋に訪ねて来たらどう話を切り出そうか、私は手ぬぐいを頭に乗せて、熱い湯に浸かりながら考えた。しかし温泉の心地良さに眠気に襲われるだけで、何のアイデアも浮かばなかった。沢井氏が現れたら「娘さんが待っているから、すぐに家に帰ってやって欲しい」と言う以外にないだろう。ここまできたら成り行きだと思った。温泉から出て部屋に戻り、真鈴に電話した。彼女は三度のコールで出た。 「ちょっと今、電車の中なの。あと三十分位してから電話して」 「電車の中って・・・まさかまた変なことをしているんじゃないだろうな」 「学校の帰りだよ、変なことって何よ!」 「それならいいんだ。大丈夫だよな?」 「大丈夫に決まってるよ。いつまでも言わないで!」 真鈴は怒った口調で電話を切った。午後四時ごろ再度電話をかけた。 「さっきは怒ってごめんなさい。岡田さんが疑うようなことを言うから」 私はそれに答えず「お父さんの居場所が分かった」と冷静に言った。 「それ、本当なの?」 「本当だ」 真鈴は黙っていた。沈黙の時間が十五秒を過ぎたころ「また泣いているのか?」と訊いた。すすり泣く声が受話器から伝わってきた。無理もないことだ。 「やっぱりお父さんは鹿児島にいたよ。今そこの温泉宿にいるんだ。夜、お父さんと話をすることになると思うけど、どう話をすればいいかな?」 「分からない・・・。でもよかった。ありがとう、岡田さん」 真鈴は小さな声で言ってからまた泣いた。しばらくそのままにしておいた。 「僕に任せてくれるか?」 「うん、お願い」 「すぐには戻ってくれないかも知れない。いろいろ事情があるようだからね。おとなにはおとなの難しい事情があるものなんだ。今度会ったときに詳しく話すよ。それでいいかな?」 「うん、それでいい。本当にありがとう。私、嬉しい」 「どうってことない」と言って私は電話を切った。 |
| 二十八 |
|---|
|
昨今は事情が違っているようだが、昔からパチンコ店の従業員や地方の温泉旅館、さらに風俗業界などの従業員は、雇用の際にキチンとした身分の確認をしない業種といわれてきた。 悪い言い方をすれば「どこの馬の骨か分からない」人物を躊躇なく雇ってきた。それは、いちいち手続きを踏んでいたら人が集まらない、雇えないという業界事情もあったからだ。だから家出人捜しの依頼があれば、先ずは手がかりを依頼人から聞いてから、本人が暮らしていそうな地域が推測されればその地域のパチンコ店、温泉街があれば旅館などから聞き込みを開始したものだ。 沢井圭一は森京子とここに移って来た。ふたりが知り合ったのは、彼の姉が昔から療養していた穴吹療育園だった。ふたりはずいぶん前から関係ができていたのだろう。会社経営が順調なら真鈴たちと平穏な家庭生活を継続していたに違いない。でも会社は潰れた。そしてそれが引き金になった。沢井氏は森を頼って穴吹療育園に来た。 人間は金銭的なことよりこころの部分がはるかに重要だ。沢井氏が妻子を捨てて、ひとりの女性にこころの中の城を求めた行為は責められるべきことだろう。でも、道徳や観念のとおりに生きていけないのが人間だ。社会のルールどおりに皆が生きていければ、世の中に犯罪は存在せず不幸も少なくなる。世界は戦争のない、公園が町のいたるところに溢れる平和な楽園になるに違いないのだ。私のような人間が沢井氏の行為を批判する資格はないかも知れないが、降り続く雨のような天降川の流れの音を聴きながらそういうふうに思った。 疲れからしばらくうたた寝をしていた。コツコツという音に目が覚めたのが午後六時過ぎだった。ドアを開けると年配の男性が宿の茶羽織を着て立っていた。沢井圭一だった。 「ようこそいらっしゃいませ。係りの者から聞きましてご挨拶に参りました」 彼は戸惑ったような表情だった。「少しお時間はございますか?」と私は訊いた。 「いま少し雑用がございまして、午後九時を過ぎますと手が空きますので、よろしければそのころもう一度こちらに寄らせていただくということでいかがでしょうか?」 彼は申し訳なさそうに前かがみになって言った。私はお待ちしていますと返事し、沢井氏は「それではのちほど」と言い残して部屋を出て行った。食事前にもうひと風呂浴びてから部屋に戻った。ちょうど仲居が食卓に山菜料理を中心にたくさんの小鉢を並べていた。 「この辺りは山に囲まれて、綺麗な川が滔々と流れていて、本当にすばらしい景色ですね。温泉も濃厚で疲れが取れます」 「観光地の温泉と違って、何の色気もありませんけどね」 仲居は笑って言った。私はこの温泉宿がこんな安価で営業されていることへの驚きや、宿は家族で経営されているのかなどを訊いてみた。当たり前だが、この宿は名称のとおり田丸氏という昔からの地主がオーナーで、明治の中ごろから営業を行っているとのことだった。 ビールを二本飲み、出された料理をすべて平らげ、午後九時を少し過ぎたころに沢井圭一があらためて部屋に来た。茶羽織を着ていたが、仕事は一段落ついたと言った。 「もうビールを飲んでもいいのですか?」 「いただきましょう」と沢井氏は言って部屋の電話からビールを二本頼んだ。 「今日のお仕事は終わりですか?」 「いえ、まだ雑用がございますが、皆様の夕食が済みますと、ほぼ終わりでございます」 運ばれてきたビールをグラスに注ぎ、私と沢井氏は一口飲んだ。化学関係の会社を経営していたとは思えないほど彼の茶羽織は似合っていて、有名旅館の有能な番頭のような感じがした。 「岡田様とは以前どちらかでお会いしておりましたでしょうか?」 ビールを旨そうに飲み干してから彼は遠慮がちに言った。 「いいえ、初めてお会いします」 沢井氏は腑に落ちないような表情をして、何かを思い出そうとしているように思えた。私はビールを飲み干してから名刺を取り出し、それを手渡した。彼はその名刺をジッと見ていた。しばらくの沈黙があった。 「実は沢井さん、お嬢さんがピンチなんです」 私は奥沢氏を正面から睨みつけるようにして言った。コップ一杯のビールで酔うはずもないが、怒りが急に込み上げてきたのだ。自分勝手な行動をとるな。娘がどんなに困っていると思っているんだ。僕が真鈴に捕まらなかったら、アンタの娘はどうなっていったか分からないんだ。売春をしていたかも知れないんだぞ。アンタは会社をつぶして現実逃避で女と行方をくらましてそれでいいだろう。でも残された奥さんや真鈴はどうなるんだ。娘はアンタを求めている。素晴らしいお父さんだったと言っている。それが何だ、このザマは。私は様々な思いが次から次へこころに湧き上がってきて、興奮で震えているのが自分でも分かった。 「妻からの依頼ですか?」 沢井氏はしばらく考えてから言った。 「真鈴さんから頼まれたんです。沢井さん、何も言わないで帰ってやってください」 「真鈴がですか?お金はどうしたんでしょうか、それに妻は・・・」 「お金は関係ありません。真鈴さんとは友達だからです。奥さんは事情があって家にいません。家には彼女がひとりですが、精一杯頑張って暮らしています」 「妻はどうしたのですか?」 「帰ってやってくれませんか。あなたの事情は訊きません。女性と一緒にいるのかどうか、そんなことはどうでもいいんです。沢井さん、帰ってやってください。真鈴は、いや真鈴さんは今、大変なんです。彼女は母親を庇っています。あなたの奥さんはあなたがいなくなってからずいぶん苦労をしたようです。精神的に参ってしまって、宗教団体を頼って家を出てしまっています。真鈴さんはそれを咎めていません。彼女はいい子です。素晴らしい高校生です。ただ、今すごく苦しんでいます。寂しくて死にそうです。お父さんが必要なんです。帰ってやらないといけません」 私は言葉の最後のあたりで感情が込み上げてきて、どうにも制御できずに涙声になってしまった。真鈴、絶対に帰ってもらうから心配するな。私は心の中で叫んだ。 |
| 二十九 |
|---|
|
翌日の夜、私は宮崎港にいた。往路を逆戻りして明日の朝には大阪南港に戻る。 昨夜、沢井氏とは一時間も話ができなかった。私が少し感情的になって真鈴のもとに帰って欲しいと説得すると、彼は黙り込んでしまった。五分も経ってからようやく「岡田さん、あなたの言うとおりです。私は逃げていました」と静かに言った。 「明日、岡田さんの都合がよろしければ、私の寮に来て下さい。今夜はこのあと少し残務がありますので失礼しなければいけません。明日午前中でしたらゆっくり話せます」 もしかすれば今夜のうちにここを去って、再び彼は姿を晦ませるのではないかと一瞬思ったが、万が一そんな行動に出たとしたらそれは仕方のないことだ。そんな父親なんてもう捜さなくてもいいと真鈴を説得してやろうと思った。 翌日、私は天降川のせせらぎに目覚め、温泉にゆっくりと入ってから十時過ぎに沢井氏の寮を訪ねた。寮は田丸本館に隣接する旧館のはずれにある木造の二階建のアパートだった。彼はどこにも姿を晦まさず私を待っていた。きれいに片付いた一DKの部屋の隅には絵画用材が無造作に置かれ、未完成の風景画がキャンバスに貼られていた。 「休みの日は特に何もすることがなくて、少し前から絵を描くようになりました」 沢井氏は苦笑いをして説明した。絵なんか書いている場合かと、私は苛立った。彼はインスタントコーヒーを僕の分も淹れて、それらをテーブルの上に置き、それからゆっくりと語り始めた。 沢井氏は森京子と一緒に穴吹療育園を出て、この田丸本館に住み込みで働くようになった。京子が調理補助の仕事、彼は宿全般の雑用係と客の送迎や食材などの買い出しに従事した。しばらくは従業員寮でふたり暮らしをしていたが、三年ほど前に京子は実家のある鹿児島県垂水市に帰り、今ではときどきここに京子が来るか、沢井氏が京子の実家を訪ねるかという関係になっているという。 沢井氏は離婚していないので京子と結婚できるはずもないが、実質二人の関係はすっかり冷えてしまっていると彼は語った。 「妻や真鈴のことは気がかりでしたが、人間、一方向へ走ってしまうと歯止めが利かなくなるのです。それに今更、どんな顔をして戻ればいいのか考えているうちに六年程が経ってしまいました」 沢井氏はそう説明した。「甘いな」と私は思った。甘すぎるよ沢井さん。家族を抱えている人間の言葉じゃない。私は苛立ったが、その感情を言葉には出さなかった。 「ともかく帰ってあげるべきです。私はこれで失礼しますが、真鈴さんにはあなたの居場所は教えます。でも彼女がここを訪ねてくるかは分かりません。いえ、訪ねては来ないでしょう。もし彼女が行きたいといっても私が止めます。だから沢井さんのほうから電話をしてやってください。自宅でも携帯でもかまいません。必ず連絡してやってください」 「分かりました。できるだけ早くそうします」 「できるだけ早くじゃだめなんだ、沢井さん。しっかりしてくれ。娘さんがピンチなんだって、昨夜も言ったじゃないか。気持ちの整理があるでしょうから、今ここから彼女に電話をしてやってくれとは言わない。明日電話してくれとも言わない。でも事前に私が真鈴さんに伝えておきますから、今度の土日には必ず連絡してやってくれませんか」 私は言葉の途中から勢いを抑えて、彼に頼み込むような気持ちで言った。 「岡田さん、よく分かりました。すみませんでした。必ず数日中には電話します」 「だめなんだ、そんな曖昧なことを言っていては。明後日、土曜日に電話してやってくれませんか。踏ん切りがつかないならもう一日だけ待ちます。だから土曜日が無理なら日曜日には絶対に電話をしてやってくれませんか。ずっと待ち続けている彼女の身にもなってやってください」 「分かりました。必ず・・・必ず土曜日に電話をします」 ようやく彼はそう言った。私は真鈴の自宅とスマホの電話番号を書いたメモを二枚渡した。一枚だけでは失くしてしまうと困るからだ。 「この二枚のメモは大切です。それぞれ違うところに保管して下さい。スマホをお持ちでしたら、あとで登録して下さい」 沢井氏は頭を下げた。そして「真鈴は許してくれるでしょうか?」と言った。 「当たり前です。許すも許さないも、あなたたちは親子じゃないですか。真鈴はずっと待っています」 沢井氏はそれからきっかり五分間、泣き続けた。私はその間、窓の外に見える緑の山々と、その上の晴れ渡った青空と、部屋の片隅に置かれた風景画とを交互に見ながら、出されたコーヒーを飲むふりをし、そしてもらい涙を抑えられなかった。 彼も苦悩したのだ。捨てたほうも捨てられたほうも苦悩する。再会し、再び元に戻ることで、その苦悩はようやく報われる。化学薬品か化学肥料か知らないが、そんなものの研究開発がだめになったからといって、妻子を捨てて女性と行方をくらまし、挙句はどのような顔をして帰れば良いか分からないとは、「馬鹿なこと言うな」と私はこころの中で沢井氏を罵倒した。 そんな私の気持が顔に出ていたのだろう。昨夜は最初から沢井氏に対して攻撃的な態度になってしまった。本来の調査案件だとそんなことは決してないのだが、この件は仕事ではない。私の素敵な天使への贈り物だと思っていた。だから自分の自然な気持が攻撃的な態度に出てしまったのだ。でも、それでよかったのだろう。 午後からもう一度温泉にゆっくり浸かり、沢井氏に再度念を押してから別れを告げた。宮崎に向かいながら、真鈴に電話した。 「今ちょっと電車の中なの。あと三十分ほどしたら家に帰るから自宅に電話して」 真鈴は早口で言って電話を切った。私はいつも彼女が電車の中にいるときに電話をしているような気がした。尾行中に捕まってからこの日までのことが不思議だった。えびのジャンクションから宮崎自動車道に乗り換え、最初のパーキングエリアで車を止めて真鈴の自宅に電話をした。彼女はすぐに出た。 「どこに行っていたんだ?」 「心斎橋まで文房具を買いにいっていたの」 「本当なのか?」 「岡田さん、しつこい。私がまだつまらないことをしていると思っているの」 「だったらいいんだ。心配しているんだよ、真鈴のことを」 「大丈夫だから、信じて」 「お父さんに会った。おそらく今度の土曜日か日曜日には家に電話が入る。かかって来たら怒らないで許してやってくれ」 「・・・・・」 「泣いているのか?」 しばらく言葉が戻ってこなかった。無理もない。 「明日の朝早く大阪南港に着いて、昼ごろには自宅に戻るから、帰ってから詳しく話す。それでいいかな?」 「お父さん、帰ってくるのかな?」 「決まってる、絶対に戻ってくるから心配するなって」 「うん」 これ以上は私も感情が昂ぶってしまって話が出来ず、電話を切った。宮崎港に着いたころには陽が沈んでいた。 |
| 三十 |
|---|
|
今回の調査は仕事ではなく個人的なものだったが、鹿児島にたどり着くまでがまるでドラマみたいだと思った。私の知人に「人生はシンプル・イズ・ベスト」などとカッコつけて言う奴がいたが、そんな簡単なものじゃない。物事はすべてにおいてややこしくできている。その難事をいかにシンプルな思考で、難しく考えずに切り抜けるかが大切なのだ。難しく考えてしまって現実逃避に走ったり、精神的に参ってしまってこころの病を患ったり、人は苦悩する。 「ともかくよかった」 宮崎港の突堤から満天の星の夜空に向かって声に出して呟き、しばらく満足感に浸った。 部屋に戻るとホッとする。窓から見える兎我野町の街並みも、当たり前だが変化はなかった。フェリーの船中泊の疲れを取るため熱いシャワーを浴びてから少しベッドに横になった。真鈴に電話をしてやらなければいけないと思ったが、少しだけ寝ることにした。睡眠開始のゴングは鳴らなかったが、たちまち眠りに落ちた。どれくらい眠ったのだろう。誰かがすぐそばに立っているような気がして目が覚めた。 いつの間にか有希子がベッドわきに立っていて、悲しそうな目をして私を見ていた。 「どうしたんだ?有希子」 「大変なのよ、どうしていいか分からない」 有希子は呟くように言った。 「何が大変なんだ?」 有希子は顔色も悪く、普段の様子とは違っていた。ともかくベッドから起きようとした。だが、身体は全く動かなかった。「有希子、ちょっと起こしてくれ。手を引っ張ってくれないか」と手を差し出した。有希子はジッと私のほうを見ていたが、急に顔がどす黒く豹変し、目が釣り上がって口は大きく横に広がり、牙を見せた。そしてその顔を近づけて「何で私たちに子供がいないの!自分勝手なことばっかりして、あなたなんか死んでしまえばいいわ!」と、まるで地底から唸りをあげるような太い声で罵った。有希子の鬼のような形相に驚き、叫び声が出た。だが、叫びは声として発せず、大きく開けた口が空しく動くだけだった。喉から搾り出すようにして放った声は「ヒュー」と空気を切るような音だけだった。身体を起こそうとするが、何かに押さえつけられているように動かなかった。そんな私に背を向けて有希子は部屋から出て行ってしまった。「有希子!」とようやく声が出たときに目が覚めた。ベッド脇に置いていたスマホが震えて鳴っていた。 「真鈴です。どうしたの?」 「ああ、ちょっと夢を見ていたんだ。嫌な夢だった」 「昼ごろに大阪に着くって言っていたから、連絡を待っていたの」 時計を見るともう午後四時を過ぎていた。 「ごめん、帰ってきてシャワーを浴びたら寝てしまったんだ。今、部屋かな?」 「そう」 「お父さんのことだけどね、明日か明後日にはそっちに電話が入る。だからちゃんと話をしないといけないよ」 「分かってる。でもずっと待っているのって辛いわ」 「お父さんの働いているところの電話番号は分かっている。でもこちらからはかけないほうがいい。お父さんから電話がかかってくることが大切なんだ。分かるかな?だから、明日と明後日は外出しないようにして、電話を待っていなさい」 「分かった、そうする。明日は勉強する」 真鈴は素直に従った。 「明日電話があればいいけど、なくても明後日には絶対に電話があるから心配ない。それから、お父さんはすぐに君のもとに戻ってこないかも知れないけど、話をよく訊いてあげなさい。もう行方不明にはならないから」 「どうして?」 「それは・・・話すと長くなるから、今度説明するよ」 「今からそっちへ行っていい?」 「えっ?」 「晩御飯、一緒に食べようよ。何か作ろうかな」 「いや、今夜はちょっとダメなんだ。仕事の準備があるから」 「何よ、いつもは部屋に来ないかって言うくせに、私が行くって言ったら来るなって」 「ごめんな、お父さんから電話がかかってきたら、何か美味しいものを食べに行こう。いいかな?」 真鈴はしばらく考えてから、「うん、そうね」と言って電話を切った。難しい年頃の女の子だが、やっぱり隠しようもなく、真鈴への感情が私のこころの中に生まれていた。でも、今は考えないことにした。今夜は真鈴を部屋に呼んでもよかったのだが、さっきの夢のことが気になってしまったのだ。私はすぐに有希子のスマホに電話をかけてみた。 「どうしたの?」 有希子はすぐに電話に出た。 「いや、特に何もないんだけど、そっちは変わったことないかな?」 「な〜んにもないわ。夕方になったらお父さんの散歩に付き合って、それ以外はお母さんの家事を手伝ってる毎日よ。退屈だわ」 彼女はもともと銀行員だったが、私と結婚後は専業主婦となって、ふたりの間に子供ができることに早くから備えていた。だが、夫婦仲は良かったにもかかわらず、子供はできなかった。不妊の原因については、ふたりとも特に病院で調べてもらったわけではないが、どうしてだろうと思っているうちに私の事業失敗などもあって、彼女の両親から引き裂かれてしまったというわけである。 夢に出てきた有希子は、「何で私たちに子供がいないの!自分勝手ばっかりして、あなたなんか死んでしまえばいいわ!」と、鬼の形相で罵っていたが、彼女は子供ができなかったことをどう思っているのか、これまでそのことに触れずにいたから分からない。 「この前みたいに、またどこかで遊びたいね」 「そうね、また気が向いたら行くわ。じゃ、これからお父さんの散歩に付き合うから」 そう言って有希子は電話を切った。私のこころの中を、切なく空しい冷たい風が吹き抜けていったような感覚になった。真鈴に電話をしたくてたまらなくなったが、どうにか思いとどまった。 |