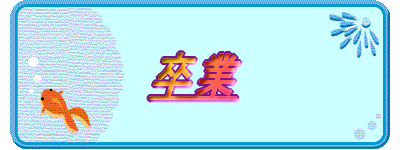
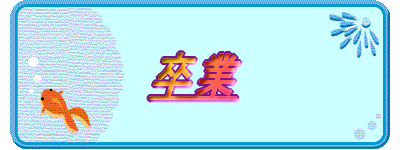
| 十九 |
|---|
|
扇町公園を出てマンションへの帰り道、真鈴に対して学校へはキチンと行くことと、これからも絶対におかしな行動はしないようにと約束をした。真鈴は「分かった」と言って、あまり元気なく部屋に消えた。そのうしろ姿が何とも形容しがたいほど切なく思え、いつでもおいでよと誘っても「嫌だって!」と言って断るが、帰ってもずっとひとりなんだと思うと、何とかして彼女の父親を捜すんだと、自分に命令を与えた。 翌日、真鈴の父が経営していた「沢井化成株式会社」の当時の役員を確認するため、地下鉄谷町線の天満橋駅近くにある法務局本庁に出向き、商業登記の閉鎖謄本を閲覧した。役員は監査役を含めて男性四人が登記されており、それらをメモしたあと真鈴に電話をかけてみた。 「今、授業中なの。昼休みに電話して」 真鈴は囁くような声で言って電話を切った。なぜ授業中にスマホに出られたのかが不思議だったが、キチンと学校に行っていたことに私は安堵し、訊きたいことを簡単に要約してLineのメッセージで送っておいた。 南森町にある大手探偵調査会社のT社へ向かって天満橋を渡っている途中、ブルブルとスマホが震えた。真鈴からの電話だ。 「Line見たよ。お父さんの会社の役員だった人のことね?」 「そう、四人の役員がいたようだけど、その中で知ってる人がいないかな?」 「佐久間という人なら知ってる。確かお正月に何度か年始の挨拶に家に来て、私にお年玉をくれた人。お父さんと一番親しかったと思う。泉大津というところに住んでいたはずよ」 真鈴は記憶に間違いないと言った。 「午後の授業も頑張れよ」 「全然つまんないよ。岡田さんとマックへ行きたい」 今度ビッグマックを食べようと約束して電話を切り、T社に顔を出した。事務所には七、八人の社員が忙しくしていたが、元いた職場なので皆が私に声をかけてきた。部長は私の姿を見ると、「ちょうどよかった。ちょっと一件仕事を頼みたいと思っていたところや」と言って、愛媛県宇和島市の調査を依頼してきてきた。私はありがたく頂戴して、調査指示書と資料を受け取った。 「部長、ちょっとEノートを使わせてもらえますか?」 「そこらにあるから、好きに使ってくれてええよ」 Eノートとは、大手通信会社の電話を架設している利用者の名前と住所の一部を打ち込んで、電話番号を検索できる端末だ。サービス自体はすでに終了しているが、既存の情報はまだ検索できる。いちいち各地の電話帳を見なくとも捜せるから便利なのだが、利用者が電話帳に非掲載希望なら絶対に出てこないから個人情報は守られている。 佐久間氏の氏名と概略住所で検索をしてみると、該当するものがひとり出てきた。事務所の電話を借りてすぐにかけてみた。すると、電話には佐久間氏の妻が出て「主人は仕事に出ています」と言った。前に沢井氏の会社にいた佐久間氏宅であることを確認し、あらためる旨を伝えて電話を切った。そしてその夜、同氏と話すことができた。お会いしたい理由を説明すると、当然ながら最初は不審に思っているフシが窺えたが、「沢井氏を捜すのはご家族からの依頼です」と伝えると同氏は快諾し、三日後に会うことになった。 佐久間氏は真鈴の父の会社が倒産したあと、大阪市中央区の北久太郎町というところにある薬品会社に勤めていた。約束の日の十八時半ごろに地下鉄御堂筋線本町駅に着くと、待ち合わせ場所とした改札口前の売店横で彼はすでに待っていた。少し白髪が混ざった五十過ぎの人物だった。われわれは地下の飲食店街にある大衆的な居酒屋に入った。 「このあたりは相変わらず賑やかですね。私は以前、この近くの会社にいたのですが、当時と全く変わっていません。もうずいぶん昔のことですが」 「そうですな、このあたりはビジネス街なのでサラリーマン相手の居酒屋が多いですな。私が世話になった沢井さんの会社があったのは、北浜と堺筋本町の中間でした。大阪証券取引所や大阪国際ビルなどが近くにありましたから、ここと同じような飲み屋がたくさんありました。いずれにしてもサラリーマンというものは、仕事の憂さや同僚や部下とのコミュニケーションに酒は切り離せません」 佐久間氏は生ビールを飲みながらそう言った。そういえば私は今、同僚や上司や部下と全く縁のない仕事環境にあるのだ。でも、金融会社にいたころを思い出すことはあるが、戻りたいとは決して思わなかった。佐久間氏は学卒後就職した大手企業で化学製品や薬品関係の研究をしていたらしいが、途中から営業に回されたため退職し、中堅の化学品会社に転職した。そこで真鈴の父とは上司と部下の関係にあり、「沢井さんが独立するというので、それならとついていったのです」と彼は言った。もう十五年以上も前のことらしい。 「岡田さんのような職業が本当にお有りだとは知りませんでした。尾行や家出人の調査もされるのですか・・・。これは大変なお仕事だ。体力がないとできませんな」 佐久間氏は私の名刺の裏に書かれている「調査項目」を見て言った。 真鈴の父、沢井圭一が突然姿を消してしまったのは、もう六年以上も前のことだ。会社が行き詰まり、支払手形の決済の目処が立たないまま突然消えた。手形は資金不足で落ちなかったが、幸いにもいわゆる筋の悪い金融会社からの借り入れがなかったことと、支払先がすべて自社の取引銀行で手形を取り立てたことなどで、大きなトラブルにはならなかった。 ただ、不渡り手形をつかまされた取引先の中には、たちまち資金繰りの悪化に陥った零細企業もあったようだ。会社整理は佐久間氏や社員が弁護士に相談して事務的に行われた。真鈴が十二歳、ちょうど小学校を卒業した春休みのことだった。当時、沢井家が住んでいた堺市の泉北ニュータウンの土地家屋は銀行に差し押さえられ、真鈴と母は現在の兎我野町のマンションに引越してきた。 「もうずいぶん前のことなので、お忘れになったことも多いと思いますが、沢井さんが失踪される前に何か変わったことはなかったでしょうか?」 「会社は事務の女性が三人と、営業が四人、そして私ともう一人の役員を入れても十人ほどのものでした。家族的な雰囲気の会社だったのです。皆が親しかったといえばそうなのですが、沢井さんの失踪について心当たりはまったくありませんな」 目を少し細めて、昔を思い起こすような表情で佐久間氏は言った。 |
| 二十 |
|---|
|
「手形決済日の翌日、銀行がもうこれ以上待てないと不渡り処理がなされ、午後から取引先から次々に手形が落ちなかったことについて問い合わせが入り、会社はあくる日の夜遅くまで混乱しました。ようやく三日目に私が奥さんと話し合って警察に届け出ました」 佐久間氏はビールを飲み干して言った。店内は冷房があまり効いておらず蒸し暑い夜だった。 「なんとか見つかりませんかなあ。会社は倒産しましたけど、どうにかこうにかカタがついたようだし、整理したあと特に借金が残ったわけでもありませんからな」 佐久間氏はそう言い、そのあとも難しい表情で何かを思い起こそうとしてくれたが、ヒントになる話は得られず、一時間半ほどで店を出た。別れ際に、当時の女性社員の名前と連絡先を念のため訊いた。帰ってから資料を探してみますと、佐久間氏は心やすく引き受けてくれた。女性社員ついて訊いたのは、私の「勘」以外に理由はなかった。 その週の土曜日、有希子が午前十一時過ぎに突然部屋に来た。私はいつもより早く起きてテーブルの上に宇和島の案件の資料を広げ、調査の段取りを組んでいたところだった。来週の木曜日と金曜日に現地を訪れる予定で、最低でも七ヶ所を回って一泊二日で帰って来る必要があった。この案件に目処がついたら、真鈴の父親の所在捜しに移りたいと考えていた。 「どうしたの?いつもは起きているのも珍しいのに」 有希子は驚きながらも、嬉しそうに笑った。 「いきなり来るんだな。お父さんが様子を見て来いって言ったのか?」 「そんなんじゃないのよ、たまにはあなたの顔を見たいじゃない」 有希子は恥ずかしげもなく言った。離婚はしていなくとも、別居中の夫婦の会話としては不思議な内容に思えた。 「今治の実家に寄れるの?」 「どうかな、時間的に難しいかもね」 「あなたの仕事が順調にいけば、両親も元に戻って一緒に暮らせって言うと思うのよ。だから、大変でしょうけど頑張ってね」 私は有希子の言葉に対して言いたいことがあったが、喧嘩はしたくなかったので黙っていた。 「私のこと、まだ愛してくれている?」 「いきなり何を言うんだ?別居中なんだからな」 「じゃ、もう醒めちゃったの?」 「勝手なことばっかり言うなよ」 この日、有希子はすぐに帰ろうとしなかった。彼女も実家では窮屈なのかも知れない。私たちは夕方までソファーにもたれてDVDを観た。「シェルタリング・スカイ」というイギリス映画で、日本の坂本龍一氏がゴールデングローブ賞の音楽賞を受賞した古い作品だった。 物語は倦怠期の夫婦が観光ではなくある目的を持って北アフリカを旅するもので、旅の途中、夫が病死してしまう。そして残された妻も心が荒廃してしまい、決して元には戻らないという悲しいものだった。人生は旅そのものだが、本当に旅に出た熟年夫婦は旅先でふたりの関係を終える形になってしまうのだ。映像と音楽がとても素晴らしく、私は久しぶりに映画で感動した。 映画を観終わったとき、もしかしたら真鈴の父は、会社がだめになったことをきっかけに、何かの目的を持って姿を消したのかも知れないと思った。長い人生には数え切れない出来事や思い出、人間関係が存在する。思い出のほとんどは、そのときは悲しく辛いことだったとしても、年月とともに懐かしいものに変化していく。結婚して、子供を育て、家族のために働き続け、平穏な家庭を構築しても、あるきっかけによって過去のひとつに身を戻したいと思うことがあるのかも知れない。沢井氏にとっては経営していた会社の倒産が引き金となって、残された妻や子供のことを考える余裕などなく、ある目的の場所、或いは誰かのもとに走ってしまったのでがないだろうか。 「光一、さっきから難しい顔をして何を考えているの?」 「何でもないよ。いい映画だったね」 私は有希子の肩を抱き寄せた。今日は拒否せずに身体をあずけてきた。シャツの上から小さな胸の膨らみを撫ぜながら、久しぶりに長いキスをした。唇を離すと、「じゃあ帰るね。頑張ってほしいけど、無理しないでね」と言い残し、有希子は部屋から去った。 数日後、佐久間氏から当時の女子社員の情報が届いた。 「先日は馳走になり恐縮です。三人の女子社員の当時の電話番号などを記しました。もしかすれば連絡が取れなくなっているかも知れません。その際は悪しからず」 手紙にはそう書かれていた。すぐに簡単な礼状を書き、それから三人の女性に順番に電話をかけてみた。三人のうち二人は携帯電話番号で、どちらも応答がなかった。知らない番号からの着信には出ないだろうから仕方がない。残る一人の三枝(ミエダ)という女性は自宅の電話番号で、留守番電話に「沢井圭一氏のことでお訊ききしたいので、あらためて連絡する」旨の伝言を残しておいた。 愛媛県宇和島市の案件は同市だけにとどまらず、大洲市や県南にある広見町にまで及んだ。松山空港に飛んで空港レンタカーを借り、全部で七ヶ所の調査先を聞き込み、写真撮影を行った。初日は宇和島市内数ヶ所の聞き込みを終えて漁港近くのビジネスホテルに泊まり、翌日は朝早くに飛び起きて広見町を訪れ、そのあと車を飛ばして国道五十六号線をひたすら北上、大洲市の調査先や母方菩提寺を訪れてから松山へ戻り、夕方の飛行機で大阪に戻ってきた。今治の実家に立ち寄る時間など、どこにも見当たらなかった。 それぞれの調査先で必要な情報を得られて満足のいく出張だったが、強行軍だったこともあってすっかり疲れてしまった。報告書は来週にでも書き上げるとして、真鈴の父の件が気になっていたので、先日留守番電話に伝言を残しておいた三枝という女性宅に電話をかけた。時刻は午後九時を少し過ぎていたが、彼女は遅い電話にも気持ちよく応対してくれた。 「沢井社長にはずいぶんとお世話になりましたが、あのような形で会社がだめになってしまって残念です。社長がずっと行方知れずとは驚きです。岡田さんには社長のご家族がご依頼されたのですね。お話はよく分かりました」 声の感じと落ち着き具合から、三十代後半あたりではないかと思えた。一度お会いしたいと伝えると、彼女は数秒間考えてから、平日よりも土日のほうが都合がよいと言った。明日では早すぎますかと訊いてみたところ、昼過ぎから夕方までなら大丈夫だとのことで、午後一時に心斎橋の日航ホテルのロビーで会う約束をした。電話を切って数分後にスマホが震えた。真鈴からだった。 「ずっとかけてたのに、誰かと話をしていたの?」と彼女はいきなり言った。 「ごめん、仕事の関係で電話していたんだ」 真鈴は「フ〜ン」とスマホの向こうで呟いたあと、「明日会いたい」と言った。 「ごめん、明日は午後から心斎橋で人と会うことになったんだ。今からこっちに来る?」 「だから、嫌だって言ってるじゃない!」 「ごめん、そんなに怒るなよ」 「明日会う人って、そんなに大事な人?」 「いや、仕事の関係だよ、もちろん」 「じゃ、もういいです」 そう言って真鈴は電話を切った。スマホだが、バシッと音がしたような怒った切り方だった。 |
| 二十一 |
|---|
|
翌日、三枝さんとの約束の時刻より少し早く日航ホテルに着き、二階のフロント前のソファーで待った。土曜日のホテルは、当然だが平日のようにビジネスで待ち合わせをしている人よりも、何かの集いで来ている人がほとんどだった。 「あのう、岡田様でしょうか?三枝ですが」 約束の午後一時を少し過ぎて、私の前に薄いオレンジ色のワンピース姿の女性が立った。フロントの様子を眺めていたので気づかなかったのだ。 「あっ、どうも急にお呼びだてしてすみません。下のティーラウンジへいきましょう」 三枝さんは少しふっくらとした体躯で、笑顔が人懐っこく、年齢は三十代半ばに見えた。私はすぐに名刺を渡した。 「三枝様の電話番号は佐久間様から教えていただきました。沢井様のお嬢様よりお父様を捜して欲しいとのご依頼なのです。何かお心当たりがありましたらお訊きしたいのです」 私は単刀直入に言った。 「奥様はお元気なのでしょうか?」 三枝さんは本当に心配そうな表情で言った。ちょっと事情があってご自宅にはいらっしゃらないと、正直に現況を答えた。 「では、お嬢様がおひとりなんでしょうか?」 「そうなりますね。ともかく、どんな些細なことでも結構です。何かお心当たりはないでしょうか?こんなことは関係がないだろうと思われることが、意外と糸口となることもあるんです」 重ねて言って、上品で高価なコーヒーに口をつけた。 「沢井社長はとても穏やかな人柄で、社員に優しい方でした。小さな会社でしたから管理職と社員の隔たりもなく、家庭的な雰囲気の職場でしたね。皆が親しい付き合いをしていたように思います。会社の経営も、どうにもならないほどには悪くなかったようでした」 彼女は膝に手を置いて当時を思い起こしている感じだった。コーヒーに手をつけずにいたので、手で合図をして勧めた。彼女は首を少しだけ傾げてクリームを注ぎ、そして一口飲んだ。 「本当に手形の決済ができない状態にまで、経営状態が悪化していたのですか?」 「毎月のように多少の資金繰りの必要があったとは思いますが、手形決済が不可能なほど詰まっていたとは思えませんでした。社長が匙を投げた理由は、おそらくご自身の夢が叶わなくなったことによって、自暴自棄になられたのだと思います」 「それはどういうことでしょう?」 「会社はいわゆるOEMで化学品の開発を行っていて、サンプル製作から製造まですべて外注だったのです。社長は化学配合飼料を研究していて、特許申請が認可されてから製品になるまでは何年もかかっていました。サンプルを持ち込んで提案するのですが、なかなか実現せずに先行投資ばかりが続いたので資金繰りは大変だったようです。そして最も期待していた大手の化学商社との開発が流れてしまったときはかなりショックを受けていたようでした。実現すれば大きな売り上げが期待できたのに」 「でも行方をくらますことはなかったのでは?」 「そう言われればそうなんですが・・・」 「ほかに何か思い当たることがありませんか?」 三枝さんはコーヒーを飲み、そしてしばらく考えていた。 「そういえば徳島へたびたび出張されていましたね。取引先の把握はしていましたが、当時徳島にはその対象となる会社はなかったですから。でもそれは関係ないでしょうね。確か社長のご実家が香川県でしたから、お墓参りに行かれていたのかも」 「そんなにたびたび徳島へ出向かれていましたか?」 「二ヶ月に一度程度でした。得意先のないところになぜかなと思ったことがありました」 「それは何日くらいの出張でしたか?」 「そうですね、四、五日程度だったように思います。水曜日か木曜日に行かれて、月曜日の朝には出社されていましたから、土日は実家に立ち寄られていたのかも知れません」 真鈴の話だと丸亀の実家には行ったことがなく、祖父母は父が結婚前にすでに亡くなっていたとのことだった。三枝さんからこのほかに特に手がかりとなるような話は得られず、一時間余りの時間を取らせたことへの礼を述べて別れた。ともかく香川県の丸亀に行ってみようと思った。 事務所に戻り、先日の愛媛の調査で得た情報を整理し、報告書にまとめはじめた。窓の外に見える兎我野町の街並み、高層ビルとビルとの間に鮮やかなオレンジ色の夕陽が沈むところだった。私はしばらくその光景に目を奪われていたが、昨日真鈴が会いたいと言っていたことを思い出し、「何してるの?」とLineを飛ばした。十数秒後にスマホが震えた。 「Lineでもよかったのに」 「そんな言い方ってないでしょ、声が聞きたかったのに」 「そうだな、悪かった」 私は素直に謝った。 「何もしていないよ。ぼんやりテレビを見ながら、ときどき勉強」 真鈴は少し眠そうな声で言った。 「来年は大学だろ。ちゃんと受験勉強しないとな」 「行きたいけど、お金がないもの」 「お金なんてどうにでもなるって。僕だって大学へ親の援助なしで入って、六年かけて卒業したんだよ。奨学金も受けられるし、心配ない」 真鈴の高校は府下でも有数の進学校で、大学進学率はほぼ百パーセントだ。 「お父さんのことで明日から動くけど、進学の問題はそのあと話し合おう」 「岡田さん」 「うん?」 「何でそんなに親切にしてくれるの?」 「何でって・・・そうだな、真鈴は尾行で初めて捕まった女の子だからかな。放っておけないんだ」 私は全く説得力のない説明をした。彼女はスマホの向こうでずっと黙ったままになった。 「香川のお父さんの実家に、君は訪ねたことがないって言ってたね」 「うん、お墓参りには行ったことがあるけど、実家はずっと昔になくなっているはず」 徳島に何か記憶がないかを訊いてみたが知らないと言う。「ともかく、帰ってきたらまた連絡するから」と言って電話を切った。 |
| 二十二 |
|---|
|
翌日、昼過ぎに丸亀駅に着いた私は、真鈴から聞いていた沢井家の菩提寺を先ずは訪れた。天台宗の由緒あるお寺で、京極通りという大通りから少し入った丸亀プラザホテルの裏手に位置していた。 駅から菩提寺に向かう途中、沢井家の墓を参りにきた理由を、首筋を流れる汗をぬぐいながらいろいろと考えた。でも上手い理由が思いつかないまま花屋に立ち寄って墓前に供える花を購入し、結局そのまま菩提寺に着いてしまった。 「沢井家のお墓をお参りしたいのですが」 「土居の沢井さんのお墓でしょうか?」 住職は不思議そうな面持ちで訊いた。私は「そうです」と答えた。住職は何か書き物をしていたが、筆を硯に置いて立ち上がり、「こちらです」と案内した。寺の本堂の裏に広い墓地があるが、沢井家の墓は裏に通じる通路の途中にあった。古い小さな墓石に沢井家先祖代々と書かれていた。墓の周りは意外にも荒れていなかった。 「圭一さんはときどきお参りに来られますか?」 余計なことを言わずに、さりげなく住職に訊いた。 「昨年秋の彼岸にはお越しになりました。まあ、年に一度来られるかどうかというところですかな。ずっと大阪にいらっしゃいますからね。あなたはご親戚の方で?」 「圭一さんには小さいころよく遊んでもらったんです。お祖父さんにも可愛がってもらいました」 思いつきで言った言葉が少し震えているのが自分でも分かった。沢井氏は昨秋にここを訪れていたのだ。 動揺を隠すようにして「それでは花を供えさせていただきます」と住職に伝えて水場に歩いた。住職は庫裏に戻って行った。バケツに水を入れて墓前に戻り、柄杓で墓に水をかけながら、私の興奮は次第に大きくなっていった。真鈴が気づかなかったことは仕方がないとしても、彼女の母が夫の菩提寺に立ち寄っていれば、沢井氏がここを訪れていることが分かったのだ。せめて電話で問い合わせでもしていたら、父の存在が確認できたというのに。やはり物事の手がかりはごく近くに存在した。早く真鈴に知らせてやりたかった。 私は花を墓前のふたつの花瓶に分けて綺麗に供え、手を合わせてからあらためて庫裏を訪れ、住職にわずかばかりの心づけを手渡した。 「圭一さんは大阪の住所をどこかに移されたようなのですが、ご存知ないでしょうか?」 少しお待ち下さいと言って彼は奥に退き、数分して戻って来た。 「連絡先は大阪府堺市槙塚台とありますな。ここから移られておるんですかな?これしかないのでちょっと分かりませんね。今度来られたら訊いておきましょう」 住職は親切に応対してくれた。あまり長居するといろいろ訊かれそうなので、頃合いを見計らって辞した。沢井氏は住職にも居所を教えていなかった。菩提寺を出て真鈴に電話をかけた。 「今、授業中なの。あと三十分ほどしたらもう一度電話して。Line送ってくれてもいいよ」 彼女は小さな声で言って電話を切った。大切なことなので、メッセージではなく電話で知らせてやろうと思った。しかし授業中にスマホに出られる状況を思い浮かべてみたが、どうもうまく想像できなかった。十二時半を少し過ぎてから再度真鈴に電話をかけると、待っていたかのようにすぐに出た。 「ごめんなさい、四時限目が終わるのが十二時半なの」と彼女は言った。 「実は丸亀のお寺を訪ねたんだけど、君のお父さん、去年の九月のお彼岸にお墓参りに来ていたよ。年に一度はお墓参りに来ているようだな。住職が言っていたから間違いない」 私は自分でも分かるくらい声が昂ぶっていた。真鈴は電話の向こうで黙ってしまった。 「どうしたんだ?」 「お父さん・・・生きていたのね」 真鈴は泣き声で言った。 「当たり前だろ、そんなに簡単に人が死んでたまるか」 「うん、分かった。嬉しい」 真鈴が泣くのは無理もないことだが、調査はこれからだ。 「実家に行ったことがないって言っていたけど、場所はどうしても分からないかな?」 「分からない。お父さんが結婚する前にお祖父さんもお祖母さんもとっくに亡くなってたみたいだから」 父方実家があった場所を今さら菩提寺の住職に訊くのもおかしな話だ。プライベートになるが、T社の部長に公簿を取ってもらうしかないだろう。 「岡田さん、どうしてそんなに私のためにいろいろしてくれるの?」 「依頼人の知りたい権利には、必ず応えないといけないからな」 「本当にありがとう」 「もう一日丸亀にいるから、また何かあれば連絡する。絶対にお父さんの居場所を捜してやるから、もうおかしなことはするなよ」 「大丈夫、していない。もう絶対にしないから」 電話を切ってからすぐにT社に連絡し、プライベートでひとつ公簿を取って欲しいことを伝えた。特急だと明日の朝には手に入るとのことだった。 「費用はいくらかかりますかね?」 「岡田君の頼みやから実費でええよ。それより一件、結婚調査を頼まれてくれへんかな。そんなに急ぎやない。来週からかかってくれてもかまわへんから」 私は了解した。こうなったらいくらでも仕事を持ってこい、何でも受けて、東奔西走の探偵になってやる。 |
| 二十三 |
|---|
|
「岡田君の依頼やから超特急で取らせたわ。ファックスが届いたから、読み上げまっせ」 急いでメモする。「早う、帰ってきなはれ」と部長は言って電話を切った。帰ってる場合ではない。 公簿による沢井家の本籍となる実家所在地は丸亀市土居町一丁目だった。地図で位置を確認すると、今いる丸亀城からわずか一キロあまりの距離だ。丸亀プラザホテル前の京極通りを東へずっと歩いていくと土器川にあたる。蓬莱橋の手前を土手沿いに南へ少し歩くと土居町だ。 はやる気持ちを抑え、首筋を流れる汗をぬぐいながら急ぐ。当該地はいったん土器川の土手を上がり、そして川床に降りたところにあたっていた。一軒の老朽化した建物が川沿いにやや傾き加減に建っていた。それは川沿いというよりも、川の畔に建っていると表現したほうが当てはまった。だが近づいてみて、私は思わずその場に立ち尽くしてしまった。 建物はすでに廃屋と化してしまっていたが、それは年月による風化のためやむを得ないとしても、木造平屋建の住居跡は川の満潮時には床下が水に浸かるのではないかと思われるほどの位置にあった。河川敷から数段の石垣の上に建っていたが、目の前は川なのだ。廃屋は玄関の扉が板で打ち付けられて中に入れなくなっていた。本当に沢井家は遠い昔にここに住んでいたのだろうか。周囲にはこの廃屋以外に住居跡のようなものは何もなかった。 沢井家について、土手向こうの住宅を訪ねてみることにした。その一帯には古くからの住宅が密集していたが、沢井家とは土手と道路とで大きく隔てられていた。何軒かを訪ねてみたが、平日の午前は不在がほとんどで、応対に出てくれた人もやはり沢井家のことは知らなかった。絨毯式に一軒一軒、丁寧に根気強く訪れてみる。そして一時間あまり経って、ついにひとりの老人から話を得た。 「市の所有地ですが、建物は今も残っていますよ。土手向こうでも同じ組でしたから付き合いはありましたな。駅の近くで川魚屋さんをされていたのですが、昔のように魚も獲れなくなってね。もうずいぶんと前に廃業されて、その後はスーパーの鮮魚店で働いていたようですが、病気で早くに亡くなりました。娘さんは何か重い病気で、徳島の療養所に入られましたな。息子さんは大阪に出られて、向こうで結婚したと風の便りに聞きました。しかし、古い話ですなあ」 高齢だがしっかりした語り口調の老人だった。 昔、真鈴の父一家はこんな川の畔で暮らしていたのだ。もちろん彼女がまだこの世に存在しないころだが、それにしても川縁に廃屋のまま放置されていた父の実家跡の光景が、私の脳裏にいつまでも焼き付いて離れなかった。 老人が語ってくれた娘さんとは真鈴の父・沢井圭一の姉、つまり伯母にあたる人物のことだ。姉が徳島の療養所に入ったと老人は語っていた。病名や療養所について訊いてみたが、そこまでは知らないとのことだった。三枝さんから得た「徳島」のヒントがこの老人から回答が出た。おそらく真鈴の父は姉の療養所に立ち寄っていたのだろう。私は急いでT社の部長に電話をかけた。 「部長、先ほどの公簿をもう一度見てもらいたいのです。沢井家の原戸籍に沢井圭一の姉に当たる人物の記載がありませんか?」 「あるある、沢井悦子という姉がいるようやな。メモ、いいかな?生年月日は・・・」 「生年月日は要りません。今の住所を知りたいんです。附票があるはずです」 「附票だと、徳島県美馬郡穴吹町口山字宮内・・・穴吹療育園となっとるな。療育園というくらいやから何か病院のようなものなんかね?岡田君」 「そうかも知れません。部長、悦子はまだ生きていますよね?」 「死亡届がないということは、まだ生きているやろ」 私は礼を言って電話を切った。「早う、こっちへ帰って来なはれ」と部長はしつこく付け加えた。しかし、本当にそれどころではなかった。ほぼ駆け足で丸亀駅へ戻り、駅前でレンタカーを借りてすぐに向かった。坂出ジャンクションで高松自動車道に乗り、五十キロほど走ると川之江ジャンクションで徳島自動車度へ入る。東へ東へとさらに五十キロあまり、ブッ飛ばして三十分ほどで脇町出口となる。そこから美馬郡穴吹町口山字宮内へは国道四百九十二号線を南へ下って行く。下ると言っても実際は山道を登って行くのだ。吉野川にかかる穴吹橋を渡って、緩やかな山道をグングン走る。私の愛車とは比べものにならない性能だ。そろそろ車を買い替えないといけないなと思うが、愛車には長年ともにした思いがあるから手放せない。乗りなれた車をなかなか手放せないのは、強い安心感があるからだ。それは男女関係でも同様である。相手への安心感がこころの中にドカンと根をおろしている間は、その居心地の良さから抜け出せない。次の相手の新鮮さが、今の相手との安心感や居心地良さを上回らない限り、ずっとそこにこころは滞在する。そんなことを考えながら、穴吹川に沿って曲がりくねった道を登って行く。宮内小学校近くに郵便局があり、車を止めて穴吹療育園の場所を訊く。郵便局員は田舎の施設の場所など間違いなく知っている。真鈴の父は、もすかすると療育園に姉と一緒にいるかも知れない。焦りと昂ぶりとが半々くらい混ざった気持ちになる。 「ああ、穴吹療育園ね。この道をもう少し走ってから右折して下さい。すると小さな橋があります。それを渡ってさらに百メートルほど走ると大きな寺が見えますから、その横の道路を抜けたところに鉄筋の大きな建物があります。お寺の裏手になりますな」 親切に男性局員が教えてくれた。車に戻ると真夏の熱射でシートが今にも燃えてしまいそうだ。全身から汗が吹き出る。汗の玉を振り飛ばしながら車を走らせると、寺の向こうにその建物が見えた。「穴吹療育園」と、遠くからでも見えるように大きく書かれていた。 |
| 二十四 |
|---|
|
私は受付カウンターまで来てくれた若い女性職員に沢井悦子に面会したい旨を伝えた。「時をかける少女」の女優にみたいに爽やかな印象の職員だった。彼女は少し怪訝そうな顔をして「ご身内の方でしょうか?」と訊いた。身内ではないが、昔、すごく懇意にしてもらった者だと伝えた。胸の名札に「関」と書かれていた。関さんは「少しお待ちください」と言って奥に退き、上司に何か相談をしていた。それから再び駆けるように戻って来て、「それではどうぞ。靴はそちらの下駄箱に入れて、スリッパをご利用下さい」と優しく言った。私は緊張しながら関さんのあとに続いた。 中央の広いスペースは概ね円形で、ここから各所に廊下が枝分かれしていた。私が誘導されたのは左側の廊下のひとつで、少し歩くと子供の遊び場みたいに様々な玩具やアニメのクッションなどが置かれたガラス張りの広い部屋があり、どう見ても大人の男女が思い思いに無邪気に遊んでいた。廊下の突き当りがエレベータホールになっていて、私と関さんは三階へ上がった。そこからは渡り廊下になっていて、その先には鉄筋の建物が廊下の窓から見えた。穴吹療育園は外からは想像できないほどの巨大な施設だった。廊下の突き当たりに再びエレベータがあり、今度はツーフロア降りた。でもそこは別棟の三階のようだった。 最初に訪ねた建物の三階が渡り廊下でもうひとつの建物の五階とつながっていた。山間部に建てられたこの施設は、渡り廊下でつながった建物が、その立地によってこのようになっていた。エレベータを出て少し歩くと両側に病室と看護師詰め所があり、その向こうに診察室が見えた。病室はいずれもガラス張りで、窺えるすべての人たちが身障者や高齢者だった。関さんは私を控え室のようなところに案内した。 「ここで少しお待ち下さい」と彼女は言って部屋を出ていった。しばらくして白衣を着た小柄な中年男性と一緒に関さんは戻って来た。男性は医師で「西川です」と言った。 「沢井悦子さんにお会いしたいと仰せでしょうか?」 西川医師は受付での関さんと同様に怪訝そうな顔をした。私は「そうです」と答えた。 「彼女はもう誰かを識別する状態ではありません。それでもお会いになりますか?」 西川医師は少し困ったような表情で言った。やはりそうなのか。廊下から見えた知的障がい者や身障者の様子、それにこの施設の雰囲気からして、ここは一般の病人向けの施設ではないことは確かだった。療育園という名称からして想像できたではないか。ちょっとまずかったかなと思った。急ぎ過ぎているのかも知れない。でも、真鈴の顔が頭に浮かぶと急がざるを得ない気持ちになるのだった。 「先生、実は沢井悦子さんにお会いしたいのではないのです」 「どういうことでしょう?」 「悦子さんの弟さんがこちらにいらっしゃらないかと思って、突然伺ったのです」 私は岡田調査事務所の名刺を一枚渡した。西川医師は名刺の裏表をしばらく見ていた。そしてそれを隣の関さんに手渡した。 「沢井様はこちらにいません。でもあなたはなぜ彼とお会いされたいのでしょうか?」 西川医師は穏やかな物腰で訊いた。 「ご身内からの依頼で沢井圭一さんを捜しているのです。決して悪い目的ではありません」 「沢井さんの居所を探していらっしゃる?それは不思議ですな」 西川医師は腑に落ちない顔で言った。私は沢井氏の行方が分からなくなった事情をかいつまんで説明した。 「ともかく私が知っていることはわずかです。大阪で会社を経営されていて、ときどき悦子さんを見舞いにこちらにお見えでした。そのころはまだ微かに沢井様の意思が悦子さんに伝わっていたようでした。でも、もう何年前になりますか、悦子さんの具合が悪くなって、弟さんのことも認識できなくなってしまったのです。それからは年に一度お越しになる程度ですが、確か大阪にお住まいのはずです。悦子さんに何か緊急事態が起こったときの連絡先を聞いていますが、居所を捜されているとはどういうことなのでしょう?」 「その連絡先は、もう今は使われていないのです」 「そうなのですか・・・それは困った。でも前回は昨年九月のお彼岸の時期に来られたように記憶しています。今度来られたときに新しい連絡先をお訊きしておきましょう」 いずれにしてもここに沢井圭一はいない。姉の病状が悪化して、沢井氏を弟と認識できなくなったことが関係しているとは思えないが、彼は年に一度程度しか訪れなくなったという。秋の彼岸といえばあと二ヵ月後だ。沢井氏は今年もここに来るのだろうか。 私は西川医師と関さんとに誘導されて沢井悦子と少しだけ面会した。彼女は車椅子に乗って、患者が談笑するスペースでほかの障害者と一緒にテレビを見ていた。 「こんにちは」 私は声をかけた。痩せ細った沢井悦子は首をこちらに向けた。 「ごいうーわぁ・・・」 文字で表すとそういう言葉で、唇を不自由に歪めながら言葉を返してくれた。私は精一杯の微笑を彼女に送った。こころの下部のあたりから胸に突き上げて来る何かの感情があった。そしてそれは鼻の奥にまでガツンと来た。 「悦子さんは先天的なものではありません。おとなになってから人間関係の絡みで頭部に大きな衝撃を受けて、それを最初に治療した病院が間違った手術を行った可能性があります。当時彼女は複雑な状況だったようで、そのころのキチンとした証拠は取れず、補償請求ができないのです。ここに来たときはまだ車椅子ではなかったのですが、平衡感覚に問題があって、あちこちに頭をぶつけるのです。ヘッドギアをつけるようにしたのですが、すでに脳の衝撃が大きすぎて、後遺症が出てこういうふうになってしまいました」 西川医師は説明した。私は口に出すべき言葉が浮かばなかった。 「突然伺ったにもかかわらずご丁寧な対応をくださり、ありがとうございました」 ふたりは玄関口まで送ってくれた。駐車場へ戻る私の気持は落胆と遣る瀬無さと、自分自身への苛立ちを感じていた。西川医師にしても、悦子に万が一の事態が生じたときの連絡先が通じないと困る。今年のお彼岸を待てば沢井氏が現れるかも知れないが、そんな簡単なものではない。徳島自動車道から香川自動車道へ入るころには日が暮れはじめた。真鈴の父が菩提寺を訪れていたことと、父の姉の所在と現況が判明したことは大きな成果なのだが、私は敗残者のような気分で帰路についた。 |