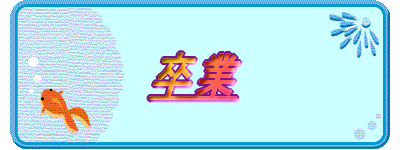
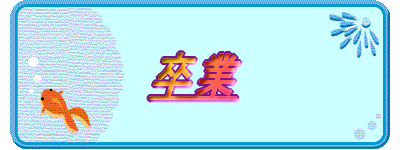
| 三十七 |
|---|
|
八月も下旬にさしかかったある日の夜、有希子から夜遅くに電話がかかってきた。 「遅くにごめんなさい」 「いや、まだ起きてたから大丈夫だよ」 「今、少し話してもいいの?」 有希子は深刻そうな声で遠慮がちに言った。 「いったいどうしたの?」 「実はね、今日病院へいってきたの。そしたら、片方の乳に腫瘍ができてるって」 「えっ?どういうことなのかな」 「前から右のおっぱいにシコリがあったのよ。痛みはないけど前より大きくなったみたいだから病院で診てもらったの。そしたら腫瘍らしいの。悪性か良性かは来週のはじめに分かるけど、すごいショック」 「それって、乳癌ということ?」 「それが来週分かるのよ。もし乳癌だったらどうしたらいいのか途方に暮れるわ」 乳癌がどんなものなのか全くの無知だが、もしそうだとしたら手術しないといけないだろう。 「ともかく結果を待とう。結果が出ないうちからあれこれ悩んでもしょうがないじゃないか。だから落ち込むな」 「分かったわ。そう言ってくれると少し安心した。遅くにごめんなさい」 有希子は電話を切った。 そしてその一週間後、近県の調査で数日駆けずり回っていた私のスマホが鳴った。着信は有希子からのものだった。応対に出て彼女の元気のない声を聞いた瞬間、私は悪い知らせだと直感した。 「この前の検査の結果が出たのだけど、やっぱり乳癌だったのよ。明日入院してすぐに切除手術することになったの」 有希子は不安がった。私は適切な言葉が見つからなかった。 「どうしたらいいのやろ・・・途方に暮れるわ」 有希子は電話口で泣きはじめた。様々なことが一気に頭の中を襲ってきた。女性の身体はデリケートなものだと知っている。もしかしてふたりの間に子供ができていれば、このようなことにはならなかったのではないか。 「ともかく、病院はどこなんだ?明日行くから」 「奈良の総合医療センターよ」 「分かった」と言って私は電話を切った。 少し前、鹿児島へ真鈴の父を訪ねた翌日、明け方にフェリーで大阪に戻り、疲れて眠っていたらベッドわきに有希子が立っている夢を見たことを思い出した。有希子は「大変なのよ、どうしていいか分からない」と言っていた。何が大変なんだと訊くと、急に顔がどす黒く豹変し、目が釣り上がって口は大きく横に広がり、牙を見せ、そしてその顔を近づけて「何で私たちに子供がいないの!自分勝手なことばっかりして、あなたなんか死んでしまえばいいわ!」と、まるで地底から唸りをあげるような太い声で私を罵った。あのときの有希子の鬼の形相が今鮮明に蘇ってきた。夢のことが現実となってしまうのか。 奈良総合医療センターは近鉄奈良線の新大宮駅から南へ十数分歩いたところに所在していた。午前中に入院手続きを行って、午後一時から主治医の説明があり、彼女の両親も当然同席する。私は顔を合わせたくなかったが、避けられないことだった。 受付で本日入院した岡田有希子の部屋を訊いた。まだ離婚していないのだから彼女が岡田姓を名乗っているのは当たり前だが、今更ながら不思議な気がした。有希子の病室は南病棟の六階の相部屋で、入ってみたがベッドに彼女の姿はなかった。一階の外科診察フロアへ降りて看護師に尋ね、教えられた診察室に入ると、すでに有希子の両親も来ていた。 「何と言って良いか・・・信じられないことです」と私は挨拶をした。彼らは軽く会釈しただけで言葉もなかった。意外に若い主治医が説明をはじめた。医師はパソコンの画面に取り込まれた有希子の右の乳房のレントゲン写真を見せながら説明を行った。レントゲンの画像は私には分からなかったが、右の乳房をすぐに切除しなければいけないことは理解した。手術は明日実施される。 説明が終わって有希子は病室に戻った。両親も一緒にエレベータで上がった。エレベータの中でも、彼らは私に話しかけては来なかった。有希子は小さな声で「来てくれてありがとう」と言った。ベッドに有希子は横になった。両親は「必要な物は明日持ってくる」と言って、病室に戻ってから間もなく帰ってしまった。私にはひと言の声かけもなく、最初の会釈だけが彼らとの消えそうな関係を表していた。まるで有希子の乳癌が私の責任でもあるかのような態度に思えた。 「一週間程度で退院できそうなのよ。でも排泄の回復具合によってはもっと早くなるかも知れないわ」 有希子はまだ手術前なので、普段の状態と全く変わりはなかった。 「大丈夫かな?」 「不安だけど、切除るするしかないものね」 有希子は元気のない声で言った。確かに僕たちは五か月ほど前に別居状態になった。原因は私の甲斐性の無さは確かにあったとしても、彼女の両親が物言いをつけて引き裂いたのだ。だから両親の私への不満はある程度は理解できる。でも、それなら私を呼ぶなと思った。私を非難しているのなら呼ぶな。私は自分の気持のまま正直に生きてきた。その正直さが、金融業で独立したが客に情を挟みすぎて失敗してしまったのだ。私の考えは間違っているかも知れないが、この世の中ではたくさんの人間が多くの間違いを犯して生きている。法の裁きの対象とならない過ちを、人はいっぱい犯して生きているに違いない。私はビリージョエルのオネスティの歌詞を思い浮かべた。これまで正直に生きてきたが、それが誠実さに表れていたかは分からない。だが有希子の両親に非難される筋合いはない。 「ともかく明日は滋賀へ出張だから、帰ってきてからすぐに様子を見に来るよ」 「ごめんね、忙しいのに」 目の前の有希子を今も愛している。彼女は一歳年下だが、私より一年早く大学を卒業した。大学のキャンパスで私が何度断っても積極的に声をかけてきて、すぐに怒るおかしな女の子だった。もう十五年以上も前のことだ。その女の子が今ベッドに横になり、明日乳癌の切除手術を受ける。 人生は予測しないことの繰り返しだ。うまくいくだろうと思っていた金融業があっけなく潰れてしまうことや、女子高生を尾行中に捕まって恋愛関係に陥ってしまうことも、いずれもイレギュラーな出来事だ。イレギュラーなことの繰り返しこそが現代の人間社会とも言えるのだ。私は病院を出て近鉄奈良線で上本町まで戻った。そのまま帰らずに、駅の近くにある早い時間から営業している居酒屋でビールを飲んだ。大瓶を一本空けたところで真鈴のスマホに電話をした。 「どこにいるんだ?」 「家にいるけど、どうしたの?」 「何してるんだ?」 「明日から二学期がはじまるの。だからいろいろ準備している」と真鈴は言った。 「参った」 「えっ、何?」 「参っているんだ。僕だって参ることもある」 「何があったの?」 「うん、ちょっとな、奥さんがね。今度会ったときにちゃんと話をするよ」 「私、今からそっちへ行こうか?」 「嬉しいことだけど、今日これから君と会えば、間違いなく僕の意志が崩れてしまう。歯止めが利かなくなってしまうから来なくていい」 「いいじゃない、崩れたって、歯止めが利かなくなったって」 今の気持のまま真鈴と会えば、おそらく許されぬ方向に突き進んでしまって、あと戻りはできなくなる。真鈴の父みたいに彼女をさらって霧島温泉へ行ってしまうような気がした。 「辛いんでしょ?」 「辛いな、すごく」 「だったらすぐ行くから。私が辛いときに岡田さん、いっぱい助けてくれたじゃない。だから今日は私が助けてあげる」 私は涙が溢れてきた。店のカウンターの中の若い従業員が心配そうに見ているのが視界に入った。でも男だって泣きたいときは泣く。 「明日から学校、頑張るんだぞ。もうすぐお父さんも帰って来るんだからな」 「分かってる。岡田さん、好きよ」 「でもいろいろたくさん辛いな」 「泣かないで」 「うん、ところで今度一緒にホテルでテレビゲームをして欲しいな」 「いいよ、いつでも言って」 「じゃあ、もう少ししたら帰るよ」 電話を切って勘定をして地下鉄に乗った。車内には大勢の人たちがいたが、彼等の中にも辛くて泣きたい気持ちの人がきっといるのだろうなと思った。 |
| 三十八 |
|---|
|
九月が急ぎ足で駆けて抜けようとしていた。私が関わっている少数の人々の周辺は、幸せとは堂々と言えないかも知れないが、幾分落ち着いている気がした。 有希子は退院後の経過も順調で、これならもう少しすれば働けるかも知れないと言っていた。予告もなくやって来る癖も復活したようで、数日前の土曜日の朝、突然部屋に来た。先への進展も見えない半面、とくに後退もない別居中のおかしな夫婦関係が続いていた。ただ、有希子が来ているときの真鈴の気持ちが気になった。 その真鈴はときどき思い出したように電話をかけてきた。私がこの前「辛い」と弱音を吐いたことをずいぶんと気にしていて、「今から部屋に行ってもいい?」と、以前とは逆に向こうから来たがった。 「何があったのか話をしてくれてもいいじゃない。岡田さんと私とは塞き止めが崩れれば一気にどこかへ行ってしまう関係じゃないの。どうして打ち明けてくれないの?」 そう言って私を責めた。でもこの部屋で真鈴と二人きりになると、何かの拍子に今度こそ間違いなくダムが決壊してしまうだろうと思ったので、理由を付けて断っていた。 「何よ、前はこっちへ来ないかってしつこく誘ってたくせに」と彼女は不満がったが、まだ環境が整っていない。 私はこれまでの人生の失策を語って、それをキチンと聞いてくれて、同情や非難や共感などの感情を持って欲しい女性は、有希子なのかそれとも真鈴なのかを考えてみた。正直なところ、妻の有希子よりも真鈴が一歩リードしているような気がした。 九月最後の日曜日、朝からあいにくの雨だった。私は午前中、出来上がった調査報告書をT社へ届けたあと、スーパーで少し買い物をして帰って来た。マンションのエレベータのところまで来ると、確かに見覚えのある女性が佇んでいた。穴吹療育園の関さんだった。 「驚いたな、いったいどうされたのですか?」 「ごめんなさい、いきなり来てしまって・・・」 「電話してみたんだけどお留守だったから、いただいていたお名刺の住所を地図で確認して、途中の交番で訊いたの」 関さんはダークグレーのジーンズに数種類の色のタータンチェックのシャツを着ていた。穴吹療育園を訪れたときの事務服姿とは印象がずいぶん違っていて、すぐに彼女とは分からなかった。 「飛び石連休を使って京都と大阪に来ました。明日徳島に帰ります」 「旅行ですか?」 「そう。たまに山奥から出ないとおかしくなってしまうの」 関さんは不安そうな表情だった。穴吹療育園を訪ねたあと、思いがけず電話をくれたときも、「森さんみたいに、私も誰かにここから連れ出して欲しい」と言っていた。仕事自体は好きだが、山奥に長くいると気分が滅入ると語っていたことを私は思い出した。 「どうしましょう、ともかく僕の部屋に来ますか?汚いですけど」 関さんは頷いた。部屋に入り、関さんをリビングの椅子に座らせてコーヒーを淹れた。真鈴が万が一、この様子を見ていたとしたら、依頼人が来たんだと言い訳しようと思った。 仕事関係の書類が散らかっていたテーブルを整理し、コーヒーカップを彼女の前に置いた。私も椅子に座り、一緒にコーヒーを飲んだ。関さんは私の動きや部屋の様子を不思議そうに眺めていた。 「お部屋をきれいにされているのね」 「ある程度はね。暮らしが荒んでいると、せめて部屋だけでも普通にしておきたいですからね。部屋も荒れ放題で生活も荒んでいると惨めじゃないですか」 「分かる気がします」と関さんは同意した。 「ひとり旅ですか?」 「そう、いつもひとりなの」 「彼氏はいないの?」 「うーん、少し前までは中学校の同級生と付き合っていたんだけど、遠距離恋愛だったからうまくいかなくて別れました」 関さんは、微笑んで言った。 「まだまだ若いし、これからいくつも恋愛しますよ。問題ない」 私は慰めにもならない無責任な言葉を関さんに与えた。彼女はまだ二十代半ばの年齢に見え、態度は落ち着いていたが、その落ち着きは少し脆さを感じさせた。 「沢井さんのことではとても感謝しています。あなたの情報がなければ、彼を捜すことができませんでしたから。あらためてお礼を言わせていただきます」 「見つかってよかったですね。森さんも一緒でしたか?」 「いえ、沢井さんとその森さんという女性とは、すでに別れていたようです。ただ、ときどきはお会いされていると仰っていました」 「そうなんですか・・・」 関さんは残念そうな表情をした。 「もしよろしければ、大阪市内を少し案内しましょう。今夜のホテルはどちらですか?旅行バッグはここに置いておけばいいです。帰ってきてからホテルまで送りますよ」 「ホテルは東急インというところです。じゃあ、厚かましく案内してもらおうかしら」 「東急インはすぐそこですね。僕は暇だし、情報を提供していただいたお礼です、全然気にしないで下さい。」 関さんを最も大阪らしいところに案内した。私がそう思った場所は、先ずは通天閣の周辺だった。地下鉄堺筋線の扇町駅から乗って恵美須町で降りた。雨はすでに止んでいて、真夏の興奮状態から少し落ち着いた太陽が濡れた路面をキラキラと照らしていた。少し寂れた商店街を抜けると通天閣の下に着く。東京タワーとは比べものにならないくらい低くて華やかさの欠片も感じられないが、大阪の象徴のような気がして好きだ。四階の展望台から見る大阪の街は箱庭のような美しさは全くなく、薄汚れたり赤茶けたりした建物ばかりが無造作に造られた印象があり、それが逆に大阪らしい風景とも言えた。 「京都とは全然違う街並みね」と関さんは言った。 「京都は街が碁盤の目に整っていますからね。人々の心も整っていて落ち着いています。大阪はグチャグチャな街並みで、無茶苦茶な人々が多いですね。僕もその一人だ」 「岡田さんって面白いことを言うのね」と彼女が笑った。 通天閣を出て、天王寺動物園方向へ歩いた。途中、新世界本通り商店街を抜けて「ジャンジャン横丁」を歩いた。特製ソースに二度づけお断りで有名な串カツ屋に少しだけ入った。関さんは昼間から将棋に興じている人々に驚き、串カツ屋の活気と、どて焼きの美味しさに眼を丸くし、大声で交わされる大阪弁に戸惑っていた。 「大阪弁って、まるでふざけているようにしか聞こえないわ」 「ふざけているわけじゃないんだけどね。つまり、気さく過ぎるという感じなのかな?」 私は説得力のない説明をした。それから天王寺公園を少し歩き、JR天王寺駅から大阪環状線外回りに乗って天満で降り、扇町公園を斜めに貫いて部屋に帰ってきた。彼女の旅行バッグを持って再び部屋を出て、東急インへ歩いた。 「さっき串カツを食べたばかりだけど、もしよければ夕食をいかがですか?」 「そうしていただけたら嬉しいです。ひとりじゃつまらないから」 関さんはチェックインして旅行バッグを部屋に置き、それからホテルの裏側の阪急東通り商店街にある居酒屋で食事をした。食事といっても私はもちろんビールを飲んだ。関さんは「私、お酒が大好きなの」と言った。 「それは素敵なことです。お酒を嗜まない人は人生の喜びの三割を失っているからね」 「面白いことばかり言う人ね、岡田さんって」 関さんはよく笑った。歯が真っ白で、とても魅力的な笑顔だった。いつもカフェオレばかり飲んでいるんじゃないかと思っていたが全く違っていて、彼女は生ビールを三杯も立て続けに飲んだ。そして「あんな場所で仕事を続けていると、ときどき疑問を感じるの」と言った。 「分かります」と私は同意した。 「だから半年に一度は数日旅行するの」 笑っていた関さんは、今度は悲しそうな表情になった。表情がよく変わり、大きな瞳がクルクルと忙しく動く関さんは、感情が落ち着かない様子だった。 「旅はこころのカンフル剤だからね。人生は終わりなき旅のようなものです」 私は素直に共感した。関さんは「ウフフ」と笑い、ほんの少しホッとした顔になった。 「私は西条で生まれ育ったの。高校を卒業して大学へ進学しようかどうか迷ったんだけど、結局、介護資格の学校を選んだのよ。それがこの仕事をするきっかけになったの」 「愛媛なの?僕は今治だよ。ずっと長く帰っていないけどね」 「偶然ね、今治と西条って近いよ。そうだったんだ。でも私も二年近く帰っていないな」 「なかなか帰れないんだよな。帰れば、ちょっと胸が締め付けられるような気持ちになって、自分が惨めになるんだよ。だから帰りたいけど帰れないんだ」 故郷に戻れば幼少時から若いころの思い出が蘇る。嫌な思い出も楽しかった思い出も、すべて懐かしいものとして蘇るのだが、それらすべてに切なさをも同時に感じてしまう。街の風景も人々の様子もすべて思い出となる時代から変化して、元のものは根こそぎ失われ、壊れてしまったような切なさを感じる。変化することが当然だとしても、自分の居場所がもう残っていない現実に、無意識に足が遠のいてしまうのだ。 「その気持は私にも分かるわ。駅に降りたら何かわからないけど胸が一杯になって、実家が近づいてくると歩きながら涙が出てきて、家に入るまでにいつもそれを拭くの。岡田さんの言うようになぜか切ないのよね」 関さんの表情が再び曇った。彼女も様々なことで苦悩しているのだろう。居酒屋を出てから私たちはパブ風の店に入った。彼女はかなり酔っていた。私はダイキリを、関さんは軽いカシスオレンジを飲んだ。このような男女のシチュエイションはかなり危険だということは分かっていた。きっと、彼女を部屋まで送っていけば男女の関係に突入してしまうだろう。でもそれがどうなるというのだ?ふたりの未来に何が開けるというのだ?だから関さん、君は魅力的だ。とても素敵だ。君と一緒にどこか遠くの果てまで翔んで行ってしまいたいくらいだ。でも今夜はだめだ。 私と関さんは店を出て東急インの方向へ抱き合うようにして歩いた。背中と腕を支えてやらないといけないくらい彼女は酔っていた。でも私の心配や予測を、まるで天使の矢で突き刺してしまうかのように、「じゃあ、岡田さん。おやすみなさい。今日はすごく楽しかったです」と言ってフロントでキーを受け取り、エレベータ方向へ行ってしまった。呆然とする私に、彼女は三歩ほど歩いてから振り返り、「また電話していいですか?」と訊いた。「もちろん、いつでも」と私は力を振り絞って返事した。関さんはウフフと笑って消えた。 部屋までの帰り道、「人間はなぜ生きていかなきゃいけないのだろう?」と思った。そして「人として生まれたからには、それを先ず喜ぶべきだ。そしてどんなに苦しいことがあっても、決して投げやりになってはいけない」と自問自答した。少し前に真鈴に説いた言葉を、関さんと別れてその帰り道に反芻した。私はずいぶん疲れていた。 |
| 三十九 |
|---|
|
秋も深まり、有希子と別居してから半年近くが過ぎ去った。でも別居しているからと言って夫婦仲に大きな亀裂があるわけではなく、ほぼ毎週土曜日は私の部屋に前触れもなくやって来る。私は有希子と一緒にいると、ぬるま湯に浸かっているような地良さをいつも感じた。彼女の病状は、退院後一時は体調が良好に向かっていたがやはり安定せず、仕事ができるまでの回復には至らなかった。 「あなたにこんなことを言うのは気がひけるのだけど、先のことを思うと不安で眠れないの。どうしたらよいのか分からない」 有希子は電話で嘆いた。 でも実家は裕福だし、ひとり娘の有希子を離そうとしない限りは、私たちが元のように同居することは難しいと考えていた。 十一月も半ばを過ぎ、私は四十歳となった。二日間、長崎へ所在調査の仕事に出て、週末の金曜日の夜に大阪に戻り、疲れた身体を引きずってそのまま「安曇野」を覗いた。 「あら岡田さん、お久しぶりね。岡田さんにはいつもお久しぶりって言っているような気がするわ」 いつものように女将さんが言った。 「でも、そのとおりですから」と私は返事してカウンターの片隅に腰をかけた。 「疲れていらっしゃるようね」 「強行軍で参りました。壱岐という島を訪れたのですが、カラスミがとても美味しかった」 「壱岐ってどこかしら?」 「ほら、福岡からずっと北の方の韓国への途中にある小さな島でんがな。ね、岡田さん」 常連客のひとりが言った。 「そうですね、でもあそこは長崎県なんですよ」 「そりゃ知りまへんでしたな。てっきり福岡県とばかり思ってましたわ」 「岡田さんって、何をしていらっしゃるのか分からないわね」 女将さんが笑って言った。 明後日は有希子と会うことになっていた。今後のことをじっくりと話し合う必要性からだった。そのことを思うと私は憂鬱な気分になった。自分の幸せだけを考えれば有希子のことは深く考えなくてよい。でも、私たちは夫婦だ、そういうわけにはいかない。私は何か画期的な策がないかを考え続けていた。二本目のビールを飲み干したときにスマホが鳴った。真鈴からだった。 「家のほうに電話したら留守番テープだったから」 「九州に仕事で出ていたんだ。少し前に帰ったばかりだよ」 「そうだったのね。実はね、お父さんが今月最後の日曜日に帰ってくるの」 「最後の日曜日って二十八日だな。うん、それはよかった。本当によかったな」 「今どこなの?」 「今か?そうだな、とても素敵な女将さんがいる店だ」 「そうなの・・・岡田さんと会いたい。今夜帰ってきたら、部屋に行ったらだめ?」 「だめだ」 「・・・分かった。じゃ、おやすみ」 電話が切れた。今すぐこちらからかけなおしたい気持を抑えた。「あら、どうされたの?」と女将さんが心配そうに訊いてきた。 「可愛いい女の子の誘いを断ってしまいました」と私は返答した。「アハハハ、本当に岡田さんって可笑しいわね」と、腹が立つほど女将さんが笑った。 部屋に帰ると留守番メッセージランプが点滅していた。再生ボタンをプッシュした。二日間の出張中にたくさんのメッセージが残っていて、その中にはT社の部長からのものもあった。 「九州案件に行ってもらったばかりで悪いけど、来週か再来週の頭でもええから、東京の企業調査と新潟の所在調査があるんやけどなあ。頼まれてくれへんかな」と彼は懇願していた。この際、何でもやってやるよ。金も欲しいし、本当に東奔西走の探偵になってやるからどんな案件でもいっぱい持って来い。有希子からのメッセージは明後日の時間と場所の確認だけだった。そして最後のメッセージは真鈴からのものだった。 「何よ、馬鹿!だめだなんてハッキリ言わないで。私、まだ女子高生よ。繊細な女子高生なんだからね。岡田さんの馬鹿!」 留守番テープには電話をガチャンと切る音まで残っていた。 「でも真鈴、君はいつも『私、もうおとなよ』って言うじゃないか」 私は小さく声に出して呟いた。 |
| 四十 |
|---|
|
二日後の日曜日。私は近鉄奈良線の東生駒駅近くの喫茶店で有希子と会った。有希子は十日ほど前に部屋に来たときより顔色が悪く、話す声もか細く弱々しかった。 「それで、君の両親は早く離婚しろって言うのか?」 「そうなのよ。岡田の姓から鈴木に戻せって、何を考えているのか分からないわ」 きっと鈴木家の財産に関係することから、離婚を急いでいるのだろうと私は思った。縁起でもない話だが、ひとり娘の有希子は鈴木家の財産のただひとりの相続人だ。私が関係していたら、万が一の時にはアカの他人に財産がいってしまうことを危惧したのだろう。有希子がこういう状態の時に、嫌悪すべき考え方だと思った。 「僕が金融業を失敗して君に心配をかけた。これは事実だし、金銭面でも苦労させたよね、悪かったと思っているよ。でも夫婦って、良いときも苦しいときも分かち合っていくものじゃないのかな?君の両親の気持ちがよく分からないよ」 両親が実家に帰って来いと言って、それを拒否しなかった有希子にも言いたいことがあった。 「世の中には難しい状態に陥っている男女や夫婦が無数にあると思うよ。それらすべてを結果や善悪で結論付けてしまうのはどうかな?君の生真面目なところは理解しているよ。それが君の良いところでもあるんだから。でもね、人間は多くの過ちや失敗を犯しながら生きているんだよ。だから、一度くらいは大目に見るという優しさや寛容さが、人間には必要なんじゃないかな。僕の失敗を許さずに、君の両親は離婚を勧めている。自己弁護をする気持ちはないよ。ただ、癌を患って苦しんでいる状態の君に、過度な心労をかけるのは、親としてはどうなんだろうと思っているんだ。先ずは有希子の病気が良くなることが第一なんだからね」 有希子は話の途中から涙ぐんだ。彼女の苦悩も分かるが、こうなった経緯は含まれていない。でも私は弱くなっている人間を前にして強くは言えなかった。 「ともかくもう一度よく考えてみるよ」 一時間半ほどで有希子と別れた。部屋に戻ると、T社からファックスが数枚届いていた。留守番電話に入っていた東京の企業調査と新潟の所在調査の指示書だった。 企業調査は東京に本社を置いているマルチレベルマーケティング企業の実態調査だった。所在調査は、依頼人が関西に住む複数の身内で、遺産相続に伴い、ひとりだけ行方が分からない同胞の所在割り出しだった。もう二十五年も居所が分からないらしいとあった。何で今ごろになって捜そうとするのかといえば、所在が不明な相続人がいると遺産相続手続きが進まないかららしいのだ。その身内のことを心配しての調査ではない。遺産という金銭をめぐっての仕方なしの調査なのだ。二十五年も会わない同胞たちとはいったい何なのだ。いずれにしてもこの二件の調査は、共に金銭欲に関係しているものだった。馬鹿げている。 私は調査資料を整理し、調査日程をあらかた組んだあと、真鈴に電話をかけた。彼女はまるで電話を待っていたかのようにすぐに出た。 「今、何しているんだ?」 「何もしていないわ。そろそろ勉強しようかなと思っているの。お父さんが一年浪人して大学を受ければ良いって言ってくれたんだけど、早めのスタートが大事なの」 「それは良かったな、君ならどこの大学でも歓迎されるに違いないよ」 「岡田さん、声が少し震えているよ。寒いの?」 「生きているといろいろと辛いことがあるからな」 「何言ってるの、岡田さんらしくない弱気な言葉」 「お父さん、優しくしてくれるか?」 「うん、すごく」 「それはよかった。お父さんがもし君を泣かせたりしたら、僕は許さないからな。絶対に許さない」 「どうしたのよ、岡田さん。何があったの?そっちに行っていい?」 「いや、来なくていい」 「でもちょっと伝えたいことがあるのよ」 「何かな?」 「お父さんが、この部屋は狭いから、以前住んでいた堺市のあたりでもう少し広い部屋を借りて引っ越そうって言うの。年内に引っ越すかもしれないの」 真鈴まで私の元から遠く去っていくのか、しばらく返事ができなかった。 「岡田さん、聞いてるの?」 「聞いてるよ、ちょっとショックだなって思っただけだよ」 「お父さん出かけてるから、そっちへ行っていいでしょ、だめ?」 「ダメだけど、今すぐ会いたいんだ。外で会おう」 「いいわ、エレベータ前で待ってる」 「万が一、お父さんと鉢合わせしたら嫌だから、悪いけど君が僕を捕まえた京橋駅で会おう。僕を捕まえた駅の二階のエスカレータのあたり、憶えてるかな?」 「分かったわ」と真鈴はシリアスな声で言った。このときの「分かった」という言い方は、私を捕まえてからこの日が来るまでの必然性を「分かった」と言ったように聞こえた。 |
|
年も明けて一月は慌ただしく終わり、二月は逃げる三月は去るというふうに過ぎ去り四月になると、有希子と別居して一年が経つのだと妙な感覚に陥っているまもなく、五月は北海道や沖縄の身上調査に追われて、ようやくホッと一息ついたのが六月だった。 私はいつものようにベッドから起きて窓の外の兎我野町のビル街を眺めていた。仕事に追われていると自分の今の状況を客観的に見れなくなってしまう。日々だけが大急ぎで通り過ぎていき、季節の変化に気づいてため息をつく。 だが、季節が移り変わっても、この部屋の窓から見える街並みは変わらないし、有希子とも別居状態のままだ。彼女は乳がんの切除手術後、一時体調を大きく崩していた時期があったが、今はかなり回復していて、2週間に一度の間隔で土曜日にこの部屋にやって来る。 探偵業の仕事としては、そろそろ電話番と事務を手伝ってもらう人を雇う必要があるほど順調で、前の金融業のテツは踏まない自信を持てるまでになった。もうしばらくこのまま利益が続けば有希子を呼び戻したいと考えていた。 真鈴は昨年末に父が六年半ぶりに帰って来てから、もともと家族で住んでいた堺市に、少し広めの賃貸住宅を借りて引っ越し、電話やスマホはときどきあるが、会うことからは遠ざかってしまった。私の仕事がずっと多忙だったこともあるが、今このように一段落してみると、ここ数日寂しさを感じていた。 そしてそんな私の気持ちをまるで見通しているかのように、久しぶりに真鈴からLineではなく電話ががかかって来た。 「真鈴です。今何しているの?」 「ああ君か、さっき起きたところだよ」 私は彼女の質問に的確に答えたつもりだった。午前十一時。 「ああ君かって何よ。失礼ね」 「あっ、あなた様でしたか。お久しぶりです。いかがされましたか?」 「・・・からかっているのね、もういい!」 ブチッと音まで聞こえるほどの勢いで電話が切れた。相変わらず彼女は気が短すぎる。ちょっと悪かったかなと思ってすぐに電話をかけた。 「悪かったよ。でもそんなに怒ることないだろ。ユーモアだったのに」 「・・・・・」 「悪かったよ。謝るから」 「もうお昼前だよ。相変わらずだらしないのね」 「そんなことはないよ。日本の政治を憂いていたところだ」 「・・・・・馬鹿みたい」 「受験勉強、頑張っているんだろうな」 「当たり前じゃない。岡田さんみたいにダラダラしていないから」 昨年の夏、真鈴の父の居所を捜し続けていたころ、「どうして私にそんなに親切にしてくれるの?」としおらしい声で彼女は何度も訊いてきた。私はその質問に対して「僕のような優秀な探偵が初めて捕まったのが真鈴だからだ」と答えた。それは本当の気持だった。私のようなベテラン探偵の尾行に気づいた真鈴。意外な力で腕をきつく掴み、京阪電鉄京橋駅の駅長室へ引っ張っていった。目に涙をいっぱい溜めて「誰に尾行を頼まれたのですか?もしかして私の父の依頼ですか?」と睨みながら訊いてきた真鈴。 「君の尾行を頼まれたのではない。依頼人の息子の動きを追っていたら君と接触したからなんだ」と答えると、ガックリと肩を落とした。あのころと違って、彼女は私に対して遠慮のない話し方になっていた。それを親しさのバロメータと考えるのなら決して悪くはない変化なのだが、正直言って少し戸惑いを感じていた。 「少しでもいいの。今日会いたい」 「受験勉強に影響はないのか?」 「しつこいよ、少しくらい息抜きが必要なの」 気だるそうな口調で真は言った。いきなりの電話と我侭な口調。こういうときは絶対にあとには引かないのだ。一年数か月の付き合いで、私はいつの間にか彼女の性格の隅々まで熟知しているような気がした。 「分かった。どこに行けばいいかな?」 私たちは午後一時に大阪環状線の天満駅の改札口前で会うことにした。外は今にも雨が降りそうな鬱陶しい天候だった。 真鈴は午後一時を少し過ぎて改札口から出てきた。グレーと濃い緑のタータンチェックのミニスカートに薄いピンクのポロシャツを着て、茶色の布製ショルダーを引っ掛けていた。首を覆う程度までに伸びた髪が少しカールされていた。浪人生になってからもさらに綺麗になっていく彼女だが、最近は可憐な中にも少し生意気さも表に出てきた。 「やあ、久しぶりだな。お昼はまだだろ?」 私はいつもと変わらず言った。だが、真鈴は声かけを無視して。黙って先を歩いた。 「どうしたんだ、何かあったのか?」 機嫌の悪さを背中に表して、急ぎ足で商店街を突き進んで行く真鈴に追いつき、肩を並べてから訊いた。 「何もないよ。岡田さんに呆れているの」 「なぜ?」 「会ったらいつも最初にお腹のことばかり訊くんだから。何か食べようか、お腹は空いていないか・・・これまでそんなことばかり最初に言うよね。レディに対して失礼だよ。少しは可愛くなったねとか、髪形が変わったねとか、そういう気の利いたことが言えないの?」 「でもちょうどお昼どきだろう。お腹の具合を訊くのが当たり前じゃないのか?」 「馬鹿みたい。いつまでも子ども扱いしないでね。私、もうすぐ二十歳なんだからね」 そうだった。真鈴はもうすぐ二十歳だ。昨年の八月九日、彼女の誕生日に鹿児島の霧島温泉にいた父から電話があり、彼女はそれを私に報告して電話口で号泣した。あれからもうすぐ一年が経つのだ。 「そうだな、悪かったよ。ところで、久しぶりにプランタンにでも行こうか?」 「うん、行こう」 ようやく表情を少女のように崩して真鈴は頷いた。 |
|---|
| 四十二 |
|---|
|
年も明けて一月は慌ただしく終わり、二月は逃げる三月は去るというふうに過ぎ去り四月になると、有希子と別居して一年が経つのだと妙な感覚に陥っているまもなく、五月は北海道や沖縄の身上調査に追われて、ようやくホッと一息ついたのが六月だった。 私はいつものようにベッドから起きて窓の外の兎我野町のビル街を眺めていた。仕事に追われていると自分の今の状況を客観的に見れなくなってしまう。日々だけが大急ぎで通り過ぎていき、季節の変化に気づいてため息をつく。 だが、季節が移り変わっても、この部屋の窓から見える街並みは変わらないし、有希子とも別居状態のままだ。彼女は乳がんの切除手術後、一時体調を大きく崩していた時期があったが、今はかなり回復していて、2週間に一度の間隔で土曜日にこの部屋にやって来る。 探偵業の仕事としては、そろそろ電話番と事務を手伝ってもらう人を雇う必要があるほど順調で、前の金融業のテツは踏まない自信を持てるまでになった。もうしばらくこのまま利益が続けば有希子を呼び戻したいと考えていた。 真鈴は昨年末に父が六年半ぶりに帰って来てから、もともと家族で住んでいた堺市に、少し広めの賃貸住宅を借りて引っ越し、電話やスマホはときどきあるが、会うことからは遠ざかってしまった。私の仕事がずっと多忙だったこともあるが、今このように一段落してみると、ここ数日寂しさを感じていた。 そしてそんな私の気持ちをまるで見通しているかのように、久しぶりに真鈴からLineではなく電話ががかかって来た。 「真鈴です。今何しているの?」 「ああ君か、さっき起きたところだよ」 私は彼女の質問に的確に答えたつもりだった。午前十一時。 「ああ君かって何よ。失礼ね」 「あっ、あなた様でしたか。お久しぶりです。いかがされましたか?」 「・・・からかっているのね、もういい!」 ブチッと音まで聞こえるほどの勢いで電話が切れた。相変わらず彼女は気が短すぎる。ちょっと悪かったかなと思ってすぐに電話をかけた。 「悪かったよ。でもそんなに怒ることないだろ。ユーモアだったのに」 「・・・・・」 「悪かったよ。謝るから」 「もうお昼前だよ。相変わらずだらしないのね」 「そんなことはないよ。日本の政治を憂いていたところだ」 「・・・・・馬鹿みたい」 「受験勉強、頑張っているんだろうな」 「当たり前じゃない。岡田さんみたいにダラダラしていないから」 昨年の夏、真鈴の父の居所を捜し続けていたころ、「どうして私にそんなに親切にしてくれるの?」としおらしい声で彼女は何度も訊いてきた。私はその質問に対して「僕のような優秀な探偵が初めて捕まったのが真鈴だからだ」と答えた。それは本当の気持だった。私のようなベテラン探偵の尾行に気づいた真鈴。意外な力で腕をきつく掴み、京阪電鉄京橋駅の駅長室へ引っ張っていった。目に涙をいっぱい溜めて「誰に尾行を頼まれたのですか?もしかして私の父の依頼ですか?」と睨みながら訊いてきた真鈴。 「君の尾行を頼まれたのではない。依頼人の息子の動きを追っていたら君と接触したからなんだ」と答えると、ガックリと肩を落とした。あのころと違って、彼女は私に対して遠慮のない話し方になっていた。それを親しさのバロメータと考えるのなら決して悪くはない変化なのだが、正直言って少し戸惑いを感じていた。 「少しでもいいの。今日会いたい」 「受験勉強に影響はないのか?」 「しつこいよ、少しくらい息抜きが必要なの」 気だるそうな口調で真は言った。いきなりの電話と我侭な口調。こういうときは絶対にあとには引かないのだ。一年数か月の付き合いで、私はいつの間にか彼女の性格の隅々まで熟知しているような気がした。 「分かった。どこに行けばいいかな?」 私たちは午後一時に大阪環状線の天満駅の改札口前で会うことにした。外は今にも雨が降りそうな鬱陶しい天候だった。 真鈴は午後一時を少し過ぎて改札口から出てきた。グレーと濃い緑のタータンチェックのミニスカートに薄いピンクのポロシャツを着て、茶色の布製ショルダーを引っ掛けていた。首を覆う程度までに伸びた髪が少しカールされていた。浪人生になってからもさらに綺麗になっていく彼女だが、最近は可憐な中にも少し生意気さも表に出てきた。 「やあ、久しぶりだな。お昼はまだだろ?」 私はいつもと変わらず言った。だが、真鈴は声かけを無視して。黙って先を歩いた。 「どうしたんだ、何かあったのか?」 機嫌の悪さを背中に表して、急ぎ足で商店街を突き進んで行く真鈴に追いつき、肩を並べてから訊いた。 「何もないよ。岡田さんに呆れているの」 「なぜ?」 「会ったらいつも最初にお腹のことばかり訊くんだから。何か食べようか、お腹は空いていないか・・・これまでそんなことばかり最初に言うよね。レディに対して失礼だよ。少しは可愛くなったねとか、髪形が変わったねとか、そういう気の利いたことが言えないの?」 「でもちょうどお昼どきだろう。お腹の具合を訊くのが当たり前じゃないのか?」 「馬鹿みたい。いつまでも子ども扱いしないでね。私、もうすぐ二十歳なんだからね」 そうだった。真鈴はもうすぐ二十歳だ。昨年の八月九日、彼女の誕生日に鹿児島の霧島温泉にいた父から電話があり、彼女はそれを私に報告して電話口で号泣した。あれからもうすぐ一年が経つのだ。 「そうだな、悪かったよ。ところで、久しぶりにプランタンにでも行こうか?」 「うん、行こう」 ようやく表情を少女のように崩して真鈴は頷いた。 |