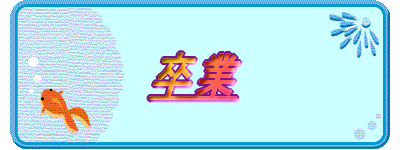
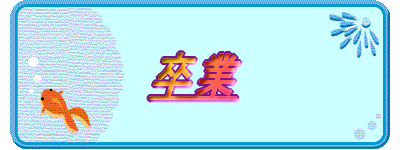
| 七 |
|---|
|
優秀な高校に通っている彼女、名前もまだこのときは知らなかったのだが、事務所開設後の最初の仕事が尾行、そして依頼人の息子と合流したのが沢井真鈴だ、私は何か予めシナリオが作られていて、それに従って動いているような錯覚さえ感じるのであった。 学校はどうしたんだ、君はあの部屋で家族と住んでいるのではないのか、いったいどうしたっていうのだ、などと驚いている時間などなく、ふたりはいずみの広場を上がって新御堂筋を少し下り、それから左折した。この先には大融寺と兎我野町のホテル街がある。先日彼女が中年のサラリーマン風の男と出てきたホテル・キャンディポケットはこの一筋南側の通りにある。 気づかれないようにかなり距離を開けて尾行を続ける。ふたりはいつの間にか手をつなぎ、笑いながら親しそうに言葉を交わし、楽しそうな雰囲気が三十メートル後ろの私にまで伝わってきた。ポケットデジカメをショルダーバッグから取り出して、ふたりが手をつないで歩いている後姿を数枚撮影した。このままピクニックへでもいきそうな雰囲気だ。だが数分後、ふたりはホテル「スイートキャッツ」に飛び込んでしまった。 「なんだ、そういうことか」 私は驚きと落胆とが入り混じった複雑な気持ちになった。 「午前十時四分だ。高校生が平日の朝からホテルだよ。有希子、これは完全にイレギュラーだろう」 私は無意識に妻の名をつぶやいていた。 「おはようございます、岡田です。社長はいらっしゃいますか?」 私はふたりが入った「スイートキャッツ」の出入り口が窺える遠目の位置に立ってから京都のA社へ電話をかけた。 「おはようございます、岡田さん、どうされたのかしら?」 「社長、宝塚の男子高校生の件ですが、今朝は学校へは行かずに梅田の泉の広場で女性とおち合って、さっきホテルに手をつないで入りましたよ。どうしますか?」 「ホテルって・・・制服のまま?」 「そんなわけありませんよ、ちゃんとトイレで私服に着替えてバッグをコインロッカーに放り込んでからの行動です。用意周到」 「そうなの・・・」 「どうします?ふたりが出て、別れたあとのことです。相手女性の家を割り出しますか?」 「そうしていただけるかしら。ともかく依頼人に状況報告をするわ。なにかあれば連絡します」 社長は電話を切った。 相手女性の家は割り出す必要がない、私と同じマンションの同じ階に住んでいるのだから。だがそれを社長には言えるはずもない。 しかし、いつ出てくるかも知れないふたりをこんなところでずっと立ちん坊か、これは目立って仕方がない。周囲を眺めてみると、「スイートキャッツ」の並びには寿司店と高野山真言宗のお寺、向かいの並びは「ホテル・アメリカン」とその隣も「ホテル・スイートゲート」といった具合だった。 ちょっと離れたところの四つ辻の向こうの角、つまり「スイートキャッツ」の対角線の位置に喫茶店「モア」があった。私はともかく店に入ってみた。すると窓際の席からホテルの出入口が窺えた。かなり遠めなので一瞬の油断で見落とす可能性があるが、見落としたところで相手女性の自宅は分かっているからどうにでも報告できるわけだ。 「ちょっと仕事の関係でこの席で二時間ほどいたいんだけど、かまわないかな?もちろんコーヒーはお代わりするから心配ない」 「お昼の間だけ少し混みますけど、お客様がそれでよろしければかまいませんよ。お代わりは気になさらないで下さい」 コーヒーを持ってきてくれた女性はニコッと笑って言った。私は朝から二杯目の熱いコーヒーを飲み、一ヶ所しかないホテルの出入口をジッと見続けた。 十二時半過ぎにスマホが鳴った。A社の社長からだった。 「動きはどうかしら?」 「入ったままですよ」 「実は、依頼人がそちらへ行きたいって言うのよ」 「いや、それはダメじゃないですか。まだこの調査は初期段階だし、今日接触のあった相手女性の家を割り出して、その次に内偵調査に進むのじゃないですか?調査はまだ四日目ですよ。残りの調査日数で相手女性の尾行も必要になってくるでしょ」 白々しいことを言っているなと、私はこころで苦笑いしながら言った。 「そうよね、分かったわ。依頼人にはそう説明する」 そう言って社長は電話を切った。 午後一時半を少し過ぎてようやくふたりがホテルから出てきた。すでにコーヒー三杯分の代金は支払っていたので、すぐに喫茶店を出てあとをつけた。ふたりは手をしっかりつないでいた。きっと依頼人は今頃「息子を誘惑するとんでもない女」と奥歯をキリキリさせていることだろうが、相手女性、というより女の子は誰もが知っている有名な女子高生だ。 ふたりは泉の広場に降りる手前で手を振って別れ、依頼人の息子はウメ地下へ降りた。そして彼女はクルリと振り返って、こちらに向かって歩いてきた。私は身を隠す間もなく、彼女に見つかってしまった。 「こんなところで何してるんですか?」 「いや、その・・・良い天気だね」 「今日は曇ってますよ」 「あっ、そうか、ちょっと事務用品を買いに出てきたんだ」 私の言葉が終わる前に、彼女はなぜ私がここにいるのかなど気にもしない様子で、兎我野町のマンション方向へ歩いていた。 |
| 八 |
|---|
|
前日の動きの結果を簡単に報告書にまとめ、A社にファックスを送った。依頼人の息子の相手女性宅も判明し、住所も明記した。私の事務所と同じマンションの部屋号が異なるだけだが、それにはA社のスタッフも気づかないようだった。 翌朝は午前七時開始で相手女性の尾行が指示されていた。外で立って張り込むわけにもいかず、ちょうど私の部屋のキッチンの窓から彼女の玄関が見えるので、準備をして待った。 しかし、彼女は高校生だから家族がいるはずだが、ここに引っ越してきてから彼女以外にあの部屋から出てくる人物は見なかった。A社の内偵担当が彼女の家族構成等の割り出しに取り掛かるだろうから、結果待ちである。 午前七時半を過ぎて彼女が出てきた。週末の金曜日、彼女はもちろん制服姿であった、昨日は学校をサボったということなのだろう。同じエレベータに乗らないと見失ってしまう可能性もあるので、やむを得ず急いでエレベーダ前に向かった。 「やあ、おはよう。よく会うね」 「おはようございます」 彼女はこちらを見ずにぶっきらぼうに言った。 「役所に用事があってね、大変なんだ」 「そうですか」 「学校も大変だね」 「いいえ、それほどでも」 会話が続かない。エレベータが一階に着いて、ふたり並んでマンションから出て、「それじゃ」と言って、彼女が向かう反対側方向へいったん歩いた。彼女を振り返りながら二十メートルほど歩いて、再び彼女の方向へ、本日の尾行を開始した。 まさか尾行されているなどと思うはずもないのだろう、彼女は一度も振り返ることなく曽根崎通りをぶち抜いて新御堂筋を横切り、大阪駅前の陸橋を渡って阪急梅田駅方面へ向かった。短めの黒髪が白のブラウスの襟元にかかり、紺色のベスト、同色のスカート、手には濃紺の学生鞄、どの角度から見ても中年男や男子高校生とホテルに飛び込むような女の子には見えない。世の中やっぱり狂っている。 梅田駅から電車に乗り、中津を過ぎて淀川を渡り、十三駅で下車、わき目も振らずに十数分後に府立高校の正門から入って行った。府下でも進学率の高い優秀な高校だ、電車の中ではときおりスマホを取り出した程度で、歩きスマホなどしない、さすがである。 さて、登校したからには少なくとも午前中は出ることはない。駅まで戻って近くの喫茶店で本を読んで時間をつぶした。昼前にランチを注文し、それからまたコーヒーを飲んで、午後二時近くまで粘ってから店を出た。この間に彼女が学校から出てどこかに行ってしまったとしても構わない、もうひとつの結果は出ている。学校の近くでずっと立っているわけにもいかず、改札口あたりが見える位置にて張り込んだ。 午後四時を少し過ぎたころに彼女が学校方面から歩いて来るのを確認、来たのと逆のルートでそのままマンションへ帰宅した。コンビニにもどこにも立ち寄らなかった。 翌日の土曜日も同様に午前七時前ごろからキッチンの窓から彼女の部屋の出入り口を張った。この日は一緒にエレベータには乗らず、彼女が降りていったのを確認してから非常階段を駆け下りた。マンションを出ると数十メートル前に彼女を確認、前日と同様に登校したのを見届けてから改札口が見える喫茶店で時間をつぶした。 だが、午後一時過ぎに十三駅改札口近くに現れた彼女は、梅田駅で下車したあとJR大阪駅に入り、大阪環状線に乗って京橋駅に出た。エスカレータで二階に下りて女子トイレに入り、出てきたときはジーンズとグレーのパーカーに着替えていた。手に持っていた大きな紙袋にはおそらく制服と学生鞄が入っているのだろう。それを同じ階のコインロッカーに放り込んだ。 そして一階まで降りて広い改札口を出たところで待っていた若い男性と合流、依頼人の息子とは別の男性だった。私は愕然としてしまった。そんな私の狼狽を尻目に、彼女は京橋駅から京阪国道へ出て、道路を向こう側へ渡って路地を入ったところにあるホテル「ブルースカイ」に男性とともに飛び込んでしまった。真っ昼間から再びラブホテルに入ったことに落胆し、「本当に世の中狂ってるよ、有希子、まったく」と、離れて暮らしている妻の名前を無意識に呟いていた。 |
| 九 |
|---|
|
張り込みを続けながらA社に電話を入れた。調査会社は土日も関係がない、社長は出社していた。 「別の男の人とホテルにね。依頼人さん、喜ぶわ。じゃあ、ホテルから出たら、念のため相手男性を尾行してくださる、あまり意味はないかも知れないけど」 社長はまるで狂喜乱舞しているかのように嬉しそうな声だった。私の憤慨と落胆とは対照的で、彼女に対して腹立たしさを覚えた。何故腹立たしさを感じるのかは分かっている、偶然にも事務所オープン後、最初の仕事が同じマンションに住む女の子の尾行だったからだ。こんな偶然は千に一、いや万に一もないだろう。驚きではなく、唖然とする。 依頼人はおそらく息子に対し、「お前のことが心配で少し尾行を依頼した。何も言わないからもう会うのはやめなさい。彼女はお前だけじゃない。別の男とも付き合いがある」と言うだろう。どのような行為がホテルで繰り広げられたのか、金銭の取引はあったのか、肉体関係があって金を求められたとなると売春行為に該当する、いや、高校生の立場なのだから、もうこれは言語道断の不純異性交遊ではないのか。私は分からなくなってきた。 午後二時過ぎにホテル「ブルースカイ」に入った二人は、午後四時半ごろに出てきた。私はホテルへの路地が見える位置にあるコーヒーショップでずっと張り込んでいたのだ。若い男とは京阪京橋駅とJR京橋駅の間にあるフリースペースで別れた。今度は男を尾行する。彼女の方をチラッと見ると、一度も振り返らずに改札口の向こうに消えた。 男を尾行すると、彼は午後五時過ぎ、近鉄奈良線八戸ノ里駅で下車し、徒歩七分程度の住宅街にある「菅原」と表札が掛けられた一戸建ての家に入った。尾行中に男の顔を観察してみたが、顔のあちこちにまだニキビがあり、高校生と見えなくもなかった。 調査も残り三日となった。もう結果は出ている、これ以上彼女を尾行する気力がなくなってきた。 プロ野球の消化試合のような尾行だ。彼女が依頼人の息子と接触する可能性はもはやゼロだろう。両親に彼女との関係を指摘され、不登校の原因を知られてしまったとあってはもう会うことはないだろう。だが、他の男性と接触する可能性はある。ただ仮に他の男性と接触があったとしても、依頼人の目的が達せられたとあってはたいした意味にはならない。必要な結果は出た。依頼された残りの調査時間を消化するための尾行なのだ。モチベーションなど上がるはずもない。 依頼人の息子は預金をつぎ込み、親からもらった書籍購入費までも貢いでいたようだ。これは恋愛のひとつの形なのか、或いはそれらにも当たらない何か他の行為があったのか?探偵は警察ではない、尾行調査で判明した結果以外のことには一切関与しない。息子は金を渡していたことを打ち明けたが、密室での行為については頑なに口を閉ざしているとのことだ。仮に息子がホテルでの行為を父親に白状したとしても、そのことを誰にも言えない。事件にならない限り、決して表には浮き出てこない。 翌日は日曜日、朝早くから出るはずはないだろうと踏んでいたが、念のためキッチンの窓から彼女の部屋の玄関を張り込んだ。予測に相反して、午前七時を少し過ぎに出てきた。慌てて尾行を開始する。 短めの髪をうしろで束ねて紺色のゴムで縛り、ジーンズに薄いピンクのシャツを引っかけ、デイバッグを背負っていた。部活にでも行くのだろうか?彼女がエレベータに乗ったのを確認してから、非常階段を駆け下りる、膝がガクガクするが二段跳びで急ぐ。 休みの日くらいゆっくりすればいいのにと思いながら、彼女のジーンズを追うと、曽根崎通りから新御堂筋に出て梅新を南下、大江橋を渡って左手に大阪市役所を見て、京阪電鉄の淀屋橋駅に到着した。いったいどこに行くのか? ホームに降りるとすかさず区間急行に乗り、すぐに発車、同じ車両のひとつ隣のドアから乗り込んでつり革を持って立ち、目の端で彼女の姿を確認する。彼女はドアの近くに立ち、スマホをいじっていた。そしてそれが終わると外の景色を眺めていた。 京橋駅で下車、三階にあるホームから二階のフロアに降りた。昨日、男性と会ったのは改札口を出たところだった。また今日も会うのか?私はガッカリした。ところがエスカレータを降りて数メートル歩いたところで急に立ち止まり、うしろを振り返った。私は知らない振りをして通り過ぎようとした。 「何でついてくるんですか?」 「えっ?ああ、よく会うね」 「白々しい、私にずっとついてきてますよね、ストーカーです!」 言葉と同時に、私の右腕は彼女に強くつかまれた。女子高生にしては意外に強い力だった。その様子を周囲の人たちが足を止めて見守っているのが視界に入った。 「駅員室へ一緒に来てください」 |
| 十 |
|---|
|
彼女に腕を掴まれたままエスカレータを降り、一階の改札口近くにある駅員室へ入った。途中の様子を見た人々には、痴漢を捕まえた勇敢な女の子といやらしい中年男に映ったかも知れない。駅員室の奥の部屋が駅長室になっていた。 「警察を呼んでください」 強い口調で言う彼女の勢いに、駅員が慌てて110番したようだった。 「何で警察なの?」 「何でって、私をずっとつけてますよね。自宅を出てから、ずっと。ストーカーじゃないですか!」 彼女はしきりに「なぜ私のあとをつけるの?」と執拗に訊いてきたが、私は警察が駆けつけるまで余計なことは一切喋らなかった。駅員たちも慌てた素振りのない私の態度に、どう取りあったらよいのか分からない様子だった。この場をどう収拾すればいいのだろうと、憂鬱な気分で考え続けていると、まもなくふたりの警察官が駅長室に到着した。 「痴漢じゃないんだよね?」 着いてすぐに年配のほうの警官が私と彼女とを交互に見て言った。 「違います。ストーカーです!」 「ストーカー?」 若い方の警官が「あなたは彼女のあとをつけていたのですか?」と私の方に向き直ってから訊いた。 「ちょっと別の部屋に、いいですか?」 年配の方の警官に隣の駅員室へ来てもらい、やむなく事情を説明した。 「実は探偵なんです。頼まれて彼女を尾行しているんですよ」 岡田光一調査事務所の名刺をその警官に手渡した。 「なんだ、興信所の方ですか。尾行、彼女に気付かれたんですね。アハハ、そりゃあ大変ですな。いや、これは失礼。笑いごとではありませんな」 「いえ・・・」 「そんなら、あの子にちゃんと説明しておきますよ。しかし尾行も大変ですなあ」 年配の警官は苦笑いをして言った。 「それでは彼女にちょっとお詫びだけでもしておきます」 「いや、私たちが彼女に説明しておきましょう。依頼人のことを口外できないのは存じています。そうですか、興信所さんでしたか。まあ今は探偵さんって呼ぶのでしたかね?」 「いえ、興信所でかまいません」 年配警官とともに再び駅長室へ戻った。彼女は若い方の警官と話をしていた。「あの人、私と同じマンションに住んでるの。朝からずっとついてくるんです」といった言葉が耳に入った。彼女は僕の姿を見て強い視線で睨んできたが、ポーカーフェイスを保ったまま椅子に座った。 「お嬢さん、この人は興信所の方なのですよ。頼まれてあなたを尾行したわけですね」 「すみません、私が説明します」 警官は「分かりました」と頷いた。 「君を何日か尾行したことは事実です。残念ながら気づかれてしまったんだけど、気分の悪い思いをさせたことについてはお詫びします。許してください」 私は椅子から立ち上がって彼女に深く頭を下げた。 「お詫びなんて要らないわ。誰に頼まれたか言ってください」 彼女は強い視線をこちらに向けて言った。ふたりの警官も部屋の隅にいた駅長も言葉を挟まず、私と彼女のやりとりを見守っていた。 「ともかく私の失敗でこんなことになってしまって、謝るしかないんだ。もし個人的に何か訊きたいのなら、いつでも連絡してくれたらいいよ。今回のことはあまり突き詰めると君の不利になることもありからね」 「不利って、どういうことですか?」 そう言いながら、彼女は私の手から名刺を受け取った。 「分かりました、電話をしてもいいのですね。拒否されるんじゃないですか?」 「いや、目と鼻の先だし、僕の部屋に来てくれてもいいよ。遠慮なく」 「何言ってるんですか、訳わかんない。Lineやってます?」 「Line?」 「スマホのアプリですよ、Line」 「ああ、一応」 「じゃ、教えてください」 私はポケットからスマホを取り出し、Lineのアプリを開いた。 「ふるふるの機能があるでしょ、そこを開いてください」 彼女の言う通り開き、互いのスマホを近づけて軽く振るとすぐに感知した。いったい私は何をしているのだろうと自分を呆れたが、ともかく彼女とはLineでつながった。 「本当にLineしてもいいんですね?」 「いいよ、いつでも」 駅長室を出て彼女と別れた。 「同じマンションなんだから、一緒に帰らないか」と誘ってみたが、「バカ言わないで」と一蹴されてしまった。 彼女は改札口から出ず、エスカレータでホームへ上がって行った。しかしこの日はいったいどこに行こうとしていたのだろう。尾行に気づかなかったなら、また男とホテルに入っていたのかもしれないと思うと気分がスッキリしなかった。それに、たとえ依頼人には分からないにしても、久しぶりの尾行が発覚という情けない結果で終わったことも憂鬱な気分の原因だった。しかも女子高生に捕まってしまったことが探偵としてのプライドを叩き潰された気がして、私はすっかり落ち込んでしまった。 |
| 十一 |
|---|
|
数日後、今回の十日間ほどの調査で撮影した写真を添えて、とてつもなく長く詳細な報告書を作成し、京都のA社にそれを持参した。 「岡田さん、さすがですね。依頼人の息子さん、勉強に打ち込むと両親に謝ったらしいのよ。やっぱり高校生でホテルはダメよね。相手の女子高校生は沢井真鈴って言うのよ。一人っ子ね」 「判明したんですか?」 「ようやく内偵調査の公簿が届いたの。ご両親と三人暮らしになってるわ」 「そうですか、やっぱり一人っ子でしたか」 「えっ?」 「いえ、何でもないんです」 あの部屋から彼女以外に出てきたところを見たことがないから、不思議だと思ってはいたが、一人っ子だったのだ。しかしそれにしても両親らしき人物は見ない。 その夜、金融業時代からの行きつけの小料理屋「安曇野」に久しぶりに顔を出した。真っ直ぐ自宅兼事務所に戻る気持ちにはならなかった。 「あら、いらっしゃい。いかがされていたのかしら?」 女将さんが微笑みながら訊いた。 「新しい商売を始めたら、すぐに仕事が入ったんですよ」 「それはありがたいじゃない、それで今度はどんな仕事なのかしら?」 「いえ、たいしたことはしてないんですよ。十日間ほど男の子と女の子を追っかけてただけです」 最初の生ビールを一気に三分の一ほど飲んでから私は言った。 「いったい、今度は何をしてるのかしら。高利貸しじゃないのは分かるけど」 「悪いことはしてませんよ」 「それは分かってるわよ。岡田さんは悪いことなんかできない人だから。幸子も言ってたわ」 女将さんは適当に「おすすめ」料理を出しながら言った。四十代半ばの彼女は年齢を感じさせない無邪気さがある。彼女の笑顔に惹かれてこの店に通う男性客も多いのだ。 社長は「一件落着。ともかくよかったわ」と言っていたが「そんなことがあるものか」と私は思っていた。何が一件落着だ、冗談じゃない。それは依頼人の息子のことではないか。依頼人の要望に応えたのだから関係がないといえばそうなのだが、私は彼女の行動の背景を知りたかった。 依頼人の息子とホテル「スイートキャッツ」に入ったときのふたりの楽しそうな様子は何だったのだ。「依頼された範囲」は終わったが私のこころの中では終わっていなかった。 生ビールを二杯だけ飲んで早々に店を出て、マンションまで帰る途中、有希子に電話をかけた。 「どうしたの?」 「いや、どうもしないよ。元気かな?」 「うん、お父さんが疲れやすくなってるから、散歩に付き合ったりね。でも暇だわ」 「開業後、すぐに仕事をもらえたんだけどね、ちょっと疲れた」 「無理しないでね。疲れているときにこの前の話で悪いんだけど、今度時間を作って、一度こっちに来て欲しいのよ」 私は「分かった」と言って電話を切った。彼女の両親は、もう離婚させようとしているのだろう、それは無理もないことだった。 部屋に戻り、シャワーを浴びてからスマホを見るとマリーンという人物からLineが飛んできていた。先日、Lineのアカウントを交換し合った彼女であることに気づいた。そういえば今日、A社の社長が彼女の名前が沢井真鈴だと判明したと言っていたが、真鈴をマリン、つまりマリーンってことなのだろう。 「真鈴です。テストLineです」 Lineメッセージとともに、アニメの熊の頭に?マークがついているスタンプが送られていた。メッセージは少し怒っているように揺れて見えた。もちろん錯覚なのだが、駅員室での彼女の鋭い目つきが浮かんだ。 「届いているよ〜」と僕は返信し、少し前に有料で買っていた名探偵のアニメのスタンプから「OK!」と両手を挙げているスタンプも送った。でも、もう夜遅いからか、返信のLineは飛んでこなかった。 |
| 十二 |
|---|
私の事務所兼自宅は2LDKだが、実質は事務所のスペースが、将来的には来客も想定して1LDKもとっているので、もう一部屋はベッドと窓際に小さな椅子を置いてあるだけで、今年四十歳になる男の居宅としては粗末なものである。 日曜日の今朝は遅めに起きて、隣室を覗くとFAXに新たな調査依頼が届いているのを確認した。岐阜県各務原市への所在調査の依頼であった。明日から取り掛かろうと、調査の資料に目を通しているとスマホが震え、Lineが飛んできた。沢井真鈴からだった。 「今、電話しちゃいけませんか?」 メッセージとともに難しい表情をした熊のアニメスタンプが添付されていた。 「大丈夫だよ」と返信して、名探偵アニメの「OK!」をまた送った。数秒後、スマホが震えた。 「おはようございます、沢井です」 彼女の声は小さく、そして早口だった。 「おはよう、君のことを心配してたところだよ」 「私の何をですか?」 「何をって・・・その・・」 私はすぐに返答できずに戸惑った。 「お訊きしたいことがあるんです。時間のある日に少しだけでも」 会ったところで依頼人のことは絶対に言えない。 「こっちに来る?さっき起きて、雑用をしているところだから時間はあるよ」 「何言ってるんですか、そんなに簡単に部屋に呼ばないでください!」 小さな声だが、きつい口調だった。何か気に障るようなことを言ったのかと、不思議に思ったが、考えてみれば未成年の女の子を、いくら近所だからといって気軽に呼ぶ私が迂闊だった。 「ゴメン、じゃ、公園にでも行こうか」 「扇町公園の入り口あたりにいます」 「ああ、分かった。何時?」 「午後一時ごろじゃだめですか?」 「いいよ、じゃあとでね」と言って、私は電話を切った。 扇町公園の南西側の入り口までは、このマンションからゆっくり歩いても五分もかからない。梅雨入り宣言があったのかどうかも分からないが、快晴の日曜日の扇町公園は、多くの人々が様々なスタイルでくつろいでいた。 真鈴は午後一時に、まるでその時刻まで近くで隠れていたかのように、きっかりに私に向かって突き進んで来た。口をへの字に曲げて、機嫌が悪そうな顔つきだ。 「こんにちは。ピッタリの時間だね」 彼女は白っぽいの膝までのスカートにエメラルドグリーンの鮮やかな半袖のセーターを着て、肩に布製の茶色の小さなバッグを引っ掛けていた。 「お昼ごはんは食べたの?」 「いえ」 「じゃあ何か食べよう。僕は朝から何も食べていないんだ。いいかな?」 「はい」と真鈴は素直に従い、私たちは扇町公園を斜めに横切って、天神橋筋商店街の中にあるグリル・レストランに入った。 「僕はピザが大好きなんだ。少し大きいから手伝ってくれる?」 メニューを見ながら彼女に訊いた。 「私もピザが大好き。でも最近は全然食べてない」 真鈴は少し肩をすくめて言った。その仕草は普通の女子高校生のものだった。スタッフを呼んで、サラミとジャーマンポテト、アンチョビ、ダブルチーズピザ、トマトとマッシュルームのサラダとなすとベーコンのスパゲティナポリタン、そして飲み物はアイスカフェオレを注文した。「二人で分けて食べよう」と提案した。 「ところで訊きたいことって何だろう?」 私は真鈴の目を見て、できる限り優しい表情を意識して訊いた。 「それは岡田さんに私の尾行を頼んだのは誰かってことです。それしかありません」 彼女はさっきの普通の高校生の表情から一変して、私の目を睨むようにして言った。 「沢井さん、それはこの前も説明したように絶対に言えないことなんだよ。僕の仕事上のルールなんだ。分かってくれないかな」 「分かりません、今日は教えてくれるまで帰らないから!」 彼女は明らかに不服そうな顔つきになり、両方の頬を交互に膨らませた。 「それにね、もう今回のことを突き詰めようとするのはやめよう。君にだって不利になることがあるだろう?」 料理が運ばれて来た。私は真鈴の皿にピザとサラダ、それにスパゲティも少しずつ取ってやった。彼女はその間、少しうつむき加減で、ジッと黙って私の手の動きを追っていた。 「さあ、熱いうちに食べよう。君をあちこちつけ回したお詫びだ。本当は少しワインが飲みたいけど、未成年を前にして、そういうわけにいかないからね」 雰囲気を和らげ、リラックスさせようと、努めて明るく言ったつもりだが、彼女はジッと黙ったまま料理も飲み物にも手をつけなかった。 「岡田さん、じゃあひとつだけ教えて下さい」 「何かな?」 私はフォークを置いてナプキンで口を拭ってから訊いた。 「私の尾行を頼んだ人って、その人・・・私の父じゃないですよね?」 「えっ?」 「依頼した人は、私の父ではないですよね?」 「君のお父さんが?」 真鈴は頷いた。 「いや、違うよ。この前もそれは言ったと思うけど、そもそも君の尾行を依頼されたんじゃないんだ。ある人物を尾行していたら、その人が君と会ったんだからね。そのあと依頼人の要望で君の動きを数日追っていたんだよ。もうここまで言うと依頼人は誰か分かってしまうけどね」 「そうだったんですね」 真鈴は肩をがっくりと落としで呟くように言った。 しばらく口を真一文字にして何かを考えているようだったが、そのあと「いただきます」と言って、猛烈な勢いで料理を食べはじめた。目の前でピザを頬張り、サラダを食べ、スパゲティをくるくる巻いて口に運ぶ真鈴の様子を、私はしばらく唖然として見ていた。そして五分ほどが経って、彼女の食事のペースが急にダウンした。うつむき加減の顔を覗き込むと、両方の目から涙が溢れ出たところだった。涙は両方の頬を伝い、あっという間に顎に達していた。 「沢井さん、どうしたんだ?」 |