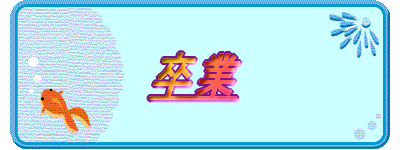
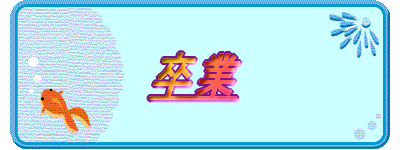
| 四十九 |
|---|
|
関さんと肩を並べてポートサイトホテルへ戻る途中、山の手散策はいかがですかと私は訊いてみた。 「今日は朝早くに山を出て、長い列車移動があって少し疲れたみたい。ハーバーランドはすごくよかったから、今日はこれで満足です」 関さんはそう言って、ホテルに戻ってバーで飲みたいとリクエストしてきた。 「さっきも訊いたけど、本当に山を降りる感覚なんですか?ジョークですよね?」 私はは気になって確認してみた。でも関さんは「いえ、山を降りる感覚なの。本当に」と真面目な顔で答えるのだった。 「明日、僕はまたこちらに来ますから、異人館や神戸の高台を少し歩きませんか?」 「えっ、今日はもう帰ってしまうの?」 関さんは急に不安げな表情に変わった。 「いえ、今日はまだ帰りませんよ。ホテルのバーで少し飲みましょう。それからゆっくり休んで下さい。明日は異人館などを回って、夕方には京都へ入りませんか?」 「よかった、まだ一緒にいてくれるのね。明日のお仕事は大丈夫なの?」 「仕事なんてどうでもいいんです。関さんと一緒にいるとホッとします」 関さんは「フフッ」と微笑み「岡田さんってどこまでが本心なのか分からないけど嬉しい」と言った。『僕はすべて本心です、関さん。僕はビリージョエルの訴えに一部は共鳴する男なんです。でも本当に「正直」と「誠実」とは同じじゃないと思うんです』と、こころで呟いた。 関さんはホテルに着くと、少し部屋に来ませんかと言った。女性一人が泊まる部屋にはちょっと・・・と私は躊躇した。でも彼女は「エレベータ前で待っていて」と言ってフロントへ鍵を取りに行った。私は指示通りにエレベータ前で待ち、それからふたりで七階の部屋に入った。 「ホテルのバーに合った服に着替えるから」 関さんはバスルームに入ってシャワーを浴びはじめた。私は置かれた状況にかなり混乱した。いったいどういうつもりなのだろう。彼女がバスルームから出てきた瞬間にもし抱きしめたらなら、高い確率で親密な関係になるに違いないと思った。これまでの数少ない女性関係で、こういったケースではほぼ男女の関係に突き進んでしまうものなのだ。 二十分近くが経過した。関さんはまだ出てこなかった。部屋の小さな窓の白いカーテンは閉められていた。いつもの習慣でそれを開いてみた。窓からは真っ黒な海と、そこに浮かぶ停泊船の灯りや点滅ライトが神戸港のあちこちに見えた。窓は締め切っているので外の音は全く届かなかった。穏やかな夜だった。この部屋だけが現実と区切られた異世界のようだった。私は関さんが出てくるまで夜の神戸港を眺め続けた。 三十分ほど経って、ようやく関さんがバスルームから出てきた。身体に真っ白い大きなバスタオルを一枚巻いただけの姿だった。薄明かりの部屋に映える彼女の露出した部分の肌の白さに目を奪われ、しかし視線を外せず、置かれた状況に戸惑った。 「岡田さんもシャワーを浴びませんか?今日は昼間たくさん汗をかいたでしょ」 「いえ、さっきから冷や汗ばかり背中を流れています」 「フフ、変な人ね」 関さんはベッドに腰をかけ、バッグから四角い化粧箱を取り出し、いったん落とした化粧を再びはじめた。私はさっきから居心地の悪さを感じていた。シャワーを浴びようかとも考えたが、汗で湿った同じ服をまた身に着けるのだから意味がないと思った。 「関さん、僕は今、あなたに飛びかかろうとしている自分と必死に闘っているのですよ。分かりますか?」 「・・・・・」 「僕だって男です。あなたのような女性とホテルの部屋でふたりきりになると、どんな気持になるか分かりますか?しかもあなたはバスタオル一枚だ。それに魅力的で・・・」 「いいのよ」 「えっ?」 「岡田さん、抱いて。私・・・穴吹でずっと岡田さんのことを考えていたの。去年大阪を案内してくれたとき、すごく楽しかった。ずっと紳士的だったし、私はあのとき岡田さんを信用したの。そして穴吹に帰ってから、体を壊したり、しばらく休職したり、いろいろと疲れて、アパートに閉じこもっていたこともあったのだけど、いつも岡田さんのことを考えていたのよ。何度も電話しようと思ったのだけど、できなかったの」 関さんは化粧箱をテーブルの上に置き、バスタオルを巻いたまま一気に喋った。もしかして、彼女は少し精神的に参っている状態なのかも知れない。うつ病とは違うだろうし、感情の起伏もそれほど激しくないが、常に相手の目を気にして気遣っているような態度は、まるで臆病なウサギみたいな感じがした。 「関さん、あなたは昨年の秋以降、何かあったのですか?春先に体調を壊したこと以外に」 関さんは私の質問に対して下を向いて黙ったままだった。考えているのか、或いは嫌なことを思い起こしているのか、表情からは読み取れなかった。悪いことを訊いたかなと思うほど、彼女の表情にはさらに曇りが窺えた。 「あなたは少し疲れている。バーで神戸の夜景を見ながら飲みましょう。明日も明後日も、僕は一緒にいます。夜は帰るけど、朝にはホテルまでまた来ますから、心配ありません」 関さんの隣に座った。右手で彼女のむき出しになった肩を抱いた。エアコンが強すぎて肌は冷たくなっていた。強く引き寄せると、関さんは私の目を見つめた。唇を合わせた。真鈴以外の女性とキスをするのは久しぶりだった。真鈴の甘い口臭とは異なった口臭がした。でもそれは嫌な匂いではなかった。私は関さんの唇の感触にこころが昂ぶりながらも、カフェオレの香りがしなかったことが少し残念に思った。 「続きは明日、京都でね」 自分を制御しないと、一気にこのベッドで関さんを貫いてしまうと思い、辛うじて欲望を耐えて言った。一度垣根を破ってしまうと、もう戻れない。今度は関さんを連れて期限不明の旅に出てしまうだろう。昔のミスチルの歌に「終わりなき旅」という名曲があったが、終わりがあるから旅なのだ。「終わりなき旅」に出てしまったら有希子を守れない。真鈴も見守ってやれなくなる。だから関さんとは止まらないといけない。 「そうね、今日は暑い中たくさん歩いたし、明日もあるものね。やっぱり紳士ね、岡田さんって」 関さんは私をジッと見て、目を潤ませながら言った。私たちはおとなだ。求め合う環境が整っていないのに無理にセックスはしない。「私たち、もう環境は整ってるよ」と、先日真鈴が言っていたが、本当にそうなのか、今度会ったときに確認してみようと思った。 それから部屋を出て、ホテルの十三階のバーで飲んだ。まだ夜八時前だったので、バーには何組かのホテルの宿泊客がいただけだった。案内された席はガラス張りの窓際で、そこからすぐ目の前に昼間訪れた神戸ハーバーランドやモザイクガーデンの夜景が見えた。それらは多くの色彩を駆使して光り輝いていた。観覧車までもがイルミネーションの光を堂々と発しながら回っていた。私は「ダイキリ」を飲み、関さんは「ギムレット」を飲んだ。 「関さんのような妖精と過ごせて、もう思い残すことはありません。明日からの人生は付録のようなものです」 私はチーズを口の中で溶かしながら言った。 「オーバーな言い方。何でいつまでも丁寧な喋り方するの?さっきキスした関係なのに、おかしいわ」 関さんは、毎回のように「フフ」と笑ってから言った。 「じゃあ、恋人みたいな呼びかたをしますよ。いいんですね」 「かまわないわ。そのほうが嬉しい」 でも私は関さんの名前を知らないことに気づいた。これまで「関さん」としか呼んでいなかったから、名前のことを意識したことがなかった。 「関さん、名前何だったかな?多分、知世さんだと思うんだけど」 「えっ?」 「関知世さんだよね。違うかな?」 「なぜそう思うの?」 「なぜって、それはその、いつもあなたが時を翔けるように僕の元に現れるからですよ」 「塚本さんって、ときどき意味不明。私は広美よ、関広美。好きじゃないの、名前」 広美か。穴吹川の広大な清流のように綺麗な関さんにピッタリの名前だと思った。 私はウエイターを呼んで「ダイキリ」をもう一杯注文し、関さんの「ギムレット」とナッツを追加した。窓の向こうには、ハーバーランドの様々な色彩の灯りが、満天の星の下で関さんの名前のように広く美しく光り輝いていた。私はそのあと今日一日のことを思い起こした。なぜ関さんとキスをしたのだろう。彼女は私をホテルの部屋に躊躇なく入れた。ひとつひとつの流れにはきっと意味があるはずだ。真鈴と私と関さんとはひとつの線でつながっている。だが真鈴と関さんとは面識がない。関さんとつながっているのは穴吹療育園の奥沢悦子だ。悦子は真鈴の父の姉、つまり伯母にあたる。そういえば奥沢悦子の病状はどうなのだろう。そのことが気になりはじめたが、今夜は関さんに訊かないでおこうと思った。 「どうしたの?急に黙り込んで」 心配そうな表情で関さんが訊いた。 「今日一日の幸せを噛みしめているんだよ」 「フフ」と関さんは笑った。そしてギムレットのグラスを口に運んだ。ダイキリのグラスを置いて、関さんに顔を近づけ、軽くキスをした。「フフ」ともう一度関さんが微笑んだ。素敵な夜だった。 |
| 五十 |
|---|
|
翌朝、私はポートサイドホテルのロビーにいた。昨夜は十時前にはバーを出て、関さんを部屋まで送り届けた。部屋には入らず、ドアの前で彼女を抱きしめてもう一度キスをした。欲望が頭を突き抜けそうなくらい昂ぶったが、自分が持ち合わせているすべての理性によって辛うじて抑えた。 関さんは別れ際に「明日ね。きっとよ」と言い残して部屋に入った。帰りの快速電車の中でずっとその言葉を考えてみたが、どの角度からも「明日はきっと抱いてね」という意味にしか受け取れなかった。妻の有希子とは、彼女が癌を患って以来、夫婦としての関係は遠ざかっているし、真鈴とは何度か危ない場面があったが、辛うじて踏みとどまっていた。セックスという行為に突入した場合、果たして機能が発揮できるのだろうかと、少し不安な気持ちのまま部屋に帰った。 ロビーに出てきた関さんは昨日と同じジーンズ姿だったが、複雑な色彩のタータンチェック柄のシャツを身に着け、髪の毛は肩まで下ろしてキャップはかぶっていなかった。 「おはようございます」と関さんは最初に言った。 「おはよう、広美。丁寧な言葉はやめてって、昨夜言わなかった?」 「そうだったね、ごめんなさい。今、チェックアウトしてくるからもう少し待って」 関さんはフロントへ駆けて行った。駆けるではなく翔けて行った感じがした。彼女が元気そうだったのでホッとした。 私たちはポートサイドホテルを出て山側に歩いた。金融会社に勤めていたころの懐かしい通りの数々はそのままだったが、アーケードの下の元町商店街は、昔立ち寄った店の何軒かは違う店に変わっていた。 JRの高架を越えてトアロードを上がった。私たちはいつの間にか手をつないでいた。北野坂はそれほど急な坂ではなかったが、関さんは暑さもあって「疲れた」と弱音を吐いた。彼女を励まし、何ヶ所かの異人館を訪ねて、小さなレストランで軽く食事をしてから神戸を離れた。 京都までの新快速電車の中でも私たちは手をつないだままだった。関さんは「こんなふうに男の人と過ごすのは初めて」と言った。関さんは男性との親しい付き合いがないまま、穴吹の山の中に篭ってしまったのではないかと思った。それはキスのぎこちなさにも表れていて、彼女のキスは唇を合わせる軽いものだったが、思い切って舌を差し入れてみると呻くような声を出した。関さんはキスにも慣れていなかった。そして何度キスをしてもカフェオレの香りはしなかった。 京都に着いたのが午後三時半ごろだった。ホテルは四条堀川にあるガーデンホテルで、地下鉄烏丸駅から西へ五分ほど歩いたところにあって、京都の繁華街からはかなり離れていた。そのため、設備は十分整ったデラックスなホテルにもかかわらず、料金は比較的低く設定されていた。関さんと一緒に部屋に入り、太陽で熱された身体を少し冷やした。このまま観光には出ずに、一日中ベッドで抱き合っていたいと思った。 「去年はどのあたりを回ったの?」 「ホテルは去年もここだったの。山の方向を目指して歩いて、清水寺とか東山のあたりに行って、それから、京都はやっぱり金閣寺へ行かなくちゃと思って、バスに乗って迷いながらようやくたどり着いたのよ。初めての京都だったからスムーズに回れなくて、結局は有名なところはその二ヶ所だけ。あとは地図を見ながら京都の街をブラブラと歩いて、夜は河原町通の京風料理屋さんで食べて、早めに部屋に戻ってジッとしていた」 関さんは瞳をクルクルと回して、去年の旅行を思い起こしながら語った。 「ひとりじゃつまらなくなかった?」 「ひとり旅は寂しいと思うこともあるけど、友達と一緒だと気を遣うし、相手に合わせないといけないでしょ」 関さんは私の肩に頭を乗せて言った。 「そうだね、誰にも気遣わず、誰とも接触を持たずに何日も過ごすことって快適だからね。もちろん広美の言うように、猛烈に寂しい気持になるときもあるけど、そのときの寂しさよりも、ひとりでいるときの快適さのほうが上回るんだよな」 ホテルを出て河原町へ向かって歩いた。鴨川は学生のころよく訪れた。大阪の北摂にある大学に、訳あって京都から通った。右京区の太秦に近い天神川という用水路のような小さな川のすぐ近くに、当時住んでいたアパートがあった。映画撮影所の敷地内にある古い二階建てアパートで、撮影スタッフの寝泊り先としていくつかの部屋が契約されていたようだった。 私はそこから阪急電車で大学へ通い、夜は木屋町という京都の歓楽街にあったキャバレーでボーイをした。今治の実家からの仕送りが一切無く、極貧の学生生活だったが、店のホステスと同棲したり、バクチに一時期のめり込んだり、今思い起こすと出鱈目な学生だった。二十年近くが経ち、多くの苦い思い出が残る京都の町を、関さんという素敵な女性と手をつないで歩いていることが不思議だ。 四条大橋の上から鴨川を眺めた。陽がほとんど落ちようとしている京都の街は情緒的だった。とりわけ、ここからの北側の景観は、どこから眺めるよりも京都らしくて好きだ。大阪や東京のように高層建築物がなく、北山の稜線がくっきりと見える。 「何考えてるの?」 「学生のころをね。僕は京都で大学時代を過ごしたからね。思い出深い京都での生活だったんだ」 「京都のことはよく知っているのね」 「庭みたいなもんだな」 「フフフ」と関さんが笑った。 四条大橋のたもとから鴨川の畔へ下りて、三条大橋をくぐってさらに歩いた。関さんはときどき立ち止まって、「ほらあの鳥たち、気持良さそう」と鴨川で遊ぶ水鳥を指差したり、「あの建物、すごく京都らしくて素敵ね」と鴨川沿いの西側に並ぶ古い料亭や公共施設の建築物を見て感嘆したり、楽しそうだった。 いつの間にか夕陽は沈み、いつの間にか私たちは丸太町通りまで歩いていた。「戻ろうか」と関さんに提案し、鴨川べりからあがって河原町通りを下り、寺町通り出て、すき焼きで有名な「キムラ」に入った。入口は普通の食堂風だが、二階には広い和室があり、ガスコンロが置かれたテーブルが並ぶ、レトロな雰囲気がする店だ。 「岡田さんってこんな店も知っているのね」 「昨日は中納言の伊勢海老を食べて、今日はすき焼きだから、ちょっと贅沢続きだね」 「でも、めったにない旅行だからいいの。今日は私がご馳走する」 関さんは上機嫌だった。すき焼きも彼女の気分に水を差すことがなく美味しかった。私たちは満足してホテルに戻った。だが、その上機嫌はいつまでも続かなかった。彼女は部屋に入ると、私が帰ってしまうことを不安に思ったのか、急に元気がなくなってしまった。 「でも、泊まるわけにはいかないだろ」 「この部屋に私ひとりで寝ろっていうのね」 関さんは今にも泣き出しそうな表情に変わった。私はベッドに腰をかけて彼女の肩を抱いた。「一緒にいて」と関さんが呟いた。唇を重ね、舌を差し入れてみた。昨日交わした何度かのキスと違って、ふたりの舌が絡み合った。こころが震えた。 「ね、岡田さん。いいでしょ?」 関さんの目は訴えるような、怯えるような目だった。 「僕は朝までいたってかまわないよ。でも、きっと我慢できなくて君を抱くよ。そうなると、もう自分の気持ちが抑えられなくなる。僕には別居中の妻がいるけど、彼女は今癌と闘っている。別居した原因は僕にあるし、彼女は闘病している。僕は女性を幸せにできない男なんだ。だから君とつながりをもっても幸せにはできないと思う」 関さんは私の首のあたりに顔を置いて黙っていた。私はひとつひとつのことを真面目に考えている。でもその生真面目さが、実は相手を不幸に導いていることになっていた。そんな馬鹿な話があるかと思うかも知れないが、事実そうなのだ。やはり正直と誠実とは別ということが、私のような社会のはみ出し者の生き様からも証明されている。 「岡田さん、考え過ぎよ。世の中は幸せと不幸だけじゃないわ。中間だってあるのよ、きっと。私は今夜一緒にいてくれるだけでいいの。もちろん明日からも岡田さんと親しい関係でいられたら、仕事や生活に元気が出ると思うわ。でもその先のことはどうなるか分からない。確かに不安だけど、それを今考えなくてもいいと思うの」 昨日からのことをずっと思い起こした。関さんとはこうなるような気がしていた。そしてその予感は確実に当たった。仕事上の「勘」とは種類の異なる「勘」が見事に当たってしまった。私は関さんを抱きしめた。 |
| 五十一 |
|---|
|
翌日、関さんと私は朝早くから新快速電車で大阪に向かった。彼女は今日大阪に一泊して明日徳島へ帰る予定だったが、急遽、ホテルをキャンセルして、私の車で大阪を発って、先ずは彼女の実家のある西条へ向かうことになった。昨夜、私は関さんとつながった。結ばれたのではなく、「つながった」のだ。 「長く女性を抱いてないから、あまり自信がないけどかまわないかな?」 一応は念を押した。 「馬鹿なことを言わないで」と関さんは少し怒った。有希子と一緒に暮らしていたころは普通の夫婦関係があった。そんな暮らしが一変して、もうかれこれ一年近くも女性との接触がなかったため、果たして男の機能を発揮できるものかどうか、本当に自信がなかった。 シャワーを浴びながら、口では「関さんを抱いてしまったら戻れなくなってしまう」と格好をつけたことを言ったが、蘇生するのかどうかが心配になった。だが、関さんの肌を直接感じると、そんな心配は吹き飛んでしまった。私は久しぶりに男になって猛獣のように関さんの中に入っていった。私は完全に蘇生し、関さんは一瞬身体が跳ねたあと、しばらく動かなかった。 「もう離れたくない」 関さんは私の胸に顔を乗せて言った。 「療育園で働きづめだったから、きっと疲労がたまってるんだよ。一度山を降りて、リセットしたほうがいい。仕事を離れて実家に帰ってみよう」 「そうね。私のことを心配してくれてありがとう。すごく嬉しい」」 こころも身体も疲れ果てた関さんを、山に戻る前に実家に帰らせてリセットさせてやりたいと思った。 「私、どうにかなってしまいそう」 関さんは呟いたが、私はもうとっくにどうにかなってしまっていた。 それから朝まで様々な話をした。関さんが九月で二十七歳になることや、穴吹療育園に勤めて七年目になること、実家には二年以上戻っていないこと、趣味は音楽を聴くことくらいだが、実際は仕事が趣味になってしまっていることなど、彼女は耳元で囁くように打ち明けた。 あと二日休みがあるのだから、明日は大阪に泊まらず西条の実家に帰って、少しだけでも顔を見せて両親を安心させようとアドバイスした。そして、そのあと穴吹まで送って行くと約束した。 「分かった。そうする。でもひとつお願いがあるの」 関さんは少しだけ考えてから言った。 「実家に岡田さんも来て欲しいの。私の彼氏だからと親に紹介したいの。ね、いいでしょ?」 「かまわないよ」 兎我野町の部屋に帰って服を着替えた。その間、関さんはコーヒーを淹れてくれた。 「この部屋に来るのは二度目だけど、何度も来ている気がする」 彼女は不思議そうに言った。ベッド脇の電話の留守番メッセージが点滅していた。三件のメッセージが入っていて、ひとつはT社の部長から所在調査の依頼だった。二件目は有希子からのもので「急がないから電話が欲しい」とあった。そして三件目は真鈴からのものだった。 「光一はこのところどうしているの?Lineを飛ばしても既読にならないし、電話してもすぐに留守電に変わるし、変だよ。八月になるまで私が忙しいと言ったら、全然無視するんだね。何しているの?どこにいるの?どうなったって知らないからね!」 どうなったって知らないからって、まただ。最近の真鈴はおかしい。何かがあったのだろう。でもそれを訊くと「会ってから話す」と言う。私は考えると疲れるから考えないことにした。 「真鈴さんって、あの沢井さんのお嬢さんね」 「そう。変な奴なんだ」 「可愛いいじゃない、何か投げやりな伝言が」 関さんは笑いながら無責任なことを言った。 十一時を過ぎに部屋を出て、駐車場から愛車を出して出発した。関さんがリセットするために実家へ向かう。彼女の二年ぶりの帰省の手助けするのだ。長年の山暮らしで、彼女の「こころ」の処理能力はもう限界を超えている。一度クリーンアップする必要がある。今の彼女には、ほかのどんなことよりも実家に戻ることが大切なのだ。土曜日だから道路が混んでいなければ午後四時までには西条に着く。新御堂筋を北へ飛ばし、中国自動車道に乗った。真夏の太陽は今日も情熱的だった。でも私と関さんは太陽なんかに負けないくらいの気持を西条へ向けていた。アクセルを踏む足に自然と力が入った。 中国自動車道から箱崎インターで播但道路に移り、山陽自動車道に乗り換えて岡山県の倉敷まで休憩なしで一気に走った。瀬戸中央自動車道に道路を移し、瀬戸大橋の途中の与島パーキングサービスでようやく休憩をとった。関さんは瀬戸大橋を車で渡るのは初めてで、「すごい!」を連発していた。実家へ久しぶりに向かうことで、彼女の眼は次第に輝きを帯びてきたように見えた。きっと彼女は仕事のことでいろいろと悩んでいたに違いない。でも真面目な性格だから仕事中心の暮らしから、わずかひとときの休息さえも取らずに走り続けてきたのだろう。まるで翔ぶがごとくに走り続けてきたに違いない。 四国に入るとますます車は順調に走り、予定より早く西条に到着しそうだった。途中、豊浜パーキングエリアでもう一度休憩し、車の中で関さんと長い間キスをした。私の気持は方向転換しそうな様相を帯びてきた。「どうなったって知らないから」という真鈴の留守番メッセージの意味が気になったが、目の前の関さんとのキスの味に酔いしれた。 「どうにかなってしまいそう。どうしようもなく好きになったらどうしよう」 長いキスのあと、関さんは困ったような表情で言った。 「もう僕と君はつながったんだ。だからどうなるかではなく、どうするかなんだ」 この言葉以上に、もっと伝えたいことがあったが、それを今、口に出すのは控えた。どうするかなのだと言っても、私も関さんも現実へ戻れば様々な出来事がある。社会と関わっていると約束事が守れなくなるときもある。関さんへの愛情がこころの中に存在する唯一のものではない限り、約束が確実に守られ、愛情を注ぎ続けられる保証はない。そんな脆弱な気持ちで未来の約束などできるはずがないのだ。これから先のことは予測がつかないし、言葉に表すこともできない。はっきりと見えない未来のことを無責任に口には出せない。 伊予西条インターから降りたのが午後三時半ごろ、関さんの実家は国道十一号線を西へ走り、加茂川大橋を渡ったところの農業区域にあった。実家は代々専業農家だったが、父は地元の中規模の造船会社に勤めるサラリーマンとなり、現在は兼業とのことだった。実家が近づいてくると関さんは黙り込み、顔つきが緊張しているように見えた。 「近くなの?」 「次の交差点を左に曲がって少し行くと、右側に赤茶けた納屋のある家が見えるから」 「大丈夫?」 「うん、多分。岡田さん、家に一緒に入ってくれるでしょ?」 「いいよ。彼氏だからな」 「うん」 私は関さんの誘導のまま、車を頭から彼女の家の敷地内に突っ込んだ。庭と納屋の間にも広い敷地があり、軽トラックと乗用車が止まっていた。車から降りようとしているところへ母親らしき女性が近づいてきた。 「どうしたの?広美。連絡してくれたらよかったのに。ちっとも帰って来んと心配していたら、急に帰ってくるんだから。どうもすみません、送ってくださったのですね」 彼女の母は私に頭を下げた。 「岡田さん。彼氏やから」 関さんは臆すこともなく、堂々と紹介した。 「はじめまして、岡田と申します」 丁寧に挨拶をすると、もう一度母が頭を下げた。 「お父さん、広美が帰って来たんよ」 母は叫ぶように言いながら家の中に入った。突然だったとしても、娘が帰ってきたことの喜びを母は身体全体で表現していた。急な提案だったが、関さんに帰省を勧めたことが間違いではなかったと、ようやくホッとした。私と関さんはすぐに玄関から入らずに、庭を横切って広い縁側に腰をかけた。 「すぐに帰るから、もう少し我慢してね」 「我慢なんかしてないよ。僕に気を遣わなくていいから、ご両親にキチンと謝らないとだめだよ。長い間帰って来なくてごめんなさいって。分かったね」 「分かった」 しばらくして両親が奥から縁側にやってきた。父親は農作業中だったようで、手ぬぐいで汗を拭きながら娘が帰ってきた喜びを表していた。まあともかく上がって下さいということになり、僕は恐縮しながらも靴を脱いだ。 「大阪の人。一年位前から付き合いしてもらってる」 関さんはぶっきら棒に言った。母親がお茶を出しながら「娘がお世話になります」と言い、「どうぞゆっくりしていってくださいね」と付け加えた。通された部屋は昔からの大きな農家にある二部屋ぶち抜きの広い和室だった。 「今日はすぐに帰らんといけんから、また今度ゆっくり来る。心配要らんから」 関さんはお茶を啜りながら言った。もう少し優しい言い方をしてあげればいいのに、彼女は両親とまともに視線さえ合わせようとしなかった。それでも両親は笑顔で娘が帰ってきたことの喜びを表し、どこの馬の骨とも分からない僕にも好意的に接してくれた。ふたりとも実直そうな人物に思えた。 「穴吹まで送ってくださるんですか?」 母が心配そうに訊いた。 「もちろんです。広美さんのアパートまでキチンと送り届けますからご安心下さい。今日はあまり時間がなくて申し訳ありませんが、今度ゆっくりご挨拶に伺いたいと考えています。広美さんとは真面目なお付き合いをさせていただいてます」 関さんが私を見て驚いた顔をしていた。でも冗談ではない。真剣かと問われれば、はっきり言って分からない。でもこの場の気持ちとしては本当だ。 父が正座している私に「どうぞ膝をくずして下さい。遠慮なさらんでくださいな」と気遣った。父も母も穏やかそうな人柄で、関さんはこの両親のもとで経済的にも支障なく平穏に育ったのだろう。でも彼女は今の職場で七年も働き、山篭りの暮らしの影響でこころが弱くなっていた。実家に戻ればリセットして再起動できるはずなのに、二年も帰っていなかったのだ。 「明日は日曜で仕事も休みだろうが?岡田さんと一緒に泊まって帰ればよかろうに」 父が私に気遣いながら、関さんに言った。 「ううん、日曜だからって仕事は休みじゃないけん、今日は帰らんといけんの」 関さんは首を振って返事した。いつの間にか奥に退いていた母が、両手でダンボール箱をひとつ、重そうに抱えて戻ってきた。箱の中には米袋や野菜類や缶詰や調味料のようなものがいっぱい入っていた。娘を思う気持ちが、段ボール箱の中の量に表れていた。 「これ、ちょっと重いですけど、すみませんが、車で運んでやってもらえませんかね?」 母親が遠慮がちに僕に言った。 「お安いご用ですよ。間違いなく広美さんの部屋まで運びます」 そのとき関さんが「そんなの要らんのに」と言って、急に涙を流しはじめた。涙はしばらく止まらなかった。これまでの寂しさや苦しさの量と、今日実家に帰って両親と会ったことの喜びを加えた分、ときにはしゃくり上げながら、いつまでも関さんは泣き続けた。 「あんた、どうしたん?」 「泣くことなかろうが」 両親が続いて関さんに声をかけた。泣けばいいんだと私は思った。両親の目の前でたまには泣くんだよ、関さん。両親は君のことをいつも心配している。いつ帰っても歓迎しない親なんていない。これを機会に辛くなったらいつでも帰ればいい。そしてリセットするんだ。私は関さんの涙を見ながらそう思った。 「何でもないけん。心配は要らんから」 七、八分も泣き続けてからようやく関さんは両親に言った。そして「彼氏に送ってもらうから大丈夫」と付け加えた。私は関さんの彼氏となった。 |
| 五十二 |
|---|
|
伊予西条から徳島の脇町インターまでは一時間あまりで着いた。関さんはこんなに近くに実家があるのに、こころが邪魔をして長い間帰省しなかった。もちろんときどき電話はしていたようだが、両親の顔を二年も見なかったことが不思議だった。でも私にしても、西条から車で一時間もあれば帰れる今治の実家に、もう何年も帰っていなかった。 見覚えのある穴吹川沿いの国道四百九十二号線を登って行った。関さんは助手席でずっと眠っていたが、穴吹町に入ると目を覚ました。 「ごめんね、今日は」 「何が?」 「彼氏にしてしまったことと、実家まで来てくれたり、穴吹まで送ってくれたこと」 「彼氏なんだから気遣うことないよ。広美はもっとリラックスしないとね。仕事が大変なのはよく分かるけど、自分のほうが仕事よりずっと大切だ。自分を大切にするということは、両親を大切にしていることになるし、僕もホッとする。分かるかな?」 関さんは少し考えてから「分かった。そうする」と言った。関さんのアパートは療育園から国道に出てきて、穴吹川に架かる橋を渡ったところにあった。彼女の部屋はC棟の2階の端部屋で、敷地内にはこのような二階建の社宅が四棟建っていた。私はダンボールを部屋に運んで、少しだけ休憩してから帰ることにした。 「泊まって帰ればいいのに。ずっと車を運転したり、うちの親に気を遣ってくれたり、岡田さん、ヘトヘトでしょ?」 「大丈夫、タフでなければ探偵はできないからね。でも女子高生に捕まってしまうこともあるけど」 「えっ?」 「いや、何でもないよ。コーヒーを淹れてくれたら嬉しいな」 関さんは小さなキッチンに立ち、インスタントコーヒーを淹れてくれた。カフェオレを作ってくれないかなと思ったが、いつまでもそんな感覚を持つ私はどうかしていた。 「もう一度エッチしたかったな」 「じゃあ泊まっていけばいいじゃない」 玄関でもう一度関さんを抱きしめた。心が揺るぎそうになったが、もし今夜泊まったら、真鈴の父がとった行動と同じことをするような気がした。守ってやらないといけない真鈴や有希子との連絡を絶って、関さんをさらって霧島温泉へ翔けて行ってしまいそうに思った。だから涙を呑んで彼女の身体を離した。 穴吹町を午後九時半ごろに出て、大阪に向かって車を走らせた。関さんとはひとつのドラマが終わったように思った。瀬戸大橋の途中でスマホが鳴った。真鈴の番号だった。 「どうしたんだ?」 「どうしたんだって、どういうこと?今、どこにいるの?」 「橋の上だよ」 「どこの橋の上なの?」 「瀬戸内海」 「ちゃんと答えてくれればいいじゃない。また私をからかってるのね。もういい!」 瀬戸大橋だよと言おうとした瞬間に切れた。彼女は気が短すぎる。瀬戸大橋の中間にある与島パーキングサービスに車を止めて電話をかけた。 「悪かったよ」 「・・・・・」 「謝ってるだろ、悪かったって。でも気短か過ぎないか?今仕事の帰りで瀬戸大橋にいるんだ」 「フン、光一だって『橋の上だよ』って、その言い方おかしいよ。普通に瀬戸大橋を車で走っているって言えばいいのに。ともかく明日会いたい。明日会えないと知らないから」 「何だよ、その言い方。予備校で忙しいんだろ。八月にならないと会えないと言ってたじゃないか」 「いいのよ、半日くらいなら。何時に行けばいいの?」 真鈴と明日の午後一時にいつもの扇町公園の入り口付近で会う約束をした。全く変な浪人生だ。 それから私はときどきパーキングサービスで休憩しながら、明け方に部屋に帰った。窓から見える兎我野町のビル群の窓は、ところどころすでに明かりが灯っていてホッとした。 二十日に新神戸駅で関さんを出迎えてから、この四日間がまるで異空間での出来事のようだった。関さんとついにつながった。「結ばれた」や「愛し合った」「セックスをした」という表現は適していない。彼女とは「つながった」のだ。この先彼女とどうなっていくのか、全く分からない。彼女の両親にとっての存在は「娘の彼氏」ということになった。ともかく落ち着いたらゆっくりと様々なことを考えてみようと思った。 約束の時刻に扇町公園に現れた真鈴は、ミニスカートではなくジーンズだった。ミニスカートではないことに少し物足りなさを感じたが、そんな感情は彼女の「相談したいこと」の内容で飛んだ。 「だから私、どうしようかなと思っているの。ハッキリと断ったほうがいいよね?」 「そうだな・・・その男は何度も手紙をよこしたのか?」 「六回もらった。全部手渡しでよ。それも短い手紙じゃないの。便箋に十五枚も二十枚も書いてくるのよ。よくあんなにいろんなことを書けるわ」 「そうか・・・」 真鈴は少し前から、京橋駅近くにある予備校の夏季講座だけ、週に三日ほど通いはじめた。予備校生ではなく自宅浪人の彼女は、夏季講座くらい受けなさいと沢井氏から言われたらしい。それは前から聞いていたが、その講座を受けている浪人生の中に、真鈴に好意を持っている男性が少し前からアプローチしてきたというのだった。 「そんなに言葉も交わしていないのよ。帰り道に声をかけてきて、一度目はマックでハンバーガーを食べながら、二度目はミスドでつまらない話をしただけ」 「そうか・・・」 「もっと早く光一に話をしたかったんだけど、すぐに諦めてくれると思っていたから、今まで言わなかったの」 「そうか」 「そうだな、そうかって、ちゃんと私の話を聞いてくれてるの?」 「聞いてるよ。考えているんじゃないか。で、その、ミスドってのは何なんだ?」 「ミスドはミスタードーナッツことだよ。ミスターチルドレンはミスチルって短縮するのと同じようなものだよ。それがどうしたの?」 「それは変だな。店とかグループの名前は堂々としたステータスだろう。それを縮めるなんて絶対におかしいな」 「そんな話をしているんじゃないよ。言い寄られてきてるんだよ」 「分かってるよ、それでどうしたんだ?」 「だから、私は困りますって一度受け取った手紙を返したのよ。でも彼は、急いで返事をくれなくてもいいからゆっくり考えて欲しいって言うんだよ」 真鈴は体育座りの膝に顔をうずめて、今にも泣きそうな声で言った。 私の本当の気持は「そんな男、断れ」だ。でもそれを言う権利はない。自分の気持に正直になることが、本当に相手に対して誠実な態度と言えるのか?ビリージョエルは「オネスティ」という有名な楽曲でしきりに訴え続けていたけど、正直と誠実とは別ではないのか?真鈴とは付き合っているわけではない。恋愛関係にあるかというと「ある」とは堂々と言えない。事実、私たちは会うと、ときどきキスはする。彼女を腕の中に抱くこともある。恋愛感情はお互いにあるのは分かっている。でも、自分の気持に正直になって本当の気持ちを伝えたとして、彼女の幸せを考えた誠実さがその言葉の中に存在するかというと、それは「違う」だ。そんな青臭いことを言ってはいけない。それは関さんに対しても言える。彼女の幸せを考えれば、つながってはいけなかったのかも知れない。でもそのときの正直な気持のまま、私は関さんを抱いた。もちろん彼女もそれを望んでいた。だから自分の正直な気持のまま突っ走った。でもビリーの訴える誠実さを考えるのなら、そこで踏みとどまって、彼女の未来の邪魔をしてはいけなかったのかも知れないのだ。 「ねえ、何とか言ってよ。何さっきから黙ってるんだよ。相談しているのに」 真鈴が不服そうな顔で言った。最近は髪をうしろで書道の筆のように括らず、少しカールしてダークブラウンに染めはじめた。本当に綺麗になった。 「真鈴の気持はどうなんだ?」 「私は特別な感情は持っていないよ。だから好きでもないし、嫌いでもない。真面目で物静かな人なの。いつも本を読んでいるような人」 「嫌いでなかったら、ちょっと付き合ってみればどう?付き合っているうちに、もしかしたら好きになるかも知れないし」 本心を言えなかった。悪い奴ではなさそうだし、スマホでLineやメールが当たり前の伝達手段になった時代に長い手紙を何通も書くなんて、きっと誠実さを持ち合わせている男なんだろう。 「それが本当の気持ちなの?ほかの男の人と付き合っても何とも思わないんだね?」 「何とも思わないことはないよ」 「じゃあ、何か言ってよ」 「そう言われてもなあ、無責任なことは口にできないし・・・」 真鈴は広場の向こうの扇町プールに来ている小学生の団体をジッと眺めていた。でもこころは何かを一生懸命考えているようだった。 |
| 五十三 |
|---|
|
「ガックリ」 「えっ?」 「ガックリだよ、光一には」 「なぜ?」 「何で正直な気持ちを言ってくれないの?私のこと好きだっていつも言ってくれるじゃない。私だってずっとずっと、もう一年も前から大好きなのに。本当に私がその男の人と付き合ってもいいの?」 真鈴は体育座りの膝の中に顔をうずめた。しばらくしてその顔が震え、小さく声をあげて泣きはじめた。父捜しを初めて頼んできたのもこの公園だった。「調査の費用は要らない。お父さんを捜すのは僕が好きでやることだから」と言っても、「それならもういい」と泣きながら帰ろうとした。一年前のことだ。 「もう泣くな。僕が悪かったよ。でもな、君は来月ようやく二十歳になる。僕はもうすぐ四十一歳だよ。君は来年大学生になる。僕は相変わらず怪しい探偵だ。誰がどう見てもおかしな関係だろ、そう思わないか?」 夏空が青色を突き抜けて水色に変わっていた。雲ひとつない水色空だった。 「そういうのって既成概念っていうんじゃないの?そんなの知らないよ。人を好きになるのって、条件なんて関係ないよ。だって私、今の光一が大好きなんだから」 真鈴は顔をあげて言い放った。そして急に立ち上がり、歩き出した。私もあとに続いた。国道を神山町に向かって歩くふたりの頭上には、真夏の太陽が存在感を示していた。カンカンと性懲りもなく容赦なく燃え、「どうだ」とばかりに熱射を注ぎ込んできた。でもふたりには通用しない。私たちはいつのまにか手をつなぎ、あらゆるものが何の関与もできないかのように平然と歩いた。ウメチカには降りずに、東急イン前の信号を渡って大融寺のほうへ歩いた。昨年の四月、依頼人の息子と真鈴はこの先にあるホテル・キャンディーポケットに入った。 「いいか?」 「いいよ。行こう、光一」 私たちは躊躇なくキャンディーポケットに入った。誰かが尾行していないかが気になってうしろを振り向いてみた。するとそこにはジーンズにグレーのTシャツを着て、一眼レフの入ったショルダーバッグを引っ掛けた「僕の幻影」が笑って立っているような気がした。その幻影は、私と真鈴の姿を見て「アンビリーバボー」と驚いていた。 私は真鈴を抱いた。これまでは車の中や生駒山頂や私の部屋で抱いたことは何度もあるが、それは抱擁の域を出なかった。でも、もう構わない。真鈴はもう女子高生じゃない。誰にも咎められる理由はない。 「お願い、シャワーを浴びさせて」 「シャワーなんて浴びなくてもいいよ」 「馬鹿」 彼女は長い時間シャワーを浴びた。 「光一はそのままでいいよ」 「アホ」 どれくらい綺麗に洗えば嫌われないかを考えたが、今更どうにもならないだろうと観念した。ベッドに入ると理性は完全に吹き飛んだ。ビリージョエルが「オネスティ」でしきりに訴えていることが、このようなシチュエイションになってみると、何だか正しいような気がしてきた。真鈴を覆っていたバスタオルを剥ぎ取り、肌を合わせた。この世の中にこんなにサラサラとした肌が存在するのかと思うほど、彼女の肌は滑るように心地よく、その感触はやがてしっとりと私の身体に溶けた。 「初めてなのか?」 「あたりまえじゃない。この前まで、まだ高校生だったんだよ」 「じゃ、ここまでだ」 混乱した。真鈴のバージンは予測していたが、私のような男が彼女を世界で最初に奪えない。身体を離してしばらく考え続けた。 「光一におとなにして欲しいんだよ。だからエッチして、お願い」 「エッチなんて軽く言うなって。儀式のようなものだろ。何がエッチなんだよ」 「憶えてる?生駒遊園地で夜景がきれいだった日のこと。これ以上の関係に進むにはもっと環境の変化が必要だって言ってたよ」 「そんなこと言ったかな?」 「もう十分変化して整ったはず。だから光一、悩まないで」 環境の変化か・・・。あのころの真鈴は精神的に不安定で投げやりで、尋常な状態ではなかった。私は私で有希子との別居問題やその後の彼女の病気のことなどで苦悩していた。月日が駆け巡って、今のふたりはお互いに気持ちを遮るものが存在しなくなっている。環境は整っていると言える。でも本当にこんなことがあっていいのか?二十歳を目前にしているといっても、まだ真鈴は少女だ。めまぐるしく考えた。でも気がつけば再び真鈴に覆いかぶさっていた。 「愛しているよ。世界中の誰よりもだ」 「うん、私もだよ」 温かくて柔らかく、それでいて軋むような感覚の中で意識が次第に遠ざかり、遥か彼方で遠雷が鳴り響いていた。雷鳴は次第に近づき、そして頭上を一気に通り過ぎ、もはや遠来ではなくなった。 「これでよかったんだよな」 「あたり前だよ。でも赤ちゃん、できちゃうかも」 真鈴はようやく私の首のあたりから顔を離して言った。 「赤ん坊を抱いて大学へ通えばいい。僕も手伝う」 真鈴は私の胸に顔をうずめ、目を閉じてしばらく動かなかった。彼女は少し疲れた様子だった。無理もない。疲労困憊の向こうにおとなというステージがある。心も身体も疲れ果てて到達する場所がおとなの入口だ。何の苦悩も精神的葛藤も経験しない人間には「おとな」というステージは待っていない。苦しいことや恥ずかしいこと、惨めな思いや怒りや悲しみなどを一杯溜め込んで、それらを濾過させて初めて人はおとなのステージに上がれる。真鈴はステージに到達し、私はそれを手伝ったのだ。 「瑠璃色の地球、聴いてみる?」 「えっ?」 「前にタワーレコードで買ったでしょ。私はスマホのアプリからダウンロードしといたの。この曲、大好き」 「そうだったな、そういうことがあったね」 「どうするの、聴いてみるの?それとも、もっとエッチする?」 「だからエッチなんて軽く言うなって。瑠璃色の地球、聴きたいな」 真鈴がバッグから取り出したスマホから透き通った女性の声が流れてきた。聴いている間、彼女は唇や首筋にキスをして邪魔をした。その邪魔さえも気にならないくらい素敵な曲だった。 「夜明けのない夜はないさ・・・泣き顔が微笑みに変わる瞬間の涙を、世界中の人たちにそっとわけてあげたい・・・」と手嶌さんは歌っていた。関さんと一昨日京都でつながり、真鈴と今日つながった。三人の「つながり」がこれからもずっと途切れることなく続くのかどうか、つながりを保ちながら生きていくのかどうか、それは分からない。 「いい歌だね」 「そうね。この歌はいろんな人がカバーしてるんだよ。でも私はこの人のが好き」 ホテルを出て大阪駅から環状線に乗った。真鈴はずっと黙ったままだった。黙って何かを考えているときの表情は、西条まで送って行く途中の関さんの表情と似ていた。私と真鈴と関さんとはひとつの線上に確実に生きている。この先、きっと彼女たちは私から離れ、それぞれの未来を生きていくだろう。そのときはまた、社会と少し距離を置いてひっそりと生きていこうと考えている。それが最も相応しい生き方なのだ。 「何考えているの?」 「ああ、いろいろとね」 「天王寺に着くよ」 「そうだな」 「光一、好きだよ」 電車天王寺に着いた。真鈴は電車を降り、乗換ホームへ向かった。ただの一度も私のほうを振り返ることもなく。それが彼女のふたりの関係への確固たる意思表示のようにも思えた。暑くて長い夏がまだまだ続きそうだ。 |
| 五十四 |
|---|
|
香織から連絡があったのは、彼女と別れてから五年半も経ってからのことだった。秋も深まった十一月末の夜、私は事務所兼自宅の窓から見える兎我野町のビル群を眺めながらビールを飲んでいた。 「私です・・・」と受話器から聞こえる女性の声が香織のものだとは分かるのに数秒を要した。絶対に連絡がないと思っていた相手だったからだ。 「ごめんなさい。いきなり電話して・・・香織です。元気にしているの?」 「どうしたんだ?」 そう言うのが精一杯だった。他に言葉が全く浮かばなかった。 「今さらあなたに連絡を取るのはお門違いなんだけど・・・それはよく分っているのよ。でも、どうしても話がしたかったの」 「誰に、その・・・誰に電話番号を聞いたんだ?」 ここの電話番号を知っているのは五人程しかいないはずだった。仕事の請負元であるT社の部長、別居中の妻・有希子、あることがきっかけで関係が続いている大学浪人生の沢井真鈴と、その浪人生の伯母が入院している徳島の穴吹療育園の関広美という女性職員、あとは行きつけの安曇野の女将さんくらいのものだ。極めて少ない私の人間関係を物語っていた。 「安曇野の女将さんから教えてもらったの。ごめんなさい」 「えっ?」 「実は、少し前に安曇野に寄ってみたの。昔、あなたが何度か連れて行ってくれたでしょ。女将さんに、岡田さんは元気にされてますかって訊いてみたら、あなたの名刺を持っていらっしゃって、この電話番号を教えてくれたのよ。女将さんに怒らないでね」 「もちろん女将さんには文句なんて言わないけど・・・それで、僕に何か用があるのか?」 香織は私が金融業で独立する前のファイナンス会社での後輩だった。私は妻子がいながら十歳年下の彼女と付き合った。彼女は新卒採用で入社して私がいた部署に配属され、極めてハイスピードで男女の関係になった。彼女とはすでに別の世界で親しい関係だったような、長いコマーシャルタイムのあと再びドラマが始まったような、形容し難い不思議な感覚が最初からあった。 「明日、造幣局の通り抜けに一緒に行かないか?」 「連れて行って下さい」 何の躊躇もなく香織を誘った。香織が返事をしたときの目には驚きの気持ちが映っていた。お互いの気持ちが瞬時に一致した感覚への驚きだった。毎年一定期間開放される造幣局の通り抜け。私と香織は大川沿いに咲き誇る様々な種類の桜を一通り見たあと、そのまま桜ノ宮のホテルに入った。決められた流れに従っているかのようにふたりはつながった。以前からのつながりが元どおりになった感覚がそこにはあった。うしろから見るとまだ少女のような小柄な体躯の香織は、私が初めての男だった。 私が金融業を開業してからも、香織とは変わりなく関係を続けていたが、ヘタを打って大きな不渡りを抱えて廃業するとともに、彼女は私の元から離れていった、もう七年以上も前の話だ。その香織が突然連絡をしてきたのだ。 「実は、馬酔木(アシビ)のマスターが亡くなったの」 「えっ?」 「突然だったのよ。夜勤から帰ってきて、玄関を閉めて部屋の上がり口で倒れていたらしいの。心不全だったみたい」 「夜勤からって・・・どういうことなんだ?」 香織と別れたころマスターはまだバーを経営していた。以前ほど頻繁に訪れることはなくなっていたが、彼の顔が懐かしくなると夜遅くに店の扉を開けた。そして店の営業形態が変わってしまってからは次第に足が遠のき、やがては行かなくなってしまった。 「店を閉めてからも付き合いが続いていた聡子ちゃんから、一昨日連絡があったの。もう十日以上も前に亡くなったって」 聡子という女性は商社に勤めるOLで、馬酔木の常連客だった。香織とは同年齢だったこともあり、今も連絡を取り合っているらしい。 「夜勤のあとって、彼はどんな仕事をしていたんだ?」 「硝子工場の作業員で働いていたんだって。聡子ちゃんが言うには、お店を閉めたのも体調がずっと悪かったかららしいの。だから工場の仕事がきつかったのかも知れないわね」 マスターが店を閉めたことは共通の知人から噂で聞いていた。以前のようなバーではなく、いわゆる男色の趣味を持つ客を対象にした店に営業形態を変えたため、昔の常連客のほとんどは行かなくなっていたが、何人かの親しい客は付き合いを続けていたようだった。当然、マスターもその趣味であることは、最初に店を訪れた夜から気づいていた。でも私は、男色の趣味を持つ人たちに対しての違和感や排除する考えはなかった。 もうずいぶん昔のことだが、ある夜、客がひけて私だけになってから、「岡田ちゃん、ちょっと入り口をロックしてもらえるかな。どうしても今すぐ聴きたい曲があるんだけど、かまわないかな?」とマスターが遠慮がちに訊いてきたことがあった。彼はその少し前に店にかかってきた電話で、誰かと深刻そうな話をしていた。電話を切ったときのマスターの表情は辛そうだった。大きな悲しみに包まれている様子が見ていて分かった。だから彼はきっと、客が気を遣わない私だけになって、自分の辛い気持ちを音楽に委ねて、少しでも静めたいのだろうと思ったのだ。 扉をロックしたあと彼は店の照明を暗くしてその曲をかけた。「ラブ・ストーリーは突然に」だった。リズミカルなイントロが流れてきた。カウンターの向こうの彼はこちらに背を向けてしゃがんだ。洋酒棚の微かな明かりだけが彼の背中を映し、大きな背中が小刻みに震えていた。 彼はその数ヶ月前の沖縄旅行の際、現地で知り合った男性と仲良くなったと話していた。その男性が関西へ遊びに来たことがあって、マスターが数日間エスコートしたと嬉しそうに語っていた。それからときどき「遠距離恋愛は辛いよね、岡田ちゃん」と、複雑な表情を見せることがあった。だから、おそらくその男性と破局したのだろうと私は思った。 電話を切ったあと、泣きたい感情をどうしても抑えられなかったのだろう。「ラブ・ストーリーは突然に」を二度、マスターは聴いた。「あの日あの時あの場所で君に会えなかったら、僕らはいつまでも他人のまま」と小田さんが歌っていた。でもそれって当たり前のことじゃないか、小田さん。それにラブ・ストーリーは突然やって来るかも知れないが、終わりも予告なく来るじゃないか、小田和正さん。突然始まった不思議な恋は、たいてい突然終わるものなんだ。実際、私と香織との関係がそうだった。 香織から馬酔木のマスターが亡くなったと聞いて、そんなことを思い浮かべた。 「それで、僕にどうしろって言うんだ?」 「そんなふうにきつく言わないで。私、光一に強い口調で言われると辛くなるから。私が悪かったのは分かっているのよ。でも、もうそろそろ許して欲しいの」 香織は言葉の終わりのあたりが涙声になった。きつく言ったつもりはなかった。 「君を許すも許さないもないよ。悪いのは僕の方だったんだし、君に何もしてやれなかったのだからね。ともかく、マスターが亡くなったことはショックだな。まだ五十を過ぎたばかりだっただろうに」 「うん、そうね。それで遺骨はしばらくお姉さんの家に置いているらしいの。だから、光一さえよければ一緒に焼香にだけでも伺いたいと考えているの」 香織と再会することに躊躇する気持があった。香織とは私に妻がいることを理解しての付き合いだった。香織は決して妻と別れて欲しいとは言わなかった。ただの一度さえも、私が妻のもとへ帰ることに対して嫉妬めいた言葉はなかった。今から思うと、その態度の背景には香織の精一杯の我慢があったに違いなかった。 愛し合ったあと妻のもとに戻る私の姿を、どんな気持で彼女は耐えていたのだろう。香織のこころの表面張力が保たれているうちは、緊張感によってふたりの脆弱な関係が保たれていた。だが金融業が破たんし、債務整理などに追われて会う余裕もなくなってしまった私の姿を見て、彼女のこころの表面にヒビが入り、パチンと音を立てるように張りつめた気持ちが萎んでしまったのだろう。 「分かった。それでいつ行く予定なんだ?僕はいつでも時間の都合をつけられるよ」 「じゃあ、急だけど明後日の土曜日はどうかしら?」 「いいよ、そうしよう」 私と香織は十二月最初の土曜日に七年半ぶりに再会することになった。二人が常連だったバーのマスターの死がきっかけだった。 「まだ僕のことを光一って呼んでくれるんだな」 「光一はいつまでも光一だから」 「嬉しいよ。じゃあ、明後日」 電話を切った。窓の外の兎我野町のビル群は、殆ど眠りに入ろうとしていたが、いくつかはまだ明るく人影も見えた。金の切れ目が縁の切れ目を絵に描いたような別れだっただけに、香織が私の元を去ってから二度とは戻って来ないと思っていたのだが、ずいぶんと年月が経って少しだけ降り立とうとしていた。それはほんの一瞬だけに違いないのだが、私はもしかすれば・・・と、未練がましい気持ちがこころをよぎった。ビールをもう一缶開けて、一気に喉に流し込み、その嫌な感情を流し去った。 |