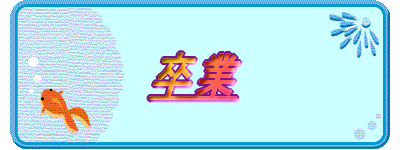
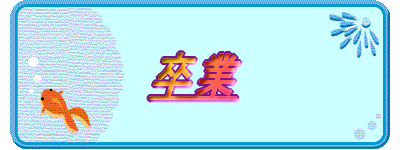
| 三十一 |
|---|
|
翌日、沢井氏から真鈴に電話連絡があるかも知れない日だったから、朝早く目が覚めて気持ちが落ち着かなかった。もし今日連絡がこなくとも、明日の日曜日には必ず真鈴に電話を架けると沢井氏から約束をもらっていた。 だが、昼前に有希子が何の連絡もなしに部屋に来た。昨夜電話したときには、「また気が向いたら行くわ」と言っていたのに、彼女の行動にはときどき慌てる。 「雨が降っているから、出かけずに夕方までここにいてもいい?」 いきなり有希子は言った。駄目だと言う理由が思いつかず、「いいよ」と了解した。 「今日はどうしたんだ?いきなり」 「あなたと一日ダラダラとしたかったの」 そう言って、有希子はソファーで寝転がっていた私の上に乗ってきた。有希子のことは勿論今でも愛している。別居を余儀なくされ、彼女の両親から引き裂かれたとしても、気持ちは変わらない。 「ベッドでイチャつこうよ、いいでしょ?」 ここしばらく様々なことを思考し判断してきた疲れを、私は有希子の抱き慣れた身体に委ねた。私たちは昼過ぎから夕方五時ごろまで肌を寄せ合って、新婚時代のことを懐かしんだ。有希子の小さな乳房や細い首や、身体の細さと不釣合いな豊かな臀部まで、すべてが私の身体の一部のような気がした。心地よい疲労の中、うたた寝をしているとスマホが震えた。時刻は午後六時前になっていた。ディスプレイが真鈴の携帯番号を示していた。右腕の中に有希子がいることで躊躇したが、左手でスマホを取り、電話に出た。 「真鈴です」と囁くような声が聞こえた。 「うん、どうしたんだ?」 「さっき、お父さんから電話があったの・・・」 そう言ったあと彼女は電話の向こうで泣きはじめた。 「私・・・嬉しくて」 彼女はときどき小さく嗚咽しながら長い時間泣いていた。私は黙ってその泣き声を聞いた。有希子が不審そうな表情で私をジッと見ていた。 「よかったな」 私はおそらく二分ほど経ってから言った。 「もしよければ明日、会おうか?」 「うん、会いたい」 「そのとき、今日のお父さんからの電話のことを詳しく話をしてくれるかな。いまちょっとお客さんなんだ。いいかなそれで?」 私は有希子の顔を見ながら言った。真鈴はそれでいいと言い、明日の午後一時にいつもの扇町公園の入り口で会うことにした。真鈴は電話を切る前に「奥さん、来てるの?」と訊いた。「うん」と答えるとすぐに電話が切れた。プツッと切ない音が異議を申し立てているように思えた。 「誰なの?」 当然のように有希子が問い詰めてきた。 「ほら、話したことなかったかな?尾行中に捕まった女子高生だよ。可哀相な子なんだ」 「どうしてあなたが尾行中に捕まった女子高生と会うのよ。会ってどうするの?」 「どうするのって、何もしないよ。ただ、行方不明だったお父さんが見つかったから、今の状況を説明するだけだ。電話では長々と話せないからね。何を心配しているんだ?相手は女子高生だよ」 有希子は少し考えている様子だった。 「まあいいわ、信用したげる。でもなんか変やね、親しそうやし?」 「変なことなんか何もないよ」 有希子は「知らないうちにこんな時間になってしまった」と言いながら急いで身支度をし、「今日はすごく楽しかったわ」と言い残して慌ただしく帰って行った。有希子が帰ったあと、部屋に真鈴を呼ぼうかとも考えたが、明日ゆっくり会ったほうが良いだろうと思いとどまった。今日は約束どおり奥沢氏から真鈴に連絡があって本当によかった。 日曜日は前日と打って変わって猛暑で快晴、午後一時に扇町公園の入り口で真鈴と会って、前にランチを食べた知り合いの店「プランタン」へ行った。真鈴はグレーにモスグリーンの細いチェックのミニスカートと白いスクールシャツのようなブラウスを着て、白のスニーカーを履いていた。ミニスカートから覗く太ももが眩しかった。 「岡田さん、何で黙っているの?やっぱり怒ってるのね。昨日、奥さんといるところに電話してごめんなさい」 「いや、そんなんじゃないよ。怒る理由もないし、奥さんは何も心配ない。そんなことより、今日はすごく可愛いな」 「えっ?」 「あっ、いや、何でもないよ。お父さんから電話がかかってきてよかったね」 真鈴は「うん」と返事したあと黙ってしまった。日曜日だからプランタンはランチタイムに関係なく混んでいた。 「いらっしゃい、岡田ハン、最近安曇野にお見えじゃないから心配しとりましたんや。さあ、こちらにどうぞ」 オーナーの伊藤氏が席へ案内した。 「このところ忙しくて、四国と鹿児島へ出張だったんですよ」 「何のお仕事してはりますんや?安曇野の女将さんも、岡田ハンの仕事のことは絶対に教えてくれまへんからな」 伊藤氏は大きな声で言った。私は真鈴に念のため訊いた上で、前回と同様にエビフライ定食を二つ注文した。伊藤氏は少し黙ればいいのにと思った。 「お父さんとどれくらいの時間、話をしたの?」 「そうね、十分位かな、うーん、十五分位かな。私、ほとんど泣いてたから」 「それで、お父さんは何て言ってた?」 「悪かったって。近いうちに必ず帰るからもう少しだけ待って欲しいって」 真鈴はそう言ってから少し涙ぐんだ。 「ともかく食事をしてから扇町公園で話そう。ここじゃ、いっぱい話せないからな」 私は慌てて言った。 エビフライが運ばれてきたあと、ふたりともほとんど会話もせずに食べ終わった。食事中に交わした言葉といえば、真鈴の学校のことと進学についてくらいだった。彼女は相変わらず「学校何てつまんない。大学何ていかない」と言った。 「岡田さん、あのう・・・お父さんを捜してくれたお礼のことだけど、こんなに早く見つけてくれるなんて思っていなかったから、私、交通費とか実際にかかった費用とかもまだ渡せないし・・・どうすればいいかしら?」 「それはあとで話そう」 コーヒーを飲み終えると店を出て、天神橋筋商店街を貫いて再び扇町公園に入った。 |
| 三十二 |
|---|
|
扇町公園に足を踏み入れてみると、さっきまでの街の喧騒が一瞬にして消え、平和で満ち溢れていた。子犬を散歩させている母子、長い杖に両手を置いて顎を乗せ、ベンチから子供たちが遊ぶのを見守る老人、彼氏の腕をとり、寄り添って歩く若いカップル、相変わらず危ないスケートボードで遊ぶ若者グループ、アイスクリーム売り、ジョギング中の健康的な若い女性、その人たちはおそらく幸せで、公園には平和がたくさん舞っていた。 そんな日曜日の扇町公園だった。公園は大切だ。でもカップルや幸せな家族だけの場所として存在しているわけではない。人々は生きることに疲れたときや、考えに結論を出せなくなったとき、人生を顧みるときなどに公園を訪れるのだ。 私と真鈴は幸せな人々の部類に入るのか、或いは苦悩している部類に入るのか、どちらなんだろうと考えてみた。おそらく、ふたりとも今はどちらかの方向への移動中のような気がした。確かなのは真鈴が少しだけ幸せに近づいたことだ。 私たちは少し奥まったところの木陰の芝生に腰をおろした。真鈴のミニスカートがさらに上にずれ、眩しい太ももが露わになった。 「真鈴、前にも注意したはずだけど、そんな短いスカートはやめなさい」 私は前を向いたまま言った。 真鈴は「えっ?」と言ったあと、両手でスカートの裾を下に引っ張った。そして「岡田さんって、本当におかしな人ね」と笑った。 「こんなの普通だよ。梅田あたりを歩いていたら、こんなじゃないよ。最近の女の子はこれくらいまで短いスカートを履いているんだよ」 真鈴は手でスカートの裾を足の付け根まで上げた。私は彼女の太ももの眩しさに目玉が飛び出しそうになった。 「アホ!おとなをからかうな。それよりお父さんと電話でどんな話になったんだ?」 「うん、お父さんね、今の仕事がすぐには辞められないから、先ずは今月中に必ず休みを取って一度帰ってくるって。岡田さん、お父さんって、今の仕事である程度の責任のある立場にいるの?」 「そうだな、印象としては支配人補佐みたいな感じだったよ。茶羽織がよく似合っていた」 「何?その茶羽織って」 「ほら、旅館の番頭さんなんかが上に羽織っている、身体の前で紐を括る着物だよ」 「ああ、何となく分かる。お父さん、そんな格好で働いているのね。昔はスーツにネクタイだったけど、信じられない」 真鈴は笑って言った。沢井氏は携帯電話の番号と勤め先の田丸本館の電話番号を彼女に教えたらしい。 「いつでも連絡できるようになってよかった。できるだけ早く帰って来るから、もう少しだけ我慢してって。お父さんが帰ってきてから、お母さんに家に戻ってもらうように説得しようって言うの。長い間いろいろ迷惑をかけてすまなかったって謝ってくれたの。それからお父さんが岡田さんにお礼を言いたいって。多分、近いうちに電話があると思うよ」 真鈴は嬉しそうな表情で言った。それほど遠くない日にようやく彼女は父と会える。 「よかったな、本当に良かった。こころから嬉しいよ」 「ぜ〜んぶ岡田さんのおかげだよ。でも、何でお父さん、鹿児島なんかに行ったんだろう。ねえ、どうしてお父さん、鹿児島だったんだろう?」 「それはな、長く生きていると、いろいろとややこしいことがあるんだよ。そのややこしいことを、あまり深く考えない人は気楽に生きていけるかもしれないけど、お父さんみたいに難しく考えると、鹿児島に行ってしまうことだってあるんだ」 私は全く説得力のない説明をしていると思った。でも現実はそうなんだ。 「お母さんのことだけど、お父さんが帰ってくるまで今のままでもいいのか?」 「うん、お父さんがそう言うのだけど、岡田さんはどう思うの?」 「僕は君の希望を叶えてあげたいと、それだけ思っているから、先ずはお父さんが帰ってきて、ふたりの暮らしが元どおり落ち着いてからお母さんの問題に取りかかるというのもいいと思うよ」 「そうね」と、真鈴は僕の意見に同意した。 「それから、さっき言おうとしていた調査費用のことだけど。あれはもういいからな。僕が自分の意思でやったことだから、気にしなくていい。気にするなと言っても気にするだろうけど、真鈴がこの先も友達でいてくれたらそれでいい。僕は友達がいないから、よければこれからも今のままの関係でいて欲しいんだ」 本当に父捜しにかかった費用なんてどうでもよかった。 「岡田さん、やっぱり私ではだめなのね。そうよね、奥さんにバレたら大変だものね・・・分かった。ありがとう」 真鈴は遠くを見るような目で、公園の平和な光景を眺めながら言った。 「ところで、レコード店に付き合って欲しいんだ」 「どうしたの?」 「うん、最近『明日への手紙』っていう歌が気に入っていてね、CDを買いたいんだ」 手嶌さんという女性が歌っている素晴らしい楽曲を、私は最近あるきっかけで耳にしてから気に入っている。歌詞も素晴らしい。 「知ってるよ、その歌。すごくいいね」 真鈴が知っていて、いい歌っていうのなら間違いないと思った。私たちは扇町公園を出てから梅田まで歩いた。東急インの前を過ぎると泉の広場に下りる階段がある。ここで依頼人の息子と真鈴が朝から会ってホテルに入ったことを思い出した。ずいぶん遠い日のことのような気がした。 「真鈴」 「うん?」 「ここで男の子と会ってホテルに入っただろ?」 「ごめんなさい」 彼女は少し考えてから謝った。 「前に君は、僕が思っているようなことはしていないと言っていたよな。ペッティングだけでエッチはしていないって」 「エッチはしていないよ。一緒にベッドに寝転んでDVDを観たり、テレビゲームをするだけ。でもペッティングって、岡田さんのその言い方、嫌いよ」 「だってそうなんだろ?」 「そりゃそうだけど、みんな寂しい男の子たちなのよ。キスくらいはしてあげるよ、胸を服の上から触らせてあげたりね。でもみんなまだ子供なの。私と一緒にいるだけで楽しいって言うのよ。受験勉強で彼らは大変なの。こころの拠りどころがないのよ。それにね、今の高校生や大学生って、凄くお金を持っているの」 私は真鈴がベッドに寝転んでDVDを見ている姿や、ゲームをする姿、ときにはキスをする姿を想像してみた。でもそれは気分が悪くなってくる想像だったのでやめた。私たちはウメチカをヘップファイブの方向へ歩いた。 「キスくらいって、そうハッキリと言うなよ」 私は真鈴のほうを見ずに呟いた。 「岡田さん、キスして」 一階へ上がるエスカレータに並んで乗ったとき、少し背伸びをした真鈴の唇が私の頬に触れた。そして柔らかい彼女の唇が私のものと重なり、すぐに離れた。 「お礼の一部ね」 わずか三秒に満たないキスのあと、呆然とする私に真鈴は言った。下りのエスカレータに乗っていた人たちが、唖然とした表情でふたりを見ていた。ヘップファイブの五階のレコード店に着いた。私はさっきのキスの後遺症に包まれたままだった。 「どうしたの、岡田さん。『明日への手紙』を買わなくちゃ」 真鈴が腑抜けみたい突っ立っている私に言った。 「そうだな、手嶌さんだったな」 「さっきのキスこと、奥さん怒るかな?」 「確実に殺されるな。でも言わなきゃ大丈夫だ」 私たちは「手嶌葵」さんの「明日への手紙」を買った。 「スマホのアプリから買えるんだよ。インストールしてないの?」 「何だよ、それ」 「岡田さん、遅れてるよ」 「うるさいなぁ」 私たちはそれからマンションまでしっかり手をつないで歩いた。四十になる中年男と女子高生、すれ違う人々は違和感を持たないだろうか。嬉しいけど何だかおかしな気分だった。 真鈴との関係はこの先どうなっていくのだろう?全く予測がつかないなと思いながら、無意識に彼女の手を強く握りしめた。真鈴は少し驚いた表情で私の横顔をジッと見ていた。 |
| 三十三 |
|---|
|
八月になっても私の日常には全く変化がなかった。だが、有希子と真鈴は動いていた。有希子は両親の提案で、お盆の期間に親子三人で南ヨーロッパへ十日間ほどの旅行に出た。父親は奈良県警の定年退職者だから経済的には裕福なのは分かっていたが、羨ましく思う気持ちを抑えられなかった。有希子とはまだ夫婦関係だ、それが何だ、勝手に連れまわしやがって、という憤慨を覚えた。 真鈴の父もお盆休みに彼女のもとに帰って来ることになった。わずか二日間だけだが、素晴らしいことだと感激した。沢井氏は真鈴に帰る日を連絡する前に私に電話をかけてきた。八月九日のことだった。 「沢井です。先日は大変失礼をしました」 電話が真鈴の父からだと分かるまでに三秒ほどを要した。 「こちらこそ、この前は若輩者が生意気なことを申しました。どうか許して下さい」 「いえ、遠いところ本当にありがとうございました。仕事柄、長いお盆休みを取れないものですから、十三日に大阪に帰って二泊だけ真鈴と過ごそうと思います。十六日から団体のお客様が入っておりますので、十五日のうちにまた鹿児島に戻りますが、岡田様のおっしゃるように、何とか今年の暮れまでには退職して、真鈴のもとに帰ってやりたいと考えています」 彼は落ち着いた口ぶりで説明した。 「それは素晴らしいことだと思います」 沢井氏は今回のお礼方々、真鈴と三人で食事でもいかがでしょうと誘ってくれたが、私は丁寧に辞退した。親子の関係に第三者が入るのはおかしいことだと思った。あくまでも真鈴と私のことにしておきたいのだ。その日は彼女からも電話があった。 「さっきお父さんから電話があって、十三日に帰って来るって」 真鈴は涙声で僕に報告してきた。 「よかったな」 「うん、よかった。すごく嬉しい・・・」 真鈴はスマホの向こうでこれまでとは比較にならないほど泣いた。長い間ずっと堪えていたものが堰を切ったように声を上げて泣いた。私は喜びの素晴らしい瞬間を聞き漏らさないようにスマホを耳を押し付け、彼女の号泣を聞き続けた。 「もう泣くな。これからまだまだいろんなことがあるんだから。泣きたい気持ちは分かるよ。僕も嬉しくて、もらい泣きを我慢できないくらいだからね。でもな、これからお母さんのことがあるだろ。まだ六十パーセントが解決した程度だからな」 「私、岡田さんが好きだよ。好きで好きでたまらないの。奥さんが羨ましい」 「錯覚だって、それは。勘違いだよ」 「あのね、私ね、今日が誕生日なの。夏の暑い季節に、私が産まれた病院の窓に風鈴がチリンチリンって鳴っていたんだって。それが凄くいい音色だったから、お父さんが真鈴って名前を付けたらしいの。お父さん、私の誕生日に帰る日を連絡してくれたのよ」 「素晴らしいプレゼントだな。きっとお父さんは姿を隠してからも、君のことを一日だって忘れなかったと思うよ。だから帰ってきてもお父さんを責めたりしないようにな」 「うん、分かってる」 「それから、今日が誕生日と聞いて、僕も何かしないわけにはいかないから、明日でも明後日でも少し会おうか?お父さんは十三日に大阪に着くんだね」 「そう」 「じゃ、明日会おうか」 「今からそっちへ行ったらだめ?」 私は数秒間考えた。今ここに真鈴がやってきたら、間違いなく一線を越えてしまう気がした。そういうわけにはいかない。 「今日は今から仕事の整理をしないといけないんだ、ごめん」 「奥さん、来てるの?」 「いや、奥さんは実家の両親と一緒にしばらくヨーロッパ旅行なんだ」 「じゃ、そっちに行くから」 「ちょっとだめなんだ、難しい調査依頼があってね。資料整理に時間がかかるんだよ」 「そうなの・・・じゃあ、明日会いたい」 翌日の午後一時にいつもの扇町公園の入り口で会う約束を交わしたが、私は複雑な気分になっていた。辛うじて踏みとどまっている彼女へ通じるこころ壁を、何かの拍子で一気に突き破ってしまいそうな畏れを抱いていた。 窓から見える兎我野町の街の風景は暑さで歪んで見えた。金融業の失敗によって、取引先などの人間関係も絶ち切れ、調査という地味な職業に就いてからは、淡々と仕事をこなすだけだった。そして妻と別居して、家庭というものも捨てた私は、社会というレギュラーな世界とは異世界にいた。いったん違った世界に入ってしまうと、ときには寂しさを感じることもあったが、その感情よりも壁で隔てられている孤独感の心地良さのほうが上回るような気にもなった。 調査に関わる人と、いきつけの飲み屋の女将さんや数人の常連客だけが私の人間関係だ。そういう生活が一変し、真鈴は必然的に私を捕まえ、彼女の父親捜しの役割を予定通り与えた。まるで決められていたかのように私を通じて父を呼び戻すことに成功した。真鈴は幸せに向かって突き進んでいる・・・と私は思っていた。 翌日、真鈴は午後一時きっかりに扇町公園の入り口に現れた。あれほどミニスカートはだめだと言っておいたのに、白と薄いオレンジ色のチェックのミニスカートに薄いピンクのポロシャツを着ていた。髪はカットしてショートヘアに近くなっていたが、それがよく似合っていて、ますます「可憐」という言葉がフィットしてきた。 「わざわざここまで出てきたけど、帰って岡田さんの部屋に行きたい」 会っていきなり真鈴は言った。 「何言ってるんだよ。今日は誕生日のプレゼントをしたいから会おうって言ったんだからな」 「じゃあ、何もいらない。岡田さんの部屋でくつろぐの」 「くつろぐ?」 「そう、くつろぐんだから」 真鈴はいつもと少し違っていた。態度に明るさと自信が湧き出ている感じだった。父が帰って来ることになって、気持ちがずいぶんと落ち着いてきたことが、彼女の言葉や振る舞いに無意識に表れていた。むしろ私をからかい、はしゃいでいるようにさえ思えた。 「くつろぐって言ってもなあ。ともかく、冷たいものでも飲もうか」 「奥さん、旅行でしょ。突然来る心配がないんだから、コンビニで何か買って岡田さんの部屋でのんびりしたい。それが私の欲しいプレゼントなの」 真鈴はそう言って動こうとしなかった。向かい合ったままの私と真鈴とを、公園に出入りする人々が怪訝そうな顔で見ていた。 「分かったよ。じゃあ、バースデーケーキを買って帰ろう。それとシャンパンだな。あっ、いや、シャンパンはだめだ。君は未成年だからな」 私たちは天神橋筋商店街にあるケンタッキーでチキンを六ピースとフライドポテトを買い、不二家で小さなバースデーケーキを買った。ケーキ屋の女の子に「MARINさんお誕生日おめでとう」と板チョコの上に白のチョコで書いてもらった。それを見て彼女はすごく喜んだ。それからコンビニでビールとコーラ、シャンパンを一本買って帰った。 「部屋は散らかっているし、汚いぞ。かまわないか?」 「平気」 「お父さんに内緒だぞ」と念を押した。 「分かってる。私も奥さんに内緒にしといてあげる」 真鈴は勝ち誇ったような顔つきで言った。どちらの言葉も彼女が主導権を握っているような気がして、どうも腑に落ちない気分になった。 |
| 三十四 |
|---|
|
曲がりなりにも事務所として使っているので部屋は汚くはなかったが、若い女の子を入れるのが初めてだったので躊躇した。でも真鈴はそんな心配をよそに、部屋に入るとキッチンに立ち、冷蔵庫から適当な野菜を取り出してサラダを作り、フライドポテトを小皿に出し、飲み物のグラスやフォークなどをテーブルに置いて、あっという間に食事の用意が出来た。 「ケーキはあとで食べよう」 真鈴は冷蔵庫の中をきれいに整理して、箱ごとそれを入れた。 「なれた手つきだな」 「そりゃそうよ。いつもコンビニ弁当をチーンするばっかりじゃないんだから」 彼女は当たり前のような顔をして言った。 私たちは食べて飲んだ。最初はコーラを飲んでいた真鈴だったが、私がシャンパンの栓を抜いて飲みはじめると「少しだけちょうだい」と一口飲み、「美味しい。私も飲みたい」と言った。グラスにほんの一センチだけ注いでやると、そのうちに自分で注ぎだし、結局シャンパンの四割は真鈴が飲んでしまった。ふたりともケーキが入らないくらいお腹がいっぱいになり、そして少し酔った。 「ここに警察が踏み込んできたら、君は未成年飲酒で逮捕され、僕はそれを幇助した罪で一緒にしょっ引かれるな」 「岡田さんと一緒なら牢屋にでも入る」 真鈴はテーブルに片方の肘をつき手のひらに顎を乗せて、気だるそうな声で言った。「岡田さんのこと、私、好きなの。どうにもならないくらい好き」 テーブルの向こう側から手を伸ばし、私の手を握ってきた。少しうつむき加減のポロシャツの胸のあたりから小さな膨らみが見えた。自然の成り行きで唇を重ねた。ヘップファイブのエスカレータでの突然のキス以来だったが、真鈴のキスはまだぎこちなく、高校生の匂いがした。私はその甘い香りを吸った。 「好きよ」 「少しだけ寝たほうがいい。調子に乗って飲んだからだぞ」 真鈴は本当に寝てしまいそうだった。私はベッドを綺麗にしてから彼女を寝かせた。「岡田さんが好き。奥さんが羨ましい」 真鈴は繰り返し呟きながら、やがて寝息をたてはじめた。頭の中が混乱してきたので整理しようと思ったが、シャンパンの酔いがそれを妨げた。絶対に踏みとどまるべきだという気持ちと、このまま抱いてしまいたいという欲望とがこころの中で闘った。でもどうにか理性が少しだけ上回った。 「もう五時前だぞ、起きなきゃ」 真鈴はエアコンのよく効いた部屋でタオルケットを腰から下にかけてぐっすり寝ていた。私はベッドに腰をかけて彼女の無邪気な寝顔を見ていた。 「うん?」 私の視線を感じたわけではないだろうが、ハッと彼女が目覚めた。 「どうしたの?」 「寝顔が可愛いから見とれていたんだ」 「岡田さん。抱いて」 意外な強い力にって引っ張られ、私の身体は真鈴の上に覆いかぶさる形になった。胸の下に彼女の小さなふくらみがあった。シャンプーの甘い香りが微かに漂ってきた。 「私、どうにもならないくらい好き。こんな気持ちになったのは初めてなの」 「錯覚だって。お父さんを見つけたことへの感謝の気持ちと勘違いしているんだ」 「違うわ、絶対に違う」 ここ数年の絶望的な寂しさと不安から解き放たれたことへの感謝の気持を、おそらく愛情と取り違えているのだ。私は少し紅潮した真鈴の可憐な顔をしばらく見ていたが、抑えが利かず唇を重ねた。そして長いキスのあと、ゆっくりと彼女の手を解いた。 ベッドから起きて、ケーキに少し太いローソクが一本と小さなものを九本立てて、部屋の電気を消してそれらに火をつけた。「こういうのって小学生のころ以来だわ」と真鈴は喜んだ。それから細い顔を思い切り膨らませて息を吐きだし、ローソクの火を一気に消した。真鈴、誕生日おめでとう。今年の誕生日のことは、君が次に好きになる人が現れるまで忘れないでくれと願った。 真鈴は午後七時前に部屋を出て行った。「もう泊まって行けよ」と言ってみたが、「お父さんやお母さんから電話がかかってくる可能性がゼロじゃないから、居たいけど帰る」と拒否した。思慮深い頭の良い子なのだ。 私は真鈴が部屋を出て行く姿をジッと見ていた。彼女がドアの向こうに消えてしまうと、さっきまで胸の中にいたのに、もう手の届かないところへ行ってしまったような大きな寂しさに襲われた。 世の中はお盆真っただ中だ。暑い夏はまだ終わらない。風鈴の音色が心地良い夏に生まれた真鈴は父と無事に会えて、幸せな二日間を過ごせたようだった。十五日の昼前に彼女からLineが飛んできた。 「今お父さんが帰ったの。空港にいるんだけど電話してもいい?」 名探偵コナンのOKスタンプを返信すると、すぐにスマホが震えた。 「楽しかったか?」 「うん、楽しかった。今年中に必ず戻るってお父さんが約束してくれたよ」 「よかったな。でもあまり嬉しそうな声じゃないぞ」 「そんなことないよ。メチャ嬉しい」 「それならいいんだけど」 「岡田さん、またそっちへいってもいい?」 「部屋に入れることはできないけど、扇町公園でマックやアイスクリームを一緒に食べるのはいつでもオッケーだよ。エビフライが食べたかったら変なマスターがいるレストランへも連れて行く」 真鈴はしばらく考えているようだったが「分かった。いろいろありがとう」と言って電話を切った。ひとつの長編ドラマがいったん長いコマーシャルタイムに入ったような気がした。 |
| 三十五 |
|---|
|
有希子は十六日にヨーロッパ旅行から帰国した。その日の夜、久しぶりに「安曇野」でビールを飲んでいるときにスマホが震えた。 「光一、さっき帰ってきたわ」 有希子の声を聞いたとき、懐かしさと同時にホッとするような気持ちになった。真鈴への愛情の種類とは対極にあるような有希子への気持だと思った。 「おかえり。無事でよかった」 「自宅に電話したら留守だし、携帯へかけたの。今どこにいるの?」 「今は・・・安曇野にいるんだ」 「どこよ、安曇野って?」 「金貸ししていたころからときどき立ち寄ってた飲み屋さんだよ。ほら、綺麗な女将さんのいる店」 「知らないわ、そんな店。綺麗な女将さんって、私が帰る日にそんな店にいるって不真面目じゃないの?」 有希子は急に機嫌が悪くなって電話を切った。何で彼女はこうなんだろう。彼女の両親が私たちの夫婦仲を引き裂いたと言っても過言ではないのに、別居中の暮らしにまで文句を言われる筋合いはない。 「あら、岡田さん、どうしたの?」 首を左右に振っている私を見て女将さんが訊いた。 「変な女なんです。僕の理解の範囲を超えています」 「綺麗な女将さんって言ってくれて嬉しいから、ビール一本奢らせてね。お盆明けで、まだ休みの会社が多いから暇なのよ」 女将さんはニコッと笑って言った。無意識な言葉から得をすることもあるのだと不思議に思いながら、綺麗な女将さんからコップにビールを注いでもらった。部屋に帰ると確かに有希子からの留守番メッセージが入っていた。 「お盆でも仕事なの?どこに行ってるの?」とそのテープは不機嫌そうだった。仕方なく有希子に電話をした。 「さっきは悪かったよ。今部屋に戻ったから」 私はとりあえず謝った。 「留守の間、何も変なことしなかったやろね?」 「変なことって、どういうことを言ってるんだ?」 「浮気に決まっていやない。許さへんからね、もしそんなことをしたら」 「許さないって?」 「終わりってことよ。浮気なんかしたら、私、絶対に嫌やから」 「本気だったとしたら?」 「光一、どうしたの・・・酔ってるの?」 「今夜はちょっと疲れてるからもう寝るよ。ともかく無事に帰ってきてよかった」 そう言って、初めてこちらから電話を切った。 私はなぜか有希子の言葉に挑戦的になってしまった。彼女の独占欲は理解する、まだ夫婦関係でもあるから当然かも知れない。独占される気持ちも悪いものではない。でもそんなに高飛車に言わなくてもいいだろう。君の知らないところで僕はひとりの女子高生の父親捜しに奔走し、その当人への気持と、その気持を抑えないといけない理性とのはざまで苦しんでいるんだ。何かの引き金で、僕は一気にその女子高生に突っ走り、そして戻れなくなってしまうかも知れない。僕は君の所有物でもかまわないと思っている。でも僕だって何もない日常じゃない。 有希子はその週の土曜日に僕の部屋に来た。最近は突然前触れもなくやって来るくせに、この日は朝九時前に電話がかかってきた。 「光一、今日そっちへ行ってもいい?」 有希子は戸惑ったような声で訊いた。私は彼女の質問の意味が分からなかった。 「どうしたの?いつも何の連絡もなく来るくせに」 「うん、じゃあこれから行く。お土産があるから」 ホッとしたような声で彼女は電話を切った。先日、私のほうから初めて電話を切ったことをずいぶん心配していたようだった。 その約一時間半後、有希子は肩にバッグをかけて、両手に紙袋とビニール袋を持って、汗だくになって部屋に現れた。でもいつもと様子が違っていた。 「今日は私、家に帰らへん。ここに泊まるからね。もし両親から電話がかかって来たら闘って。絶対に負けんといてね」 有希子はいきなり言った。 「私、今日は家に電話せえへんから。多分夜十一時を過ぎたら、ここに電話がかかってくるわ。そのとき、はっきりと言うてね。私を帰さへんって。絶対に言うてね」 興奮すると関西弁が丸出しになる癖が、彼女の真剣さを意味していた。 「どうしたんだよ、喧嘩でもしたのか?」 「ともかく今夜、闘って。私も一緒に闘ってもええから」 有希子は水玉模様のブラウスのボタンを二つばかりはずしてようやく椅子に座り、ハンカチで汗を拭った。 「ともかく落ち着いて。何があったの?」 「どうもこうもないのよ、本当にもう嫌。あの人たち、お金があれば幸せになると思っているのやわ。幸せってお金じゃなくて、好きな人と一緒にいられることなのに、それが分からへんのよ。光一が不安定な状態だから、お前はともかくいったん離婚しろって言うの。まだ若いし子供もいないんだから、安定した人からの良縁があるかも知れないって、何でもお金お金って馬鹿みたいやわ。そうやろ、光一。アンタはどう思うてるの?」 二ヶ月ほど前に彼女の実家を訪れて以来の苛立ちを、有希子は私にぶちまけるように言った。 「ともかく冷静になろう」 冷蔵庫から冷たい麦茶を出してグラスに注ぎ、有希子の前に置いた。彼女はそれをゆっくりと飲んだ。額の汗が引き、興奮状態だった表情も次第に落ち着いてきた。 「今夜泊まればいいよ。僕たちは夫婦だし、親にどうこう言われる筋合いじゃない。でも、泊まることをキチンと言っておいたほうがいいだろう。電話がかかってくる前に、僕のほうから連絡して筋を通しておくよ」 私は有希子を諭した。 「光一がそうしてくれたら嬉しいわ。あの人たちの言うことばっかり聞いてられへん。私、これまでずっと親の言いなりになって、仕事も生活もキチンとやってきたのやから」 有希子はそう言ってから、彼女にしては珍しく泣いた。私は彼女の肩に手を置き、そして長い髪を撫ぜ、こちらを向かせてキスをした。今飲んだ麦茶の香ばしい匂いが漂ってきた。今、私が守ってやらなければいけない女性はふたりいると思った。 有希子と商店街へ買出しに出た。得意の「お好み焼き」を作ってやると提案、適当な材料とビール、彼女が好きなワインと少しのお菓子を買って部屋に戻った。「新婚夫婦みたいね」と有希子は喜んだ。朝まで一緒に過ごすのは本当に久しぶりだ。 お好み焼きは鉄板やホットプレートがなくともフライパンがあればことは足りる。お好み焼き粉に水をあまり入れずに卵を多めに入れて溶くことが大切で、それ以外にはとろとろにすりおろした長芋を加える程度で美味しいお好み焼きができる。焼き上がったお好み焼きを一枚、大きな皿に乗せて有希子の前に置いた。「美味しそう」と彼女は喜んだ。これが幸せな生活の一部なのか、こういう暮らしが有希子との過去の暮らしにあったのだろうかと、すっかり忘れていた瞬間を思い起こそうとした。でも、彼女との夫婦生活は、私の仕事が多忙だった関係で、記憶の中にそういったシーンはすぐに浮かんでこなかった。 「光一、少し焦げているんじゃない?」 有希子の声に我に返った。目の前のフライパンから焦げた匂いと煙が漂っていた。 「何か心配事でもあるの?さっきからボーっとして」 「うん?またこういうふうに暮らせたら幸せだろうなって思ってたんだよ」 「早くそうなればいいね」 お好み焼きを食べて、私はビールを飲み続け、有希子は一本のワインをほぼ一人で空けてしまった。心地よく酔った身体をベッドに横たえると、二人ともいつの間にか眠ってしまった。目が覚めると午後九時を過ぎていたので、有希子の実家に電話をすることにした。 「本当に泊まるのか?」 有希子は躊躇なく「泊まる」と言った。電話には母親が出た。 「岡田です、夜分遅くにすみません」 「あら、こんばんは。今日そちらに有希子がお邪魔していますよね」 「はい、ここにまだいます。それでお母さん、有希子はちょっと熱があって、さっき計ったら三十七度八分なんです。高熱ではないんですが、大事をとって今夜は僕のところに泊まっていただきます。近くに病院もありますけど、たいしたことはないと思います。解熱剤や風邪薬も一応手元にありますから、どうかご心配なく」 私は一気に言った。有希子がリビングで苦笑いしていた。 「ちょっと、それは困ります。今は別居しているんだから・・・。有希子を電話口に出してもらえませんか」 「彼女は今寝ています。さっき薬を飲んだところなんですよ」 「お父さんと代わりますから」 母親はかなり慌てた様子で、次に父親が出た。もう一度「こんばんは、岡田です。いつもお世話になります」と挨拶から入った。 「これはどうも。何ですって、有希子が熱を出したんですって?」 「はい、さっき薬を飲んで寝入っていますので、今日はこちらに泊まっていただきます。明日できるだけ早くそちらに送って行きますから、ご心配でしょうがご安心下さい」 有希子のほうをチラッと見ると、今度は泣いていた。 「分かりました。ではお任せします。よろしくお願いします」 父親はそう言って電話を切った。私は受話器を置いて、小さくため息をついた。何で夫婦なのに妻の実家にこんなふうに気遣いをしなければいけないのだろう。いつの間にか横に有希子が立っていた。 「ありがとう。すごく嬉しい」 彼女は身体をあずけてきた。有希子の身体もこころも、しっかり受けとめてやる責任が確かにあると思った。 |
| 三十六 |
|---|
|
翌日、有希子を昼前には家に送り届けた。よっぽど疲れがたまっていたのか、或は少しはホッとして気持ちが落ち着いたのか、阪神高速道路を飛ばす車の中でずっと彼女は眠っていた。一時間半ほどで有希子の家に着いて、彼女の父も母もそろって玄関に出てきて恐縮がったが、決して家に上がれとは言わなかった。でもそんなことはもうどうでもいいと思った。有希子は両親の許認可など必要ない。人間は自由に生きていけばいい。それを阻む人がいても、その場面でやむなく従うのか、或いは自分の意思を通すのかが問題になるだけだ。 急いで帰る必要はないので高速道路には乗らず、阪奈道路から国道八号線をゆっくりと車を走らせた。ハンドルを軽く握りながら、今の暮らしと人間関係について、本当に自分が満足しているのかどうかを考えてみた。私にとっての幸せな人生とは、いったいどのようなものなのだろう? 人間はひとりで生まれ、ひとりで逝く。人生でどれだけ多くの人と関わったとしても最期はひとりだ。両親に守られて成長し、平穏な学生生活を送り、その過程で多くの友人を得て楽しくつながりのある生活を送る。結婚して子供をもうけて妻とふたりで力を合わせて幸せな家庭を築いていく。職場での人間関係、平穏な家庭、過去から続く友人たち、そういった人と社会とのつながりのある生き方が真っ当な「人生」なのか?それを人々は「良い人生」と呼ぶのか? 喧嘩もせずに仲良く年齢を重ね、孫の世話をして、次第に身体が動かなくなって朽ちていき、最期は妻や子供や孫に見守られて次の世界へ旅立つ。溢れるほどの様々な思いを胸に抱いて逝ければ幸せかもしれないが、たいていは認知症や病気のために思い出など消えてしまっているに違いない。それが素晴らしい人生なのか?孤独死が同情されるべき死に様なのか?孤独死という名称は人と社会とのつながりを維持し、経済的にもそれなりの優越感を持ち備えた、鼻持ちならぬ人間たちが勝手に名付けたものではないのか?当人はひとりで逝くことなど覚悟の上かも知れないではないか。多くの人たちに見守られながら最期を迎えることが素敵なのか?私はゆっくりと車を走らせながら、様々なことを考え続けた。車が峠に差し掛かったあたりでスマホが震えた。私は右手だけでハンドルを握り速度を緩めた。 「今どこにいるの?」 電話は真鈴からだった。 「阪奈道路かな」 「どこって?」 「生駒から大阪へもどる国道だよ。もう少ししたら峠を越えるけど、どうしたんだ?」 「どうしたんだって、酷い言い方ね」 「じゃあ、いかがされましたか?」 「からかっているのね。もういい!」 スマホが切れた。ちょっと悪かったかなと思ってすぐにこちらからかけた。 「ごめん、謝るよ。悪かった」 「・・・・・」 「悪かったよ。もうすぐ奈良から大阪に入る。そっちは何処にいるんだ?」 「今は京橋の駅だよ」 「京橋?また変なことしてないだろうな」 「まだそんなこと言うんだ、信用してくれてないんだね。ガックリだよ」 「いや、信用してるよ。でも心配してるんだ」 「今から学研都市線に乗ってそっちへ行く。どこの駅で降りたらいい?」 「じゃあ、四条畷の駅まで来るか?」 「仕方がないから付き合ってあげる」 真鈴は勝ち誇ったような声で言った。彼女と話をしていると、心が自然と弾んでいる自分が分かる。有希子への愛情を持っていることは間違いない。しかし何度も思うのだが、真鈴への気持ちは種類が異なるのだ。京橋から四条畷まで三十分もかからない。私は真鈴と午後三時頃に待ち合わせをした。 四条畷駅の近くに着いたのが午後二時を過ぎていた。真鈴は改札口の近くに立っていた。また今日もミニスカートだった。あれほどだめだと言っていたのに聞き入れない。私は近づいて手を上げた。真鈴は私を見つけて小走りに駆けてきて、右腕を取った。まるで恋人だ。この前、私の部屋で初めてしっかり抱き合ったことが、ふたりの距離を一気に縮めていた。 「待ったのか?」 「一時間も」 「アホ」 「三十分待った」 「そんなウソばかり言うなら、もう帰るぞ」 「ごめん、今来たところよ。でも岡田さん、短気だね」 「昼ごはんは食べたのか?」 「まだよ、何でもいい」 私たちは国道八号線へ戻る手前にある和食レストランに入った。 「奈良に行っていたの?」 「そうだよ」 「日曜日の午前中に奈良に用事があったの?」 「そうだ」 「そうだ、そうだって、何の用事だったのよ。話してくれたらいいじゃない」 真鈴は膨れっ面をしてお茶をひと口飲んだ。このところ彼女は急激に遠慮のない口調に変わってきていた。それは私にとって嫌じゃなかったが、同時に戸惑いも感じていた。 「実は昨日奥さんが来て泊まって帰ったんだ。両親には急に体調を崩したから泊まってもらいますって説明していたから、できるだけ早く送って行ったんだよ」 「体調悪くなったの?彼女さん」 「そんなの嘘だよ。両親に嘘を言って、泊まる口実にしたんだ。彼女の初めてのレジスタンスなんだ」と説明した。 「レジスタンスって分からない。でも岡田さんの部屋に泊まったのね」 料理が運ばれてきた。「さあ、食べよう」と私は言った。でも真鈴はなかなか箸を取ろうとしなかった。 「どうした?奥さんが泊まったことが気分悪いのか?」 「いいの、ごめんなさい」 難しい年頃の女の子なんだが、嘘は言えない。レストランを出てから大阪に向かって帰ろうとしたが、彼女は嫌だとごねて、奥さんの住む生駒に行きたいと言い出した。私は少しドライブすることにした。 「お父さん、具体的にはいつ帰って来るんだ?」 「十一月いっぱいで辞めて、家に帰って来るって。一昨日も電話で話をした」 「お父さんの仕事、すぐに見つかれば良いね」 「うん、どうなんだろう・・・」 「僕が見た感じ、何でもできる人のような気がするよ。会社を経営していた人だし、まだ五十歳少しだろ。まだまだ大丈夫だ」 「岡田さんがそう言うと、本当に大丈夫のような気がする」 真鈴は微笑んで言った。 「やっと笑ったな。もっと笑わないとだめだぞ。笑う角には何とかって言うじゃないか」 「岡田さんって、ときどき変なことを言うのね。おかしな人」 真鈴はそう言って助手席の窓のほうを向いてしまった。愛着のある車を走らせ、国道八号線から途中大阪方面へ折れて山道を登り、信貴・生駒スカイラインに入った。そして生駒山遊園地に午後五時ごろに着いた。真鈴は車の中でずっと黙ったままだった。私は少し空気を変えようと昔よく聴いたビリージョエルのCDを流した。真鈴はそれでも黙ったままだった。生駒山遊園地は、夏の間は午後九時まで営業していた。 「どうする、入るか?」 「この遊園地って幼児や小学生向けよ。ほら、乗り物の種類や出てくる家族連れの人たちを見てよ。岡田さん、私を子ども扱いしないで。私、おとなだからね」 真鈴が何を怒っているのかよく分からなかった。車内ではビリージョエルが歌い続けていた。ちょうど懐かしい「オネスティ」が流れて来た。「正直、誠実・・・なんて孤独な言葉なんだ。皆嘘をつく。誠実なんてどこにも見当たらない。でも君だけはそうあって欲しい」とビリーは訴え続けていた。私は駆け引きなどない正直で誠実な男でありたいと常々思って生きている。でも正直な生き方に固執していると平穏な暮らしは得られない。それは実感としてある。現実の社会では、たくさんの駆け引きや我慢や、ときには偽りも必要なのだ。正直に生きることが誠実とは限らない。真鈴は黙ったまま、助手席のドアに凭れていた。 「なぜ黙ってる?」 「・・・・・」 「もう帰る時間だろ、そろそろ暗くなってくるぞ」 「帰ったって私を部屋に入れてくれないんでしょ?」 「どうしたんだ、真鈴」 「私、岡田さんが好きなの。でも奥さんがいるし、私、すごく辛いの・・・」 こうなるような気がしていた。いったいどうすればいいんだ。真鈴の気持ちは嬉しいし大好きだ。有希子とは違った愛情を持っている。抱きしめてキスをして服を脱がせて、ひとつになりたい。そう強く思う。でもそれを抑えるのが、ビリージョエルが強く訴えている「誠実さ」じゃないのか? 「もう泣くな。僕も同じ気持ちだよ。でもな、思いのまま突き進むわけにはいかないことも、面倒で難しい世の中にはいっぱいあるんじゃないかな?」 真鈴は涙で頬を濡らした顔をようやくこちらに向けた。私は左手で真鈴の肩を抱き寄せながら、右手で頬を撫ぜてゆっくりキスをした。涙の粒がふたりの唇の間に流れてきてしょっぱい味がした。真鈴は小さく呻いて私の身体にしがみついてきた。 「すべての恋愛が結ばれることなんてないんだ。たったひとつの恋愛がそのまま結婚につながって、夫婦間に子供が産まれて、そして夫も妻もほかの異性に興味も持たず、平穏な家庭を築いて、そして仲良く歳をとっていくなんてことは現実的には難しいんだよ。男女関係はややこしいし、世の中はもっと複雑で、全然単純なものじゃない。僕は今、奥さんがいる。でもこの先、何が起きるか分からない。真鈴だって同じだ。僕と変な出会いをして好きになってくれた。僕も大好きだ。僕が悪い奴だったら、真鈴をうまくホテルに誘ってエッチするだろう。でもそんなその場限りの欲望には何の未来もない。そんなふうに僕は考えていないいんだ、分かるかな?君はまだ女子高生で年齢差が大きいけど、僕にとってはすごく大切な女の子だと思っているんだ」 「うん」 「だからな、真鈴。いつでも僕は会えるよ。でもこれ以上の関係に進むにはもっと環境の変化が必要だ」 「環境の変化が必要って、それどういうこと?」 「それは・・・君が考えてみてくれ」 「分かった。考えてみる」 私たちは生駒山の山頂から見える夏の終わりの大阪の夜景を眺めた。散りばめられた満天の星と、その下に様々な色の明かりが点滅する大阪の夜景は圧巻だった。私たちは車から出て夜景と星とを眺めながら抱き合ってキスをした。今年の夏もそろそろ終わりだ。激しい動きのあった夏だったと、真鈴を包み込みながら思った。 それから車を慎重に運転して、大阪に向かった。慌ただしい一日が終わり、マンションに帰ってエレベータを降り、部屋の前で真鈴と別れるときに自然とキスを交わした。私たちは、確実に恋愛関係に突き進んでいた。四十歳を目前とした男と女子高生でだ。 |