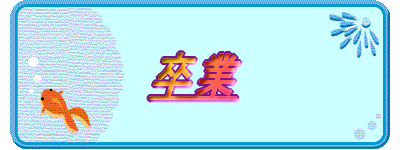
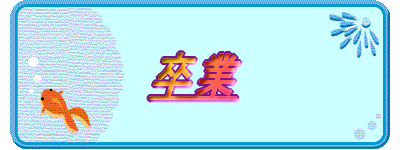
| 五十五 |
|---|
|
翌日、午前十時を過ぎてようやくベッドから出た。兎我野町のビル群はとっくに活動を開始していて、ビルがかすかに揺れているようにも思えた。 今年もあと一ヶ月ほどになって、窓から見える往来を人々が慌しく動いていた。私はマンションの一室を居宅兼事務所にして、相変わらずたったひとりで「岡田調査事務所」を営んでいた。ベッドから起きてインスタントコーヒーを淹れ、リビングの中央に置いている小さなテーブルの前に座ったときに電話が鳴った。T社の部長からだった。 「おはよう、岡田君。緊急事態なんだが、今どこにいるのかな?」 「今どこにって、この電話は僕の自宅ですよ」 「あっ、そうやったな。そんなら、すぐにこっちに来てくれるかな?」 緊急事態?ここしばらく請け負った案件に問題はないはずだ。もちろん調査が発覚するようなヘマは絶対にない。尾行に気づかれて女子高生に捕まったことはあるが、概ね調査で失敗はしないのだ。 「どういうことですか?」 「実はちょっとややこしいというか、難しい調査でな。昨日の夜に電話で相談してきた依頼人が朝から社に来とるんや。直接会って聞いてやってくれへんかな」 「尾行ならお断りしますよ。僕はタッグを組まないですからね」 「尾行と違うんや。変な依頼内容なんや。岡田君しか適任者がおらんねん。頼むわ」 「また過去の愛人の現況調査ですか?もううんざりですね、そんな非道徳的な案件は」 「まあ、そう言いなはんな。そういう依頼人がいるよって、われわれが食っていけるんやからな。そういうのとは今回は違うんや。別れた元愛人と、今は完全に縁が切れていることを証明してほしいという調査なんや」 「えっ?何ですって」 「ともかくすぐに来てや。待ってるから」 電話が切れた。師走になってから、部長までもが忙しくなっているのか?それにしても、「別れた元愛人と縁が切れていることを証明して欲しい」だと? 私は憂鬱な気分になりながらも、急いでシャワーを浴びて髭を剃り、久しぶりにスーツを着こんで出かけた。 マンションから徒歩十数分のところにあるT社の事務所を訪れると、十二月に月が替わっただけで皆が忙しそうな雰囲気を漂わせていた。自社の調査員を持たないT社は調査の案件によって下請けを持っていて、奥の応接では私のような外注の調査員が社員と打ち合わせ中だった。 「悪いね、いきなり呼び出して。ちょっとこっちに来てくれるかな」 部長は私を応接室へ呼んだ。部長と並んで座った反対側にひとりの女性が足を組んで優雅な雰囲気で座っていた。年齢は一瞥したところ三十代後半、影ができるほどの付け睫毛と濃いアイシャドウを塗っていた。彼女は目が痛くなるほどの真っ白なスーツを身にまとい、組んだ足先の豹柄のハイヒールが水商売の女性を表しているように思えた。 「こちらがご依頼人の泉井麻由美さん。泉井さん、彼が岡田君と言いましてな、弊社の最も優秀な探偵ですわ」 私は軽く頭を下げてからテーブルの上の調査資料に目を移した。彼女はセクシーな足をさりげなく組み替えて、豊かな胸を少し突き出すようにして話をはじめた。 「実は部長さんにも説明したのだけど、私の元彼との関係が間違いなく終わっていることを証明していただきたいの。つまり、今はもう何の関係もないと、何かの方法で証明して欲しいのだけど、できるかしら?」 「どういうふうに確証を取ればよろしいのでしょうか?」 これまで様々な調査を担当してきたが、過去の男との無関係の証明なんて案件はもちろん初めてだ。 「どういうふうな確証って・・・それはあなたが考えてくださらないとね。私はお願いする側ですもの。そうでしょ?」 彼女は「そうでしょ?」の部分を、私の顔を覗き込むようにしながら言った。少し微笑んだ口元から真っ白い歯が覗き、鮮やかな白のスーツに包まれた胸元とともに私を戸惑わせた。何しろここしばらく、女性との接触のない暮らしを送っていたからだった。 「今の彼が異常なヤキモチ妬きなのよ。私の元彼のことも仕事の関係で少し知っているから、第三者的な立場の人から、私と元彼とが確実に別れていることを証明しろと言うのよ」 「どうかな、岡田君。こんなお綺麗な方のご依頼だから、何とか引き受けてくれんかな」 少し考え込んでいると部長が横から言った。依頼人の綺麗も不美人も関係がないが「できるかしら?」などと言われたとあっては、差別調査や復讐屋や別れさせ屋のような公序良俗に反する調査依頼でない限り必ず引き受ける。 「分かりました。方法については私が考えます。もちろん相手には絶対に分からないように結果を出しますのでご安心ください」 泉井麻由美はニコッと笑って「それじゃ、よろしくね」と言い残して立ち去った。懐かしい香水の香りが微かに残った。その香りに包まれて過ごした日がよみがえって来そうな気がしたが、誰のものだったか思い出せなかった。 「悪いな、岡田君。こんな変な依頼をこなせるのはアンタしかおらんのや」 依頼人が帰ったあと部長と調査方法について打ち合わせを行った。こういう調査は若手スタッフでは難しく、私のような何でも屋が担当することになる。 「これはかなり難しい調査ですよ。調査というよりも、証拠取りですけど」 「依頼人は必死みたいやから、前の男と会っていないことは間違いないやろうけど、それをどう証拠を取って報告書にまとめるかやな」 部長は難しい顔をして考え込んだ。私は調査指示書を受け取ってT社を出た。天神橋筋商店街には早くもクリスマスソングが流れていた。人々の歩く速度もこころなしか先月より速くなっている気がした。だが私のこころは、明日七年半ぶりに会う香織のことを重く感じていた。その気持ちが歩く速さを緩慢にしていた。 十二月最初の土曜日の午後一時、私は阪急梅田駅三階の改札前で香織と落ち合った。七年半ぶりに会った彼女は前よりずいぶん痩せていた。濃いグレーのスーツ姿の香織は病気じゃないかと思うくらいに細く見え、以前の少しふっくらした健康的な体躯とは違っていた。 「光一、痩せたね。ちゃんと栄養のあるもの、食べているの?」 私が痩せたことを気遣う香織は、自分の体躯の変化に気づいていないようだった。私はもともと太ってはいなかったが、身体が弛んでいた時期があった。以前は仕事に追われる日々が続き、運動不足が影響していたのであって、このところもとの体重に戻りつつあったのは、ストレスのない自由な生活を送るようになったからだ。 「香織こそどうしたんだ。ずいぶんと痩せたよ。驚いた」 「そんなことないわ。だって私、病気ひとつしないのよ。私も三十歳を超えてしまったから太らないように食事に気をつけているの」 七年半ぶりに会った元恋人との最初の会話としては不適切だった気もするが、私と香織は別れたときの苦しみや傷など、今はまるで残っていないかのように再会を素直に喜んだ。 馬酔木のマスターの姉の家は阪急京都線の摂津富田駅近くに所在していた。車中、香織は意外にも饒舌だった。年月の経過は苦く嫌な思い出も浄化してしまう。「こころ」というものが持つ軟弱な性質だ。 彼女は私と別れてから三歳年上の会社員と知り合い、平野区内のマンションでその男性と暮らしていることや、ファイナンス会社をとっくに辞めて産業機械メーカーに勤めていることなどを語った。私はそれらにときどき相槌を打ちながら耳を傾けた。彼氏はプラント関係の設計技師で海外出張が多いことや、いつも遅くまで残業なので不規則な生活が心配だと、私には直接関係のないことを途切れなく語った。香織はそういった自分の生活について、「私は今、幸せなの」とでも伝えたいかのように喋り続けた。だが私には興味のある話ではなく、心地良くはなかった。それはおそらく、こころの隅に残っている彼女へのわずかな愛情がそのような気持ちにさせるのだろうと思った。香織と久しぶりに会ったのに、私は車窓から見える景色を眺めながらそんなことを考えていた。香織は相変わらず興味のない話を喋り続けていた。 「光一はあまり喋らないのね」 「いや、君と付き合っていたころを思い出していたんだ。断片的だけど」 「どんなこと?」 「グアムへ遊びに行ったことがあっただろ。あのころのことだよ」 決してそんなことを思い起こしていたわけではなかった。だが、私は香織とグアムへ遊びに行ったことがある。彼女にとっては初めての海外旅行で、深夜にグアムの空港に到着してから帰国するまでの数日間、まるで少女のようにはしゃいでいた。マリンスポーツや射撃やショッピングを楽しみ、夜はシーフードや肉料理を味わった。蜜月の夢のようなひとときだった。あのころのふたりは、先々のことを決して口に出さなかった。確かな未来が見えないことを考えるのが怖かった。 「楽しかったね、あのころ」と香織は言った。 「そうだな」 私は同意したが、あのころの楽しさや幸せは、今思い起こせば何の基盤もない脆弱なものだった。香織のことを真面目に考えていたが、妻ある自分の環境をどう整えてよいのか模索しながら日々が過ぎていくといった現実だった。だからこそふたりが共有できる時間を、まるで明日がやって来ないかのように生きた。どこへ行くにも何をするのも一緒だった。 |
| 五十六 |
|---|
|
馬酔木のマスターの姉宅は阪急摂津富田駅から五分あまり歩いた住宅区に所在し、広い敷地内の古い建物はきれいにリフォームされていた。マスターはここで生まれ育ったのだ。私たちを案内してくれた姉は、一度結婚したが離婚して実家に戻り、両親が亡くなったあともずっと家を守っていた。 「よくお越しくださいました。弟も喜びます」 私たちは広い和室に案内され、仏壇に飾られたマスターの遺影と遺骨に焼香し手を合わせた。遺影のマスターは大柄な身体を縮めるようにして恥ずかしそうに微笑んでいた。バックには洋酒棚があり、IWハーパーやワイルドターキーなどのバーボンウイスキーが並んでいた。スコッチよりもバーボンを飲ませる店だった。 その洋酒棚の下にしゃがみ込み、身体を小刻みに震わせて「ラブ・ストーリーは突然に」を聴いていたマスターの姿が目に浮かんだ。沖縄で知り合った男性と別れたあと、彼は男色趣味のある客だけを対象にしたバーへ店のスタイルを変えた。失恋したことで何かを変えたかったのだろうと私は思った。 姉がお茶を淹れてくれてから、私たちはマスターと過ごしたころを懐かしんだ。香織は終始ハンカチを目にあてて姉の話に相槌をうち、涙を流した。涙もろい部分は以前とちっとも変わっていなかった。静かに故人を偲び懐かしんでいる様子を、もしかすれば天国からマスターが見て喜んでいるかも知れない。でも私は、店を閉めた時点で、マスターはきっと幸せというものと決別したに違いないと思うと、不思議と悲しい気持ちにならなかった。マスターはバーを廃業したときにすでに昇華していた。あとの人生は付録だったのだ。 帰りの電車の中でも香織は様々なことを語り、ときどき今の彼氏の話題が含まれた。私には彼氏のことは関係がないのだが、香織は自分が今幸せなのだと訴えているのかと、あらためて彼女の表情を観察した。でもそこからは本意を読み取れなかった。 「君ももう三十一歳だろ。その彼はちゃんと結婚してくれるのか?僕がこんなことを訊く資格はないかもしれないけど」 「うん、多分・・・考えてくれていると思うのだけど」 もしかすれば香織の恋愛は、彼女が望んでいる形のものとは違っているのかも知れないと思った。 「光一、少し時間が早いけど、もし予定がなければ何か食べて帰らない?」 阪急梅田駅に着いて香織が言った。時刻は午後四時を少し過ぎたところだった。彼女の提案に数秒考えたが、「仕事の準備がある」とその誘いを断った。香織は明らかに落胆の表情を見せた。付き合ってもよかったかなと一瞬思ったが、その気持ちを無理に振り払った。「それじゃ、元気でね」と私が言うと、香織は今にも泣き出しそうな顔になった。でもこれ以上彼女との時間を持つと、昔のことがよみがえってきて気持ちが苦しくなってしまう。君には今、見守ってくれる人がいる。 「また連絡してもいいかしら?」 香織はまるで何かを恐れるような表情で訊いてきた。 「いつでもかまわないよ」 「迷惑じゃない?」 香織は私の目を覗き込むようにして言った。「問題ないよ」と返事して、私は彼女に背を向けて軽く手を振って別れた。少し歩いて振り返ると香織の姿はもう見えなかった。雑踏の中、大勢の行き交う人々が映像のように動いているだけだった。 私は急に切なさに襲われた。別れた場所に駆け戻り、香織が乗る地下鉄谷町線の方向へ姿を追った。たくさんの人とぶつかりながら香織の小柄な姿を捜した。どうして食事を付き合ってやらなかったのだろう。簡単なことじゃないか。私は香織の姿を追いながら後悔した。結局、東梅田駅の改札口近くまで捜したが、彼女の姿を見つけることができなかった。携帯に電話をかけてみたが電源オフか圏外のアナウンスが流れるだけだった。 香織と別れてから、夢遊病者のようにふらつきながら兎我野町の部屋に戻った。ふとベッド脇の電話を見ると留守番メッセージランプが点滅していた。またT社からの追加案件だろうと思い、すぐに再生する気にならなかった。冷蔵庫から缶ビールを取り出し、リビングの椅子に崩れるように座った。窓の外のビル群を眺めながら、さっき別れ際に香織が見せた表情を振り返った。久しぶりに会ったというのに、どうして食事くらい付き合ってやらなかったのだろう。香織は何かを恐れているようなぎこちない表情だった。きっと今、彼女は幸せではなく、何かに苦悩しているのだ。そう思うと、さっき優しくしてやれなかった自分を激しく責めた。 その後も香織の携帯電話に何度もかけた。だが、ずっと電源をオフにしたままか、或いは電波の届かないところにいるようだった。私は焦り苛立ちながら十分おきに香織に電話をかけた。何十回も何百回もかけた。でも空しいアナウンスが流れるだけでつながらなかった。一時的に電源を切っていても、そのうち気づいてオンにするだろうし、圏外の場所にいたとしても時間が経てば電波の届く場所へ移動するはずだ。でも、香織の電話はつながらなかった。 電話に残っていた留守録を再生しないまま部屋を出て、行きつけの小料理屋「安曇野」で食事をかねて飲んだ。今夜は香織と過ごした日々のことを思い起こしながら飲みたいと思った。食事の誘いを断ったあと、「それじゃ、元気でね」と言ったときの今にも泣き出しそうな香織の顔がずっとこころから離れなかった。せめて今夜は香織のことを思いながら酔いたかった。 「あら、岡田さん、お久しぶりでしたわね」 女将さんが男を蕩けさせそうな笑顔で言った。この笑顔に男は参ってしまうのだろう。 「岡田さんっていつもお久しぶりのような気がするのよね。もうずいぶん長いお付き合いなのに」 女将さんが本日の「おすすめ」を適当に出しながら言った。この日は土曜日ということもあって、店には男性二人の常連客だけだった。 「久しぶりでんなあ。また追っかけしてはりましたんか?」 私の顔を見て訊いてきた。追っかけとは尾行のことだ。 「追っかけは女子高生に捕まって以来、できるだけ断っているんですよ。プライドが崩れてしまいましたからね」 「そういえば女子高生がどうのこうのとか言うてはりましたな。岡田さんの仕事は私らにはよう分かりませんな」 そりゃそうだろう、僕だって分からないんだから。「別れた愛人と完全に切れていることを証明してほしい」なんておかしな依頼が舞い込む業界なんだから。 生ビールを半分ほど飲んだときに携帯電話が鳴った。ディスプレイに表示された番号はさっき話に出た女子高生、今は大学浪人生になっている沢井真鈴のものだった。私は返事をしながら店の外に出た。 「今どこにいるの?」 「どこって、いつもの飲み屋さんだけど、どうしたんだ?」 「自宅にかけたら留守番電話だったからメッセージを残しておいたんだけど、ちゃんと聞いてくれたの?」 「あっ、いや、まだ帰っていないんだ。それで何かあったのか?」 「だから明日会いたい。明日会えないと、私どうなるか分からないから」 「どうしたんだよ、久しぶりに電話してきたと思ったら藪から棒に。落ち着けよ」 「明日、何時に光一の部屋に行けばいい?」 「部屋はだめだ、扇町公園で待ってるよ。何時でもかまわないぞ」 「何で部屋に入れてくれないのよ。ともかく午後一時に行くから。それから、会ってすぐにお腹空いていないかって、絶対に訊かないでね」 「分かったよ」 電話が切れた。店に戻ると女将さんが「どうされたの?」と訊いてきた。 「さっき話に出た女子高生からだったんです。今は大学浪人生なんですけど」 「何の電話だったんですか?」 女将さんと常連客の一人が同時に訊いてきた。 「明日会えなかったら、どうなるか分からないからって言うんです」 女将さんも常連客も「アハハハ」と大きな声で笑った。腹が立つほどの大笑いだった。 「それで会わなかったらどうなるんでしょうね」 「それが僕にも分からないから明日会うんです」 女将さんは口を手で覆って笑い転げていた。私は苦笑いして生ビールをお代わりした。そして香織のことに思いを戻そうとした。でもさっきの真鈴の言葉が頭から離れなかった。「明日会えないと、私どうなるか分からないから」と真鈴は言っていた。香織が別れ際に見せた泣き出しそうな表情への心配度を、真鈴の意味不明な言葉に対するそれが大きく上回った。 ビールを三杯飲み終えてから、この夜は早々と店を出た。女将さんが「あら、もうお帰りなの?」と不思議そうに言った。「過去と現在の女性のことを整理しないといけないんです」と私は答えた。女将さんも常連客も再び「アハハハ、それは大変。おやすみなさい」と笑った。でも笑いごとではないのだ。 爆笑を背に店を出ると、濃紺の空に微かに浮かぶ月は三日月よりも細く、ほんのわずかしかその姿を見せていなかった。月を押しのけるように真っ黒な雲が堂々と動いていて、目の前の新御堂筋の高架をわしづかみにしているように見えた。私はわずか三杯の生ビールでかなり酔った。部屋に戻ってベッド脇の電話の留守番メッセージを再生してみた。やっぱり真鈴からのものだった。 「真鈴です。十二月になったね。光一は最近どうして電話してくれないの?携帯に電話したら圏外になっているよ。どうしたの?受験勉強の邪魔だからって思っているのなら、そんな気遣いは要らないよ。来年の合格には自信があるんだから。それより急いで相談したいことがあるの。このメッセージを聞いたら連絡ください。絶対だよ」 十二月二日午後二時十八分・・・と留守番メッセージのテープ嬢が録音された時刻を発表していた。そして二件目のメッセージも真鈴からのものだった。 「まだ電源オフだよ。自宅にもいないし、いったいどこに行っているんだよ。もしかして居留守?いるんじゃないの?光一!・・・本当にいないの?何があったの?自分が寂しいときは私の携帯に何十回も電話してくるくせに。明日会いたい。どうしても会いたい。明日会えないと私・・・どうなるか知らないからね、馬鹿!」 十二月二日午後四時三分・・・とメッセージテープ嬢が淡々と録音時刻を述べていた。真鈴は最後を馬鹿で締めくくっていた。さっき店にかけてきたときに、最初から機嫌が悪かったのはこういう経緯があったからなのだと分かった。香織と会っている間は携帯電話の電源をずっと切っていた。香織といる間、他からの電話には応対したくなかったからマナーモードにもしていなかった。電源オフの間に真鈴はかけてきて、そのあと自宅に二度も電話をくれたのだ。 「それにしても相変わらず気が短すぎるんじゃないか?」 窓から見えるビル群に向かって無意識に呟いていた。 |
| 五十七 |
|---|
|
これまでこの扇町公園の入り口で、私は真鈴を何度待ったことだろう。真鈴のもとに父が帰ってきてから、私は意識的に彼女との距離を置いた。あとは母を宗教団体から呼び戻す作業が残っていたが、私にできることはすでに終えていた。でも真鈴は距離を置くことを許さなかった。逆に遠慮のない態度になり、親密度を増していった。 この部屋に一度来たときも、未成年だからと忠告したにもかかわらずシャンパンを飲んで酔っ払い、強引に私をベッドに引っ張り込んだことがあったが、そのときも寸前のところで切り抜けた。二十歳も年齢差があることに僕躇し、これまで何度もギリギリのところで踏み止まっていたのだ。ふたりの年齢差のこともあったが、私には別居中の有希子がいる。しかも彼女はずっと乳癌と闘っている。真鈴の気持ちを受け入れられない大きな理由だ。 午後一時ちょうどに真鈴はいつもの公園の入り口にフラリと現れた。このところずいぶんと寒くなってきたのに、グレーと濃いグリーンのチェックのミニスカート姿だった。 「寒くないのか?そんな格好で」 「ちゃんとマフラーを巻いているじゃない。全然寒くなんかないよ」 そう言って彼女はグレーのパーカーのポケットに両手を突っ込んで堺筋通りを横切り、天神橋筋商店街を先に歩き出した。濃紺に赤の細い線が入ったマフラーがよく似合っていた。カジュアルな服装だが会うたびに彼女は少しずつおとなになり、綺麗になっていくような気がした。 前に会ったのは十月の初旬だった。土曜日の夜、突然電話をかけてきて「明日会いたい。どうしても万博公園のコスモスが見たいの」とわがままを言った。 「平日は予備校の集中講座で大変なの」と、そのとき真鈴はずいぶんと疲れた様子だったが、それでも手作りのサンドイッチを持って来ていた。まるで仲のよい恋人みたいに私たちは手をつないで、コスモスが満開の公園を散策した。四十歳の胡散臭い探偵と、K大学を目指す可憐な浪人生。ふたりをどの角度から見ても、誰もが首をひねるような関係に違いなかった。 「ちょっと待って、どこへ行くんだ?」 「どこって、プランタンへ行くんじゃないの?」 「会ってもお腹空いていないかって絶対に訊くなって、昨日言ってたじゃないか」 「今お昼どきだよ。お腹空いているに決まってるよ。さあ、行こうよ」 私は頭が痛くなってきた。 喫茶・グリル「プランタン」は昔ながらの「なにわの喫茶店」で、天神橋筋商店街の二丁目、地下鉄南森町の駅を上がったところにある。ときどき立ち寄る居酒屋「安曇野」の常連客である伊藤氏がオーナーで、コーヒー専門店やセルフサービスを主体とした店などが増え続ける中、昔からの純喫茶スタイルを貫き続けている立派な店だ。オーナーの伊藤氏の人柄はともかくとして、ここのエビフライは抜群の味なのだ。 店は日曜日のお昼時でかなり混んでいた。伊藤氏が私たちを見つけて近寄ってきた。 「よう来てくれはりましたな。今日も別嬪さんとご一緒でんな。まあこっちへ座りなはれ」 彼は私たちを厨房近くの奥の席に案内した。厨房から離れた席がいいのにと思ったが、「どうぞ、さあどうぞ」と強引に奥へ誘導するからやむなく座った。 「忙しそうですね。ともかくいつものエビフライ定食と、飲み物はホットカフェオレを」 「おおきに。まあゆっくりして下さいな。めったにお越しになりませんのやから」 伊藤氏はそう言って厨房に戻った。彼とは出身が同じ愛媛で、私の実家がある今治と彼の宇和島とはずいぶんと離れているが同郷の親しみやすさというものがあって、「安曇野」でも気軽に並んで飲むことがある。ただ、奥さんが大阪の人なので、無理をして喋る大阪弁のアクセントがおかしいのだ。 「ごめんな、別嬪さんなんて。品がなくて」 「いいの。もう慣れたから」 真鈴は笑った。 「ところで相談ってどんなことなんだ。お母さんのことなのか?」 「ううん、違うの。エビフライを食べてから、あとで話す」 昨年十一月に沢井氏が真鈴のもとに戻って来てから、彼の無理のない働きかけで今年の三月に母は家に戻ってきた。その後も宗教団体とは決別できておらず、ときどき数日家を空けて教会に泊り込むことがあるらしい。夫の失踪によって巨大な重荷と不安を背負わされた母は、その気持ちのよりどころを宗教に求めたことは責められない。完全に元に戻るにはさらなる月日が必要な様子だった。 「本当にここのエビフライって奇跡的に美味しいよね」 運ばれてきたエビフライ定食を、私たちはほとんど無言で食べた。真鈴はエビの尻尾までガリっと噛んで食べていた。 「奇跡的に美味しいってどういう表現なんだ?やっぱり、K大受験生の言うことは僕のような凡人とはちょっと違うね」 「馬鹿にしてる?」 「馬鹿になんかしていないよ。詩的な表現だと感心しているんだ。僕が真鈴を馬鹿になんかするわけないだろ」 「光一」 「何だ?」 「私のこと、好き?」 「えっ?」 飲みかけていたカフェオレのカップを危うく落としそうになった。伊藤氏のほうをチラッと見ると、彼は接客で大変な様子だったのでホッとした。いちいち茶々を入れられるとうるさいのだ。 「ちっとも電話をくれないのはなぜ?」 「それは、僕もいろいろと忙しかったんだ。変な不動産屋の案件も頼まれたしね」 「前はどんなに忙しくても電話くれたじゃない。浪人生の私を気遣っているの?」 「真鈴のほうこそ、前は深夜でも電話をくれたじゃないか」 「それは・・・私だっておとなになったんだからね。おとなにしてくれたのは光一だよ」 「ともかく出よう。緊急の相談があるんだろ。公園へ行こう」 店内は暖房がよく効いていたが、周りの客に会話が聞こえていないかと、背中を冷や汗が流れ落ちた。レジまで伊藤氏が来て、「年齢差なんか気にしたらあきまへんで」と、ダメ押しのようにわけの分からないことを言った。彼は少し寡黙になるべきだ。 店を出て天神橋筋商店街を北へ歩いた。商店街には当たり前のようにクリスマスソングが流れていた。少し歩いたところで真鈴がさりげなく手をつないできた。彼女と手をつなぐのは二ヶ月ぶりになる。本当に恋人のようで、少し照れくさかった。商店街を歩く人々全員が、ふたりの不釣合いに首をひねっているような気がした。 初冬の扇町公園は静かだった。神山町の通りと、キッズパークの出入り口を斜めに横切る人々が急ぎ足で通り過ぎた。公園を急ぎ足で歩いてはいけない。公園はのんびりと歩きながら様々なことを思考する場所なのだ。この時期になると、人々は公園でくつろぐこころのゆとりさえ失くしているかのようだった。私たちはいつも座る芝生に腰を下ろした。 「それで、相談って何なんだ。ちゃんと話すんだぞ。今日会えなかったらどうなっても知らないって言っていたくらいなんだからな」 「分かってる。ちゃんと話すから。でも、もう一度訊くけど、どうして前みたいに電話をしてくれなくなったの?私たち、もう深い関係だよ。遠慮なんか要らないのに」 「何?」 真鈴の言葉にときどきドキッとすることがある。深い関係・・・確かにそうかもしれない。私たちは今年の夏につながった。彼女はおとなの仲間入りをした。様々なことに苦悩し続けた彼女は、それらをようやく濾過しておとなになった。 「前に言い寄ってきた予備校の男の子の話、覚えている?」 「長い手紙を何通もくれた予備校生のことだな」 「そう。この扇町公園で相談したよね。どうしたらいいかなって」 「そういうことがあったな」 「何だよ、忘れたの?その日に私、光一におとなにしてもらったんだよ。そういうことがあったなって、ガックリだよそんな言い方」 真鈴は体育座りの足の間に、本当にガックリしたように顔をうずめた。チェックのミニスカートから覗く太ももが眩しかった。 「真鈴」 「何だよ」 「いつも言ってるだろ。僕と会うときはそんな短いスカートはやめろって」 「またそんなこと言うのね。馬鹿みたいだよ。こんなの長いほうなんだからね。予備校の女の子だってみんなもっと際どいミニスカを履いてるよ」 「その・・・ミニスカっていうのはミニスカートを縮めた言葉か?」 「そうだよ」 「何でも縮めればいいってもんじゃないだろ。僕は反対だな」 「相変わらず変な人だね。でもそんな話をしてるんじゃないよ。その男の子のことだよ。ちゃんと聞いてよ」 「分かってるよ。だから私にはその気はありませんって断ったんじゃなかったのか?」 「断ったよ」 「じゃあ、今度は何を言ってきたんだ?ストーカー行為でもされたのか。もしそうなら蹴散らしてやってもいいぞ」 「そんなんじゃないよ、そんなことをする人じゃないの。私と同じ大学を受けるって言い出して、もし僕が合格したら、正式に付き合ってくれる約束をして欲しいって言うんだよ」 真鈴はそう言って再び体育座りの股間に顔をうずめた。同じ光景を今年の夏も見たことがある。真鈴にとっては忘れられない日だと言ったが、私だってあの日を決して忘れない。あの日、しばらく股間に顔をうずめて泣いていた真鈴は急に立ち上がり、私を先導するように真夏の太陽の下を歩き出した。あのときの、彼女の全身から放たれていた先導力のようなものはいったい何だったのだろうと、私はときどき思い起こして不思議な気持ちになる。強烈な熱射を注ぎ込もうと、どんなに太陽がはしゃいでも、あのときのふたりには全く通じなかった。あのときの真鈴の姿は、まるでオルレアンへ向かって旗を掲げて兵士を先導するジャンヌ・ダルクのようだった。 「頭良いんだな、その予備校生。それに真鈴のことが本当に好きなんだな」 「良い人だよ。とても優しくて寡黙で真面目だし。光一みたいに私を放っておかない」 「どういうことだ?」 「光一は私にめったに電話してくれないじゃない。でも彼は二日に一度は電話やLINEをくれるよ。手紙も前ほどじゃないけど、ときどきすごく長いのをくれるの。真面目すぎて引いてしまうくらい」 真鈴は綺麗だ。彼女の可憐さはひと際、目を引かれるものがある。仕草や表情にときどき私もドキッとすることがある。 「クリスマスイブにコンサートに行ってから食事をしようって三日前に誘われたの。これまで予備校のあとマックとかミスドで少しだけ喋って帰るだけだったんだけど、キチンとした言葉で誘われたのは初めてなの。私、ちょっと怖いの。どう思う?光一」 「相談って、そういうことなのか?」 「そうだよ。明日また予備校があるから、そのときに返事しないといけないの」 私は考え込んだ。真鈴と意識的に距離を置いているといっても、世界で最も好きな女性は?と問いかけられたら、躊躇なく「沢井真鈴」と答えるだろう。でもいくら好きだからといって、自分の気持ちに正直になろうなんて青臭いことを言っているようでは誠実な人間とはいえない。私には癌と闘っている別居中の妻がいるのだから。オネスティはサッチァ、ロンリーワードだ。正直イコール誠実ではない。正直に生きれば生きるほど誠実という言葉は空しく感じるものなのだ。自分の気持ちに固執して、真鈴の将来を狂わせることはできない。だから「彼には悪いが断ってくれ。君は僕のものだから」と堂々と言えないのだ。 「どうしたんだよ。何でずっと黙ってるんだよ」 「真鈴」 「何よ?」 「僕は君とずっと一緒にいられたらいいなと思っている。でも、現実に目を向ければそういうわけにもいかない。君は来年から大学生だし、僕は別居中の妻を見捨てるわけにはいかない。その前に、君は僕のことをどれだけ深く考えているんだ?」 「考えているよ、光一のこと・・・私、好きだよ」 「でもな、僕は独身じゃないんだよ。一緒に暮らしていないけど、れっきとした奥さんがいるんだ。だから、悪いがその予備校生の誘いを断ってくれないかって、自信を持って言えないんだ」 真鈴は私の言葉のあと、しばらく遠くを見るように目を細めていた。 「どうして完璧を求めようとするの。そんなの難しいと思うよ。前に光一が何度か言っていた環境の変化が必要だっていう言葉、私好きだよ。変化して、ある程度整えばいいんじゃない?理想の条件になるのを待っていてもなかなか来ないよ」 「なんだ、生意気なこと言って」 「だからさ、七月に初めて光一とエッチしたのは環境が整ったんだよ」 「エッチなんて軽い言い方するなよ。ガックリくるよ」 「じゃあなんて言えばいいの?」 「それは・・・やっぱり、つながるって言葉だろう。重厚な趣がある」 「変な人」 私たちは扇町公園を出た。神山町の交差点を越えて兎我野町へ歩いた。いつの間にか再び真鈴は私の手を取っていた。 「ホテルでゲームするか?」 照れ隠しに思ってもいないことを口に出した。七月以来、五ヶ月も経っていたら、初めて真鈴を抱いたときとあまり変わらない緊張感があった。 「ゲームなんかどうでもいい。たまには息抜きが必要なの。受験勉強なんて本当につまらないんだから」 「じゃあ、一回だけ抱いてやるよ。何度も抱くと受験勉強どころじゃなくなるからな」 「こっちだって、一回だけ抱かせてあげるよ。何度も私を抱くと、光一だって明日から仕事ができなくなるよ」 七月以来の真鈴とのつながりは初めてのときのように身体もこころも震えた。二十歳になっても真鈴の吐息にはまだ少女の匂いが残っていた。 「本当にたびたびこんなことはしないんだぞ」 彼女にクギを刺した。大学受験生の女の子が、中年にさしかかる男とラブホテルなんかに入ってはいけないのだ。でも真鈴のほうも「そんなに私をたびたび抱けると思わないで。リョウに飽きられるのが怖いから」と言っていた。ともかく彼には悪いが「私、クリスマスイブも翌日も家族といなくちゃいけないの。それとあなたが大学に合格することと私のこととは別だから、そんな約束はできない。ごめんなさい」とでも言って断ってくれと提言した。 「分かった、そうする」 真鈴はニコッと笑って抱きついてきた。これでよかったのかどうか、考えても分からなかった。こんな場合どうすればよいのか、ビリージョエルに訊いてみたいと思った。 |
| 五十八 |
|---|
|
翌日、T社から無理やり依頼された気の進まない案件に取りかかった。事前に依頼人から提出してもらった元彼は御手洗剛彦(ミタライ タケヒコ)、兵庫県西宮市に妻子との家庭を持つ四十八歳の不動産業者だった。平安商事の屋号で同市内に事務所を構えているとあった。 依頼人は「別れてから一度も会っていないわよ。連絡も取り合っていないわ」と少し投げやりな口調で言っていた。おそらく本当なのだろう。金融会社に勤めていたころに不動産会社との付き合いは多々あったが、総じて押しが強く一筋縄ではいかない輩が多かったことを思い出した。大手不動産会社ならともかく、個人経営に毛が生えたような不動産業者に対して持つ印象は、正直言ってあまりよくなかった。 今回の依頼内容は全くレアなものだ。依頼人の今の彼が年下のお金持ち。いわゆる玉の輿に乗りたいが異常なヤキモチ妬き。せめて直前に付き合いのあった男との関係が確実に切れていることだけでも証明して欲しい、という内容だ。本当にアンビリーバボーでクレイジーな依頼内容だと思った。 私は調査方法に頭を悩ませた。調査期間は報告書を手渡すまでに一ヶ月だが、年内には手渡してスッキリしたい。御手洗氏を一週間尾行して、妻以外の特定の女性との接触が確認できたとしても、それが依頼人との関係が切れていることの証明にはならない。妻以外の女性とホテルに入る現場を撮影して、それを依頼人に見せたところで何の調査結果にもならない。要するに尾行調査では元彼と縁が切れていることを証明するのは不可能なのだ。だが、他にどういう方法があるというのか? 西宮市内の御手洗剛彦の自宅、または自営する不動産業・平安商事の店舗のいずれを訪問したほうがスムーズにいくかを考えてみた。でもどう考えてみても、家族や従業員がいるところに訪問することは、相手の心証を最初から刺激することになる。 外で一度お会いしたいと誘うには、先ず電話でアポイントメントを取る必要がある。面会したい理由を何にするのか?まさか電話で依頼人の名前を挙げるわけにいかない。御手洗氏へいきなり電話をしたとしても、用件が曖昧だと話にならない。ましてや相手は街の不動産業者だ。百戦錬磨の押しの強い灰汁のある人物と相場が決まっている。T社の部長は「塚本君のやり方に任せる」と言うが、方法を思索するまま数日が過ぎてしまった。 「だめでした。前に付き合っていた男性と縁が切れている証明なんて、どこの調査会社でも無理ですよ。調査費用の半分はお返しします」 それでは依頼人は納得しないだろう。プライドにかけても何とか結果を出さないといけない。事務所の窓のからえるビル群を眺めながら、調査方法についてずっと考え続けた。こんなに考え込むのは初めてかも知れない。 「ともかく、あたってみるしかないか」 一人暮らしを長く続けていると、無意識に何かに向かって呟くことが多い。自分の生き方や直面する問題について、ときには目の前のビルに向かって問いかけてみたり、夜中ベランダに出て夜空の月や星に向かって「どうしたらいいんだ?」と相談を持ちかけてみることもあるが、もちろん彼らは無言で私を見下ろしているだけだ。 酔った夜にベランダに出てみると、ときどき真っ白で巨大なマシュマロマンが新御堂筋の高架の向こうに立っていることがある。そんな夜には、「教えてくれよ」と彼にも問いかけてみる。でも彼はいつものように口の片方だけを上げて「ニヤリ」と笑い、何も答えてくれない。答えてくれない代わりに唇をすぼめて心地良い風を送ってくれるのだ。 さて、そうと決まったら先ずは電話でのアプローチだ。朝の忙しい時間帯を避けて、午後一時過ぎに電話をしてみた。 「平安商事でございます」と若い女性が応対した。 「私は岡田と申します。御手洗社長をお願いしたいのですが」 「少々お待ちくださいませ」 女性は簡単に御手洗氏に取り次いだ。 「はい、お電話ありがとうございます、御手洗です」 低い厚みのある声が返ってきた。プロの探偵の僕でも少しだけ緊張する。 「私は岡田と申します、初めて電話させていただきました」 「どちらの岡田様でしょうか。どのようなご用件で?」 声のトーンが一段階低く変わった。怪訝そうな顔つきになっていることが想像できた。 「突然で申し訳ありません。実は御手洗様がご存知の方にこのたびご縁談話がありまして、是非その方についてのコメントを少しいただければと」 「何ですって、縁談話?誰ですかな、その人は?」 「恐れ入ります。まことに勝手なお願いですが、お会いしてから申し上げたいのですが」 「縁談話がある当人が誰か分からんのに会えませんわ。あんたちょっといきなりで失礼とちゃいまっか?今忙しいので切らせてもらいますわ」 御手洗氏は電話を切った。アポイント一回目は失敗に終わった。そりゃそうだろう。僕が反対の立場でも同じアクションを起こすだろう。作戦不足だったと反省し落胆した。ベッドに仰向けになり、次の作戦を考えているうちに眠りにおちた。どれくらい眠ったのだろう。誰かが頬に冷たい手で触れていた。見上げると有希子が私をじっと見おろしてベッド脇に立っていた。 「久しぶりだな、有希子。でもどこから入ってきたんだ?」 だが有希子はベッド脇に立ったまま何も言わなかった。ほとんど無表情で、私の目をジッと見つめていた。 「有希子、体調はどうなんだ?しばらく生駒にも行けないから、心配していたところなんだ」 「光一、今度こそ私はもうあなたの手の届かないところへ行くわ。本当にサヨナラなの」 長い沈黙のあと、有希子は今にも泣き出しそうな表情で呟いた。 「なぜ?」 「光一、あなた本当にしっかりしないと、また同じように女の人を泣かせるわよ」 有希子は静かに囁くような声で言い、そのあと私の頬に涙の雫が数滴落ちた。 「サヨナラ、大好きな光一」 有希子はそう言って私の唇に濡れた冷たい唇を合わせ、唇を離したあともしばらく見おろしていたが、やがてゆっくりと背中を向けた。 「有希子、ちょっと待ってくれ」 手を伸ばそうとしたが、身体が一センチたりとも動かなかった。「どうして行ってしまうんだ、有希子!何でサヨナラなんだ!」と言おうとした。だが彼女は瞬時に消え、同時に私は激しい寂しさに襲われた。そのときベッド脇の電話が鳴った。 「お久しぶりです、関です」 電話は徳島の穴吹療育園の関さんからだった。彼女から電話をもらうのは今年の九月以来だった。九月の彼岸のあと、関さんから「沢井さんがお姉さんのお見舞いにいらっしゃったの」と電話があった。沢井圭一氏は長年身障者施設に入院している姉を、今年の秋の彼岸にようやく見舞に訪れた。それは真鈴のもとに帰ってきてから、同氏による家族復活の仕事が順調に進んでいることの裏付けだと思った。 「やあ関さん、元気ですか?」 「どうにかね」 彼女は静かな声で答えた。関さんとは七月に会って以来、ときどき電話で話をするだけだが、私はレッキとした彼女の彼氏なのだ。 「こちらにはなかなか来れないんですか?」と関さんに訊いた。 「そうね、もうあれから半年近くにもなるのね。月日の経つのは早いわ」 「西条の実家にはときどき帰っているの?」 「うん、九月のお彼岸のあと少しだけ帰省したのよ。岡田さんがときどき帰りなさいって言ってくれたから」 「それは良いことだね。帰省は疲れたこころのカンフル剤だから」 「フフフ」 ようやく関さんが電話口で笑った。 「それでね、私ももうすぐ二十八歳になるから、そろそろ考えないといけないと思って」 「考えるって、何を?」 「結婚」 「・・・・・それは、少しショックだな」 「でも相手がいないのよ。岡田さん、私の彼氏でしょ、ずっと待っていていいのね?」 「えっ?」 関さんが冗談で言っているのか、それとも本気なのか、電話でのやり取りでは分からなかった。私はしばらく黙ったまま考えた。 「岡田さんと京都で一晩過ごしたこと、ずっと忘れないの。そのあと西条の実家まで私を連れ戻してくれたこと、すごく感謝しているのよ。実家に九月に帰ったときも、そのあと電話で話すときも、両親が岡田さんは元気なのかって訊いてくるのよ」 「年が明ければ、時間を作ってそっちへ行くよ。年末までちょっとややこしい調査案件があるんだ。我慢してくれるかな」 「うん、もちろん大丈夫よ。会えるのを楽しみにしているわ。またときどき電話していいかしら」 「いつでも待っているよ」 「じゃあまた電話するね。私、これから当直なの」 そう言って関さんは電話を切った。徳島の山奥にある身障者施設で働き続けていることが、彼女の不安定な精神状態の一因には違いなかった。だからと言ってどういう風に環境を変化させればよいのか私には明確に分かっていなかった。今すぐにでも関さんのもとに車を飛ばして行きたい気持ちはあった。でもそういう行動に走ることが、彼女の将来に何か指針を与えることになるのかどうか、それを考えると躊躇するのだ。自分の気持ちに正直になることが、相手に対して誠実とは限らない。いや、誠実とは結びつかないのだ。オネスティはサッチャ、ロンリーワードなのだ。 時計を見ると、すでに午後五時前だった。いったい何時間寝ていたのだろう。窓の外が薄暗くなっていた。ふと私の顔が涙の糊で覆われていることに気づいた。だが、それが有希子の涙の糊なのか、それとも私のものなのかは分からなかった。 「そうだ、有希子に電話をしないといけない」 夢のことが気になって、慌てて生駒の彼女の実家に電話をかけた。 |
| 五十九 |
|---|
|
この世の中は男と女としか存在しないとはいっても、私の周りは男女の様々な問題が蠢いていた。それは私が調査業という職業に関わっているからかも知れないが、職業柄は別にしても、右を見ても左を見ても、ネットでもTVを観ても週刊誌を見てもスポーツ新聞の芸能欄を見ても、男女に関わる愛だの恋だの、結婚しただの破綻しただの、そういった話で溢れかえっていた。 もちろん私自身もなんだかおかしな具合になっていた。真鈴は先日久しぶりに会って以来、三日を置かずに電話をかけてきた。ときには日付が変わってから遅い時刻に寝入りばなを起こしてきた。朦朧として受話器をとると、「真鈴」と言ったきり彼女はしばらく黙っていることがあった。 「どうしたんだ、こんな時間に」と訊くと、彼女は先ず「フー」と必ず大きなため息をついた。おそらく両方の肩が五センチは上下しているはずだ。 「岡田さんはなぜ私を部屋に入れてくれないの?」 「なぜって、それは君を部屋に入れると、もう帰したくなくなるからだよ」 「じゃあ、帰さなくていいから部屋に入れて」 「だめだ」 「たまにはいいじゃない、私は子供じゃないんだからね。それにもう深い関係だよ」 「だめだと言ったらだめだ。環境が整っていない」 「馬鹿みたい。もういい!」 こんな調子だ。でもまた三日以内に電話をかけてくるのだ。もしも三日を過ぎても電話がなければ、気になってこちらからかけてしまう。すると「どうしたの、寂しいの?」と真鈴は必ず訊いてきた。 「うん、まあそれもあるけど、真鈴のことが心配だからな」 「光一」 「うん?」 「私のこと好き?」 「好きじゃなければ、こんなにたびたび電話しないだろ」 「じゃあ今度は部屋に入れてよね。何か作ってあげるから」 「いや、それはだめだ」 「何だよ、それ。せっかく手料理を食べさせてあげようと思っているのに」 「そんなことよりしっかり勉強しないと、K大学に受からないぞ」 「もういいよ、そんなことばっか。馬鹿!」 つまりいずれにしても馬鹿で電話が切れるのだ。難しい年代の女の子というよりも、彼女は短気すぎるのだ。でも私はいつも苦笑いをして、真鈴とのそういう関係を心地良く思っていた。 真鈴はすでに以前の不安定な状態から抜け出していた。父が戻ってきたことでこんなにもこころが落ち着くのだ。私はそれをずっと見ていて驚いた。最近の真鈴はずいぶんとおとなになり、考え方もしっかりとしてきた。もともと頭のよい器用な女の子なのだから、もう私などいなくとも大丈夫なのだ。 関さんも先日の電話のあと、たびたび電話があった。当直の夜か或いは自宅から夜遅くにかかってきた。囁くような声で「こんばんは〜」と言ったあと「お仕事、順調?」といつも彼女は訊いてきた。 年が明けて仕事が落ち着いたら穴吹へ行くと言った約束を信じていた。こころが脆弱な関さんだから、必ず約束を守ってやらないと彼女は混乱し、以前のように不安定な精神状態になってしまうだろう。私は少しばかりプレッシャーを感じていた。関さんとの約束は誠実に守らなければ彼女はまた逆戻りしてしまう。 いずれにしても私の数少ない人間関係に於いて、自分以外の人のことを考える時間の割合が、真鈴と関さんとで半分程度を占めていた。抗癌治療を続ける有希子の病状は一進一退の様子だった。ときどき覗く「安曇野」の女将さんはいつも明るく、常連客にこころの安らぎを与え続けていた。T社の部長は面倒な調査案件を何とか私にやらせようと常に目論んでいるようだった。でも今の案件が終了するまでは、他の仕事はやりたくなかった。 そのややこしい案件で私は悩んだ。平安商事の御手洗氏への襲撃の件だ。先日の電話をいわゆる「ガチャ切り」されていから、ずいぶんと日にちが経ってしまっていた。焦ってばかりいても仕方がないのでともかく電話をかけてみた。先日と同様に女性社員が応対に出た。丁寧にこちらの名前を伝えて、御手洗氏に取り次いでいただくよう依頼した。しかしいったん電話が保留になったあと「まだ出社しておりません」と答えるのだった。 一時間後、再びアポイントの電話をかけた。同じ女性が応対に出た。だが、「御手洗は取引先のもとに直行してそのまま帰る予定なので、本日は戻りません」との返答だった。今年もあと二週間を切ってしまった。ぐずぐずしているとクリスマスがやって来る。依頼人には年内に報告書を手渡したい。 翌日もさらに電話アポ、同様の女性、「御手洗は外出中、帰社時刻?不明です」、さらに次の日も「外出中、帰社時刻?不明」。女性の声もこころなしか冷たく感じてきた。 その間、T社の部長からたびたび電話がかかってきた。「急ぎの企業調査や結婚調査が入っとるんや。二件ほど持ってくれへんかな」と、彼はこの案件に苦しんでいる私への気遣いもなくシレッと言うのだった。 「いえ、この案件に目処が立たないと無理ですよ。他の案件を持ちたいのはヤマヤマですけど、これを何とかしないと気持ちの上で難しいんです」 「そうか、仕方がないな。まあ頼むわ」 部長は落胆した声で電話を切った。繁忙期には五件や六件の調査を平行して持つことは普通なのだが、今は情けないことにこころの余裕がなかった。それほどこの「御手洗案件」はイレギュラーなのだ。 夕方早い時刻に「安曇野」を覗いた。客はまだひとりもいなかった。女将さんが煮物料理を仕込んでいた。懐かしい母の料理の匂いが店内に漂っていた。 「あら岡田さん、今日はめずらしくお早いのね」 女将さんが片手に菜箸を持ちながら微笑んだ。和服に白い割烹着がとても似合っていた。 「不動産屋のオヤジに面会を拒否され続けて困っているんです」 「あら、どこかに引っ越されるの?」 「いえ、そのオヤジと新地のマダムの愛人関係が切れたかどうか、それが問題なだけなんです」 「えっ?」 「世の中にはおかしな男女が蠢いています」 「アハハハ、可笑しいわね。でも岡田さんも真面目な顔でそんな冗談を言うから、もっと可笑しいわ」 女将さんは大きな口を開けて笑った。「冗談ではないんです」と言おうとしたが、女将さんの目尻から笑い涙が出ていたので言うのをやめた。カウンターに頬杖をついてビールを飲んでいたらスマホがけたたましく鳴った。真鈴からだった。 「どこにいるの?」 いきなり訊いてきた。遠慮のない奴だ。 「綺麗な女将さんがいるいつもの店だよ」 「フーン、そうなんだ。私より綺麗な人?」 「そりゃそうだよ。年季が違う」 しまったかなと思った瞬間、「馬鹿!」と言って真鈴は電話を切った。全く私はどうかしていた。でも真鈴も冗談を分からない女の子だ。 「どうされたの?」と女将さんがご機嫌顔で訊いてきた。 「女の子を怒らせてしまいました。僕はだめな男です」 「あらあら」と女将さんが笑った。本当にあらあらだと思った。そのとき常連客二人が入ってきた。私はホッとしてビールを飲みながら作戦を考え続けた。 御手洗氏の会社の従業員の誰かにアポイントを取って、いくらかの謝礼を手渡して同氏の現在の女性関係を訊いてみようかとも思ったが、「馬鹿げている」とすぐにその考えを打ち消した。ビールのお代わりをしてからも沈思黙考したが、どうにも名案は浮かばなかった。午後七時半を過ぎたので早めに店を出た。肌が痛くなるような寒い夜だった。マンションのエレベータを降りて五階のフロアに着くと、部屋の前に見覚えのある女性が体育座りをして壁にもたれていた。真鈴だった。 「どうしたんだ?」 真鈴は太ももの間に挟んでいた顔を上げた。 「予備校が終わったから電話してみたら、あんなこと言うから腹が立って待ち伏せしたんだよ。私と年季が違うって、それってどういうことなのよ、光一」 真鈴はかなり怒った顔だった。 「悪かったかなと思ってすぐに謝ろうとしたら、君が馬鹿って言って電話を切ったんだ。本当だよ。でもともかく悪かった、ごめん、謝る。今ちょっと難しい案件を抱えていて、僕はおかしいんだ。許してくれよな」 真鈴は立ち上がって私の目をジッと見た。目に涙が溜まっていた。 「寒いだろ、部屋に入るか?」 彼女は頷いた。 「晩御飯食べてないんだろ?何か作ってやろうか、インスタントしかないけど」 真鈴は椅子に座って、膝に両手を揃えた格好で首を左右に何度か振った。 「お父さんが心配するから帰る。でも光一、もう一度訊くよ。その飲み屋さんの女将さんと私と、本当はどっちが綺麗?」 「そんなの真鈴に決まってるだろ。当たり前だ」 「それなら許す」 彼女は立ち上がり、私たちは抱き合って唇を合わせた。 「コーヒーくらい飲んでいかないのか?」 「ううん、今度ゆっくり来るから。だから部屋に入れてね」 真鈴は訴えるような目で言った。「問題ない」と私は答えた。近くの駅まで送ろうとしたが「ここでいいから」と玄関で彼女は頑なに断った。こういうときはあまり無理しないほうが良いのだ。難しい年頃の女の子なのだ。 「じゃあ気をつけて帰るんだぞ」 「大丈夫よ。それから光一、難しい案件って、前に言っていた不動産屋さんの話?」 「うん」 「そんなの、アポイントなんか取らずにいきなり行けばいいじゃない。光一らしくないよ。私のお父さんを捜してくれたとき、あちこちへいきなり行っていたじゃない。光一なら大丈夫だよ。私はそう思う」 それから真鈴は「バイバイ」と言って、うしろも振り向かず右手をヒラヒラと振って行ってしまった。 明日、真鈴が言うようにアポイントなど取らず、いきなり御手洗氏を訪ねようと決めた。新御堂筋の高架の向こうの高層マンションのうしろに真っ白なマシュマロマンが今夜も立っていた。 「いきなり行ってみるよ」と私はマシュマロマンに向かって呟いた。 「それがいいさ」と彼はいつものように口の片方を上げてニヤリと笑った。 |
| 六十 |
|---|
|
翌日、私は午後三時を過ぎて部屋を出た。阪神梅田駅から特急電車に乗り、西宮駅で各駅停車に乗り換えた。御手洗氏が経営する平安商事はここから三つ目の打出駅近くにある。一日の仕事の終わりが近づく夕方の訪問のほうが、御手洗氏も気分がリラックスしているだろうと考えた。 午後四時過ぎに打出駅に着いた。下車して浜側へ少し歩いたところに平安商事はすぐ見つかった。入り口横のガラス張りのスペースには、賃貸物件や分譲物件の資料がたくさん貼られていた。私は躊躇なく勢いをつけてドアを開けた。店舗事務所はそんなに広くなく、入ったところに低い受付カウンターがあり、その向こうに女性のスタッフがふたりと若い男性がひとりいた。奥は衝立で仕切られていた。 「御手洗社長にお目にかかりたいのですが・・・」 立ち上がった女性スタッフの「いらっしゃいませ」の声が終わらないうちに私は言った。 「何でっか?」 依頼人からは四十八歳と聞いていたが、衝立の奥から現れた御手洗氏はもう少し老けて見えた。髪はフサフサだが白髪が多く、浅黒い顔は艶があまりなく、疲れた中年男という印象だった。彼は突然の訪問者に明らかに不機嫌そうな顔付きだった。 「お忙しいところお伺いして申し訳ありません。何度か電話でお願いしたのですが、ご了解をいただけなかったものですから、いきなり来てしまいました。すみません」 「あんたでっか、何度も失礼な電話かけてきやはったのは。それに今度はいきなりでっか?ちょっと失礼でっしゃろ」 彼は正面を向いて厳しい表情で言った。三人の従業員も仕事の手を止めて、私と御手洗氏のやりとりを見守っていた。 「お怒りはごもっともですが、少しお時間を頂戴できませんでしょうか?」 「忙しいから今日はあきまへん。訊きたいことがあるなら、あらためて電話してくれまっか。どうぞお引取り願いますかな」 相手の立場になってみれば無理もないことだった。でもここで引き下がってしまったらお終いだ。結果を出さないとゼロと一緒だ。様々なことをハイスピードで考えた。 「御手洗さん、実は泉井麻由美さんのことでお聞きしたいことがあるんです。ほんの少しだけでもお時間をいただけないでしょうか?」 私の言葉に御手洗氏は数秒間動きが止まった。従業員たちはずっと見守ったままだ。 「ちょっと外で待っといてくれまっか。すぐ出まっさかいに」 私は店舗の外に出て待った。数分後、御手洗氏がブランド物のセカンドバックを小脇に抱えて出てきた。不動産屋まるだしの風貌だった。 「その先にあるレストランへ行きまひょか」 阪神高速道路神戸線の高架手前の道路沿いにファミリーレストランがあった。この時間帯、店内に客の姿はまばらだった。御手洗氏は「喫煙席でもよろしおまっか?」と訊いてきた。私は非喫煙者なのだが「それは困ります」とも言えず、「かまいませんよ」と同意した。店員はわれわれを最も奥の席へ案内した。二人ともホットコーヒーを注文した。 「それでいったい麻由美のどんなことを訊きたいのですかな?」 しばらくの沈黙のあと御手洗氏は切り出した。鋭く相手を射すくめるような目だった。バブル景気の崩落をも乗り越えて、小さいながらも不動産業を維持している男の目だった。だがこっちだってバブル景気のころは「泣く子も黙る金融業」に関わってきたのだ。 「あまり時間がおまへんねん。しかもいきなりで、はっきり言うてあまり気持ちのいいもんではありまへんな」 御手洗氏はタバコにブランドのライターで火をつけて大きく吸い込み、ため息とともに煙を吐き出しながら、言葉も吐き捨てるように言った。大量の煙が、彼の人格とともに換気扇方向へ飛んで行った。 「大変申し訳ないと思っています。実は泉井様のお相手が、御手洗様と泉井様がすでに無関係であることを証明して欲しいと仰られているようなのです。実際問題として無関係を証明するなどということは難しく、直接お会いして御手洗様の口からお訊きする以外に方法がなかったのです。どうかお許しください」 「何でんねん、そんなことでっか?そういえば電話で縁談がどうのこうのとか言うてはりましたな。私はまた、慰謝料の追加を麻由美があんたに頼んだものと勘違いしてましたわ。そうでっか、麻由美がねえ、結婚でっか」 御手洗氏は首を縦に何度も振りながら、まるで自分に言い聞かせるように頷き、「それはめでたい話でんなあ」と表情が崩れた。 「彼女が結婚を考えている男性は存じ上げませんが、相当のヤキモチ妬きだそうです」 「岡田さん、あいつに言うといておくんなはれ。一切無関係やでと。そして、昔の関係は今となっては貴重な人生の思い出としてずっと持ち続けると。そういうふうに御手洗が言うてたと伝えてくれまっか。気の強いわがままな女ですけど料理も上手だったし、気持ちの優しいところもあるんですわ。きっと結婚したら家庭的な奥さんになるのとちゃいまっか。こころから幸せになって欲しいと思いますな」 彼が語っていることはすべて、私のスーツの内ポケットにあるマイクロカセットテープに録音されている。これを依頼人に聞かせれば、調査報告としては完璧である。最初の険悪なやり取りから録音されているので、わざと御手洗氏に言わせた訳ではないことも証明される。このあと少し世間話などを交わし、御手洗氏に礼を言って別れた。 「岡田さんらの仕事も大変でんな。わしらの業界も不景気続きですけど、どうか頑張っておくんなはれな」 御手洗氏は別れ際にこう言って事務所に入った。 バブル景気で大もうけした不動産業者をはじめ、土建業者や町の小さな鉄工所の大将まで、当時は儲けた金を何か名目を作って愛人を囲った人も多かった。当時私は金融会社に身を置いていたが、周りでそういう人々を数え切れないくらい見てきた。だが、そういう関係はいつまでも続かない。自分の気持ちに従えば、愛人や妻への誠実さは失われる。両方に誠実を保つなんてことは不可能なのだ。男性側の立場で述べているが女性とて同様だ。誠実を保とうと思えば決して自分に正直にはなれない。オネスティはサッチャ、ロンリーワードだ。自分の気持ちに正直になればなるほど、相手を傷つけ誠実さを保てなくなるのが現実なのだ。それは男女関係だけではなく、商取引、果ては社会自体がそういう仕組みになっている。御手洗氏は妻子への誠実さを保ったから依頼人と別れた。そういう意味では彼は自分の気持ちに正直ではなかった。でもそれでよかったのだろう。 数日後、T社の応接室で報告書と録音テープを依頼人の前に出した。依頼人は再生された元愛人の言葉を聞いてホッとした表情になったが、その中に少し悲しげな曇った部分があるのを私は見つけた。少し前に阪急梅田駅で香織が別れ際に見せた表情と同じ種類のものだった。過去に愛した人のことは、糸を切るようには簡単には忘れられないものなのだ。 クリスマスイブの前日の夜、真鈴から電話があった。 「明日のお昼過ぎに行くよ。だめって絶対に言わないでね」 やや強い口調で彼女は言った。 「部屋で待っているよ。クリスマスケーキとシャンパンを用意しておくから」 「オッケー、じゃあ私はケンタのチキンを買って行く」 相変わらず彼女は店の名前を縮めて、しかしずいぶんと弾んだ声で言った。 「真鈴」 「うん?」 「ちょっと変なことを訊くけど、君にとって、僕はどういう存在なんだ?」 「何よ、いきなり。本当に変な質問だよ。でも、光一は私にとってはヒーローだよ。そう、間違いなくヒーロー。じゃあね」 電話が切れた。私と真鈴はどうなっていくのだろう。それに関さんや香織は、この先こころの平安を保って生きていけるのだろうかと心配になった。でも私がどう関与すればよいのか、明確には分からなかった。 窓の外では濃紺の冬空がひたすらに人々を守っていた。新御堂筋の高架の向こうにはビル群と高層マンションがそびえ立っていた。多くの人々がそれらの中で様々な人生を送っている。自分に正直に生きようとしている人や、相手に誠実さをもって付き合っていこうと思っている人、人は対人関係や恋愛関係、さらに夫婦関係親子関係、様々な人間関係で苦悩し、それでも精一杯生きていこうとしているのだろう。 今回の難解な案件のヒントは、意外にも真鈴からもらった。 「そんなの、アポイントなんか取らずにいきなり行けばいいじゃない。光一らしくないよ。私のお父さんを捜してくれたとき、あちこちへいきなり行っていたじゃない。光一なら大丈夫だよ。私はそう思う」なんて、生意気言いやがって、でも本当に君の言うとおりだったよ。 私は冬空に向かって「真鈴、ありがとう」と小さく声に出して呟いた。 - 了 - ※ 穴吹町は2005年3月に美馬町、脇町、木屋平村が合併して美馬市となっている。 |