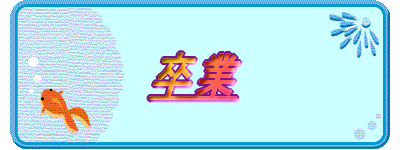
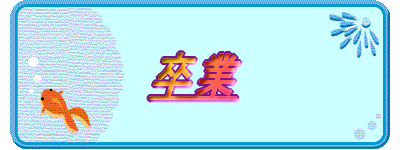
| 十三 |
|---|
|
沢井真鈴は両手で顔を覆い、指の間から嗚咽が漏れるほど激しく泣いた。近くの客や店の人が驚いた顔で私たちのほうを見ていた。でも、そんな視線よりも目の前の彼女のことが心配になった。 「もしよければ話してくれないかな。何か事情があるようだから」 真鈴は布製のペチャンコのバッグからハンカチと手鏡を取り出し、目尻を拭った。 「ここじゃ話し辛いだろうから、もう一度扇町公園にでも行こうか?」 真鈴は素直に頷いた。アイスカフェオレをほんの少しだけ飲んで、私たちは店を出た。 扇町公園のキッズパーク側から入ると、たくさんの人たちがスマホを持って佇んでいた。相変わらず人気のポケモンに、みんなこころの大部分を奪われている。その人たちの横を通りすぎる私と真鈴は、第三者から見ると兄妹と思うだろうか?深刻そうな顔つきの兄と妹、或いは親子だと思うかも知れない。若い父親と高校生の娘・・・。 扇町公園の北側の方には緑あふれた静かなスペースがある。その片隅に、中層の団地が周辺と不釣り合いな感じで建っている。昔は平屋建ての市営住宅が立ち並んでいたところだが、建て替えられて、住民はそっちへ優先的に入居している。 公園内には二組の若者のバンドが、青空に轟き渡るほどの音響で激しいリズムの音楽を演奏していた。若者グループがバンドの前に陣取って、リズムに合わせて身体を揺すっていた。公園には季節の花が咲きほこり、まるでこの世に不幸など存在しないかのような堂々たる陽気と幸せな光景だった。 「さっきは何であんなに泣いたの?」 私と真鈴は芝生の上に腰をおろした。周りではバドミントンをするグループや三脚を立てて本格的に公園の風景を撮影している人々などがいた。「平和」という二文字が頭に自然と浮かんだ。 「差し支えなければ話せばいいよ。女子高生に目の前であんなに泣かれてしまうと、男として黙っているわけにはいかない」 しばらく沈黙の時間が流れた。バンドが演奏する賑やかな音楽が離れたところで聴こえ、意外に心地良く感じられた。 「父は私が小学校六年生のときに急にいなくなってしまったんです。経営していた会社がうまくいかなかったみたいで、突然どこかに消えてしまったの。両親と三人で平凡にに暮らしていたのに、何も言わずに急にいなくなって、そのあとはもう滅茶苦茶」 「お父さんは今も戻って来ないの?」 「もう六年以上」 「お母さん、大変だね」 「母は精神的におかしくなってしまって、入院しています」 私は言葉が見つからず、困った。父が失踪し母は入院中、つまり真鈴は今ひとりで暮らしているということになる。 「じゃ、君はひとりであの部屋に?」 「父の会社の人たちや取引先の方たちが次々に家に来ました。母は突然の出来事が理解できなくてうろたえて、父が失踪してしまったと分かるとショックで倒れてしまうし、会社の整理で家は売り払って出ていかなくちゃいけなくなって、二ヶ月間ほどは安心して眠れなかったんです。ひとりの男の社員の方が心配してくれて、その人の口添えで今のマンションに引っ越してきたんです。でも、こんな話、岡田さんには興味ないことですよね」 真鈴はそう言って、遠くの方を眺めた。彼女の視線の先には、小さな子供の親子連れが芝生に寝転んで、初夏の日差しを浴びていた。 「そんなことはないよ。調査の仕事って信じられないような依頼があるからね」 「探偵さんって、尾行以外にどんな調査があるんですか?」 「それはいろいろだな。所在や家出人調査っていうのがあって、つまり何かの事情で連絡が取れない人や突然失踪した人を捜す仕事なんだけど、ほんの少しの手がかりを頼りに捜すんだ」 「見つかるんですか?」 真鈴は興味深そうな表情で僕を見た。 「もちろん見つけ出せないこともあるよ。でも諦めないで粘り強く追っていると大抵は捜し出せる。人って多くの悩みを抱えていて、こんな些細なことで姿を隠すんだなって驚くこともあるよ。ともかく君と知り合ったのも何かの縁だし、力になれるかも知れないな」 真鈴は難しそうな顔をして、しばらく私の言ったことを考えているふうだった。 「父の会社は社員が十人ほどだったみたい。小さな会社だったけど、母の話だと製品の開発をしていたらしいの。特許とか何かが絡んでなかなか先に進まなくて、先に資金がどんどん要るから、自宅を担保にかなりのお金を銀行から借りていたらしいんです」 「資金繰りが大変だったんだね」 「うん、そうみたい。でも父は私たちには何も言わなかったの」 「心配かけたくなかったんだよ、男だから」 真鈴は「男だから」という言葉を聞くと、不思議そうな目で私を見た。 「警察は動いてくれたのかな?」 「母が捜索願いを出したけど、事件性がないって判断されたようで、失踪届けを受け取ってくれただけでした」 「そうだろうなぁ、警察はね」 警察は失踪者をいちいち追っている余裕はない。身元不明の人物が出た時に照会をかけるだけだ。でも、そういう実情を彼女には言わないでおこうと思った。 「私、父がきっとどこかで生きていて、必ず帰って来てくれるって信じているんです。でも母がずっと精神的に不安定な状態で、半年ほど前から入院しています」 真鈴は目を細めてキッズパークの方向を眺めながら言った。そのとき私のスマホがブブーと震えた。妻の有希子からだった。 「今、大丈夫?」 「かまわないよ」 「実はこの前からの話だけど、両親が今度の日曜日あたりに来れないかって言うのよ」 「何だか急いでいるんだな、君のご両親は」 「ごめんね、私は今のままでもしばらくは構わないのよ、でもふたりがうるさいのよ」 「分かった。今度の日曜日、君の家に行くよ」 有希子はありがとうと言って電話を切った。 「彼女さんですか?」 「いや、別居中の嫁さんからなんだ」 「ふ〜ん、岡田さんも大変そう」 真鈴は少し微笑んで言った。 「いろいろと大変だな、お互い。まあ、仲良くやろうよ」 私が言うと、真鈴は「そうね」と言って立ち上がった。私たちは並んで扇町公園を出て、同じマンションへ向かってゆっくりと歩いた。 |
| 十四 |
|---|
|
扇町公園を出て、マンションへ真鈴と肩を並べて歩いた。途中、彼女は遠慮がちにいろいろと質問をしてきた。 「なぜ、奥さんと一緒に暮らさないんですか?」 「なぜって、その・・・奥さんのお父さんやお母さんがね、もう帰って来なさいって言ったからね、仕方がないんだ」 「なぜ帰って来なさいって言ったのかしら?」 「そりゃあ、僕がヘマをしたからね」 真鈴は「ふ〜ん、そうなんですね」と言ったが、それ以上は訊いてこなかった。 「それより、君の話をもっと訊きたいな」 「私の恥ずかしい話を?」 「恥ずかしいことなんかないだろ、ひとりで頑張ってるんだから」 「そうね」 真鈴は私の顔を見て微笑んだ。ようやく彼女が少しだけ白い歯を見せて笑った。 「岡田さんっておかしな人ですね。何か話し方がフワフワしていて。でもどうしてひとりで探偵なんかやっているんですか?」 「さあ?何でだろう、自分でもよく分からないんだ」 「私、これからも岡田さんにたびたびLineするかも知れません。かまいませんか?」 「いいよ、いつでも」 「いきなり電話するかも」 「大丈夫。でもすぐ前の部屋なんだから、いつでも来ればいいよ」 「だから、女の子をそんなに簡単に部屋に呼ばないでくださいって、この前も言いましたよ」 「ごめん、でも近くだし」 真鈴は公園での話以上には積極的に言いたがらず、私も無理には訊かなかった。彼女は家に帰っても父も母もいない。生活費や学費などはどうしているのだろう。訊きたいことがたくさんあったが、あまり言葉を交わさないままマンションが近づいてきた。 「ともかく、何か相談に乗れることがあるかも知れないからね。だから、もうおかしなことはやめなさい」 「えっ?はい・・・分かりました」 言葉の意味が分かったのか、生返事なのか、真鈴の横顔を見てみたが、動揺した感じはなかった。エレベータで五階に上がり、別れ際に「もし何か手がかりがあれば、お父さんが今どこにいるのか調べることもできるよ」と付け加えた。真鈴は「ありがと」とポツンと言っただけで部屋に消えた。 翌週、月曜日に岐阜県各務原市の所在調査に向かった。事前に調べていたこともあって、依頼人が連絡をとれなくなった人物の所在はすぐに判明し、現在の生活状況などを聞き込みして調査は一日で終了、翌日報告書を作成し、A社にファックスを送った。翌日にはこの前の長い尾行調査の報酬と含めて、かなりの金額が口座に振り込まれていた。 怠惰な日常を復活した。目覚めた時刻にはとっくに世の中は一日の動きを開始していて、社会の歯車が円滑に回転していた。雲ひとつないバカ陽気が、当分部屋から一歩も出ないと固く決意していた気持ちを焦らせた。午前十一時を過ぎて、ようやくベッドから出た。定期的にこのように怠惰な日常になってしまうことを、有希子が嫌っていたのは分かっていたが、性分だから仕方がない。 A社からの電話がスマホを震わせ、社長からのメールやLineも何度か届いていたが、緊急案件ではないようなのですべて無視していた。だが、今朝のメールには「緊急!」と書かれていた。 「緊急!明日から開始して欲しい尾行案件が入ってきました。何とか連絡頼みます」 でも、尾行は当分やりたくない。私はそのメッセージを睨みつけながら憂鬱な気分になった。そのときスマホがブブーと震えた。着信は真鈴からのものだった。 「は〜い、岡田」 寝起きだったので、不注意にも欠伸をしながら電話に出てしまった。 「真鈴です。欠伸しながらって、失礼じゃないですか?」 「ご、ごめん、ミステイク」 「今何してるんですか、いったい?」 真鈴は怪訝そうな声で私の現在の状況を訊いた。 「今はその、起きたところだよ」 「こんな時間まで寝てたんですか?」 「ああ、ちょっとね、昨日の夜が遅かったものだから。ところでどうしたのかな?」 「どうしたのかなって、いつでも連絡してかまわないって言ってくれたからかけたんですけど、ご迷惑ですか?」 「ああ、そうだったね、ごめん。ちっとも迷惑なんかじゃないよ」 「岡田さん、もしかして彼女さんがそばにいらっしゃるの?」 「いや、彼女なんていないよ。奥さんは実家だし」 電話の向こうで真鈴は十秒ほど考えているようだった。そして「今日、少しだけ会いたいんです」と言った。 「学校はどうしたの?」 「体調がよくなくて、今日は休みました。でもたいしたことないの。もう元気」 「今日は一日何も予定がないから大丈夫だよ。こっちに来る?」 「だからぁ、簡単に部屋に呼ばないでって」 「あっ、そうだった、ごめん。じゃあ、三十分後にこの前の扇町公園の入り口にするかな?」 真鈴は「それでいいです」と言って、スマホを切った。 |
| 十五 |
|---|
|
スマホを切ったあと、すぐにシャワーを浴びた。数日間の怠惰な暮らしで、おそらく身体にこびりついているであろう臭いを、丁寧にボディソープで消し落とした。三十分後の約束をしたが、髭を剃ったりしているうちに時間が経ってしまい、扇町公園の南西側入り口に約束より十分近く遅れて着いた。真鈴は入ってすぐのところの花壇の前で待っていた。 「やあ、ごめん、ちょっとシャワーに時間がかかったんだ」 真鈴はこの日、ジーンズに淡いピンクのTシャツ姿だった。いつものように短めの髪を書道で使う太い筆のようにうしろで束ねていた。 「昼ごはんは食べたの?」と私は訊いた。会ってすぐの言葉としては不適切だったかもしれないが、他に言葉が思い浮かばなかった。 「まだです」 「マックでも入る?それとも他にリクエストがあるかな。お腹が空き過ぎて死にそうだ」 「岡田さんって、私がいつもお腹を空かしているって思ってるんですか?」 「えっ?」 「この前だって、会ってすぐに何か食べようって言ったでしょ」 真鈴は不服そうに意見した。 「そうだった?レディに対して失礼だな、ごめん。でもまあ何か食べようよ。美味い物を食べているときって幸せな気分になれるじゃないか」 真鈴は私の言葉に何も答えずに歩き出した。私は彼女を天神橋筋商店街の中にある喫茶・グリル「プランタン」へ連れていった。この店のオーナーの伊藤氏は、あの兎我野町の行きつけの小料理屋「安曇野」に、自分の店が一息ついたころにときどき現れるので、以前からそこそこ懇意にしているのだ。 「これはどうも岡田さんやおまへんか。珍しいでんな。おっ、別嬪さんのお嬢さんですな。岡田さんとは似ても似つきまへんがな」 伊藤氏が私のうしろに立っていた真鈴を見て余計なことを言った。 「伊藤さん、僕の娘じゃありませんよ。僕には子供はいませんからね」 「あっ、そうどしたな。こりゃ失礼」 私は真鈴を席に座らせた。彼女はなんとも表現するに難しい顔をしていた。 「ごめん、悪い人じゃないんだけど」 「別にいいですよ。私、気にしてません」 メニューを見ている真鈴に、私はエビフライ定食を勧めた。 「岡田さんが勧めるならそれでいいです」と彼女は言った。ウエイトレスにエビフライ定食をふたつと食後の飲み物はホットコーヒーを注文した。 「飲み物はジュースがよかったかな?何でもいいんだよ、遠慮なく言ってくれれば」 「コーヒーでいいです。私、もうおとなですよ、コーヒーくらい飲めます」 真鈴は少し不満そうに言った。私は彼女の気に入らないことばかり言っているような気がした。私と真鈴はほとんど黙ったまま食事をして、食後に運ばれてきた熱いコーヒーを飲んだ。この間の会話は、今日の陽気のことと彼女の学校のことだけだった。 「母がいなくなってから学校をよく休むようになってしまったの。親しい友達もいないし、学校はあまり好きじゃないです」 特に表情を変えずにポツリポツリと話をしながら、真鈴はエビフライ定食を付け添えのサラダの一切れまで平らげ、コーヒーを飲み干した。几帳面な子なのだと私は感心した。 「それで今日はどうしたの?」 「どうもしないの。ちょっと家にいると気持が塞ぎこんでしまって・・・。でも岡田さんと会えて元気が出そう」 「お腹も満足したし、ともかくここを出ようか」 「塚本さん、あきまへんで。捕まっても知りまへんで」 店を出るときに伊藤氏が耳元で囁くように言った。私は呆れて言葉も出なかった。 私たちは天神橋筋商店街を抜けて再び扇町公園に入り、中央の広場を横切って花壇の近くの陽のあたるベンチを選んで座った。平日の午後、暖かい太陽の下では営業を一息ついたサラリーマンや近くの中学校や商業高校の生徒たちが思い思いにくつろいでいた。 「気持ちがふさぎ込んでいるときはいつでもおいでよ。事務所にはソファーがあるから、自由にしていけばいい。女の子を簡単に呼ばないでって君は言うけど、僕は安全パイだよ、分かるだろ?」 「どなたか事務員さんを雇わないんですか?」 「まだ始めたばかりだから、もう少し忙しくなったら電話番や事務をしてくれる人を探そうと思ってるんだ」 仕事は大手の調査社に営業をかければ常に入ってくるだろうし、有希子の両親の信用を得るためには、この仕事を軌道に乗せないといけないのだが、元来の怠け癖がときどき顔を出してくるのだ。 「沢井さんは高三だろ、来年大学受験だね。そろそろ受験勉強を・・・」 「私、大学なんかいきません。高校を出たら働くの」 真鈴は私の言葉を遮るように言った。 「両親がこんな状態だし、お金がないから無理。卒業したら働くの。今日はありがとうございました。少し元気が出ました」 真鈴はそう言ってベンチから立ち上がった。彼女と肩を並べて歩きながら、私ができることを考えているうちにマンションに着いてしまった。エレベータが上昇している間も彼女の父を捜す手がかりを訊きたいと思っていたが、結局この日はそのチャンスがなかった。 「今日はありがと。また連絡してもかまいませんか?」 「いつでも待っているから、本当に一度事務所においでよ。遠慮は要らないからね。近所のよしみだし」 真鈴は小さく頷いてからクルリと背を向け、自分の部屋に消えてしまった。こころの中に消化されていない気持ちが明らかに残ったままだった。 |
| 十六 |
|---|
|
七月に月が替わってから少しずつ仕事を請けた。結婚調査が一件と所在調査が一件。結婚調査は父方実家と母方実家の現場を踏んで、それぞれの菩提寺まで知りたいという依頼内容だった。 父方は和歌山県の田辺市というところにあり、母方は富山県の氷見市だった。この二十年ほどで、IT革命やグローバル化などであらゆる物事が多様化し、核家族化した現代社会において、なぜそこまで調べないと結婚を許さない親がいるのかが、私には全く理解できなかった。でも仕事なので仕方なく現場を踏み、聞き込みを実施し、詳細な報告書を作り上げ、依頼内容を簡単にこなした。 梅雨入り宣言がとっくに出されて鬱陶しい天候が続いていた六月下旬の日曜日、私は遅めの朝食のあと交通機関を利用して奈良県の生駒市へ向かった。JR天満駅までブラブラと歩き、鶴橋駅で近鉄奈良線に乗り換え、東生駒駅で下車、妻・有希子の実家は駅から十五分ほど歩いた丘の中腹の住宅街にある。 「両親が一度こちらに来て欲しいって言うのよ。この関係をずっと続けるのもどうかって、あなたと話し合いたいらしいの」 有希子は実家に帰ってから、たびたび困ったような声でそう言った。「できるだけ早い時期に来て欲しい」と、先週電話がかかってきたとき、「君も板挟みで辛いよね。今度の日曜日に必ず行くよ」と返事してしまったのだ。だが、向かう電車の中ではずっと憂鬱な気分だった。 私は大学を二年遅れで卒業して、同じ大学の一年後輩の有希子と結婚した。子供には恵まれなかったが、有希子との関係は穏やかだったし、私は彼女の欲のない人間性が好きだった。お金や物には興味がなく、ただ何もない日常を愛しているような女性で、一緒にいるとこころが落ち着き、幸せな気持ちになるのだった。 だが私は男だ、独立欲は生来のものだと今になって思うのだが、人間欲が出るとダメだ、金融会社に新卒入社し、そこそこ仕事に自信がついたころに退職して、それから私の人生はおかしな方向へ向かってしまった。 スポンサーに恵まれて、周りの客からも勧められたりもして、中小企業への融資を業とする事務所を出した。今からちょうど十年ほど前のことだ、しかも事務所は今回引っ越してきた兎我野町界隈である。違うのは、前回はかなり見栄えの良い高層マンションの一室で起業を行ったことだ。そして今回はこの老朽化著しい五階建てマンションの一室、再起する場所としては問題ない。 妻は「生真面目」と「純粋」という文字を、大きな画用紙に太いマジックペンで力強く書いて、それを大きな額に入れて部屋の壁にドーンと飾ったような女性である。金融業として独立する際に激しい反対はあったが、私はそれを無視してオープンし、「あなたは絶対に失敗するわ、人が良すぎるから」と言った妻の予測通り四年で破たん、反省をして探偵調査会社のサラリーマンとなったわけで、凝りもせず再び独立、妻も義父母もあきれ果てるのは当然のことである。 「絶対に離婚しないって言ってくれてもいいのよ。私、あなたと別れたくはないし、両親がいつまでも反対するなら、そのうち黙って家を出るから」 今も同じ気持ちかどうかは分からないが、有希子は前にそんなふうに言ったことがある。ただ、家に呼びつけるということは、彼女の両親はまだ私を完全には排除してはいないのだろうと考えていた。 有希子の両親を安心させる言葉を探しながら、そしてそれが見つからないまま、彼女の実家に着いてしまった。元奈良県警の要職に就いていた義父の家は、このあたりでは最も広い敷地と立派な建物に思えた。 「岡田さん、何度もしつこく呼びだてしてすんまへんなあ。私も家内も有希子のことでいろいろと心配してましてな。それで久しぶりにお顔を見ながら話がしとうおましてな」 出されたコーヒーにミルクを入れて、カチャカチャと音を立てていた手を休めて、有希子のほうを見ると、彼女は手を膝の上に置いて下を向いたままだった。きっと彼女なりに辛いのだろう。 「私は今年の秋に四十歳になります。一度は金融業で失敗しましたが、今度は四年ほど勤めた調査会社での経験を生かして、興信所をはじめました。今は探偵調査業と呼ぶことが多いです。お父さんもお母さんもご心配とは思いますが、しばらく様子を見ていただけませんか」 「前の商売の借金はどうなりましたんや?」 「それは全部法的整理をして、今は無借金です」 「まあ、ワシらは有希子の気持ちが第一やと思うとりますから、無理に離婚せえとは言いまへんけどな、子供もないんやから、お互い別々になって一からやるのもどうかと思いましたや」 有希子は私と義父母とのやりとりを、首を少しだけ上げて不安そうに見守っていた。 「四十にもなろうかという男がいつまでも不安定では困りますわな。失礼なことを言うてるのはよう分かってますけど、こういう大事なことはキチンと言わしてもらわなあきませんからね」 確かに義父は遠慮なく物を言ってきた。仕方のないことだ。 「商売と言っても一人でやっている零細なものですが、前の金融業や物販とは違ってリスクはありません。有希子さんを幸せにする術ですが、それは商売が軌道に乗ればできると考えています」 少し苛立っているのが自分でも分かった。私のような男を好きになってくれた有希子を大切にしなければいけないことはよく分かっていたが、具体的な術を述べることはできなかった。 一時間余りの顔見世は終わった。離婚はしないが、いつまでも今の状態と続けるわけにはいかないという結論となった。義父母は久しぶりに私の顔を見て、少しはホッとしたようにも思えた。有希子は駅まで見送ってくれ、別れ際に「あなたとは別れたくはないのよ。でも私も板挟みで辛いの、それだけは分かってね」と言い、手を振って私たちは別れた。 帰りの電車に乗っているときに真鈴からLINEが飛んできた。「学校が退屈!」「最近夜眠れないの!」などの短いメッセージが、困った表情のクマやウサギのスタンプとともに飛んできた。彼女も有希子に負けず劣らず、いやもっともっと苦悩しているに違いなかった。 |
| 十七 |
|---|
|
妻の有希子は、私が生駒の実家を訪れたあとたびたび連絡をしてきた。義父の「四十にもなろうかという男がいつまでも不安定では困りますわな」といった言葉を、彼女は意外にも気にしていた。 「あなたに頑張ってもらいたいがための言葉だったと思うけど、ちょっと失礼だった気がするの。ごめんなさい」 彼女は気遣ったが、私が不甲斐ないのは事実だし、「気にしなくていいよ」と返事した。結婚して十五年近くになるのに、ふたりの間に子供ができなかったことについても義父は少し触れたが、この問題は私も原因が分からない。有希子もここ数年は諦めているフシが窺えた。 真鈴はときどき昼間や夜に「学校が面白くない!」「夜はひとりで怖い」などの短いメッセージが、困った表情のクマやウサギのスタンプとともに飛んできた。「怖いのなら、すぐにこっちへ来たらいいから」とメッセージを返しても、「女の子を簡単に呼ばないで!」と、相変わらずの返信のあと、怒っているウサギのスタンプが必ず飛んできた。 いきなり夜中にスマホが震えるので慌てて出ると、「真鈴です。今何しているの?」と、けだるい声で言うのだった。「何もしていない」と返答すると、彼女は「フー」と先ず大きなため息をついた。おそらく上半身が肩の動きとともに沈むようなため息に違いなかった。「どうしたんだ?」と訊くと、「人って、何で生きていかなきゃいけないの?」と難しい質問をぶつけてきた。さらに「私が死んでも誰も悲しむ人なんかいない」と自暴自棄なことを言う夜もあり、「奥さんと別居しているのは、きっと岡田さんに原因があるんだわ。私には分かる」と、私を非難することもあった。 そのたびに私は「苦しいことがあっても投げやりになるな」と柄にもなく説いてみたり、「君がこの世にいなくなってしまったら、少なくとも三人は悲しみに暮れる。君の両親ともうひとりは僕だ」と慰めたりもした。そして私を非難する言葉に対しては反論の余地もなく、素直に謝った。 真鈴から何度も電話やLINEのやりとりをしているうちに、私は彼女に対して友達みたいな親しさを感じるようになっていたが、その感覚は次第に同志或いは戦友みたいなものに思えてきた。おそらく私が有希子のことや彼女の実家のことで悩んでいるのと同様に、彼女も父や母のことで苦しみ続けているから、無意識のうちにそんな感覚になってきたのだろうと思った。そのことは自然と「マリン」と呼ぶようになったことにも表れていた。 梅雨明けが宣言されて暑さが日に日に厳しくなってきた土曜日、昼過ぎに有希子から「すぐ近くまで来ているから」と突然電話があり、慌てて部屋を片付けて近くまで迎えに出た。彼女は「暑い、暑い」と言いながら私の部屋に来て、「思ったよりいい事務所じゃないの。キチンと片付いているし」と珍しく褒めた。 私はソファーに腰を落として、有希子が部屋の隅々まで見て回る姿を追っていると、つい二か月ほど前まで一緒に暮らしていたことが懐かしく思えて、思わず立ち上がって彼女を抱きしめようとした。 「だめよ、キチンとなってからね」 有希子は私の腕からするりと抜けて、困ったような顔をした。おそらく義父母が様子を見て来いと言ったのだろう。彼女との距離は、私が思っている以上に遥か遠くになってしまっているように思った。 「どうしたの、ぼんやりとして」 「いろいろと考えることが多くてね。こんな暑い日だというのに」 「変な人」 有希子は一時間余りいて、上本町のデパートで買い物をして帰ると言って部屋を出ていった。彼女が去った部屋の中には、巨大な空白が浮かんでいるような気がして、私の気持ちを大きく落ち込ませた。 有希子が帰ってから、ベッドに寝転んで本を読んでいたらスマホがブーブーと震えた。真鈴からだった。 「どうしたんだ?」 「今から会いたい」 「こっちへおいでよ」 「嫌だって!」 「じゃあ、いつもの場所で待っていたらいいのかな?」 「それでいい」 「何時ごろ?」 「三時ごろじゃだめ?」 「問題ない」 「じゃあ」と言って彼女は電話を切った。まるで同級生に電話をかけるように、四十歳になろうとしている私に三日をおかずに電話をかけてくる。完全にイレギュラーだ。 |
| 十八 |
|---|
|
午後三時、真鈴はいつものようにきっかりの時刻に、突如として待ち合わせの場所に現れた。私は口癖のように「お腹、空いていないか?」と訊いた。真鈴は「フー」といったふうに肩でため息を吐いたあと、「岡田さんはいつもそうね」と言って呆れた。 私たちは天満駅の近くのマックでバリューセットをふたり分買って、再び扇町公園に戻って食べることにした。梅雨明け宣言のあと、太陽はこれから真夏に向かって右肩上がりへの助走に入っているかのように、強烈なエネルギーを発揮しはじめていた。 木陰の芝生に座ってダブルチーズバーガーとマックポテトを食べてコーラを飲んだ。周りからはこの光景はどう見えるのだろう。私たちの前を人々が行き交っていた。正面の芝生では女の子が数人でバドミントンの羽を追っていた。中央のコンクリート広場の隅では、老人や子供たちが歩いているというのに、数人の若者が緩やかなスロープを利用してスケートボードで遊んでいた。 「急にどうしたんだ。何かあったのか?」 「あのね、岡田さんはひとりで調査の仕事をしているから、すごく忙しいと思うんだけど、どうしてもお願いがあるの」 「忙しくはないよ。で、頼みって何?」 私はダブルチーズバーガーを頬張りながら訊いた。真鈴は私の目を見てから視線を外し、口を窄めてストローでコーラをひと口飲んだ。そして言いにくそうに切り出した。 「実はお父さんを捜して欲しいんです。でも調査の費用がないの」 「そんなの分かっているよ」 「だから、私を好きにして。私、岡田さんだったらいいから」 「は?」 「私、今は両親が家にいないから生活が苦しくて、でも表向きは両親がいることになっていて・・・市の補助なんかも受けられなくて、いろいろと大変なの。親が残した少しの預金と私が何かで調達しないといけないんだけど、なかなか難しいのよ」 真鈴は視線を地面に向けたまま、言葉のひとつひとつを確かめるようにしながら言った。 「私を好きにしてって、何を言い出すんだ」 「冗談で言っているんじゃないの、真面目よ。私を尾行して、どんなことをしていたか知ってるよね。私はそういうことをしていたの。そういうことの内容は、きっと岡田さんが思っていることとは違うんだけど。でも、男の人とホテルに入ってお金をもらっていたのは事実よ。調査ってすごくお金がかかるんでしょ?だから父を探してもらう費用は私の身体。岡田さんとなら、我慢できるから」 「我慢できるからって・・・ひどいな、それは」 「ごめんなさい、岡田さんなら、いいから」 真鈴は正面を向いて、遠くを見るように目を細めた。 「君は確かに何人かの男の人とホテルに入った。部屋で何をしていたかは知らない。でももう過ぎたことじゃないか。今はそんなことしていないんだろ。まだやってるのか?」 「やっていないわ。岡田さんを捕まえてからは、やっていない」 「捕まえてからって・・・、知り合ってからって言えよ。プライドが傷つくじゃないか。あのな、自分を粗末にするのはやめよう。何か解決方法を考えよう」 「ちっとも分かっていない」 「えっ?」 「岡田さん、全然分かっていないわ。当たり前だけど」 「どういうこと?」 「もしかして、私がホテルで彼等に売春行為をしたと思っているの?」 「えっ?」 「エッチなんかしてないよ。私は彼等に楽しく過ごす時間を売っていただけなの。そりゃあ、ときにはキスをしてあげたり胸を触らせてあげるよ。でもそれだけだよ」 真鈴の反論しているような口調に呆気に取られた。 「キスをしてあげたりって・・・そんなことはっきりと言うなよ。楽しく過ごす時間を売っていたって、わけが分からん」 真鈴の過激な言葉にショックを受けていた。尾行の際に会った彼らとキスをする彼女を想像してみたが、情景がうまく浮かばなかった。 「いいのよ、もう」 真鈴は投げやりな口調で言った。 「ともかくお父さんの居所を捜して欲しいという希望は分かった。それはそれとして、前から不思議に思っていたことがあるんだが・・・」 「何ですか?」 近くを通った若いカップルが、私たちの様子を見て不思議そうな顔をしていた。やっぱり、私と真鈴とはどの角度から見ても変なんだろう。 「君のご両親の親戚のことだけど」 「親戚?」 「うん、つまり君のお父さん側やお母さん側の親戚なんかが何か手助けをしてくれないのかな?状況を知っていたら、放っておかないと思うんだけど」 真鈴は僕が言い終わらないうちに正面を向いたまま、「そんな人はいません!」と吐き捨てるように言った。ピシッと耳元に音が飛んできたようだった。 「どういうことなのかな?」 「お父さんの両親は結婚する前にどちらも亡くなったって。実家は香川県の丸亀市というところで、小学生のときに二度ばかりお墓参りに行ったことがあるけど、もうそこに実家はないみたい。お父さんの姉が一人いたようだけど、早くに病気で亡くなったらしいの。お母さんの実家は泉南の岬町というところだけど、お祖父ちゃんやお祖母ちゃんもとっくに亡くなってるし、兄弟は何人かいるらしいけど、連絡もないし全然分からない」 真鈴は言葉の合間にため息をつきながら言った。 「親戚なんて、ないのと同じよ」 「そうか、事情はよく分かったから、そんなに怒るなよ」 「怒ってなんかないよ」 真鈴は明らかに不機嫌そうな顔つきで言った。そして、体育座りの足の間に顔を埋めてしまった。 「分かった、引き受ける。でもな、費用は要らないよ。お金の心配なんかしないで、僕に任せておけばいい」 「そんなことできない。私、何もお礼ができないのに頼めない」 「僕みたいな人間に好きにしてなんて言うなよ。何でそう投げやりになるんだ?もっと自分を大切にしろよ」 「私が何をしようと、いいじゃない」 「バカ!心配しているのに、そんな言い方ないだろ。ともかく空いている日にお父さんを捜してみるよ。時間がかかるかも知れないけど、やるだけやってみよう」 「私、それならもういい。ハンバーガーご馳走様でした」 真鈴はそう言っていきなり立ち上がった。 「何でそんなに強がるんだ。甘えろよ。素直になればいいんだ」 私はもう一度座るように手で示した。真鈴の伏せた両目から涙が流れ出ていた。彼女の寂しさは分かる。女子高生が置かれている状況としてはあまりに厳しすぎる。誰だって泣きたくなるだろう。まるで暴風雨の中でもがいているようなものだ。 「余計なことを考えないで任せておけよ。僕が好きでやるんだから。分かったね」 真鈴は五秒ほど考えてから大きく頷いた。 |