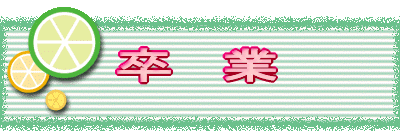
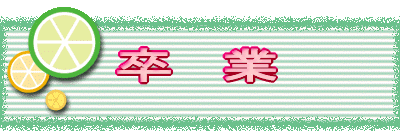
|
卒業 |
|---|
|
一 卒業式が終わったあと、大勢の在校生や教師や父兄たちに見送られながら体育館を出たとき、お前は思いっ切り顔を崩して笑っていたから、俺もつられて笑ってしまったんだ。 「嬉しいなぁ、もうここに来んでええねんで」 「そやけど、和田。そんなに嬉しいか?」 「当たり前や、今度は大学で楽しくやったらええやん」 お前は細い目をますます細くしてそう言ったが、俺の本当の気持ちは笑って卒業できるものではなかった。何しろ卒業式の一週間前まで、教頭をはじめ三年生の各組の担任教師たちが「藤田は卒業させてはいけないでしょう。こんな前例は作ってはダメだと思いますよ」なんて、学年会議で皆が口角泡を飛ばして俺を非難していたらしいのだから。 「藤田!お前何やってる?今日は追試の日やろが!」 和歌山中央郵便局に担任教師の木田が血相を変え目をつり上がらせて怒鳴り込んできたとき、俺は仕分けの作業が一段落ついて、仲の良い郵便局員と卓球に興じていた。 「追試?」 「そうや、追試が通らなかったら、お前、卒業できへんからな。今ならまだ学年教師たちが学校で待ってるから、すぐに、ホラ、支度せんかい!」 「そやけど先生、俺、もう大学受かってますやん。初年度納入金も払ってますよ」 「関係ないんじゃ、アホ!早う支度せんか!」 俺は木田先生に引きずられるようにして、県立K高校の職員室の奥にある会議室に連れて行かれ、そこで裁判にかけられた。 「藤田君、大学受験に関係する教科ばっかり勉強するから、こういう結果になるんやで。何ですか、この数Ⅲの試験結果。一学期も二学期も一桁の点数、三学期はとうとう零点って、完全になめてるよね?」 「ヤマカン」というあだ名の現代国語の女教師が、片手でメガネの縁を持って資料を覗き込みながら、さらに顔をしかめながら言った。 「でも現国は満点でしたでしょ」 俺は堂々とヤマカンに向かって言った。すると隣席にいた物理の西谷先生が「アホ!関係ないわい、今は数Ⅲの落第点のことを問題にしとるんや」と怒った。 「ともかく藤田の落第点は個人的にもう一度追試のチャンスを与えましょう。私が教えますよってに」 担任の木田先生はたまたま数Ⅲの教師であった。そういう気楽さもあって、俺は数学なんてたった一分の時間さえ家で勉強などしたこともなかったのだ。 「こんなことを許す前例をつくったらアカンのとちゃいますか?」 ヤマカン他、数名の担任教師が最後の最後まで反対をして、なかなか結論が出なかったが、時間も時間になったので、教頭が「卒業式の一週間前にもう一度追試をやりましょう。それでまた欠点やったら、もう今度は有無を言わさず落第ということでいかがですかな?」と言い、俺ひとりの数Ⅲ追試欠席事件の会議はお開きとなった。 「木田先生、もし追試が欠点やったら、大学どうなるんですか?せっかく頑張って合格したのに。新聞に僕の名前も載ったんですよ」 俺は納得がいかずに訊いた。 「大学の合格は辞退や。もう一年間三年生をやらなアカンわ」 木田先生は冷たく吐き捨てるように言うのだった。だが、駅までの帰り道、「心配するな、お前の家に行って試験に出るところをこっそり教えたるよってな」と、ニヤッと笑い、「ホナ、ともかく今度の土曜日に行くからな、家の人に伝えとくんやで」と言い残して和歌山線に乗って行ってしまった。 家に帰って両親にこの話をすると、父親はカンカンになって怒り狂い、母親は右往左往して父の怒りを鎮めていた。 「世の中にはルールがあるんじゃ!ええ大学合格して、お前は天狗になっとるんや。払ろうてしもた金はもったいないけど、もうええわ。いっそのこと落第してもう一年高校へ行け!その方がお前のためじゃ」 父親はビールを飲みながら俺を非難し、荒れ狂った。 俺はその夜、親友の和田に電話をして、この日のことを話した。 「俺、教えたろか?家に来いよ、特訓してやるわ」 「お前が俺の先生か?」 「そやそや、数Ⅲ、簡単や。任せとけ」 和田は電話の向こうで得意そうに言うのだった。 二 翌日、和歌山中央郵便局に電話をかけて、急なことでバイトには行けなくなった旨を伝えた。理由を正直に係りの人に伝えると、「そらアカンわ。卒業が第一やで、藤田君。ともかくちゃんと卒業して、大学生になったら夏休みにまたバイトに来てや」と優しく言ってくれるのであった。 学校は一月末頃からずっと休みに入っていて、卒業式までに数日登校するだけになっていたが、卓球部の友人やクラスメートからときどき「○✖大学に合格した!」と電話がかかってきたりもした。追試に通らなかったら本当に卒業できないのかと、俺は焦りに焦り、午後から親友の和田の家を訪ねた。 「おう、教えたるわ、数学なんて屁みたいなもんやで。国語とか倫理社会なんかと違うて答えが決まってるんやからな。数Ⅲの三学期試験で押さえとかなアカンポイントは統計と微分積分だけや」 和田は大きな家の敷地内の離れになっている自分の部屋に俺を連れて行き、教科書と参考書を開いて緊急特訓を始めるのであった。彼もすでに大阪の近鉄沿線にある大学の工学部に合格していたので、微積分は「解き方」さえ公式通りにやれば簡単だと、例題を解きながら説明するのですごく分かり易く、別に追試で良い点数を取らなくても30点以上取ればいいのだからと、不思議なことにこの一日だけで少し自信がついたような気になった。 晩ご飯時まで和田に特訓をしてもらって帰宅すると、母親が「明日、木田先生が来てくれるよって、どこも出かけたらアカンで」と言った。 「連絡あったの?」 「お母ちゃん、今日木田先生の家に菓子折り持って行ってきたんや。よろしゅう頼みますって言うといたからな」 余計なことをしてくれたものだと思ったが、母親も必死なんだろう。近所に息子がK大学に合格したと、喜びのあまり言いふらしてしまったのだから、ここで「高校を卒業できませんでしてん」とは言えないだろうから、俺は「そうか、おおきに」と素直に礼を言うしかなかった。 翌日、和田から昨日教えてもらった統計と微分積分の練習問題を解きながら木田先生を待った。先生は気遣ってか、昼時を過ぎたころにやって来た。母親が一緒に僕の部屋に来て「ちゃんと教えてもらうんやで。今日だけやねんからな」と言って、一旦引っ込んでからお茶とお菓子を運んできた。 「藤田、どこ勉強してんねん?」 「昨日、和田に統計と微分積分のところを特訓してもらったんです。ちょっと分かってきました」 「そうか、和田はお前と逆に数学は抜群やけど英語と国語がサッパリアカンのや。ともかく和田の言うとおりや、出る範囲は微分積分のところが半分近いよってな、そこをある程度できたら、統計は○✖式の問題がちょこっと出るだけや。30点は間違いのう取れるわな」 木田先生は当然和田以上に分かりやすい解き方を教えてくれて、さらに「問題は俺知っとるんや。そやけど教えられへん。ひとつだけ統計のところやけどな、○✖式が6問出るさかいに、上から✖✖○✖○○や。今俺はつぶやいただけやからな」と言い、早うメモしとけとまで、ちょっと怒りながら言うのであった。 結局、俺はなんとか追試をクリアしたが、そんな経緯があったためか、卒業式では泣く余裕など全くなかった。大勢の在校生や教師や父兄たちに見送られながら体育館を出たとき、お前は思いっ切り顔を崩して笑っていたから、俺もつられて笑ってしまったんだ。 「嬉しいなぁ、もうここに来んでええねんで」 「そやけど、和田。そんなに嬉しいか?」 「当たり前や、今度は大学で楽しくやったらええやん」 大学生活が始まった。俺と和田とは南海電鉄の難波駅までは同じ通学経路だったので、週に何度かは同じ電車で通った。通学にもなれてきた六月のある日、たまたま小学校の同級生だった森内さんという可愛い女の子と偶然出会った。 「藤田君?」 「うん、久しぶりやね。森内さんはどこに通ってるの?」 「うちは本町のS短大やねん」 「俺はK大、こいつはD大や」 そのとき和田と一緒だったので彼女に紹介し、それがきっかけでふたりは付き合い始めた。大学の行き帰りに電車の中や駅などでふたりの姿を見かける日もあったが、俺は遠くから見守っているだけにした。 実は小学生のころから中学生になっても、ずっと俺は密かに森内さんが好きだったのだ。高校が別々だったので、自然と思いは薄れていったような気がしたが、偶然会ったとき思いの全てが蘇ってきたのだ。でも俺は照れ隠しのように一緒にいた和田を紹介してしまった。 やがて長い夏休みに入り、俺は和歌山駅近くの倉庫会社で、それこそ何かを忘れるためにバイトに明け暮れた。和田とも森内さんとも誰とも会わない日が続き、そして九月になって大学が再び始まった。 三
大学の後期の授業が始まった矢先、俺はちょっとしたことで父親と口論してしまい、母親の制止を振り切って家を飛び出した。部屋でかなり大きな音で音楽を聴いていたことに父親が文句を言ってきたもので、それは当然の注意であって、普段なら素直に謝ってボリュームを下げるのだが、大学は思った程面白くもないし、親友の和田は俺がずっと恋焦がれていた女の子と付き合ってしまう始末で、異常に苛立っていたのだろう、後戻りできない態度を取ってしまった。 家を出た俺は、高校の同級生でK産大へ進んだTのアパートに転がり込んだ。そこからK大ヘ通い始めて数日後、俺は森内さんに電話をかけた。 「和田とうまくやってるの?」 「ふつう・・・かな」 「俺な、和歌山を出て京都から大学に通ってるんや」 「えっ、何で?」 電話の向こうで驚いた様子が分かるくらい森内さんは驚い声で訊いた。 「親父と喧嘩したこともあるけど、やっぱり和歌山からは大学まで遠いからな」 「そんなん、嫌や。もう会われへんやん」 京都の居候先から大学に通うことを説明すると、森内さんは慌てたよう「明日会いたい」と言った。俺たちは翌日淀屋橋駅で会って、中之島公園のベンチに座った。 「藤田君、おかしいわ」 「えっ?」 「自分の気持ち、捨ててるみたいに思える」 公園の向こうには土佐堀川が流れていて、砂利を積んだ船が「ポンポンポンポン」と音を立てて、少しだけ煙を出しながら下流に向かっていた。そのさらに向こうには、古茶けた雑居ビルが建ち並び、初秋の陽射しが壁を焦がしていた。 「どういうことかな?」 「藤田君、うちのこと好いてくれてたやろ?うち、分かってたんやで」 森内さんは遠くを眺めるように正面を見ながらそう言った。 「高校、別々になったやん、そやけど、うちはずっと気にしてたんやで。ホンマやで」 なぜこんなに森内さんが積極的に言うのか、俺はどう答えていいのかも分からず、「うん」と相槌を打ったきり、黙ったまま何も言えなかった。 「ええやん、和田君にはうちからちゃんと言うとくから」 「どういう意味?」 「そやから、藤田君とうち、付き合いたいねん」 その日、中之島公園から今度は天王寺公園へ場所を変えて、夕闇が次第に深くなってきたころに、俺と森内さんは木陰でキスをした。俺にとって初キスだったが、彼女も「当たり前や」と言っていた。 それから俺と森内さんは週に一度か二週間に一度、公園や喫茶店でデートを重ねた。森内さんは和田にはキチンと話をして、納得の上で別れたと言っていた。俺は和田に電話をする勇気が出てこず、一ヶ月が経ち二ヶ月が過ぎた。 俺が居候している友人のアパートには公衆電話があった。考えてみれば、家を飛び出してしまった俺に、両親は連絡の取りようがないのだ。弟や妹はどうしているのだろうと、季節が次第に寒さを増してくるとともに、和歌山の実家が懐かしく思えて来、無意識のまま受話器を取っていた。 「はい、藤田ですが」と母の嗄れた声が耳に懐かしく、すぐに言葉が出なかったが、「俺やけど、何かかわったこと、ないかな?」と言った。 「あるある、和田君から何回も電話があったで。連絡があったら必ず電話してくれるように伝えてくださいって言うてたわ」 俺は電話を切ったあと、しばらく考えた。和田とは高校生活で最も親しかった友人だ。いつも下校は一緒で、お互いに家に泊まりあったり、図書館へ行ったり、時には授業を一緒にサボったり、隠れて酒を飲んだり・・・大事な友達に違いなかった。森内さんと偶然会ったとき、照れ隠しに和田に彼女を紹介などせず、自分の気持ちに正直になるべきだったのだ。 俺は和田の家に電話をかけた。最初は母親が出て、しばらくしてから奴が出てきた。 「藤田、よう電話してくれたな」 「和田、俺な・・・お前に謝らなアカンことがあるんや」 「何を謝ることがあるんや、お前が俺に気い遣って電話できへんようになってしもうたことは、俺はな、よう分かってるんや。俺らな、女の子ひとりのことで終わりになる友情か?違うやろ?」 「和田・・・悪かったな」 「そやから、それがアカンねんって!俺らずっと親友やないか。森内さんと付き合うたらええやん。俺はなんとも思うてないで、お前とこのまま離れていくのが辛いだけや」 俺は電話口で涙を止められなかった。しばらく何も言えずに泣いた。 「泣くな、藤田。たまには和歌山へ帰ってこいよ。卒業式に体育館から出たときの、あの気持ちのええ状態でお前と友達でいたいんや」 「分かった。今度の土日に帰る」 俺はひとりの女の子のおかげで、本当の親友の存在を知った。重い受話器をガチャリとおろすと、こころの中の蟠りが受話器の重さの分ほど軽くなったと思った。 ‐了‐ |